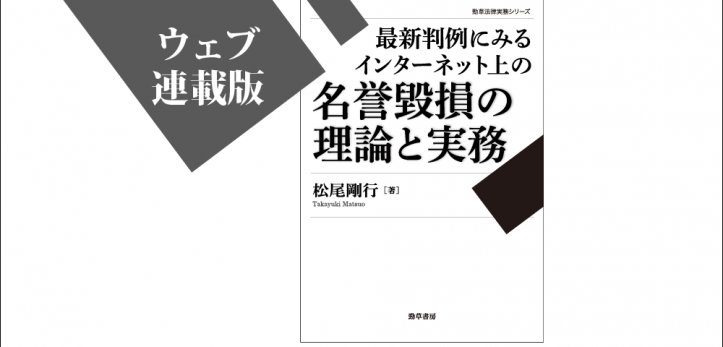
ウェブ連載版『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』第14回
名誉毀損も問題ですが、「名誉毀損だ!訴訟するぞ!」と正当な言論を抑圧するのもまた問題です。[編集部]
名誉毀損を理由とする訴訟提起が不法行為となるかが問題となった事案から、SLAPP訴訟について探る
これまでの連載で触れてきた名誉毀損の免責法理である「真実性の法理・相当性の法理」の特徴を一言でまとめると、「表現内容が社会的評価を低下させるものだと一応いえれば、あとは表現者(インターネット上に投稿等をした人)の方で、それが正当な表現活動であることを立証しなければならない」ということです。
その表現内容が(名誉毀損の不法行為等を成立させる程度に)社会的評価を低下させるものどうかかがポイントとなることは、連載第3回で述べたとおりですが、たとえば、犯罪、暴力団との関係、不倫、セクシャルハラスメント等を内容とする投稿であれば、基本的には社会的評価を低下させるといってよいでしょう(注1)。
その結果、基本的には被害者側(名誉毀損をされたと主張する側)は、その投稿を裁判所に提出し、表現者が投稿したことを立証すれば、あとは表現者側が真実性・相当性の立証をする必要があり、その立証ができなければ損害賠償等を命じられるという仕組みです。
この点については、「記事を書かれた側が問題の記事を甲1号証として提出して訴えれば、あとは表現者(メディア)側が記事の真実性等の立証を負担することになるが、訴訟上の立証活動は手間もかかるし容易なことではなく、メディア側にとっては、訴えられるだけでかなりの負担になる」(注2)と指摘されているように、(資金力が比較的豊富で組織的対応も可能と思われる)新聞社やテレビ局のようなマスメディアにとってさえ、訴えられることが負担であると指摘されています。
もちろん、このような法制度は、被害者の名誉権を守りやすくするという意味で、一定の意義があります。しかし、名誉毀損をされたと主張する者が、この制度を濫用するおそれも否定できません。インターネット上で発言する個人にとっては、その負担はより大きく、訴訟を提起されることによる表現への影響は、インターネット上の場合にはより大きな問題となるといえるでしょう。
近年、SLAPP訴訟(スラップ訴訟)という言葉が使われるようになりました。これは、公的参加を妨げるための戦略的訴訟(注3)であり、たとえば、ある社会問題について、表現者Aが発言をしたところ、それと反対の立場にあるBが、Aの発言が名誉毀損であるとしてAを訴えて(ないしは「訴える」と脅して)黙らせようとするといった場合が考えられます。
最近ではこの問題はさらなる展開を見せており、AのBに対する誹謗中傷に対し、Bが「Aの行為は名誉毀損であり、法的措置を講じる」と発言したり、実際に訴訟を提起したりすると、Aが「BはSLAPP訴訟を仕掛けてきた、Bはそこまでするひどい奴だ」などとして、Bをさらに中傷するといった事案もあるようです。
こうしたSLAPP訴訟の基本的な法的構造をご理解いただくため、インターネット上の名誉毀損に関する訴訟提起が不法行為であるか問題となった事案(注4)について、東京地方裁判所の判決を題材に取り上げます。ここでは、基本的には法律面だけを扱い、道徳的側面や社会学的側面、心理学的側面等に触れないことをあらかじめご了承ください。
*以下の「相談事例」は、判決の内容をわかりやすく説明するために、判決を参考に筆者が創作したものであり、省略等、実際の事案とは異なる部分があります。判決の事案の詳細は、判決文をご参照ください(注5)。
相談事例:不当訴訟を提起された事案
Aはフリージャーナリストとして、不正や犯罪等に関する記事を雑誌やインターネット上に発表していた。
Bは甲社の代表者であるところ、AはBが甲社に対する特別背任行為を行ったとの記事を雑誌とインターネット上に発表した。
すなわち、甲社のグループ会社が別の会社に下請に出した業務の報酬の一部を、Bの指示の下、Bの設立したファミリー企業に還流させることで、Bが不正に蓄財していると指摘したのである。
Bは、Aの行為がBの名誉を毀損するものであるとして訴訟を提起した。
Aは、慎重な取材を重ねた結果、真実を報じたものであり、名誉毀損は成立しないと考えている。むしろ、Bの行為はSLAPP訴訟、つまり、Aを黙らせるための不当訴訟だと考えている。
M弁護士はAに対しどのように助言すべきか。
1.法律上の問題点
Bの特別背任といった犯罪を内容とする表現は、Bの社会的評価を低下させます。
しかし、連載第8回、第9回、第12回での真実性の法理の解説の中でご説明したとおり、公共性・公益性・真実性のある表現であれば、Aは免責されます。そして、企業の犯罪の告発は公共性・公益性がありますので、問題は真実性です。
ここで、判決の事案では、Aは取材で入手した合意書や請求書等を証拠として提出しました。これらの証拠からは、甲社のグループ会社である特定の会社が、ある会社に2億9000万円の報酬を支払い、その約半額が、Bのファミリー企業に支払われていることが明らかでした。
そこで、裁判所は真実性を認めたのです(注6)。
これにより、名誉毀損に関してAは免責されるわけですが、AはBに対して不当訴訟を受けたとして損害賠償等を請求できるのでしょうか。
この点につき、最高裁判所は、一般に訴訟提起が不法行為に当たる場合は「提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるとき」であるとしています(注7)。
要するに、裁判所はかなり限定的な要件の下でのみ、訴訟提起が不法行為にあたるとしているのですが、このような要件を本件は満たしているでしょうか。
→【次ページ】不当訴訟になるか?