
《ジェンダー対話シリーズ》第4回 王寺賢太×森川輝一:愛・性・家族のポリティクス(前篇)
[テーマの語りにくさ]
王寺賢太 王寺賢太と申します。森川さんの実に周到なお話をうかがうと、やはり法学部の先生ともなると与えられた制限時間内できっちりと見晴らしのよい議論を展開されるのだなと思って感心して聞いていたのですが、僕はふだん京大でも人文科学研究所というところにいて、午後をまるまる費やして行われる共同研究に携わっており、日頃は往々にして、良く言えば談論風発、悪く言えば冗長散漫とも言える議論をもっぱらとしています(笑)。今日は古くからの友人である藤田さんが宮野さんと編集した『愛・性・家族の哲学』シリーズを中心に議論をするということで喜んで出かけてきたので、いつもどおり、ざっくばらんにしゃべってみたいと思います。
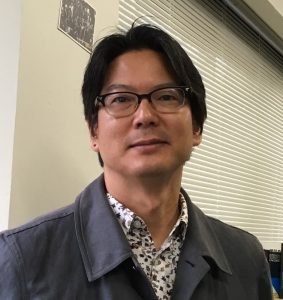
だから、18世紀ヨーロッパ研究という自分の専門に照らしても、愛・性・家族の問題は決して無縁ではありえないし(もっとも、時代や地域によって、無縁でありえる社会があるかどうかは疑問です)、学問的関心もなかったわけではないのですが、個人的にはどうも苦手意識があって(笑)、結局のところ、大学のなかでは愛・性・家族といった問題にあえて触れないようにしてきました。それに比べれば、「政治哲学」とか「歴史叙述」とかいった、いわば公的かつ脱性化された話の方がずっとやりやすいように感じてきた。ただ逆に言うと、苦手意識があるということは、僕にとって、愛とか性とか家族といった問題がつねに躓きの石だったということでもあります。こんなことをカムアウトする必要はまったくないわけですけど(笑)、僕は男性であり、ヘテロセクシュアルであり、妻子持ちであり、この『愛・性・家族の哲学』でとりあげられているような、現在さまざまなかたちで現れている多様な性や家族のあり方からすれば、いたって規範的な属性をそなえた主体ということになると思います。こと性や家族のことに限って言えば、法的にも社会通念的にもさしてプレッシャーを感じる必要のない存在ということになるかもしれない。しかし、にもかかわらず、個人的に考えてきて、やはり愛や性や家族の問題は、自分にとってすごく困難な、難しい問題を突きつけてくるものだったという感覚があります。つまり、僕はそうした問題について、まったく専門的な知見を持ち合わせてはいないわけですが、それでも愛・性・家族という問題については、その自分自身が無縁ではいられない。そしてまた、こと愛・性・家族といった問題に関しては、どれほど規範的な属性をそなえた主体であっても、うまくいくとは限らない。むしろそうした問題こそが、「ノーマル」な主体にとってもしくじりの源になるというところがあるのだと思います。
言い換えると、一方では法制度とか社会通念といった次元で、性関係をどう考えるのか、家族関係をどう考えるのかといった一般的な次元での議論があります。それと同時に、それぞれの性関係、家族関係は、それこそ取り替えがきかないもの、それぞれの主体、それぞれの人間がほかならぬその主体・ほかならぬその人間であるということと切り離しがたい、そうしたシンギュラー(単独・特異)な次元もあるわけですね。ただし、そこで愛・性・家族の問題を、いきなりシンギュラーな次元の問題として把握してしまうと、当の性差の問題を消去してしまうことにもなりかねない。たぶん、愛・性・家族といった問題について語ることの難しさは、この一般性の次元と単独性・特異性の次元の交錯から来るような気がします。今日は、そのあたりの難しさを念頭に置きながら、僕なりにお話をしてみます。
[3つの次元――生物学的な次元、文化的な次元、法制度の次元]
王寺 藤田さんと宮野さんが共編された『愛・性・家族の哲学』は、僕にとってはなかなか語るに難しい一連の主題について、多様な視点から多くの情報を与えてくれる優れた入門書です。ビブリオグラフィもついていて、愛の思想史に興味のある方にも、現在の性愛や家族関係の変動について社会学的な知見を得たい方にも、あるいはバイオテクノロジーの発展が性関係や家族制度に及ぼしうる影響について興味をもつ方にも、非常にとっかかりの良い本です。なにより、僕自身がそういうふうに、この本を通じて主題の広がりと奥行きを感じることができました。
僕なりにざっくりと見通しを示せば、この連作は、愛・性・家族という問題系を、生物学的次元、文化的次元、そしてこの文化的次元のなかでもとりわけ法的次元に区分しながら議論する本だと思います。第1の「生物学的」次元というのは、個体で言えばあれこれの性器をそなえた身体において現れる解剖学的次元、あるいは種としてのヒトの生殖・再生産にかかわるような次元です。第2の「文化的」次元は、その生物学的・解剖学的な次元とはひとまず区別されるセクシュアリティの次元、個々の主体の欲望や性的志向にかかわる次元ですね。この次元に「ジェンダー」の問題が置かれている。それはまた、欲望とかかわるかぎりで、誰と出会うのか、誰を欲望し、愛するのかという非常に個人的な、取り替えがきかない次元ともかかわる。これに続く第3の次元が、結婚や家族を制度化する法的な次元です。この法制度の次元は、誰と誰が性的なパートナーであるということに承認を与えるのみならず、一方では、苗字の問題1つをとってみてもわかるように個々人をいかに法的に登記するかということともかかわりますし、他方では、家内分業や財産所有・分与にも、さらには子どもや老人の養育の問題とも密接に結びついている。先ほども森川さんから議論があったように、家族制度は生殖や人口の再生産と切り離せないわけですが、その生殖・再生産を家産の保有と養育の義務と結びつけるところに、われわれの知る家族制度の1つの要があり、これが容易には切り離せないからこそ、家族制度はさまざまな批判にもかかわらず、しぶとく制度として残りつづけているんだろうと思います。
藤田さんと宮野さんの『愛・性・家族の哲学』には、従来の日本の法制度が、以上の生物学的次元、文化的次元、法制度的次元という、本来区別しうるはずの3つの次元をべたっと一致させて考えてきた、あるいは一致させることを唯一の規範としてきたことに対する批判が通底していると思います。歴史的に辿っていけば、ヨーロッパにおけるローマ法とキリスト教のフォーマットの上で動いてきた制度だと言っていいと思いますが、それに対して、「ジェンダー」の多様なあり方を認めるべきだ、あるいは男女の一夫一婦制にとどまらない多様な家族のあり方を認めるべきだ、という発想がある。日本ではそれこそ夫婦別姓をめぐる議論の1つをとっても、反対派はもとより賛成派までもが「家名を守る」というなんだか大時代的な家父長制的信念に突き動かされているありさまらしいので、本書の主張がどこまで一般常識になっているかは覚束ないわけですが、実はこのジェンダーや家族のあり方の多様性を求める主張自体は、大学の言説のなかではもはや目新しい主張ではありませんね。最近、現首相の側近で、極右的な立場で名高いさる女性閣僚が、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー)の権利擁護の運動を支持したということで巷間をちょっと騒がせました。僕などは、これは「婚姻は両性の合意のみにもとづく」とする憲法24条の改正を要求するためのパフォーマンスなんじゃないかとも感じましたが、ある意味で、セクシャル・マイノリティの権利を擁護したり、結婚の多様性を要求したりすること自体は、そんな極右的な政治家にも十分に受け容れられるところまで来ているということなのかもしれません。だとすると、生物学的次元、文化的次元、法的次元を一旦切り分けて、性的志向と家族の多様性のありかたについて選択の幅を広げましょうというのは、それ自体としてはなかなか反論の難しい議論ではあるのだけれども、同時に、その主張のもとで、現在いったい何が行われているのか、あるいはそれがどんなふうに行われようとしているのかについては細心の注意を払ってみていく必要があるだろうとも思うんですね。
[バイオテクノロジーの発達]
王寺 家族形態の変容とか、性的パートナーシップの多様化についてはすでにお話があったので、これまでに出ていない1つの論点を示しておくと、現在の性的パートナーシップ、家族関係に非常に大きなインパクトを与えているものに、バイオテクノロジーの飛躍的な進歩があると思います。われわれ人文系の研究者たちは、生物学的次元と文化的次元は腑分けできるよ、という話をずいぶんしてきたわけですが、いまや生物種としてヒトの再生産が、これまで自明だと思われていた一対の男女による生殖というモデルによらずに可能なところまで来ているわけです。どうやら現在の技術レベルではまだ、生殖のためには女性の子宮は必要なようですが、もはや必ずしも精子は必要ない。つまり性行為、性愛自体が人口を維持し、管理してゆくための手段としては不可欠のものではなくなってしまったということです。それを良いことと考えるべきか、悪いことと考えるべきかについての判断を一概に下すことはできないと思いますが、ともあれ、現在の性的パートナーシップ、家族制度の変容は、そうした新たなテクノロジーの勃興とも軌を一にしており、また否応なくそうしたテクノロジーの進展に巻き込まれているということは確認しておかなければならないでしょう。
次ページ:性的主体の選択と合意のリミット――ペドフィリアと近親姦