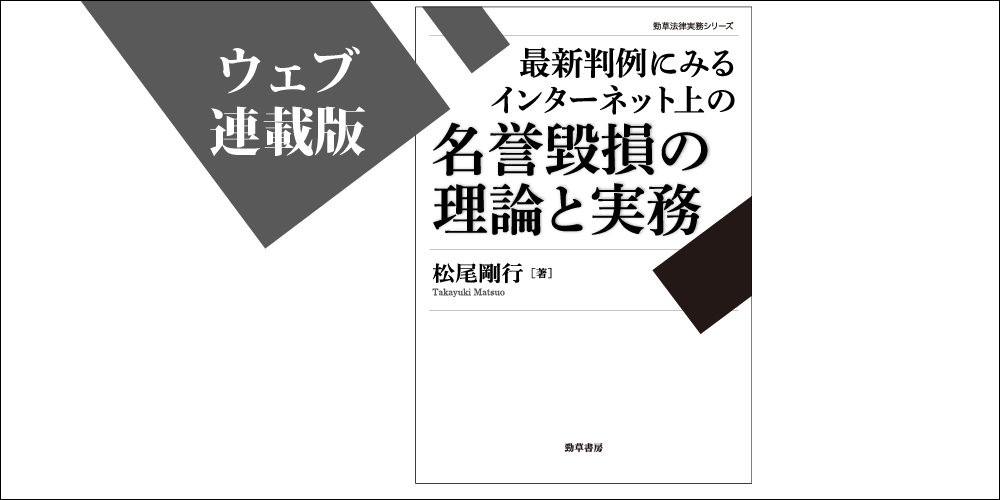今回は書評回となります。本年4月に勁草書房からダニエル・ソロブの翻訳『プライバシーなんていらない!?――情報社会における自由と安全』が発売されました![編集部]
書評:『プライバシーなんていらない!?――情報社会における自由と安全』(原題:Nothing to Hide)
本連載ではプライバシー、特にインターネット上のプライバシーを重要な問題として扱ってきた。ここでオンラインないしデジタル時代プライバシーにはいくつかの重要な特徴がある。
まず、インターネットがインフラ化(注1)するにつれ、ほとんどの人にとって毎日多数のデータ・ログを残すことなく生活することが困難となっている。
次に、アナログの情報はそれを1つ1つ突き合わせることに大変な労力がかかる。しかし、デジタル情報はデータマイニングツール等、最新の技術を利用することで容易にそれを結合・分析し、そこから様々な情報、場合によっては極めてセンシティブな情報を取り出すことが可能である。また、蓄積されたデジタル情報に対して特定のアルゴリズムを用いることで、例えば飛行機の搭乗禁止等の措置を講じることも可能となっている。
さらに、オンライン上の情報はプロバイダ等、本人以外の第三者が所有している可能性があるが、これらの者に対して書簡を送付したり、令状を用いることにより政府は文字通り「ごっそり」とプライバシーに関わるデータを取得することが可能である。
加えて、最近のGPS事件最高裁判所大法廷判決(以下「GPS判決」)(注2)が示すように、GPS等の新技術の発展により、政府は様々な情報を取得することができるようになったが、インターネットやGPSが普及する以前に制定された憲法や法律はそのような新技術に追いついていない。
このような特徴はいずれも、現代こそ、プライバシー保護が極めて重要な時代であることを示している。
ところが、現代において、「テロとの戦い」等「安全」の名の下にプライバシーは比較的容易に制約されている。例えば、刑事捜査においてはGPS捜査(注3)のような様々な新たな捜査手法が導入されており、それらは事案解明の役に立つ一方、プライバシーの侵害も懸念される(注4)。「安全」の利益と「プライバシー」の利益をどのようにバランスさせることが適切なのだろうか。
 このような問題について、世界的なプライバシー研究の権威であるダニエル・ソロブ(Daniel J. Solove)が一般向けに分かりやすく論じたのが『プライバシーなんていらない!?――情報社会における自由と安全』である。
このような問題について、世界的なプライバシー研究の権威であるダニエル・ソロブ(Daniel J. Solove)が一般向けに分かりやすく論じたのが『プライバシーなんていらない!?――情報社会における自由と安全』である。
ソロブは、これまで『プライバシーの新理論』(注5)等の学術書を多く出版し、学術論文を発表してきたが、本書は一般の読者、特に「安全のためなら多少プライバシーを犠牲にすることはやむをえない」といった議論に興味を持っている読者に対し、プライバシーと安全のバランスを適切に取るためにはどうすればよいかを分かりやすく教えてくれる。
衝撃的なのは、ソロブが、現在なされている、「安全かプライバシーか」という議論の枠組みそのものが誤っていると指摘していることである。すなわち、プライバシーを尊重するということは、安全保障対策をやめる(テロリストに自由にさせる)ということではない。あくまでも、政府の行う(プライバシー制約の懸念がある)特定の活動を一定程度監視し、一定程度規制し、そのことにつき政府に説明責任を負わせるということに過ぎないのである。そこで、プライバシーを尊重した結果、安全保障対策を一切やらなくなる/やれなくなるといった事態はほとんど生じない。このようなソロブの指摘は、上記のGPS捜査判決にそのままあてはまる。すなわち、GPS捜査も、これを全面的に禁止する必要はなく、立法的な措置が講じられ(注6)、裁判所に対し政府がGPS捜査の必要性を説明してはじめて令状が発布され、またその特質に応じた、実施可能期間限定、第三者の立会い、事後の通知等の様々な(プライバシーを守り、適正手続を担保するための)制約がなされるのであれば、そのような捜査を行うことに何ら問題はないのである。
また、ソロブは、裁判所が政府(立法・行政)に敬譲するのではなく、政府と裁判所がそれぞれその役割を果たすべきとも指摘している。新技術が毎日のように生み出され、発展する現在、法律はすぐにアウトオブデートとなる。たしかに専門技術的事項も存在するが、ある安全保障措置が正当化できるかという問題は、(技術の専門家ではない)裁判官でも理解可能である。ここで、法律に細目を書きこんでしまうからこそ、技術の発展に伴い法律がすぐにアウトオブデートになり、簡単に法の抜け穴を突くことができてしまう。そこで、立法府が法に原理・原則を書き込んだ上で、裁判所がその原理・原則を具体的な事案にあてはめていくというような形で適切な役割分担を果たすべきであると提案している。GPS判決において、最高裁は「GPS捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査手法であるとすれば、その特質に着目して憲法、刑訴法の諸原則に適合する立法的な措置が講じられることが望ましい」としており、このような裁判所と立法の間の役割分担を示唆していると言える。
このような議論を経て、ソロブは、安全とプライバシーをめぐる問題についての正しい問いの立て方を提案する。
1.その安全保障対策はうまく働くのか(無意味ではないか)(注7)
2.それは、プライバシーと市民的自由に対する問題を引き起こさないか。
3.どのような監視や規制を行えば、それらの問題を解決し、改善することができるのか。
4.もし、プライバシーと安全とのトレードオフ関係が必然的に生じるのであれば、どの程度まで安全保障措置がプライバシー保護のために制限されるべきか。そのような制限がどの程度安全保障措置の実有性を阻害するのか。その規制の便益は、実効性の減少による費用に見合うのか。
このように考えることで、プライバシーと安全という問題に対し正しい回答が得られるというソロブの指摘は、ソロブが研究のメインテーマとする米国プライバシー法のみならず、日本のプライバシー法、例えば、GPS判決を踏まえ、GPS捜査に関する立法措置をどのように行うべきかといった議論においても参照価値が高いと思われる。
上記はあくまでも、本書のうち興味深いと思われる議論の一部を拾ったものにすぎない。興味を持たれた方は、本年4月に勁草書房から邦訳書が刊行されたので、ぜひ購入されたい(注8)。
【編集部からのお知らせ】本連載の執筆者である松尾剛行先生も参加するトークイベントが2017年5月29日(月)に八重洲ブックセンターで開催されます。詳細は → http://www.keisoshobo.co.jp/news/n18941.html
(注1)『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』9頁参照。
(注2)最判平成29年3月15日判例集未登載
(注3)GPS判決によれば「車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査」。
(注4)その他、日本人の自宅や職場での通話、メール、画像等が監視されていることにつき、宮下紘『ビッグデータの支配とプライバシーの危機』12頁以下参照。
(注5)同書に関する優れた書評に大島義則「ダニエル・J・ソローヴ(大谷卓史訳)『プライバシーの新理論』(みすず書房、2013年)」http://tower-of-babel.hatenablog.com/entry/2015/01/27/014626がある。
(注6)ただし、岡部・大谷・池上補足意見は立法措置が講じられる前の暫定的な現行法に基づく令状によるGPS捜査の実施について述べている。
(注7)ソロブは「セキュリティー・シアター」という、安全性を高めるためには実際のところ無意味だが「安全感」ないしは「体感安全性」を高めるための(ニセ)安全保障対策について論じている。
(注8)この書評を書くにあたっては大島義則弁護士と、成原慧氏にアドバイスを頂戴したことを感謝している。ただし誤りはすべて筆者の責任である。
 2016年2月25日発売!
2016年2月25日発売!松尾剛行著『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』
時に激しく対立する「名誉毀損」と「表現の自由」。どこまでがセーフでどこからがアウトなのか、2008年以降の膨大な裁判例を収集・分類・分析したうえで、実務での判断基準、メディア媒体毎の特徴、法律上の要件、紛争類型毎の相違等を、想定事例に落とし込んで、わかりやすく解説する。
書誌情報 → http://www.keisoshobo.co.jp/book/b214996.html