週に一、二度は実家に寄っている。
ひとりで住む母の様子を見がてら、頼まれたものを、ちょっとした手土産とともに買ってゆく。
わたしの妹、紗枝はなかなか足をむけられないので、これはもっぱらわたしの役目だ。
そして、ときどき、サイェもついてくる。
繁華な駅のあたりから、道を三、四ほど横切ると、とたんに店がなくなり、住宅街になる。
住宅街といってもわたしが生まれ育ったころとはだいぶ様変わりしていて、二三階ほどのアパートやマンションが、一戸建てを上回ってしまった。
庭が残っている家もあまりない。
サイェははじめすこしだけ緊張している。
でもお茶を飲み、人心地つくと、ほとんど毎日わたしの部屋にいるのとおなじように、リラックスする。
応接間のソファに深く腰かけて、温室とそのあたりの木々を、
サンルームの籐椅子に深く腰かけ、池を、見る。
ときどき、となりの、というよりもほとんど野良の猫たちを、白と黒の、茶色と白の、猫たちが歩いたりじゃれたりしてするのを、ぼんやり、と。
母は新聞で、テレヴィで、知ったことを、町内会の回覧板をまわすときに見聞きすることを、脈絡もなく、話す。
うんうんとうなずきながら、わたしはときどき他愛ない感想をはさむ。
サイェは叔父であるわたしに、祖母であるわたしの母に、ときどき気をつかうのだろう、ときどきやってきて、顔をうえにむけ、しばらくそうしていると、また、もといたところにもどってゆく。
もうすっかり十月、数日前までは半袖で過ごしていたというのに、一日二日で急に気候が変わって、すこしまえにだしっぱなしにしていた長袖シャツとジャケットを着こんだ。
学校帰りのサイェと待ちあわせて、わたしの母のところへ。
そんな日。
公道にいたときには気づかないのに、大谷石の門柱につけられた蝶番がわずかにきしんで焦げ茶色の木戸をあけると、とたんにつよい香りにつつまれる。
そう、この時期はキンモクセイ。
丹念に刈りこまれた三、四メートルの、一枚の葉っぱのような木の下にオレンジの小さな花が無数におちている。
冬の日、雪が降りはじめて、茂った葉の下にはまだ地面がみえる、そんなことをおもいださせもして。
あるいは、
新年を迎え、春が近くなってきたかな、と、それでいて雪が、それまでの怠惰の帳尻をあわせるように降る時期には、ジンチョウゲが、そしてまた、四月の終わりから五月の連休にかけては、池のそばにあるフジが、かおる。
母の庭だ。
――あのかおり、どうしてのこしておけないの?
とサイェが何かを我慢するかのように、ちょっと眉間に皺をよせて、問いかけてきたのは、ジンチョウゲのとき。
――かあさんの棚にあるどの香水にもない。
フジの、あの藤棚のところでかおるのも、あのときにしか、ない。
いつでも、あのかおりが、ほしいのに。
サイェは、五月の光をあびながら、わたしが長いことつかっていたカセット・テープ・レコーダーを持ちだして、藤棚の下に立っていたこともある。
光はうすむらさきの花弁とうすみどりの葉とつるをとおして、サイェの顔に陰影をつけていた。
花のあいだをとびまわるハチたち、ミツバチとマルハナバチの、ふるえている振動を、音を、なんとか、なんとかして持ち帰りたい。
その次の年には、母、紗枝から借りてきたICレコーダーで、何度も何度も、試していた。
でも、タテにもヨコにも、いや、こっちにもむこうにも、ひろがっている、その音のありようが、どうしてもちがうのだ、と、サイェは泣いた。
夕べ。
わたしはいつものように、台所の、母のそばにいた。
習慣だ。
齢をとって、何をするにも昔より何倍も時間がかかるとぼやきながら、わたしがこの家にいたころより一時間近く前には台所に立って、したごしらえをはじめる。
台所にたつ母のそばで、わたし、わたしたち、はとりとめない話をする。
こどものときから、この時間、家にいるときにはずっとおなじことをしてきた。わたしが手をはなせないとき、母が体調をくずして休んでいるとき以外には。
こうやって母の手つきを、料理をするしぐさをみてきた。
サイェは紗枝の手もとをあまり見ていない——かもしれないことをちょっとばかりおもいおこしたりもしながら。
そろそろ門灯をつけてサイェを呼んでらっしゃい、
あんたはすこし飲むんでしょ?
玄関の扉をあけると、外はもう真っ暗になっていた。
そして、夜の闇とともにわたしのからだを取り巻いたのは、虫の音。
瞬間、すこし、静かになる。でも、すぐにまた、この音、音たちは戻ってくる。
サイェは家の壁に寄りかかってじっとしている。
顔は庭に、そしてそこいらに立っている木々に、先の塀に、道路に、いや、そっちのほう、に、むいている。
――さされないか?
――もう、蚊、なんかいないよ……
サイェは、虫たちの、音、のなかにいた。
どこがどう、じゃなくて、「なっている」、その「なか」にいた。
――むこうでね、やんだり……、こっちがよわくなったりして、でも、ずっとなってる……ないてる……
何が、なんて言わない。
ほとんど独り言のよう。
くるまが、バイクが、通ってゆく。
ドップラー効果とともに音がポルタメントし、光がすぎてゆく。
ひとの声、話し声。
夕暮れになると、いつのまにかひとはするようになる口笛や鼻歌。
おばあさん、おじいさんのゆっくりした、なかなか過ぎていかない足音、ひきずったり。
カッカッとはやく鋭い音が、するような音が、ひたひたひたという音が、あっちからこっちへ、こっちからあっちへ、と。
サイェはききいっている。
これも、持って帰りたい、って言うのか、とおもったけれど、わたしは黙っていた。
そしてそのまま、しばらく、そこにおなじように、べつべつに、いた。
母、の声が、うちのなかでくぐもって、呼んだところで、サイェは姿勢を正して、わたしを見上げた。すこしだけ、笑った。
戦争がはじまりかけていたころのこと。
駅の前にはまだロータリーもなく、道路も舗装されていなかった。
それからずっとここにいる。
きみがおとなになっても、サイェ、ここは、このまま、だろうか。
そして、きみはここの音をおぼえている、だろうか。
おぼえていて、いつ、まで、だろう。
[編集部より]
東日本大震災をきっかけに編まれた詩と短編のアンソロジー『ろうそくの炎がささやく言葉』。言葉はそれ自体としては無力ですが、慰めにも、勇気の根源にもなります。物語と詩は、その意味で人間が生きることにとって、もっとも実用的なものだと思います。不安な夜に小さな炎をかこみ、互いに身を寄せあって声低く語られる物語に心をゆだねるとき、やがて必ずやってくるはずの朝への新たな頼と希望もすでに始まっているはず、こうした想いに共感した作家、詩人、翻訳者の方々が短編を寄せてくださいました。その一人である小沼純一さんが書いてくださったのが、「めいのレッスン」です。サイェちゃんの豊かな音の世界を感じられる小さなお話、本の刊行を記念した朗読会に小沼さんが参加されるたびに続編が生まれていきました。ここではその続編にくわえ、書き下ろしもご紹介していきます。
【バックナンバー】
〉めいのレッスン ~手紙
〉めいのレッスン ~かぜひいて
〉めいのレッスン ~クローゼットの隅から
〉めいのレッスン ~ゆきかきに
これまでの連載一覧はこちら 》》》
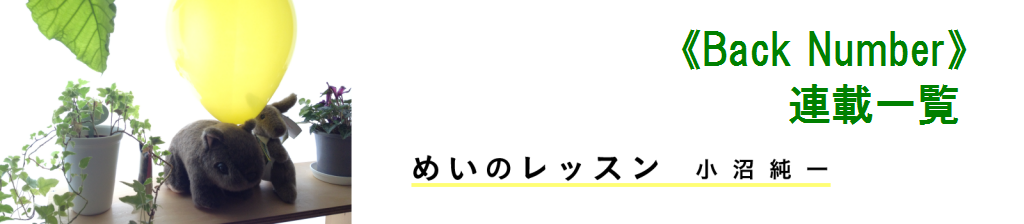
 管啓次郎、野崎歓編『ろうそくの炎がささやく言葉』
管啓次郎、野崎歓編『ろうそくの炎がささやく言葉』「東日本大震災」復興支援チャリティ書籍。ろうそくの炎で朗読して楽しめる詩と短編のアンソロジー。東北にささげる言葉の花束。
[執筆者]谷川俊太郎、堀江敏幸、古川日出男、明川哲也、柴田元幸、山崎佳代子、林巧、文月悠光、関口涼子、旦敬介、エイミー・ベンダー、J-P.トゥーサンほか全31名
書誌情報 → http://www.keisoshobo.co.jp/book/b92615.html


