新しい店なのに、前から知っているような。
カトラリーは真新しいのに、壁や天井や柱やカウンターは手の感触がある。
工業製品、ではなく、手作業の、か。
−−−サイェ、オレンジ、ジュス?
フィリップはサイェに正面から視線をあわせて、尋ねる。
サイェはこくりとうなずく。
フィリップは右手の人差し指をたて、ちょっちょっと動かし、あわせて、くちびるの両端を上にあげる。
ほとんど観光地と化している大きな坂道の一本裏手には、小さな店が軒をならべる。
大概は夜になるとあかりがともる飲食店。
ところどころに古くからの八百屋や豆腐屋、牛乳屋、また理髪店や銭湯が。
人通りは表通りとは比較にならないけれど、
昼も夜も、あたりを見知った落ち着いた視線が、少し暗い道を、ゆっくりした足どりで過ぎてゆく。
急ぎ足なのは、髪の短い板前法被のおにいさんが、八百屋に駆けこむときときくらいか。
日が落ちかけると、道はわずかに活気づく。
店じまいしはじめるお年寄りの店主と、これからお客さんを迎える店と。
来たときにはもう陽が落ちていて、二人ほどお客さん。
二階にもあと二人、とチャコが言う。
飲みものと小さな皿が二つ三つのるくらいの足の長いテーブルについて、
サイェは弾力のあるパンをどうしたらうまく千切れるか苦心しながら、落ち着かなさを誤摩化している。
小学生の子を連れてくるのにすこし抵抗はあったが、フィリップの店に、フィリップが新しく開いた店に行きたい、とせがまれてのことだった。

店をやるんだ。
小さな、でも、ありそうにない店。
気軽にはいれて、ワインがあって、ちょっとつまめる。
バル、みたい……でも、イタリアやスペインのじゃなくて、フランスの、南の料理で。
夢みたいなものだとばかりおもっていた。
フィリップがチャコと暮らしはじめて四年、いや、五年か。
南仏のペンション・オーナーとして、夏は帰国するものの、
それ以外はこの極東で、一見、気ままに暮している。
店の目星はついている。食器は揃えたし、あとは内装をやるだけ。
そう聞いてもまだ半信半疑だった。
こっちは毎日ほとんど変わりなく過ごしているのに、いつのまにかフィリップは店の準備を整えていた。
絵空事のように感じていたのは、フィリップが内装を自分でしている、と聞いていたから。
壁に漆喰を塗り、床に板を張る。骨董市で買ってきたお気に入りを飾る。
誰かにやってもらえばいいのにと言うと、高いし職人なんて信用できない、と。
フランス人だからね。
チャコが笑う。
いくら、フランスとは違うんだよ、と言ってもだめ、自分でやる、ときかない。
何年もかけてヨーロッパの人は別荘をつくったりするものね、とかえしたのは紗枝。
チャコと紗枝は昔からの仲良しで、よくうちに遊びにきていた。
妹の友だちだったチャコは、いつのまにかわたしにもなった。
そして、忙しくうごきまわっている紗枝より、よく顔をあわせるようになって、
フィリップを紹介されたのも、親しくなったのも、先だった。
新しい店は、でも、フィリップがひとりで内装をやっているときから、
ときどき顔をだし、差し入れをしていたこともあり、紗枝が先んじていた。
骨董市をまわって、運びこんだものたち、使いこんだものたち。
出かけるたびにものがふえていく、部屋が、居住空間がせばまると悲鳴をあげていたチャコは
こっちにものたちが移ってゆくのを、減っていくのを、一日一日と、体感してきた。
あそこにあった箪笥が、ワイン・オープナーがいっぱいの箱が、
積み重なっていた皿が、壁に立てかけてあった古びた油絵が、
あぁ、こんなふうにならぶんだ、
と、やっとここに来て腑に落ちた、と。

新しいお客さんがやってくる。
はいってきて、三つのテーブルを順繰りにみまわす。
あれ?という表情の後、奥の階段をみつけて、
友だちが……、と一言。
チャコが、どうぞ、と手をむけると、二人の女性は階段にむかってゆく。
そのときだ。
サイェは顔を不意に上げ、天井を見上げ、
口をちょっと開いたまま、眼を泳がせる。
どうした、と声にださずに、尋ねる表情をむけると、
サイェは視線を手元の皿に瞬間、落としてから、こっちをむいて、言うのである。
−−−−ブケッティーノ、だよ!
チャコとわたしの視線が交わる。
そして、ブッケ・ティーノ?と小声でくりかえす。
今度は、フィリップが、声を高めて、言うのである、アァ、ブケッティーノ!
フィリップを、チャコとわたしが、見る。
フィリップはサイェにむかって笑みをおくっている。
あらためて、チャコとわたしは顔をみあわせる。
さっきまでの、サイェの緊張はすっかりなくなっている。
−−−そ、ブケッティーノ。
しばらく、沈黙
フィリップは、うんうん、と小さく頷いている。
おじさん、おぼえて、ない? ブケッティーノ……
前に、行った、おしばい、親指こぞう、って、
みるんじゃなく、きく、おしばい。
小屋みたいなのができてて、そこにはいる。
はいってくときに、かさ、かさ、ってなる。
あれは枯葉だったかな、あしのうらの、踏んでる感触がもある。
においもしてたっけ。
何のだったかは忘れたけど、なんか、いい、におい。
ベッドがいくつもいくつもならんでて、大人も子どもも、横になる。
毛布をかけたりもして、さ。
電球がひとつだけ下がってて、あとはまっくら。

おはなしはおねえさんがひとりだけ。
絵本読むみたいに、
「むかしむかしあるところに」。
おねえさんは声を変えて、
おじいさんになったり親指こぞうになったり、
人食い鬼になったり。
でね、
いろんな音がする。
外で動物の声がしたり、動いたり。
とびらがぎーってなると、ほんと、こわい……。
小屋の壁を外からたたいたりひっかいたりこすったりもして、ね。
うん、
突然、だと、びく、っとする。
それがむこうだったりこっちだったり、むこうとこっちだったり、動いたり。
だんだんだんだん、
とたたきながらはしってきたりして、なんか、こわかったりおかしかったり。
部屋のあちこちでひびいて、
あ、くるな、くるな、とか、
とおざかってく、とか、
するといきなり、
天井からばーんと音がしてびっくりしたり。
たしかにそんな芝居を、ちょっと変わった芝居を観に行った。
何年前だったっけ。
サイェはそのときはじめてフィリップに会ったんだ。
でも、それが?
とおもった瞬間、フィリップはカウンターのなかから外にでて、
階段を駆け上がっていった。
いまさっきのお客さんの註文をとりにいったとおもっていたら、
あっちで、そして、こっちで、どんどん、と、かんかん、と天井から音がする。
二階を歩き回っているのだろうか。
お客さんたちがあげる笑い声も届く。
−−−フィリップが「ブケッティーノ」してる!
フィリップは階段を、わざと不規則に、かかとをつよくあて、
踏みならし、はね、すって、みる。
テンポを変えながら、
壁をてのひらで、げんこで、指先でたたいたり、こすったり。
お客さんが、何、この店?とおもってもおもわなくても、
フィリップは気にしない。
ここはこういうこともおこる店。
いまはサイェがいて、誰よりもサイェとつうじているのは、
からだで、音でつうじあっているのはフィリップだ。
まばらに通ってゆく人、人たちは、
新しい店のかまえに注目し、外にでているメニューをのぞきこむ。
そして、ガラス張りの店内に笑顔があふれているのを、不思議そうに、
ちょっと名残惜しそうに、通り過ぎてゆく。
☆
『親指こぞう ブケッティーノ』は、シャルル・ペローのよく知られたストーリーを、イタリアのキアラ・グイディが演出した作品。2006年に神奈川県民ホールで公演されて以来、現在も全国で上演されている。
[編集部より]
東日本大震災をきっかけに編まれた詩と短編のアンソロジー『ろうそくの炎がささやく言葉』。言葉はそれ自体としては無力ですが、慰めにも、勇気の根源にもなります。物語と詩は、その意味で人間が生きることにとって、もっとも実用的なものだと思います。不安な夜に小さな炎をかこみ、互いに身を寄せあって声低く語られる物語に心をゆだねるとき、やがて必ずやってくるはずの朝への新たな頼と希望もすでに始まっているはず、こうした想いに共感した作家、詩人、翻訳者の方々が短編を寄せてくださいました。その一人である小沼純一さんが書いてくださったのが、「めいのレッスン」です。サイェちゃんの豊かな音の世界を感じられる小さなお話、本の刊行を記念した朗読会に小沼さんが参加されるたびに続編が生まれていきました。ここではその続編にくわえ、書き下ろしもご紹介していきます。
【バックナンバー】
〉めいのレッスン ~南の旅の
〉めいのレッスン ~あかりみつめて
〉めいのレッスン ~気にかかるゴーシュ
〉めいのレッスン ~クリスマス・ツリー
〉めいのレッスン ~秋の庭
これまでの連載一覧はこちら 》》》
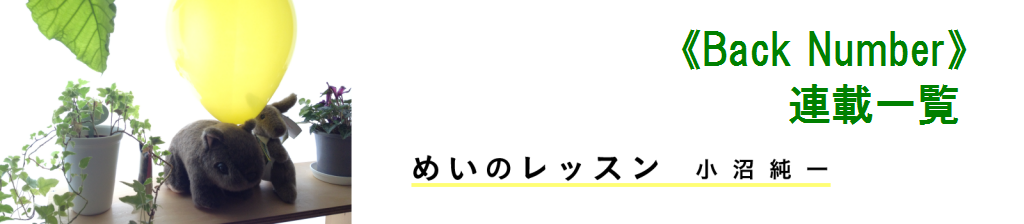
 管啓次郎、野崎歓編『ろうそくの炎がささやく言葉』
管啓次郎、野崎歓編『ろうそくの炎がささやく言葉』「東日本大震災」復興支援チャリティ書籍。ろうそくの炎で朗読して楽しめる詩と短編のアンソロジー。東北にささげる言葉の花束。
[執筆者]谷川俊太郎、堀江敏幸、古川日出男、明川哲也、柴田元幸、山崎佳代子、林巧、文月悠光、関口涼子、旦敬介、エイミー・ベンダー、J-P.トゥーサンほか全31名
書誌情報 → http://www.keisoshobo.co.jp/book/b92615.html


