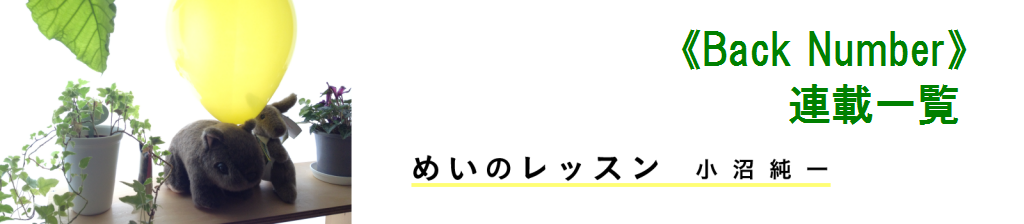ジーンズがだいぶくたびれて、藍色が薄くなってきた。ストーン・ウォッシュとまではいかないが、ところどころ擦り切れている。
とおもっていたところ、膝に小さく穴があいて、あとは日ごとに領地が広がっていった。はじめのうちはおずおずと隠れていた白い糸たちが、いまでは大手をふって何本もはみだし、さすがにこのままではとおもうのものの、どうしたらいいものかとんとわからぬまま、そしてまた穴は大きくなってゆく。
おなじ大きさのままならいい。だが、ちょっとしたきっかけで思い掛けない拡大をする。履くときには穴のないほうに先に足をいれ、注意をしながら、もう片方をいれ、ず、ず、ず、とのばしてゆく。寝起きで忘れたまま間違えると、穴に足指をひっかけて一気に進んでしまうことがあるから、特に用心する。
予想外だったのは、低い位置にあるタオル・ハンガーにちょっとしたひっかかりがあることで、ふだんは気にしてなどいないのに、洗面所から廊下にでるところで、どうしてこんなにうまくとおもうのだが、これがちょうど穴にはいって、こちらの歩くテンポを乱す。しかも性懲りなく何度もひっかかる。穴そのものの拡大に影響しないのが救いだが。そもそも実家のような古い家屋だと障子や襖、引き戸がほとんどで、取っ手のついたドアはあまりなかった。マンションとなると、部屋ごとの区切りをドアでしていることが多いのだろう、ジーンズの穴だけでなく、トートバッグやショルダーバッグをこの取っ手に引っ掛けて、つい、と、引きとめられてしまうことしばしばだ。
ジーンズの穴、もちろん、はじめてのことではない。ないのだが、以前にどうしたのかはまったく記憶から抜け落ちている。買い替えているはずだが、捨てた記憶もない。実家のどこかにジーンズたちが安らいでいる押し入れでもあるのだろうか。古い家屋でどこかに引っ掛かった記憶もない。たぶん。
サイェはジーンズの穴を見て見ないふりをしつづけていた。だが、さすがにめいの目の前でタオル・ハンガーに引っ掛かるおじの姿には呆れたようで、修繕するか捨てるかしたら、との提案をおずおずとしてきた。そんなことに応えるのも恥ずかしいやら苛だつやらで無愛想に喉の奥をならしただけだったのだが。
それから何日かして、つぎにやってきたとき、サイェは言うのである。
――おじさん、ちくちく大会をやるから、そのデニムはきょう持ってくね。
そうだ、まず、サイェはジーンズなんて言わない。デニム、と言うのだ。おなじものがべつの名称になっていることはしばしばある。リンスをめいはコンディショナーと言う。サイェがそう言うということは、きっと母親が、紗枝が言っているのだろう。
そもそもなんだい、そのちくちく大会、って?
予想はついたがそのまま納得してしまうのもどこか腑に落ちなくて、わざと尋ねてみる。案の定、針仕事をそう呼んでいるのだが、ひとつだけではなくて、いくつもいくつもとれたりとれかけていたりするボタンをかがったり、かぎざきやほころびをなおしたりするときにそう言うのだという。
――だって、おかあさん、お裁縫してると黙っちゃうんだもん、機嫌が悪くなって。
ここでおもわず吹きだしてしまう。
紗枝はこうした針でこちょこちょやっているのが大の苦手だった。学校に通っている頃も、熱があろうとどこかが痛かろうと、大量の計算問題や工作の宿題がでていようと淡々とこなすのだが、何かを縫ってくるとかいうのだととりかかるのにまずぐずぐずしていて、はじめてもおもいのほか時間がかかる。はじめはまだいいとしてもだんだんと内にこもってしまう。それがいつもの紗枝だった。そんなときの妹にはできるだけあたらずさわらず、こちらの存在をできるだけ消すようにつとめさえした。
そんな紗枝につきあったり、アドヴァイスしたり、他愛ないはなしを問わず語りにしながら、ときどきちょっと手伝ったりしていたのは、母の母、もう還暦はすぎていた祖母だった。還暦はすぎていた? そうか、あのときの祖母はいまの母よりずっと若かったんだ。
祖母の姿でいちばんよくおもいだすのは、畳の上に座布団を敷き、裁縫をしている姿だ。
のちに孫たちふたりの部屋へと改装される二階の六畳の和室は、南向きの窓がとても大きく、大人が正座してちょっと前屈みになれば、窓枠に腕をのせてのんびりと、外がみえた。いまのように二階三階のマンションが建っていなかったから、緩い勾配の上のところにあるこの家からは、二区画先の銭湯の屋根とその屋号が記された煙突が、またもっとむこうには左にかつてのアメリカ空軍の家族宿舎に立っている細いアンテナが、右側にはゴルフ練習場のネットが見えた。祖母がいた頃、空はもっと広かった。むこうまでずっと広がっていた。
祖母の部屋にはミシンもあって、こちらは母がつかっていたものだったが、黒光りしたシンガー製を模した戦時中にどこかから祖父がこっそりと手にいれてきた独特な形状をした本体は、子どもにとって精密機械のイメージを与えずにはいなかったもので、本来はニスが塗られた茶色い箱のなかにそのたびごとにしまわれるはずだったのに、しまったらすぐには使えないじゃないとの口実のもと、ふだんはそのままふわりとかるい布だけがかけられていた――そうした口実はしっかりと紗枝ではなくわたしに伝わっている――。布で隠されてはいても、木箱からのびている脚と足踏みペダルは鉄のレースのようでむきだしになり、後年パリで間近にエッフェル塔をみたときに連想したのはこのミシンだったりしたものだった。もっともペダルはいつも粗いつくりの小さな「おざぶ」がのってもいたが。
足踏みミシンをつかうときは家のどこにいてもわかった。テンポはいろいろに変わるが、木造家屋はそれとともにかなり揺れるのである。あ、動き始めた、とおもう。そしてかなり喧しく感じる。妹とわたしは、あ、攻撃が始まった!とわざと盛りあがってみるのがつねだったのだが、でもそんなことをおもうのははじめだけ。機械にむかっている者もそうでない者も、いつしかそれほど意識しなくなってしまう。せいぜいおやつの時間にまで食いこむと催促をしに二人のどちらかがあがっていくくらいで。
子どもたちは自分たちの部屋をほしがった。そして、洋間にして勉強机とベッドを置いた。祖母はそれまでいた部屋のとなりのもっと小さな部屋へと移った。そこには大きな窓はなかった。子どもの身勝手さと鈍感さは、ふと沸きわきあがってきて、いたたまれなくなる。祖母にはずっとあそこにいてほしかった。いまも、だから、祖母はあの部屋にいつづける。いてもらっている。薄茶色の老眼鏡をかけて、手元の針をゆっくり動かしている。
ふと、わたしはわれにかえる。すくなくとも身近でめいが針を手にしている姿を見たことはない。なかった、とおもう。この部屋にはそもそもそんなものはないのだし。
サイェも針を持つ?
――わたし、おかあさんより得意、なんて言えないかもしれないけど、好きだよ、おさいほ。
意外なこたえだ。紗枝の娘がそんなことが好きとは。針仕事だけではなく、編みものでも紗枝はおなじだった。母の「かいぐりかいぐり」ということばにはぴんと耳をたてたり、毛糸玉に子猫のように反応したりはした。かといって自分で縫い針を手にすることはついぞなかった。サイェが母親を促し、あいている時間に、手をつけるものを積みあげて、ちくちく大会を敢行するのだという。
――そばにカップにいっぱい紅茶をいれて、学校のこととかをおしゃべりしながら、やってく。おじさんのズボンはいやがるかもしれないけど、かあさん。
紗枝は、祖母から手先のこととは違ったものを教わったのかもしれない。そんなふうに、ふと、おもう。わたしは、何か、受けとったのはあったか、どうか。
とおもったら、サイェはにこにこしながら言うのである。
――おじさん、今度、編みもの、してみる? 一緒に、マフラー、編んでみる、とか。
》》バックナンバー《《
〉めいのレッスン ~ポワソン・ダヴリル
〉めいのレッスン ~ルンバ・ストーカー
〉めいのレッスン ~えと~てむ
〉めいのレッスン ~まわりにたくさん
〉めいのレッスン ~小さな店で
 管啓次郎、野崎歓編『ろうそくの炎がささやく言葉』
管啓次郎、野崎歓編『ろうそくの炎がささやく言葉』「東日本大震災」復興支援チャリティ書籍。ろうそくの炎で朗読して楽しめる詩と短編のアンソロジー。東北にささげる言葉の花束。
[執筆者]谷川俊太郎、堀江敏幸、古川日出男、明川哲也、柴田元幸、山崎佳代子、林巧、文月悠光、関口涼子、旦敬介、エイミー・ベンダー、J-P.トゥーサンほか全31名
書誌情報 → http://www.keisoshobo.co.jp/book/b92615.html