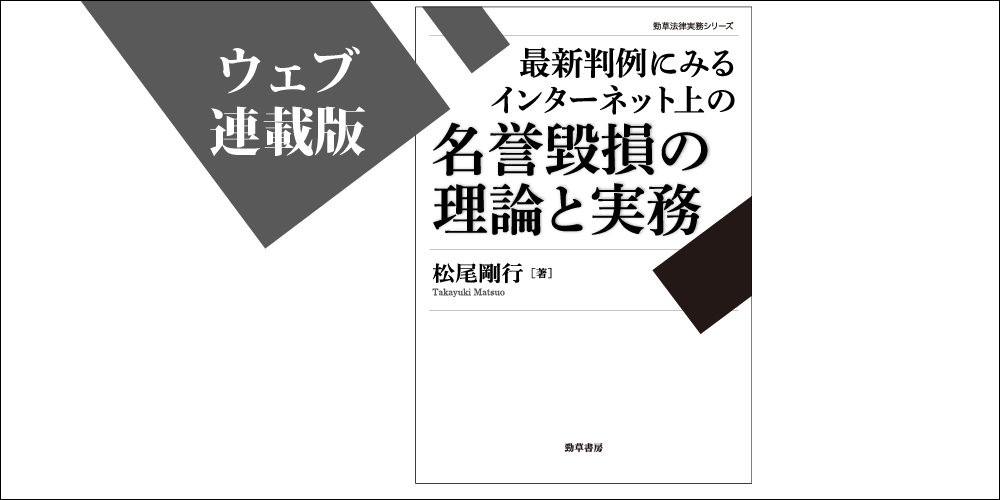3.管轄の問題
日本の裁判所に管轄があるかは、日本法、具体的には民事訴訟法3条の2以下により定められます。
国際商取引の場合には、当事者間の契約で管轄裁判所について合意することがありますが、名誉毀損について事前に当事者間で管轄裁判所について合意がされることはほとんどありません(注4)。
そこで、名誉毀損について日本に管轄が認められる場合としては、被告の住所地が日本国内にある(民事訴訟法3条2第1項)(注5)、または不法行為地が日本にあるとき(同3条の3第8号)(注6)のいずれかの場合が多いといえるでしょう。
具体的にいえば、相談事例2であれば、被告Aは日本に住んでいますので、もしBが日本の裁判所に訴えれば、管轄が認められるでしょう(実際に訴えたいか、という問題はあります)。また、不法行為地には、加害行為地と結果発生地の双方が含まれます(注7)。そこで、相談事例1であれば被害結果発生地が日本である、相談事例2であれば、加害行為地が日本であるとして、いずれにせよ日本の裁判所に訴えれば、管轄が認められることになります(注8)。
ただし、民事訴訟法3条の9は、特段の事情がある場合には、管轄を否定し、訴えを却下できるとします(注9)。この、「特段の事情」による例外的な処理については、以下の5.で具体的に説明します。
なお、例えば、相談事例1であれば、日本の裁判所に訴えることがBにとって便宜ですが(注10)、相談事例2であれば、Bはアメリカの裁判所に訴えるかもしれません。この場合に、アメリカの裁判所に管轄権があるかは、日本法では解決することができず、アメリカ法の問題ということになります。本連載ではアメリカ法の問題については割愛させていただきます。
4.準拠法の問題
日本の裁判所に管轄がある場合、日本の裁判所に訴えが起こされると(適法な送達を前提に)日本の裁判所で実質審理が始まることになります。
この場合、アメリカ法が適用されるか、日本法が適用されるか、これが準拠法の問題です。
日本の裁判所が適用する法の適用に関する通則法19条は、名誉毀損について比較的クリアな規定を置いています。すなわち、「第十七条の規定にかかわらず、他人の名誉又は信用を毀損する不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、被害者の常居所地法(被害者が法人その他の社団又は財団である場合にあっては、その主たる事業所の所在地の法)による。」としているので、事例1のように被害者の常居所地が日本である場合には日本法、事例2のように被害者の常居所地がアメリカである場合にはアメリカ法となります(注11)。
なお、法の適用に関する通則法は日本の裁判所が適用するものであり、アメリカの裁判所はアメリカの準拠法に関する規定を適用し、何法が適用されるかが決まります。
5.訴訟戦略と国際訴訟競合
ここで、事例2において、Aがアメリカでの訴訟を嫌がることがあります。この場合、日本の裁判所に債務不存在確認の訴えを起こせば、管轄が認められる可能性がある程度高いと言えるでしょう。
もしBがアメリカで訴訟を起こしたら、Aの起こした日本の訴訟と、Bの起こしたアメリカの訴訟という形で、実質的に同一の紛争が国内の裁判所と外国の裁判所で同時に係属する事態が生じます。これが国際訴訟競合(international parallel litigation)です(注12)。このような国際訴訟競合は、事例1でBが日本で訴訟を起こし、Aがアメリカで訴訟を起こすことでも発生する可能性があります。
最近、事例1にやや近い事案で、最高裁が日本の国際管轄について判断した事案があるので紹介します(注13)。
最高裁の事案では、アメリカの会社甲が日本の会社である乙にコンプライアンス上の問題があるというプレスリリースを掲載したことから、甲の行為が乙に対する名誉毀損にならないかが問題となりました。
この事案では、甲はゲーミング(カジノ等)の業務を営み、乙は甲に投資していたのですが、アメリカのゲーミング法はコンプライアンスを重視しており、株主がコンプライアンス違反を行うと、資格はく奪等の可能性があります。甲の取締役会が、乙のコンプライアンス違反を疑って調査を行い、その結果、調査の依頼を受けた米国の法律事務所から「乙らが米国海外腐敗防止法違反をしていた」等という報告書を受領したことから、その旨のプレスリリースを掲載したところ、乙はプレスリリースは事実無根で、乙の名誉を毀損した等として東京地裁に提訴したという事案です。
この事案においては、既に甲側が乙の保有している甲株式を償還したこと(注14)等を理由に、アメリカにおける紛争が発生し、先に甲がアメリカの裁判所に提訴して取締役の行為の適法性等の確認を求め、乙が反訴を提起して取締役会決議の履行の差し止めを求めるという関係にありました。
東京地裁は、不法行為に関する訴えとして、不法行為地は日本にあるので、原則として日本の管轄が認められるものの、民訴法3条の9にいう「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情」があるとして、訴えを却下しました(注15)。
乙は上訴しましたが、東京高裁(注16)、そして最高裁は、いずれも民訴法3条の9を理由に訴えを却下した東京地裁の判断を是認しています。
最高裁が日本で裁判をすべきではない特段の事情があるとしたのは、以下のような具体的な事情に鑑み、米国で訴訟を行うことが適切と考えたものと理解されます(注17)。
① 米国訴訟が先に係属していたところ、日本訴訟は米国訴訟の紛争から派生した紛争についてのものといえ、米国訴訟と日本訴訟では事実関係や法律上の争点について、共通し又は関連する点が多いものとみられる。
② 主な争点についての証拠方法は、主に米国に所在するといえる。
③ 乙も、甲の経営に関して生ずる紛争については米国で交渉、提訴等がされることを想定していたといえる。
④ 実際に、乙は米国訴訟で応訴するのみならず反訴も提起しており、名誉毀損についての訴訟を米国で改めて提起させても過大な負担にならない。
⑤ 反面、証拠の所在等に照らせば、これを日本の裁判所において取り調べることは甲にとって過大な負担を課すことになる。
この最高裁の判断は、あまりこれまで裁判例が多いとはいえない(注18)国際訴訟競合についての管轄の肯否の問題について事例判断を下したという意味で、重要な意義があるといえるでしょう。
最高裁は、単に外国において先行する関連訴訟があるというだけで一律に「特段の事情」があるとしたものではなく、乙が甲に投資をしており、名誉毀損も甲への投資に関する紛争から派生するものであったという事情が、特段の事情を認めた理由において占める割合が大きいと理解されます。もっとも、実務的には、米国訴訟が先に提起され、それに対し、名誉毀損の点を含まないとしても、単に応訴するだけではなく、反訴までして争っていたことが、名誉毀損についての訴訟を米国で改めて提起させても過大な負担にならない等として日本における審理を否定する理由の1つとされていたことは、事例1や事例2における日本側当事者が、米国訴訟でどのような訴訟対応をするかや、日本での訴訟をどのタイミングで提起するか等の訴訟戦略の決定の際に参考になります(注19)。
いずれにせよ、このような国際訴訟戦略は、名誉毀損法及び国際訴訟に関する知識と経験に基づく判断が必要であることから、このような事案に直面した場合には、専門家に相談することが望ましいでしょう。
【次ページ】注と書籍紹介