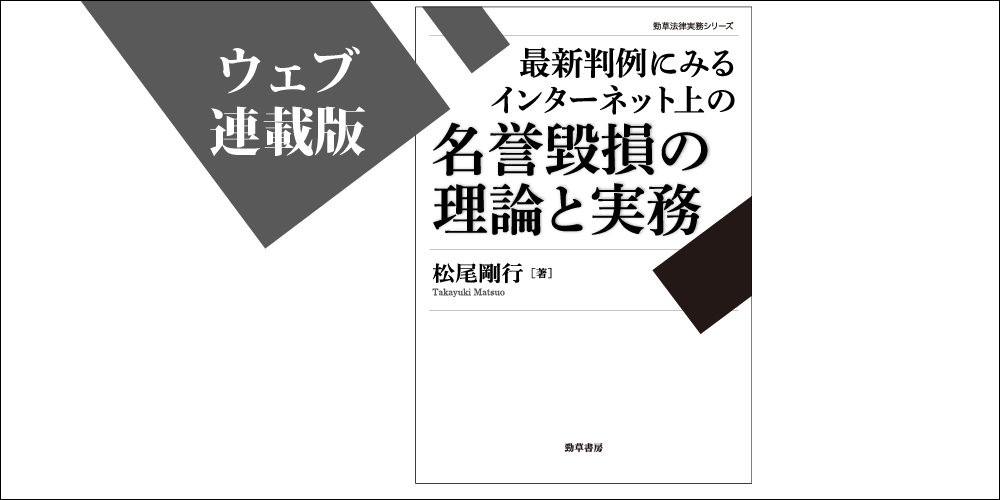3.国際的プライバシー侵害
(1)はじめに
事例1-1および1-2そして事例2はいずれも日本のBから見れば、A(およびA1)という外国の主体がBのプライバシー情報を不適切に扱い、Bのプライバシーを侵害した事案と言える(注15)。このような場合には、BはAないしA1を訴えたいと考えるだろうが、どの国の裁判所でどの法を適用して判断さされるのだろうか(注16)。
(2)裁判管轄
日本の裁判所に管轄があるかは、日本法、具体的には民事訴訟法3条の2以下によって決定される。ここで、プライバシー侵害について日本に管轄が認められる場合としては、被告の住所地が日本国内にある(民事訴訟法3条の2第1項(注17))又は不法行為地が日本にあるとき(同3条の3第8号(注18)のいずれかの場合が多いと言えるだろう。不法行為地には、加害行為地と結果発生地の双方が含まれる(注19)。そこで、相談事例においては日本のBのプライバシーが害され、被害結果発生地が日本であるとして、日本の裁判所に管轄が認められる可能性がある(注20)。
ここまでは、国際的名誉既存の場合とほぼ同様である(注21)。もっとも、特に事例1-1においては、例えば約款でBがAを訴える場合には、カリフォルニア州の裁判所でしか訴えられない等と規定されていることがあり、その場合、このような合意によって日本の裁判所に訴えられなくなるのかが問題となる。この点、民事訴訟法3条の7第5項が特別規定を置いている(注22)。要するに、消費者の住所地(事例1-1の場合日本)が合意された裁判所である場合か消費者自身が当該契約上の管轄合意を援用した場合でなければ当該合意は有効とされない。そこで、事例1-1のBは日本に訴えを起こすことも妨げられない。
(3)準拠法
次に何法を元にプライバシー侵害の成否が判断されるのだろうか。上記のとおり日本の裁判所が裁判をすることを前提とすれば、日本の国際私法すなわち法の適用に関する通則法の問題である。
ここで、国際名誉毀損・信用毀損については、法の適用に関する通則法19条は、「第十七条の規定にかかわらず、他人の名誉又は信用を毀損する不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、被害者の常居所地法(被害者が法人その他の社団又は財団である場合にあっては、その主たる事業所の所在地の法)による。」として、被害者の常居所地法とする。
問題は、これに類似したプライバシーについても同様に考えるべきかである。
この点、立法担当者は、プライバシーは法適用通則法19条の範囲に入らないという見解のようである(注23)。ところが、学説上はプライバシーも法適用通則法19条の範囲に入ると解すべきとする見解が有力である(注24)。現時点では関係する裁判例もないようであるが、名誉権とプライバシー権が重なり合う場合も多いことから、仮に19条の範囲に入らなくとも、20条(注25)等他の条文によって結局被害者の常居所地法を適用すべき場合が多いように思われる。
なお、事例1-1においては、AB間の契約上、例えば準拠法をカリフォルニア州法とすると合意されていることがある。この場合には、法適用通則法11条により、基本的には消費者(B)が自らの常居所地法(日本法)上の強行法規を援用すれば、これが適用されることになる(法適用通則法11条1項等)。ここで、いわゆる能動的消費者については法適用通則法11条6項1号、2号の例外規定(注26)があるものの、典型的なインターネット取引についてはこれに該当しない(注27)。よって、Bは、例えば責任制限規定が公序良俗違反である(民法90条)とか消費者契約法違反である(消費者契約法8条)等の主張を行うことができる可能性がある。
4.まとめ
国際名誉毀損と国際的な個人情報・プライバシーの問題は、一部類似する点もあるが、一部相違する点もある。
いずれにせよ、国際性が引き起こす様々な特殊性に鑑みると、国際的な個人情報・プライバシーが問題となった場合には、専門家に相談することが適切であることが多いと思われる。
【次ページ】注と書籍案内