親を介護する息子の増加は著しく、その割合は娘や義理の娘(「嫁」)による介護と僅差になりました。結婚していようと、仕事をしていようと、いまや男性が親の介護から「逃げる」ことはできなくなっているというデータもあります。それなのに男性のなかには、親の老いにいつまでも見て見ぬふりを決め込む人も少なくなく、また、いざ親の介護者になれば、今度は「問題事例」として周囲をやきもきさせることも多いことがわかっています。刊行以来、介護問題のみならず男性学に新たな論点を提示したと高い評価を受けている著者によるブックガイド、ぜひご覧ください。[編集部]
 “なぜ男の介護は困難なのか? 介護する息子のミクロな経験を通じて、自分の依存を「なかったこと」にし、弱者を支配せずにはいられない「男性性」の謎を解き明かす、著者の探求はスリリングだ。”――上野千鶴子氏推薦!
“なぜ男の介護は困難なのか? 介護する息子のミクロな経験を通じて、自分の依存を「なかったこと」にし、弱者を支配せずにはいられない「男性性」の謎を解き明かす、著者の探求はスリリングだ。”――上野千鶴子氏推薦!
※刊行時トークイベントはこちら→《ジェンダー対話シリーズ》第3回 平山亮×上野千鶴子:息子の「生きづらさ」? 男性介護に見る「男らしさ」の病
平山亮『介護する息子たち 男性性の死角とケアのジェンダー分析』
男性にとって「息子である」とはどんなことか。親を介護する男性の経験を通し、「男らしさ」の規範とその虚構性を問う刺激的論考。→〈書誌情報〉
→本書の〈「序章」「あとがき」ページ(pdfファイル)〉はこちら
定価:本体2,500円+税 2017年2月刊行
四六判上製280頁 ISBN978-4-326-65405-5
「男性の生きづらさ」への注目がアカデミアに限らず共有されつつある一方で、成人した男性の息子としての経験は、これまでほとんど語られずにいる。あるいは、こうも言えるかもしれない。息子であることは、「男性であること」には含まれていないのだ、と。(略)息子としての自分に向き合わざるを得ない経験としての親の介護。本書は、息子としての男性とはどのような存在であるかを、親を介護する男性(息子介護者)の経験を通して考察したものである。――「序章」より抜粋
■『介護する息子たち』ブックガイド“オトコとケアの見方・変え方”■
[選書&紹介文]平山 亮
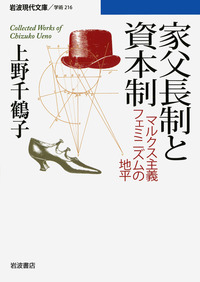 「不払い労働」をキイワードに、男たちが当たり前のように履かせてもらっている下駄を、痛烈に描き出します。90年代当時の著者の将来予測が、現在あまりにも当たっていることにも驚かされるでしょう。
「不払い労働」をキイワードに、男たちが当たり前のように履かせてもらっている下駄を、痛烈に描き出します。90年代当時の著者の将来予測が、現在あまりにも当たっていることにも驚かされるでしょう。『家父長制と資本制 マルクス主義フェミニズムの地平』上野千鶴子(岩波現代文庫)
 国際比較データをもとに、日本の税・社会保障の現状をジェンダー視点で分析します。そこから明らかになるのは、この国では共稼ぎ世帯が苦しくなるようにお金が流れている、という衝撃の事実……。
国際比較データをもとに、日本の税・社会保障の現状をジェンダー視点で分析します。そこから明らかになるのは、この国では共稼ぎ世帯が苦しくなるようにお金が流れている、という衝撃の事実……。『生活保障のガバナンス ジェンダーとお金の流れで読み解く』
大沢真理(有斐閣)
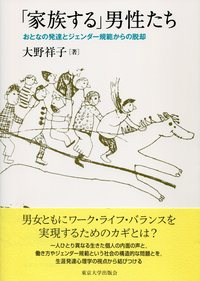 父親たちへの調査から、性別分業構造を変える道筋を探ります。制度が変わるのを待つだけでいいの?男たち一人ひとりができることもあるはずでは?という本書のメッセージは、いくら強調しても足りません。
父親たちへの調査から、性別分業構造を変える道筋を探ります。制度が変わるのを待つだけでいいの?男たち一人ひとりができることもあるはずでは?という本書のメッセージは、いくら強調しても足りません。『「家族する」男性たち おとなの発達とジェンダー規範からの脱却』
大野祥子(東京大学出版会)
 女たちが行ってきたケアという営みをもとに、弱者を中心にした政治のあり方を考えます。社会的包摂の概念を180度転換する、目からウロコの議論に圧倒されるでしょう。
女たちが行ってきたケアという営みをもとに、弱者を中心にした政治のあり方を考えます。社会的包摂の概念を180度転換する、目からウロコの議論に圧倒されるでしょう。『フェミニズムの政治学 ケアの倫理をグローバル社会へ』
岡野八代(みすず書房)
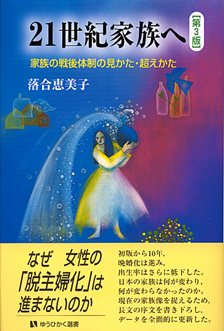 人口構造の変動に注目しながら、戦後の家族のあり方がなぜ・どのように私たちの「標準」になっていったのかをわかりやすく語ります。英訳され、海外でも広く読まれている日本の家族社会学の必読書。
人口構造の変動に注目しながら、戦後の家族のあり方がなぜ・どのように私たちの「標準」になっていったのかをわかりやすく語ります。英訳され、海外でも広く読まれている日本の家族社会学の必読書。『21世紀家族へ 家族の戦後体制の見かた・超えかた』
落合恵美子(有斐閣)
 社会学の視点から、高齢者介護を見つめ直してみるための必読の一冊。現場に駆けつけ、支援者とともに問題に取り組んできた著者だからこその鋭い観察と指摘にうならされることでしょう。
社会学の視点から、高齢者介護を見つめ直してみるための必読の一冊。現場に駆けつけ、支援者とともに問題に取り組んできた著者だからこその鋭い観察と指摘にうならされることでしょう。『介護問題の社会学』
春日キスヨ(岩波書店)
 私たちはどのような家族像を前提に、どのように現実を組み立てているのか。本書が詳説する構築主義の家族社会学は、家族の定義をあれこれ聞いてもどこかしっくりこないあなたにこそオススメです。
私たちはどのような家族像を前提に、どのように現実を組み立てているのか。本書が詳説する構築主義の家族社会学は、家族の定義をあれこれ聞いてもどこかしっくりこないあなたにこそオススメです。『概念としての家族 家族社会学のニッチと構築主義』木戸 功(新泉社)
 性が社会的につくられるとはどういうことか。性差の起源を説く進化心理学は何を見落としているのか。法解釈のなかでは女と男の何が当たり前にされているのか。緻密で真摯な分析の連続に酔いしれてください。
性が社会的につくられるとはどういうことか。性差の起源を説く進化心理学は何を見落としているのか。法解釈のなかでは女と男の何が当たり前にされているのか。緻密で真摯な分析の連続に酔いしれてください。『実践の中のジェンダー 法システムの社会学的記述』小宮友根(新曜社)
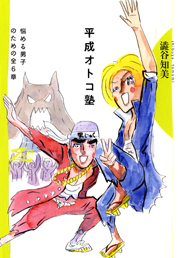 腕力と性欲で繋がり合うことが「ふつう」になり過ぎた日常を、男子はどうやって変えられるのか。そのためのエッセンスが詰まっています。若者向けに書かれているものの、この本を読むべきはむしろオジサンかも。
腕力と性欲で繋がり合うことが「ふつう」になり過ぎた日常を、男子はどうやって変えられるのか。そのためのエッセンスが詰まっています。若者向けに書かれているものの、この本を読むべきはむしろオジサンかも。『平成オトコ塾 悩める男子のための全6章』澁谷知美(筑摩書房)
 マタニティハラスメントの概念を打ち出した記念碑的著作。身体とは本来的にままならないものであることを前提に、その身体をケアする権利が皆に保障された就労システムの必要性を、誠実な分析を通して訴えます。
マタニティハラスメントの概念を打ち出した記念碑的著作。身体とは本来的にままならないものであることを前提に、その身体をケアする権利が皆に保障された就労システムの必要性を、誠実な分析を通して訴えます。『働く女性とマタニティ・ハラスメント 「労働する身体」と「産む身体」を生きる』杉浦浩美(大月書店)
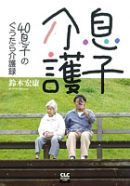 同居の親をひとりで介護する日々を綴った息子の手記。淡々とした筆致ながら、介護する家族を八方ふさがりに追い込む制度の矛盾を、こんなにも簡明かつ的確に突いた本は他にありません。
同居の親をひとりで介護する日々を綴った息子の手記。淡々とした筆致ながら、介護する家族を八方ふさがりに追い込む制度の矛盾を、こんなにも簡明かつ的確に突いた本は他にありません。『息子介護 40息子のぐうたら介護録』
鈴木宏康(全国コミュニティライフサポートセンター)
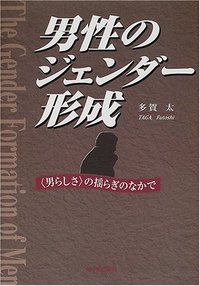 男としての自己がつくられ、揺さぶられる過程が丹念に描かれます。その人にとっての「あるべき男像」をつくるのは抽象的な社会などではなく、顔の見える相手との日々のやりとりなのだということがよくわかります。
男としての自己がつくられ、揺さぶられる過程が丹念に描かれます。その人にとっての「あるべき男像」をつくるのは抽象的な社会などではなく、顔の見える相手との日々のやりとりなのだということがよくわかります。『男性のジェンダー形成 〈男らしさ〉の揺らぎのなかで』多賀 太(東洋館出版社)
 日本では一人前の男のイメージはどのようにつくられているのか? 男性学の理論を駆使しながら、日本社会のなかの男たちの序列と、それを通してできあがる「理想の男」像を解剖した力作です。
日本では一人前の男のイメージはどのようにつくられているのか? 男性学の理論を駆使しながら、日本社会のなかの男たちの序列と、それを通してできあがる「理想の男」像を解剖した力作です。『男性学の新展開』
田中俊之(青弓社)
 これからの介護を担うことになる若い世代の親子観・介護観に迫った、貴重な成果と論考。親子関係に対する「ふつう」の見方に、どんなジェンダーバイアスがひそんでいるかを気づかせてくれます。
これからの介護を担うことになる若い世代の親子観・介護観に迫った、貴重な成果と論考。親子関係に対する「ふつう」の見方に、どんなジェンダーバイアスがひそんでいるかを気づかせてくれます。『若者の介護意識 親子関係とジェンダー不均衡』中西泰子(勁草書房)
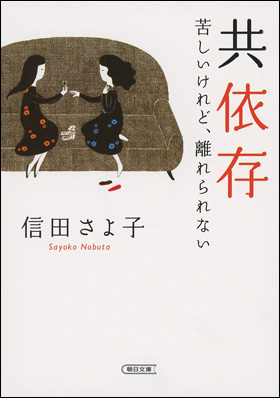 ケアが支配のツールになることを思い知らされる一冊。妻を甲斐甲斐しく世話する夫の抑圧性を描いた第3章には思わず背筋が凍ります。自立と依存の二項対立を斥ける熊谷晋一郎さんの解説も秀逸。
ケアが支配のツールになることを思い知らされる一冊。妻を甲斐甲斐しく世話する夫の抑圧性を描いた第3章には思わず背筋が凍ります。自立と依存の二項対立を斥ける熊谷晋一郎さんの解説も秀逸。『共依存 苦しいけれど、離れられない』
信田さよ子(朝日文庫)
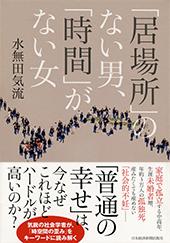 多様な統計資料と社会科学の知見にもとづいて、日本の働き方の「ここがヘンだよ」を解きほぐします。「ふつう」に働くことが、女性と男性にもたらす窮屈と不健康。その背景に迫る一冊。
多様な統計資料と社会科学の知見にもとづいて、日本の働き方の「ここがヘンだよ」を解きほぐします。「ふつう」に働くことが、女性と男性にもたらす窮屈と不健康。その背景に迫る一冊。『「居場所」のない男、「時間」のない女』水無田気流(日本経済新聞出版社)
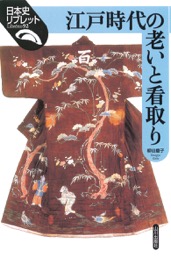 日本では介護はずっと嫁の務めだった? 史料をひもとき、お侍さんの時代の高齢者ケアの実像に迫ります。あなたが日本の伝統だと思っていた家族の姿は、そこにはありません。
日本では介護はずっと嫁の務めだった? 史料をひもとき、お侍さんの時代の高齢者ケアの実像に迫ります。あなたが日本の伝統だと思っていた家族の姿は、そこにはありません。『江戸時代の老いと看取り』
柳谷慶子(山川出版社)
 家庭でも職場でも、いつの間にか「ケア=女の役割」になっているのはなぜ? 女にとって割に合わないはずの選択を「合理的」に見せてしまう社会のからくりを、スッキリと解き明かしてくれます。
家庭でも職場でも、いつの間にか「ケア=女の役割」になっているのはなぜ? 女にとって割に合わないはずの選択を「合理的」に見せてしまう社会のからくりを、スッキリと解き明かしてくれます。『なぜ女性はケア労働をするのか 性別分業の再生産を超えて』山根純佳(勁草書房)
 老いをめぐる社会学に関心がある人には必読の論集。個人的ベストは、認知症の家族を介護することの不安に寄り添った木下衆さんの論文。クールで精緻な分析と著者の繊細な優しさが同居した傑作です。
老いをめぐる社会学に関心がある人には必読の論集。個人的ベストは、認知症の家族を介護することの不安に寄り添った木下衆さんの論文。クールで精緻な分析と著者の繊細な優しさが同居した傑作です。『現代思想』2015年3月号特集「認知症新時代」(青土社)
 親を介護する息子たちの語りを通して、男たちが「ふつう」に築いてきた他者との関係が、介護の場面に何をもたらすかを描きます。「男には弱さを認められない弱さがある」と説く、上野千鶴子さんの解説は男性必読。
親を介護する息子たちの語りを通して、男たちが「ふつう」に築いてきた他者との関係が、介護の場面に何をもたらすかを描きます。「男には弱さを認められない弱さがある」と説く、上野千鶴子さんの解説は男性必読。『迫りくる「息子介護」の時代 28人の現場から』平山亮(光文社新書)
 女友だちとの経験を通して、ミソジニーによる分断を乗り越える道を模索する自己省察の軌跡。著者の率直で伸びやかな文章に触れるたび、翻って男が友情を語るときの語彙の貧しさを思い知らされます。
女友だちとの経験を通して、ミソジニーによる分断を乗り越える道を模索する自己省察の軌跡。著者の率直で伸びやかな文章に触れるたび、翻って男が友情を語るときの語彙の貧しさを思い知らされます。『メロスのようには走らない。 女の友情論』
北原みのり(KKベストセラーズ)
■ブックガイドのpdfファイルはこちら→「オトコとケアの見方・変え方」ブックガイドpdf〉

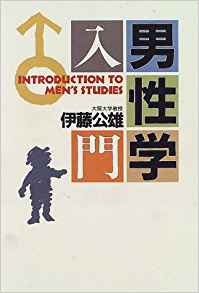 日本の男性学はここから始まった――フェミニズムを受けて立った著者が、男ならではの困難と課題を、ユーモアを織り交ぜながら優しく明快に語ってくれます。
日本の男性学はここから始まった――フェミニズムを受けて立った著者が、男ならではの困難と課題を、ユーモアを織り交ぜながら優しく明快に語ってくれます。