あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
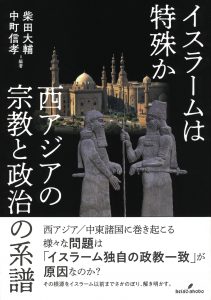 柴田大輔・中町信孝 編著
柴田大輔・中町信孝 編著
『イスラームは特殊か 西アジアの宗教と政治の系譜』
→〈「はじめに」ページ(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報はこちら〉
はじめに
本書の課題は副題に明示した通り「西アジアの宗教と政治の系譜」である。より正確には、西アジアとその周辺地域の歴史における「宗教的なもの」と「政治的なもの」の関わり方の系譜を明確にすることと表現できる。そして、この課題に取り組む背景となる問題意識の一端として、「イスラームは特殊か」という問いがある。このセンセーショナルな主題は何も、単に耳目を引くためだけに付けられたものではない。
本書が取り組む地域は、現在の国名で言えば、イラク、シリア、トルコ、サウジアラビア、パレスティナ、イスラエル、ヨルダン、レバノン、イエメン、イラン、そしてエジプトなどである。より耳慣れた呼称で言えば、近東、中東、そして高校の世界史で習った「オリエント」に相当する地域である。あえてこれらの地域名を避けたのは、「いかにも西欧中心主義の匂いがプンプンする」(常木 二〇一四、二)からだ。近東と中東はそれぞれ英語のNear East とMiddle Eastの訳語であるが、「東」とはヨーロッパから見た方角であり、「近」・「中」はつまるところヨーロッパからの距離を意味する。東アジアを指す極東と同様である。「オリエント」は、「東方」を意味するヨーロッパ諸語のOrient(英独仏)をカタカナで表記した語ではあるが、後述するこの概念自体の政治性に加えて、日本独自の誤用が蔓延っている。現在の日本で人口に膾炙しているカタカナの「オリエント」は前記の国々、特に古代における当該地域を指しているが、ヨーロッパ諸語のOrientはこのカタカナの「オリエント」とは意味が異なる。例えばヨーロッパ諸語のOrientには、現在の国で言えばインド、中国、そして日本も含まれる(ただし、ヨーロッパ諸語のOrient が東洋やアジアの同義語とも言えないことにも注意(1))。日本語カタカナの「オリエント」の用法は日本における当該地域の研究の途上で生じてしまった誤解に由来し、これ以上の誤解を広めないためにも本書では原則としてこの用法を使わない。本書においてオリエントとはあくまでヨーロッパ諸語のOrientをカタカナに置き換えただけの用語であり、従来の日本語カタカナの用法で使う場合にはカッコ付けにして明示する。本書はこれらの地域名称を避け、現在、この地域の歴史研究に取り組む専門家が好んで用いる西アジアを採用した。ただし、エジプトの大半はアフリカ大陸北東部にあり、またイランも国連による地理区分では南アジアに入る。このため正確に言えば、「西アジアとその周辺」ということになる。
さて、この地域の国々がメディアに登場しない日はほとんどない。ただし周知の通り、それは得てして好意的な理由からではない。戦争や内戦など、この地域で日々起こっている様々な紛争に関する悲惨な報道により、この地域は多くの人々の関心を集めている。それは不安と言い換えることもできる。この地域の紛争に端を発した諸問題、すなわち難民やテロリズムが世界に広がり、それがときに一方的な偏見に満ちた表現とともに報じられているからだ。
当然人々は、なぜよりにもよってこの地域にこうも問題が多く発生するのかと疑問を持つことだろう。今では日本でも、このような疑問に答える書籍や記事が数多く著されている。そこでは、巨万の富を生む石油や天然ガスの利権をめぐる覇権争い、様々な民族(エスニック・グループ)の抗争、そしてヨーロッパ諸国によるかつての植民地政策などが紛争の要因として取り上げられているが、それらの問題と並び、頻繁に指摘される要因が宗教問題である。より踏み込んで言えば、政治と宗教の関係をめぐる問題、政教関係、政教問題である。
紛争のファクターとしての現代西アジアの政教関係についても、一般向けの解説から専門的な論考に至るまで多くの著作が数多く出版されているが、それらの出版物は往往にしてこれをイスラーム(教)の問題として論じている(以下、イスラームと呼ぶが、初出で「教」を丸括弧に入れた点に注意してほしい)。また多くの場合、問題の鍵はイスラームの「特殊性」(あるいは「独自性」「性質」「特質」「特徴」など)にあるとされ、そのような「特殊性」がやや紋切り型に語られる。曰く、本来は個人の信仰の問題であり、特に生臭い政治の世界からは切り離されなくてはならないはずの宗教が、イスラームの場合は事情が異なるのだ。イスラームに政教分離の思想や制度はない。イスラームは政治と宗教が一体化した政教一致なのだ。そもそもイスラームは政治だけではなく、司法や経済などのすべての社会・生活領域を包括しているのだ。イスラームは単なるイスラーム「教」ではないのだ。それこそがイスラームに独自の特殊性であり、現在巻き起こっている紛争の一要因がこのように特殊なイスラームの問題にあるのだ。西アジアの紛争を理解するためには、石油利権や民族問題だけではなく、イスラームの問題、その歴史を理解しなくてはならないのだ。否、石油利権や民族問題すらもイスラームの歴史とは切り離せないのだ。表現の使い方は様々だが、大凡このような紋切り型の指摘は本書に関心を持つ読者であれば、誰しもが耳にしたことがあるだろう。
このような紋切り型の言辞は、周知の通り、「イスラーム恐怖症」を扇動する一部の欧米メディアとそれに追随する日本のメディアにより往々にして「暴力」や「狭量」などのような負の価値づけとともにヒステリックに繰り返されている。かつてエドワード・サイードが『イスラム報道』(一九八六[原著一九八一])において批判的に分析したメディアの言説は、今世紀に入りより硬直化していると言えよう。他方で実はイスラームに好意的な知識人・研究者もまた、ときに正の価値(例えば「平和」や「寛容」)を強調しながらも同様の紋切り型の言辞を放っている。前者と後者の論述の内容は全く異なるものの、政治と宗教をめぐるイスラームの問題を安易に「イスラームの特殊性」などと片付けるその語り口は表裏一体と言えるほどに共通している。
現代西アジアの諸問題における政教関係の重要性は確かに疑い得ないが、それは本当に「イスラームの特殊性」などの紋切り型の説明をもって片付けられるものなのだろうか。そのような説明をする我々にバイアスはかかっていないのだろうか。イスラームだけを考察すればそれで十分なのだろうか。そもそも「イスラームの特殊性」は本当にイスラームに「特殊」なのだろうか。本書の課題は、このような疑問を持ちながら、西アジアの政教関係について歴史を遡って考察することである。この問題の歴史的系譜を明確にすることである。我々は、ともすれば看過されがちな次の三つの点に着目して、この課題に取り組む。
第一点は、西アジア史の問題に向けられた現在の「我々」の眼差し自体を批判的に検討し直すことである。「我々」と言ってもここで問題になるのは、現代の日本ではない。現代の日本を含む「西側」世界における思想と制度の「源泉」にもなっている近現代ヨーロッパが西アジアに向けてきた眼差しである。現在の日本の人々による西アジアやイスラームの見方もまた、つまるところ近現代ヨーロッパの制度と言説によって深く鋳造されているからだ。
第二点はイスラームに着目しつつも、イスラーム以前の宗教伝統に遡り政教関係の歴史的系譜を明らかにすることである。西アジアの宗教史におけるイスラームの伝統の重要性は明白であるが、イスラームの伝統は突然「無」から生じたわけではない。イスラームもまた数千年を超える西アジアの歴史を「背景」にして成立した。よって本書は、イスラームに一定の重点を置きつつも、メソポタミアやエジプトに最古の国家が誕生した古代から西アジアがヨーロッパ列強と対峙した近現代までの長いタイムスパンを射程に入れてこの地域の政教関係について考察する。
第三点は、イスラーム誕生後も現在に至るまで西アジアにおいてムスリムと共存してきたユダヤ教・キリスト教の多様な宗教伝統も視野に入れて論じることである。西アジアではイスラームだけではなく、ユダヤ教やキリスト教の伝統も誕生し、これらの諸宗教の伝統は西アジアにおいて受け継がれ現在に到っている。この地域の多様な宗教伝統を課題の範疇に含めることによって、問題の包括的な理解を目指す。イスラームの政教関係に関しても、このようなマクロな広がりの中に位置づけ直すことにより、「イスラームの特殊性」などと安易に片付けられてきたその政教関係の様相を再考する。
* * *
さて、以上が本書の課題であり、あとはこの課題に取り組む本書の構成をまとめれば「はじめに」の役目は果たせたと言えよう。しかし、実はこのような「表の」課題のほかに、右に掲げた三点に着目しながらこの研究に取り組むことを我々が決断した理由が二つある。言ってみれば、学問分野の状況に関わる「裏の」課題である。少し長くなってしまうが、この二つの「裏の」課題について述べさせてもらいたい。
ひとつめは「宗教」(religion)という概念である。先述の通り、本書は西アジアの政教関係を考察する「我々」の視点自体をまず検討し直すわけだが、ここで最も重要な問題になるものがこれである。現代の日本においても「宗教」はキリスト教、仏教、神道、そしてイスラームなどを包括する類概念とみなされており、また人類に普遍的な固有の領域として認知されている。イスラームは単なる宗教ではない、などと論じられる際にも現在一般的に通用しているこのような「宗教」概念が前提になっている。実は宗教学では類概念としての「宗教」/レリジョンの普遍性に疑問が呈され、特に一九九〇年代ごろからはこの概念に関する批判的な検討が重点的に実施された。宗教概念論あるいは宗教概念批判と呼ばれる議論である。この議論の中で現在の「宗教」概念が成立した歴史的プロセスも解明された。この概念が近世ヨーロッパにおいて徐々に形成された後、ヨーロッパの植民地政策の展開によって普遍化するとともにグローバル化し、また「宗教」の「本質」の「解明」に取り組む近代ヨーロッパの学者の言説を通じてさらなる意味づけをなされた様相が詳らかにされた。現在用いられている日本語の「宗教」も、端的に言えば英語のreligionなどのヨーロッパ諸語の翻訳語であり、明治時代に定着した。イスラームの政教関係をめぐる語りの中でもしばしば口にされる、宗教とは本来個人の信仰の問題である、あるいは、政治分野とは切り離されるべき問題である、などという現在の「常識」的な理解も、近代ヨーロッパにおける「宗教」をめぐる議論に由来する。「宗教」概念をめぐる問題は実際にはこのように単純な事柄ではなく、またこの議論をめぐる立場も一様ではない。今も議論は絶えない(詳しくは本書序章第一節を参照(2))。しかし、宗教学に転回をもたらしたこの議論の大まかな内容は現在の宗教学では共通の理解となっており、例えば宗教学の概説の授業においても必ず教示される。しかしながら、この問題に関する知見は宗教学の外部には必ずしも周知されていないように思える。特に、前近代の事象に取り組む研究分野にはほとんど受容されていないと言わざるを得ない。この議論を踏まえたうえで─せめて近代ヨーロッパ的な「宗教」概念の脱自明化だけでもしたうえで─各時代・地域の専門家がそれぞれの専門分野に立脚しながら関連する諸課題に取り組むことは、新たなる論の可能性をもたらし得る。本書はその実験的な試みでもある。
ふたつめは、近現代ヨーロッパと近現代日本において西アジア史研究に取り組んできた学問分野に関する問題である。先述の通り、本書は古代から現代に至る長いタイムスパンを射程に入れたマクロな研究に取り組むわけだが、このような研究の意義はおそらく自明であろう。むしろ多くの読者は、こうした通時的研究の取り組みをわざわざセールスポイントとして大げさに強調する必要性に疑問を持つのではないだろうか。実は理由がある。古代西アジアの歴史研究と中世以降の西アジアの歴史研究の間には大きな亀裂が広がっているのだ。西アジア地域の歴史の研究・教育を包括的に扱う「西アジア史」(あるいは「中東史」)などという学問分野は後述する京都大学の西南アジア史学研究室のような例外を除くと日本には存在しない。確かに日本でも現在では古代や中世、近現代の西アジアの歴史を研究・教育する環境がある程度整いつつあるが、それは時代によって異なる学問分野に分けられている。すなわち、日本の学界において西アジアの古代史研究は「古代オリエント史」と呼ばれる学問分野を形成し、中世以降の方はと言うと、主として「イスラーム世界」の歴史をあつかう「イスラーム(世界)史」の範疇とされ、それを「ユダヤ史」や「キリスト教史」などが補う体制になっている。さらに、日本の大学ではこれらの「古代オリエント史」と「イスラーム(世界)史」が異なる学科において研究・教育されている。史学科の細かい区分がある大学では、「古代オリエント史」の研究・教育が「西洋史」に組み込まれている一方、「イスラーム(世界)史」の方は「イスラーム(世界/文明)史」などの独自の学科がなければ「東洋史」に入る。同じ西アジア地域の歴史を扱う研究分野でありながら、「西洋史」と「東洋史」に分断されているのだ。
すでに杉田英明(一九九五)や羽田正(二〇〇五)によって論じられているように、この「東西分裂」は、西アジア地域の歴史研究が日本において展開する過程で生じた。まとめて言えば、一八九四年に歴史学者那珂通世が外国史を西洋歴史と東洋歴史に二分するよう提案した際、西アジアは「西方アジア」として「アジア」の中に含められてはいたものの、東洋史の研究対象は実質的に中国を中心とする東アジアの歴史であり、また「西方アジア」の歴史はむしろヨーロッパ世界の歴史の理解に資するとされ、「上古東方」と呼ばれた古代も「サラセン」の中世以降も西洋史の片隅に位置付けられた(羽田 二〇〇五、二二三~二二七)。この状況は第二次世界大戦前夜の時代に一転した。日本による大陸進出の過程で、タタール系の「回教徒」すなわちムスリムとの接触がはじまり、一九三〇年代には大川周明らによって提唱されたアジア主義の思想と政策を背景に、「回教徒」の世界「回教圏」を研究する機運が急激に高まった。そして、「回教圏」はアジアの一部、アジアは一つ、日本はそのアジアの盟主たらんとする野望の後押しによって、イスラーム勃興以後の西アジア史は西洋史から東洋史に移籍させられた(羽田 二〇〇五、二二九~二六六(3))。さらに、この政治動向とも連動するように、東アジア史研究者(あるいはその学統)は「西方」へと研究対象を拡大し、西アジアに「たどり着いた」。戦中・戦後直後における中世以後の西アジア史研究第一世代は、東アジアに取り組む東洋史学科において教育を受けたのち、東西交渉などに関する問題意識から中央アジア、そして西アジアへと関心の幅を広げたのだ。一方、イスラーム以前の古代西アジア史はこのような新たな潮流から取り残され、相変わらず西洋史の片隅に据え置かれた。これらの要因により、第二次世界大戦前後に日本における西アジア史研究の「東西分裂」が生じた。その後、京都大学における西南アジア史学研究室の開設(一九六九年)など、「東西分裂」を克服しようとする試みもなされたが、戦後も現在に至るまで「東西分裂」は続いている。
このような「東西分裂」は日本独自の現象だが─そもそも「西洋史」対「東洋史」という二分法自体が日本の歴史学に特異な制度である─古代西アジアの歴史がヨーロッパの歴史の一部とみなされる一方で、中世以降の西アジアの歴史がヨーロッパの歴史からは分離された要因の大元は近代ヨーロッパに求められる。近代ヨーロッパの大学制度において西アジアの歴史や文化、社会の研究が行われた学問分野は、歴史学、言語学、法学、政治学、経済学、社会学などではなかった。これらの学問分野の研究対象はおおむね古代ギリシア・ローマから近現代欧米に至る「西洋世界」の事象に限定された。西アジアの諸課題は、オリエント学(英語はOriental studies、独語はOrientalistik、仏語はOrientalisme)という名前の分野において行われた。日本語では「東方学」、「東洋学」とも訳されるが、本書では原語を単にカタカナに置き換えただけのオリエント学を採用する(前述の通り、日本語カタカナの「オリエント」とは意味が異なることに注意)。オリエント学とは、要するにヨーロッパ以外の「文明世界」を研究する学問であり、東アジアや南アジアの研究もオリエント学に含まれた。文献学を方法論的基礎としながら各「文明」の言語や歴史などが研究された。また、研究対象ごとにセム(語)学、インド学、中国学、そしてイスラーム学、アッシリア学、エジプト学などと細分化された(4)。対して「未開」の社会・文化の研究には、人類学あるいは民族学と呼ばれた学問分野が用意された。
エドワード・サイードが『オリエンタリズム』(一九八六[原著一九七八])において指摘し、その後、多くの識者によっても論じられてきたように、このヨーロッパのオリエント学は近代ヨーロッパの植民地政策と切り離すことができない。サイードらが指摘しているように、オリエント学はその研究対象をヨーロッパによって支配されるべき、ヨーロッパならざる「他者」として鋳造してきた。また、このような近代西洋オリエント学の眼差しはヨーロッパのみの問題に留まらない。例えば、近現代西アジアの知識人によってもオリエント学の視点が受容され、彼らの言わば「裏返しの」自己理解を形成した。
ここで着目したいことは、西洋オリエント学(あるいはその後継学問分野)において古代の西アジアと中世以降の西アジアに向けられた眼差し、そして関心の様態が実は全く異なることである。イスラーム以後の西アジアがサイードらの論じるように「私たち(ヨーロッパ)の歴史」の外側に置かれ「他者化」されてきた一方で、イスラーム以前の西アジアは「私たちの歴史」の最初の一ページとして「我有化」されたのだ(詳しくは、本書序章、第一章第一節、第八章第一節を参照)。日本における西アジア研究の「東西分裂」が生じた過程は如上の通りだが、西アジアの古代史が「西洋史」に位置し続けた原因は、西洋オリエント学による古代西アジアの「我有化」を日本の研究者が無批判に受け入れてきたからに他ならない。
西アジア史研究分野の断絶は研究対象である西アジアの歴史の諸問題そのものに起因しているのではない。近現代におけるヨーロッパと日本の植民地政策、そして少なからぬ誤解と不注意によって招かれたものである。このような事情により生じてしまった「東西分裂」により、西アジア史研究の可能性は大きく損なわれてきた。サイードの『オリエンタリズム』の登場後も、西アジア史研究の分断は等閑にされてきた。確かに現在では地理的な広がりを枠組みにした歴史研究である地域史の意義には疑問も呈されてはいる(例えば、羽田 二〇一一)。歴史学にとっては地域史もまた自明の枠組みではない。しかしながら、特定の地域に着目した歴史研究が重要な意義ある研究成果をもたらしてきたこともまた事実である。最古の文明の誕生から現在の紛争に至るまで、西アジアは人類史を大きく左右してきた。時代によって分断されることなくこの地域に着目した歴史研究分野の創設がもたらし得る研究の成果は疑いようがない。古代から現代までの長いタイムスパン、そして多様な宗教伝統を射程に入れ、異なる時代と地域の専門家が協働で西アジアの政教関係の歴史的系譜を明らかにしようと取り組む本書は、西アジア史研究におけるこの「東西分裂」を克服するささやかな試みでもある。
* * *
これらの「表」と「裏」の問題意識を踏まえ、本書は次の構成にする。まず序章において、近代西洋的な「宗教」概念の何が問題なのか、政教関係の系譜学的研究にはどのようなアプローチが可能なのかを整理したうえで、西アジアを見るヨーロッパの眼差しの問題に取り組む。近現代フランスにおける三人の碩学(ゴーシェ、マシニョン、アルクーン)とその研究を具体例にとりあげ、近現代フランスの学知が「宗教」をどのようにとらえ、西アジアにどのような眼差しを注いでいたのかを検討する。この序章の成果を踏まえたうえで、古代(第Ⅰ部)、古代の終焉期(第Ⅱ部)、中世(第Ⅲ部)、そして近世・近現代(第Ⅳ部)と時代順に政教関係の系譜の研究に取り組む。第Ⅰ部ではメソポタミアやエジプトに最古の文明が成立し、国家が形成され、神殿を中心とする祭祀が行われていた時期の状況に取り組む。つづく第Ⅱ部では、古代神殿が徐々に衰退し、代わって俗に「一神教」などと呼ばれる新たな思想と教団組織が形成された状況に取り組む。第Ⅲ部ではイスラーム誕生のインパクトを受け、新たな社会秩序が構築された後のイスラーム政権とその支配下で繁栄したユダヤ教徒・キリスト教徒の社会の状況に取り組む。第Ⅳ部では西アジアとその周辺地域の大半が強大なオスマン帝国の支配下で統合された近世、そして飛躍的な発展を遂げたヨーロッパ諸国の植民地化の脅威に晒されたのち、ヨーロッパとの対峙の中で国民国家が成立するがグローバルなイスラーム化の中で揺れる近現代に取り組む。本書は、この問題に関心を持つ読者が最初に手に取るハンドブックになることも目指した。よって、各章はまずそれぞれの時代・地域の研究が基づく史料、そして研究の脈絡となる学問分野について簡潔に整理する。そのうえで、それぞれの時代・地域におけるこの問題の概要を提示する。
このように本書は広範にわたる時代と地域の多様な問題を検討する。しかしながら、本書の課題に取り組む上で重要な時代と地域の論考が少なからず欠落していることもまた明らかである。「序章」において後述される通り、政教関係の系譜にとって国家誕生はターニングポイントとみなすことができる。このため論述は国家誕生以前の先史時代からはじめるべきである。また、現在の西アジアの政教問題を理解するうえでも極めて重要な近世と近現代のイランに取り組むチャプターも当然望まれる。本書がきっかけとなり、これらの本書に欠落している時代と地域の研究を含むより総合的な共同研究が進展することを望む。
なお、本書では、キリスト教の立場からの呼称である『旧約聖書』という呼称の代わりに、記述に使用された言語に因む『ヘブライ語聖書』の呼称を用いる。『コーラン』は原語の音に近く、現在では人口にも膾炙している『クルアーン』と表記する。本書に登場する地名は、現在の国名などを除き、本書冒頭の地図に記載した。参照してほしい。
編者
参考文献
Marchand, S. L. (2009) German Orientalism in the Age of Empire. Religion, Race, and Scholarship, Cambridge University Press
アサド、タラル(二〇〇四[原著一九九三])『宗教の系譜 キリスト教とイスラムにおける権力の根拠と訓練』岩波書店
磯前順一(二〇〇三)『近代日本の宗教言説とその系譜 宗教・国家・神道』岩波書店
磯前順一・山本達也編(二〇一一)『宗教概念の彼方へ』法蔵館
姜尚中(一九九六)『オリエンタリズムの彼方へ 近代文化批判』岩波書店
サイード、エドワード(一九八六[原著一九七八])『オリエンタリズム』(今沢紀子訳)、平凡社
――(一九八六[原著一九八一])『イスラム報道 ニュースはいかにつくられるか』(浅井信雄・佐藤成文訳)みすず書房
島薗進・鶴岡賀雄(編)(二〇〇四)『<宗教>再考』ぺりかん社
杉田英明(一九九五)『日本人の中東発見』東京大学出版会
伊達聖伸(二〇一〇)『ライシテ、道徳、宗教学 もうひとつの一九世紀フランス宗教史』勁草書房
常木晃(二〇一四)「西アジア文明学の提唱」筑波大学西アジア文明研究センター(編)『西アジア文明学への招待』悠書館、二~八
羽田正(二〇〇五)『イスラーム世界の創造』東京大学出版会
――(二〇一一)『新しい世界史へ 地球市民のための構想』岩波書店
深澤英隆(二〇〇六)『啓蒙と霊性 近代宗教言説の生成と変容』岩波書店
星野靖二(二〇一二)『近代日本の宗教概念 宗教者の言葉と近代』有志舎
増澤知子(二〇一五[原著二〇〇五])『世界宗教の発明』みすず書房
注
(1) 確かにヨーロッパ諸語のオリエントが特に西アジアを念頭に置いて用いられることもある。例えばドイツ語の「古代オリエント」(Alter Orient)は英語の「古代近東」(Ancient Near East)の意に近く、古代西アジアとその周辺地域における文明世界を指す。また「古代オリエント学」(Altorientalistik)も古代西アジア世界の文献学的研究(特に楔形文字学)に相当する。ただしドイツ語にしても「古代」を冠さない場合のオリエントの意は、英語・フランス語とほぼ同様である。
(2) 日本語だけでも既に多くの関連する書籍(訳書を含む)が出版されている。例えば、アサド 二〇〇四(原著一九九三)、磯前 二〇〇三、伊達 二〇一〇、深澤 二〇〇六、増澤 二〇一五(原著 二〇〇五)、星野 二〇一二。ほか、この課題に関する論文集に島薗・鶴岡 二〇〇四、磯前・山本 二〇一一。
(3) ここには、日本型の「オリエンタリズム」を読み取ることもできる。姜尚中(一九九六、一二一~一四六)が指摘する通り、「西洋史」と「東洋史」に対する関心のあり方、そして研究者の眼差しは異なる。戦前において「西洋史」は模範として学ばれた一方、「東洋史」は支配のために研究された(その傾向は現在もある程度存続している)。すなわち、当初イスラーム以後の西アジアは見習うべき「西洋」の一部であったが、アジア主義の高まりとともに支配すべき「東洋」に移り、古代西アジア(「古代オリエント」)の方は学ぶべき「西洋」の一部に留まったとも言える。
(4) 近代西洋オリエント学の歴史に関しては、例えば近代ドイツのオリエント学に取り組むMarchand 2009が参考になる。なお、サイードらによる批判を受け、多くの欧米の大学は一九九〇年代末から今世紀初頭にかけてオリエント学科を改組した。改組後には、「アジア・中東学科」などの政治的に「正しい」(ように見える)地域名を冠した学科や、今世紀になってドイツで流行している「文化学」(Kulturwissenschaft)の学科など、新しい人文学の枠組みを提唱する学科が創設された。ただし、大きな大学では大枠の「看板」を掛けかえつつも、オリエント学の枠組みは今も継承されていると言って良い。

