あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
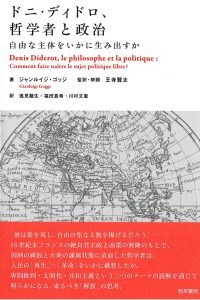 ジャンルイジ・ゴッジ 著
ジャンルイジ・ゴッジ 著
王寺賢太 監訳・解題
『ドニ・ディドロ、哲学者と政治 自由な主体をいかに生み出すか』
→〈「まえがき」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報はこちら〉
まえがき
フランス一八世紀、「啓蒙の時代」を代表する哲学者ドニ・ディドロは、一七一三年に生まれ一七八四年に没している。絶対君主政の盛期であるルイ一四世の長い治世の末期から、一七八九年七月一四日のフランス革命の開幕直前まで、大きな政治の転換期を生き抜いた哲学者ということになる。
二〇一三年はちょうど、このディドロの生誕三百年にあたった。本書には、その年日本に招かれたディドロ政治思想研究の第一人者、ジャンルイジ・ゴッジ(当時ピサ大学教授)が東京・名古屋・京都で行なった三つの講演のテクストが収められている。訪日に先立って、ゴッジは過去三〇年あまりの研究成果の一部を『百科全書から共和主義的雄弁へ De lʼEncyclopédie à lʼéloquence républicaine』(パリ、シャンピオン社、二〇一三)と題された大部の論文集として刊行したが、本書は、その大著を含むゴッジの仕事全体への恰好の手引きでもある。三つの講演のなかで、ゴッジはおもに一七七〇年代のディドロの政治論をとりあげ、テクストの綿密な考証と同時代のコンテクストの再構成を踏まえて、その政治思想の特質に光をあてる。順に「ディドロの政治的言語における三つのイメージ」、「植民地建設と文明化──ディドロによる『ロシアの文明化』論とその周辺」、「最後のディドロと政治的雄弁」と題された一連の講演では、それぞれ「専制批判」、「文明化」、「共和主義の選択と革命の展望」という後期ディドロの政治論の主要テーマが論じられている。
やがて「アンシャン・レジーム」と呼ばれることになる時代の終わりにあって、ディドロはつねにその時々の状況のなかで、その状況のなかから政治について考えた哲学者だった。読者はゴッジによるディドロ政治論の読解から、「啓蒙から革命へ」の転換期にあって、哲学者が同時代の政治にいかに相対し、いかに介入しようとしたかを知ることができるだろう。けれども本書は、啓蒙の時代の暮れ方に一人の哲学者がなした政治的考察についての歴史的証言にはとどまらない。ディドロがさまざまな状況の違いを超えて一貫して問い続けているのは、「解放 affranchissement」についての問い、自由な主体をいかに生み出すか、という問いだからである。
ディドロにとって、この「解放」の出発点となるのは、大多数の人々が隷属状態のもとに置かれている現状である。そこでは、各人が自己の身体も財産も自分の意志にしたがって好きなように用いることが許されず、そもそも所有権自体が保証されない「民事的隷属」のみならず、自分自身が構成員となる政治体で政治に参加することが許されず、統治者の恣意的な権力行使に従属するほかない「政治的隷属」が問題にされる。だから、ディドロが目指す「解放」は、たんに国家権力がもたらす拘束からの「解放」ではないし、そこで生み出すことが目指される「自由な主体」は、所有権を保証され、自分の意志にしたがって自己の身体と財産を用いる個人にはとどまらない。むしろ、そんな個人たちから、恣意的な権力を行使する統治者に対峙し、その恣意を妨げる「対抗力」をそなえた一つの集団的主体を出現させること、さらには統治者を制御するのみならず、自ら自己自身を統治する集団的主体を出現させることこそが目指されるのである。その集団的主体は「人民」とも「国民」とも呼ばれるが、いずれにせよ重要なことは、ディドロにおいて「自由」が、人間集団の「自律」の理想と結びついていること、そして「解放」によって生み出されるべき自由な主体は、なによりも自ら政治権力を行使する主体であるということだ。
ディドロがさまざまな状況のなかで隷属の現状に直面する以上、「解放」の理想はただちに実践的な政治的アクションをめぐる問いと結びつかざるをえない。すなわち、隷属状態のもとに置かれた人間たちに、当の隷属状態のただなかから、いったい誰が、いかにして「解放」をもたらし、自由な主体を生み出すことができるのか、という問いである。そこにはさらに、「解放」のアクションを可能にする歴史的条件はいかなるものであり、そのアクションにはいったいなにがどこまで可能なのかという問いも付随するだろう。自由な主体、自律的主体をいかに他律的に(外からの介入によって)構成するか──ここにはおそらく啓蒙の哲学が抱え込んだ最大の難問がある。ディドロはほかならぬ政治的な次元でこの難問に直面し、その解決策を考えたのだ。二一世紀初頭に生きる私たちにとって、フランス革命が生み出し、資本主義とともに近代世界に拡大した国民国家や代議制民主主義といった制度に対する懐疑や批判は、すでに耳慣れたものになっている。その現在もなお、ディドロの政治論が刺激的でありうるとしたら、それは、あらゆる近代の政治制度の手前にあって、その制度を支えるだけではなく、その制度を内側から揺るがせても来た「解放」と「自由」の理想を実現することの困難に、ディドロが直面していたからである。
とはいえ、なぜ、いまあらためて「哲学者と政治」なのか。一般にディドロは、ダランベールとともに『百科全書』を編纂した人物として、あるいは一八世紀ヨーロッパを代表する唯物論哲学者の一人として知られている。この多才の人はまた、一連のサロン評で近代的美術批評を創始した一人として、あるいは『ラモーの甥』、『ダランベールの夢』、『運命論者ジャックとその主人』といった自由闊達なフィクション作品の作者として、美学史や文学史に確固たる地位を占めている。けれども、こと政治論にかんしては、日本のみならず欧米の研究史においても、これまで必ずしも相応しい扱いを受けてはこなかった。たしかに、この『百科全書』の編纂者には、学問や技術の有用な知識を流布した知識人というイメージがつきまとっている。また、本書でとりあげられる一七七〇年代におけるレナル『両インド史』への寄稿や、ロシアのエカテリーナ二世との対話/対決も、存在だけは古くからよく知られていた。しかし、過去三〇年来ゴッジたちが研究水準を飛躍的に上げるまで、それらの政治論は、啓蒙期を代表する反植民地主義的著作とか、啓蒙専制君主との危うい接近とかいった紋切り型で語られるのがほとんどだったのである。
このディドロの政治論に対する相対的な無関心には、いくつかの理由が考えられる。ディドロの政治論が強く時論的な性格をもち、一貫した政治理論の体系として捉えがたいことが理由の一つに挙げられるだろう。モンテスキューの『法の精神』のような、政治権力の作用を拘束する諸条件を考量しながら各政体特有の機能のしかたを分析し、総体として専制批判を目論む精緻な企てとか、ルソーの『社会契約論』のような、あらゆる正統な統治の根拠として主権者人民の一般意志を置き、その一般意志を貫徹させるための条件を考える理論的考察に相当するものを、ディドロの政治論から引き出すことはおそらくできない。だからといって、ディドロの政治的考察に原理的考察が欠けているわけではない。ディドロはむしろ、政治を一つの閉じた理論体系のなかで処理できない問題としてとらえたからこそ、哲学者として同時代の現実政治に対峙し、「解放」の理想を実現するための具体的な政治行為と歴史的条件について同時代の状況のなかで考え続けたのだ。ディドロはこの点で、フランス啓蒙最大の政治の思考者とさえ言ってよい。
受容側の問題としては、ディドロの政治思想に対する偏見を挙げることもできる。この『百科全書』の編纂者は、往々にしてルソーに対置されながら、人間本性にそなわる社交性を信奉し、社交性の発展の果てに「文明化」の理想の実現を展望する、楽天的な進歩主義者として紹介されてきた。しかしそのとき、ディドロにおける自然的社交性の仮説が、それを展開しさえすれば理想的な社会秩序に到達するといったオプティミズムとは無縁だったことはあっさり無視される。それとともに、社会が自然に存在することと、社会内に紛争が遍在することが矛盾しないからこそ、政治が回避しがたい問題となるというディドロの根本的な前提も看過されてしまうのだ。そもそもルソーと同様、ディドロが直面していたのは、なによりも彼自身にとっての「近代」の終わりであり、すなわちルネサンス期以降、絶対君主政や商業の興隆のもとで進行した国制や習俗の「腐敗」と人民の「自由の喪失」だった。ゴッジも示唆するように、ディドロが私たちの生きる「近代」の始まりを告げる思想家であるとしたら、それは彼が自分自身の生きた「近代」の鋭い批判者であり、その「腐敗」と「自由の喪失」の現状からの「再生」の方策を考え続けたからなのである。
とはいえ、ディドロの政治論が長くさしたる関心を惹かず、偏見ばかりが流布されてきたのにも無理のないところがある。一七六五年の『百科全書』言説篇の刊行後、ディドロが活発に手がけた政治論の主なものが、ディドロ自身の著作として読まれるようになったのは、ようやく二〇世紀後半のことだったからである。もともとディドロは、『百科全書』によって一八世紀フランスを代表する哲学者として知られながら、世紀中盤のヴァンセンヌ投獄以来、自分の名を付して公刊した著作の数少ない人だった。一連のサロン評もフィクション作品の多くも、生前にはわずかに、友人のグリムが編集し、ヨーロッパの王侯貴族宛に手書き写本で送られた『文藝通信』に掲載されたにすぎない。しかし、それらの著作が曲がりなりにも彼の著作として少数の読者に知られていたのに対し、ディドロは政治論を自分の名において公表することにはとりわけ慎重だったし、ディドロの遺稿を相続した彼の子孫たちもまた同様だった。レナルの『両インド史』の三つの版に寄稿された断章群と、ロシア旅行(一七七三-七四)前後に書かれた『哲学・歴史等雑考』(通称『エカテリーナのための覚書』)および『訓令についての考察』について言えば、前者がディドロのものとして認知され、後者の全貌が次第に明らかにされたのは、一九五一年、女婿の家系に秘蔵されていたディドロの手稿・写本群(ヴァンドゥール・コレクション)がフランス国立図書館に寄贈されたことをきっかけに、著作の文献学的研究が進んでからのことにすぎない。これらのテクストについては、現在もまだ、決定版となるべき批評校訂版を準備する作業が続けられている最中なのである。
本書の著者ジャンルイジ・ゴッジは、そのエルマン社版全集の『両インド史』寄稿断章群の責任編集者であり、ロシア政治論の責任編集者ジョルジュ・デュラックとともに、過去三〇年間、後期ディドロの政治論についての知見を飛躍的に豊かなものにしてきた学者である。両者とも、詳細な文献考証と歴史的実証から出発して、ディドロをとりまく同時代の政治状況を再構成し、背景となる汎ヨーロッパ規模の哲学的・政治的議論を踏まえて、ディドロ自身の立場を明らかにする手法において一致している。ゴッジの場合はさらに、ディドロをルネサンス以来の近代政治思想史のなかに位置づけてみせるところに大きな特徴があるだろう。ゴッジの仕事は、ホッブズやスピノザと一八世紀の唯物論哲学の関係や、フランスとスコットランドにおける啓蒙期の歴史叙述に及ぶ視野の広いものだが、その原点にはつねにディドロと『両インド史』に対する旺盛な関心があり、本書の一連の講演もいずれも哲学者が『両インド史』に寄稿した断章を中心に据えている。ゴッジの経歴や研究の背景についてはあとがきに譲ることにして、ここではレナルの『両インド史』を中心に、本書で論じられるディドロの政治論の時代背景を簡単に紹介しておこう。それはおのずと、ゴッジのアプローチがなにに由来するかを示すことにもなるはずだから。
現在、フランス語の批判校訂版と相前後しながら邦訳も刊行されつつある『両インド史』という書物は(1)、公式の著者をギヨーム=トマ・レナル、正式の表題を『両インドにおけるヨーロッパ人の植民と商業についての哲学的・政治的歴史』という、啓蒙期のフランスを代表する歴史作品である。レナルの生前には、一七七〇年の初版(刊行は七二年)、七四年の第二版、八〇年の第三版と増補改訂を続けている。表題の「両インド」は、喜望峰からアフリカ東岸・アラビア半島・インド洋沿岸を経て中国・日本にいたる「東インド」と、喜望峰からアフリカ西岸を経て南・中・北アメリカ全域を覆う「西インド」を指す。つまり『両インド史』とは、一五世紀末の大航海時代以来、アメリカ合州国が独立を宣言してイギリスと戦争(一七七六-八三)に入るまでのヨーロッパ諸国民の盛衰を、植民地主義と商業の世界規模の拡大を中心に据えて描く特異なヨーロッパ近代史の書物なのだ。このアンシャン・レジーム末期のベストセラーは、英語・オランダ語・ドイツ語など各国語にも翻訳されて、同時代の大西洋両岸で広く流通した。
レナルは世紀半ばからフランス外交当局の近傍にあって、パリの論壇の中心に位置した歴史家であり、ジャーナリストであった。ただし、八折版で初版六巻、第二版七巻、第三版十巻を数える『両インド史』の執筆にあたって、レナルはヨーロッパ各国の外交官・植民地官僚・知識人から情報提供を受け、複数のパリの哲学者たちに匿名で協力を求めている。そのうちもっとも有名な協力者がディドロである。このディドロの寄稿は版を重ねるごとに質量を増し、第三版では、あるときはレナルが書いた本文に寄り添い、またあるときはそれに異を立てるかたちで、この書物の各所に挿入されている。しかし『両インド史』の多声性は、たんにこの複数の執筆者の存在によるものだけではない。レナルは先行する歴史書・旅行記・行政文書・政治経済論・哲学書・定期刊行物の記事から小説まで、膨大な源泉資料を踏まえ、それらの資料を突き合わせてこの書物を綴っているからである。
この歴史書の誕生をうながしたのは、一七六〇年代後半、七年戦争(一七五六-六三)でアジア・アフリカ・アメリカを舞台とするイギリスとの海外覇権の争奪戦に敗れたフランスにおける通商・植民地政策の練り直しの機運だった。議論の焦点は、東インド貿易はインド会社の独占とし、西インドのカリブ海植民地には宗主国との排他的通商を強制する、いわゆる重商主義体制の改革である。そこでレナルたちは、フィジオクラット(重農主義者)以下、「商業の自由」を声高に要求した一群の政治経済学者たちと一線を画し、重商主義体制の漸進的緩和を求めた。彼らはまたその議論の過程で、スペインのアメリカ征服や、カリブ海植民地における黒人奴隷の現状にも批判の目を向けることになる。同時期、フランスに劣らず多大な債務を抱え込んだイギリスでは、インドにおけるベンガルの植民地化の開始とともに、北アメリカ植民地と宗主国のあいだで課税をめぐる紛争が勃発していた。「アメリカの革命」(レナル)にいたる動乱の始まりである。レナルが七〇年代を通じて『両インド史』の増補改訂を続けた直接の原因は、この同時代の「両インド」の政治的動揺にあったのだ。
しかし、動揺はヨーロッパのなかでも大きかった。そもそも七年戦争は、ルネサンス以来のハプスブルグ家とフランス王家の対立に終止符を打ち、イギリスとフランスの対立をヨーロッパ列強の勢力均衡の中軸に押し上げた国際関係の大変動を発端としている。この戦争後、北方の新興国家であるフリードリッヒ二世のプロイセンとエカテリーナ二世のロシアは、七二年にはオーストリアとともにポーランド第一次分割に踏み切った。他方、戦争をきっかけにカトリック諸国から追放されたイエズス会は、七三年にはローマ教皇によって解散を命ぜられる。ちょうどルイ一五世治世末期のフランスでは、宰相モープーによる高等法院の強制的改組が、王国の国制を損なう専制政治の典型として哲学者・政治経済学者たちに一斉に批判された頃である。その後、七四年にはルイ一六世即位とともにテュルゴが財務総監となり、財政再建を期してふたたび国内の政治経済改革に着手するが、その成果も出ないまま、七六年からはジュネーヴ出身の元銀行家ネッケルが、イギリスに対する報復を目指して合州国独立戦争に参戦した王国の財政を切り盛りすることになった。皮肉なことに、一七八九年にネッケル自身が主導する三部会招集は、この戦争当時、公債を乱発して王国財政がいっそう悪化したことを遠因としていたのである。
「ヨーロッパにおけるアンシャン・レジームの終わり」(フランコ・ヴェントゥーリ)の政治的動揺のただなかで変貌を続けた『両インド史』は、征服の暴力や黒人奴隷制のみならず、ローマ教会の世俗権力への容喙やヨーロッパ諸国の専制にも激しい批判を加える一方、「アメリカの叛逆者たち」に熱烈な支持を与えて、そののち啓蒙の哲学のもっとも急進的な政治批判の書と目されることになる。ただし、『両インド史』をたんに「植民地世界の百科全書」とか、同時代の政治的クロニクルとしてとらえただけでは不十分だろう。それは同時に、同時代の政治的動揺を一五世紀末以来の歴史的変動の帰結として位置づける、ヨーロッパ近代史でもあったからである。実際、ヨーロッパ近代の特質は、この書物のなかで古代や中世と対比されるだけではなく、ヨーロッパ外の「野生状態」や諸帝国との比較を通じてくりかえし問われている。そこでレナルやディドロがヨーロッパ近代の特徴とみなしたのは、主権国家分立体制と主要各国における君主政の確立、そして商業の発展に伴う農奴解放の進行と、そうして生まれた人民の経済的・政治的権力の伸長だった。それだけならいかにも啓蒙期に特徴的な「文明化」擁護論にとどまるのだが、『両インド史』の最大の特徴は、この「文明化」につきまとう不安を喚起し続けたところにある。主権国家分立体制はつねに戦争の脅威と隣り合わせではないか。軍事と財政の権力を独占した絶対君主政は専制にほかならないではないか。また商業の発展のもとで、人々は政治的自由を犠牲にしてまで私的利害の追求に走り、国家さえもが経済的利益の追求に走って世界規模の「商業戦争」を惹き起こしているではないか。『両インド史』において、ディドロが最終的に「解放」の要求を突出させることになったのは、ヨーロッパ発の主権国家と商業資本主義のネットワークが世界を覆い尽くしつつあった時代にあって、ヨーロッパ近代の遺産を踏まえつつ、その近代がもたらした政治的行き詰まりを打破する鍵をそこに見出したからだった。
しかし、対象の大きさ、作品自体の変貌、複数の匿名執筆者の存在、源泉資料の膨大さのどれをとっても、『両インド史』という書物について一貫したヴィジョンを提示することは容易なことではない。ディドロ執筆の断章をとっても、ヴァンドゥール・コレクション所蔵の一連の資料のほとんどは女婿が集成した『両インド史』第三版の抜粋にすぎず、そこに含まれない断章や、初版・第二版に挿入されたと思しき断章の大半については、ディドロの他の著作や同時代の証言と照らし合わせて、ディドロが執筆したかいなかを推定するしかない。だが、ひとたびその労多い作業をくぐり抜ければ、そこからディドロと同時代の哲学と政治についてこの上なく豊かな知見が得られることは察しがつくだろう。過去三、四〇年間、ゴッジが辛抱強く続けてきたのはまさにそんな仕事だった。
本書の三つの講演でゴッジがとりあげるディドロの政治論の主要テーマは、どれも一七七〇年代の政治的動揺のいずれかに対応している。最初の講演で焦点となる「専制批判」は、ルイ一五世の治世末期の「モープーのクーデタ」を背景とする議論であるし、第二の講演で論じられる「ロシアの文明化」は無論、ロシアに現れたエカテリーナ二世がディドロに庇護を与え、ディドロ自身がロシアに旅行して、実際にこの啓蒙専制君主と対話/対決したという事実と切り離せない。最後の講演で中心的テーマとなる「共和主義の選択と革命の展望」も、一方ではルイ一六世治世初めのフランスにおけるテュルゴの政治経済改革の失敗に、他方ではアメリカ合州国独立を支持したイギリスのイデオローグたちの雄弁に触れることなしにはありえなかった。けれども、ゴッジはこうした政治的コンテクストを明らかにするだけでなく、ディドロが用いるイメージや概念をとらえて、そこに含意された同時代の哲学的・政治的言説に対する哲学者の態度決定を明らかにし、この哲学者独自の思想を引き出そうとする。その読解はまた、同時代の公共空間からは隠れることの多かったこの哲学者が、フランス、スコットランド、イングランド、北アメリカに及ぶ広域に流通した同時代の言説にどれほど深く身を浸していたかを示してくれるだろう。
しかし、ゴッジによる読解の最大の魅力は、ディドロが下敷きにしているルネサンス以来の近代ヨーロッパの政治思想の地下水脈を掘り起こすところにこそある。その際、ゴッジが強調するのは、ディドロがマキァヴェッリ以来の古典的共和主義とロック的な僭主弑逆論、「政府の解体」論を独特なやりかたで折衷していること、またその折衷が、絶対君主政の最大の理論家ホッブズへの敵対を含意していることである。ただし、ゴッジがディドロに見る古典的共和主義は、J・G・A・ポーコックが言うような、共和国内の諸身分の勢力均衡の維持を目指すものとは異なっている。むしろ、いかなる政治体もそれを構成する人間たちなしにはありえない以上、あらゆる政治は政治体を構成する人間たち自身の手に委ねられるべきであるという主張にこそ、ゴッジは共和主義の核心を見てとるからだ。
ゴッジのディドロ読解において、政治体を形成する人間たちの集団的な主体性が重要な問題となるのも──一八世紀の用語で言えば「習俗」の問題である──、ディドロにおける「マキァヴェッリアン・モーメント」が容易にロック的な僭主弑逆論と結びつけられるのもそのせいである。
この古典的共和主義とロック的僭主弑逆論を理論的な基礎として、ディドロはさらに、現存する専制のもとで、隷属状態のただなかから、いかに自由な政治的主体を生み出すかという問いを立てる。まさにこの点で、ディドロは「隷属状態にあって、習俗を腐敗させた人民はどのようにして自由を取り戻すことができるか」というマキァヴェッリ的な問いをふたたびとりあげるのである。「ロシアの文明化」を扱う第二の講演と、「政治的雄弁」を扱う第三の講演は、この問いに対するディドロの二つの異なる回答について語ることになるだろう。一方で、専制国家ロシアにおける農奴解放のためには、ディドロはエカテリーナの試みを支持しながら、西ヨーロッパの自由民による開拓植民地を建設し、植民者に土地所有を保証し、この植民地を起点としてロシア全土に徐々に経済的発展をうながすことを主張する。ヒュームがヨーロッパ近代の生成過程に見出した歴史の発展図式を踏まえた政治的提言である。他方、アンシャン・レジーム末期のフランスにおいては、ディドロは同時代のイギリスの大衆政治運動や「アメリカの革命」に触発されて自ら政治的雄弁を選択し、この雄弁を介して「騒擾に満ちた共和国」というマキァヴェッリ的理想をフランスの公共空間に復活させようとする。ディドロにとってそれは「血の海」のなかでの、あるいは「長い革命の連続」を通じた「腐敗した国民の再生」の先駆けとなるはずのものだった。
そのときディドロは、一方では専制君主その人を、他方では雄弁な哲学者を、「解放」をもたらす政治行為の主体とみなしている。しかし見逃せないことは、いずれの場合にも「解放」のためのアクションはけっして隷属状態にある人間たちに「自由であることを強制する」(ルソー『社会契約論』)ことなく、あくまでもその人間たちが自らを解放する長い歴史過程を発動させるきっかけにとどまることだ。専制君主にせよ、哲学者にせよ、「解放」を目指す主体にできることは、「自由の酵母」を散種することにすぎない。その「酵母」が発酵するには、あらかじめ予測することのできない時間の経過が不可欠なのだ。ゴッジが示すように、ディドロは最終的に専制君主のイニシアティヴによる「文明化」の可能性に懐疑を深めてゆき、内戦の暴力とも裏腹な、政治体の死から再生へのヴィジョンに最後の希望を託すだろう。だからといって、ディドロは「自由の酵母」を散種することをやめようとはしなかったし、その「酵母」がいつの日か、紛争に満ちた過程を通じて、自己を解放する人間たちのなかで「発酵」するかもしれないという可能性を断念することもなかった──ディドロ最晩年の政治論は、政治行為と歴史過程の交点で、そんなオプティミズムとペシミズムの交錯を見せる。まさにその交錯において、ディドロは一つの「近代」の終わりから、もう一つの「近代」の始まりを告げるのである。
ゴッジのディドロ読解はこうして、最終的に、「解放」の政治行為の可能性と限界に読者を直面させる。そのとき同時に、ディドロとともに、歴史の過程こそが、無数の人間たちが主体となり、互いの相克を通じて新たな政治秩序をつくりあげる特権的な舞台となったことが明かされるのだ。おそらくはこの野放図な歴史の開けを示したところに、ディドロの政治論の到達点があるだろう。だが、ディドロが逆説的なやりかたで始まりを告げた「近代」も暮れ方に近づいているように見える現在、歴史の過程はふたたび新たな政治的主体を、新たな政治的集団を出現させてくれるだろうか。そんなことがありうるとすれば、私たちはそのためにいったいなにを、いかになすべきなのか。ディドロの後世においてディドロを読むことは、そうやって、この哲学者の問いを私たち自身が異なった状況のなかで反復することとも無縁ではない。
王寺賢太
(1)Guillaume-Thomas Raynal, Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes, Fernay-Voltaire, Centre international de lʼétude du 18e siècle, 2010-, 5 vol. prévus, 1 vol. déjà paru (avec lʼatlas) ; ギヨーム=トマ・レーナル『両インド史』大津真作訳、法政大学出版局、二〇〇九―、三巻既刊。

