あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
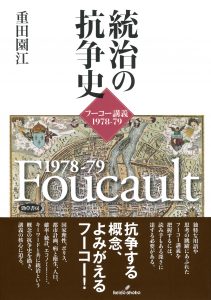 重田園江 著
重田園江 著
『統治の抗争史 フーコー講義1978-79』
→〈「あとがき」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報はこちら〉
あとがき
ミシェル・フーコーになぜこんなにも魅了されるのか。この本を書きながら、私はその理由を何度も再発見した。彼の哲学的なテーマは、近代という時代がいかに複合的で重層的に作られてきたかを示すことであり、同時に近代が数多くの人間の生をわしづかみにしてきた、そのあり方を示すことでもあった。
近代とは、人間の数と格闘し、数の多さを利用し、その欲望を煽って膨張させつづける時代である。欲望の膨張を通じて支配が貫徹する。フーコーはその過程を執念深く、また力強くたどる。彼は権力と統治を描いているようでいて、実はその裏側に、対象となる人々の生を密かに再現しているのだ。掌握される人々、数としてカウントされる人々、欲望をかきたてられ、自己満足と自己膨張をくり返す人々。また、他者の欲望充足のために利用され、あるいは邪魔になり排除される人々、周縁化され抹消され忘れ去られた人々のうめき声の残響を描写するのだ。
横浜のランドマークタワーというところから地上を眺めたことがある。高さのせいで、曇りがちの日には上層階は靄というか雲の一部にかくされた状態になる。文字通り天空のタワーだ。エアコンの効いた最上階でソファに座って下を眺めることができる。再開発によってどこの国のどの時代にいるのか分からなくなるような建物が立ち並ぶ湾岸地区。巨大観覧車のイルミネーションには季節に合わせたキャラクターや色とりどりの図柄が踊っている。洋風とコロニアル風を合わせたハリボテのような結婚式場のライトアップ。渋滞する車のランプの帯。埋め立て地のあいだの水場を行き交う船もピカピカの電飾をつけている。よく見ると蟻のように動く無数の人々の姿。光だらけの人工空間と人の群れ。
近代は欲望を刺激することで欲求対象をつぎつぎと生み出し、人々は貪るようにそれを消費してきた。地面を穴ぼこだらけにしてエネルギーを地中から取り出し、それを使用して大気を熱しつづける。欲望の放出は熱の放出でもある。気候は変動し地球は熱くなる。湾岸に達した欲望は海辺をべたべたと埋め、地形をかえてしまう。こうして作られた「海の風景」が人を吸い寄せ、欲望が水辺に漂う。
ダヴィッドの「雲海の旅人」には、切り立つ頂から自然の雄大な奇蹟を眺める黒い服を着た男の姿がある。カントが描写し、ニーチェが揺さぶられた崇高の風景。ランドマークタワーから見えるきらきらした都市は、手の届かない崇高を拒絶することによって作られている。そこにあるのは、頑強に見えながらすぐにも溶け出しかねない、欲望が具現化された街並である。夜景、イルミネーション、都市の灯り。夜の明るさは人間の欲望を視覚化し、その品位の欠如と影の忘却を示す指標である。いまの都市は明るすぎる。
フーコーが描くのは、横浜においてはアジア的模倣によってグロテスクの域に達した、近代が作られてきたプロセスである。君主の統治、国家理性、ヨーロッパの競合空間、ポリス、そして都市計画、公衆衛生、人口統計、経済学、市民社会。これらはうごめく人々をわしづかみにする技術であり、また複合的な近代を組み立ててきた部品の一部でもある。そしてそこにつねに幾多の人間たち、人の群れがいる。人々は競い合い、欲望を肥大化させ、満足を得るための新奇な回路を探し求める。模倣されたアジアのポストモダン都市を高いところから眺めるときに見えるのは、近代、その欲望、欲望を生み出しそれによって駆り立てられる統治のテクノロジーの果てにある、それらが凝集した姿である。そこには、伝統や古きもののひずみと不協和を壊しながら、その時々の欲望をぺたぺたと上塗りしてきた都市がある。ここに至るまでにどんな犠牲が払われ、どのくらいの風景と自然と人々が住まう場所を奪われ、消滅させられ、変形され、そして忘れ去られたのだろうか。近代が目指したもののフェイクが、痛ましいほどの毒々しさをはらんでそこにある。フーコーを読むとそのことが少しずつ、しかしおそろしくも哀しい姿で迫ってくる。
フランス一七世紀についての文献を参照していると、しばしば「偉大なる世紀le grand siècle」という表現に出くわす。一七世紀がフランスにとって最も偉大な時代であったことは、さまざまな意味で自明なのだろう。フーコーはこの時代、つまり彼が古典主義時代と呼ぶ時代を起点として、近代の姿を描いてきた。偉大な世紀の欲望の行き着く先に、自由という最も安上がりなエネルギーによって駆動され膨張をつづける現代の統治がある。膨張の先の未来になにがあるかは分からない。しかしいまのところ、私たちは近代が発明したものに代わる統治の技法を知らないままである。
他者の欲望をコントロールし肥大化させて利用するのが、偉大なる世紀以来の統治者の慣わしであるなら、それに対抗するのは、自己の欲求を制御し、それと向き合うことを通じて他者と関わる、そうした自己統治でしかありえないということだろうか。一九八〇年以降のフーコーの「転回」は、統治性についての研究からはこのように位置づけられる。
アジア的ポストモダン都市がなんの衒いもなく無邪気に輝く近未来へと突っ走るのに対して、フランスの石畳の街は、こうした欲望を重苦しい灰色の街並みの下に隠している。二〇一八年三月に明治大学から特別研究費を得て出かけたフランスでは、本書をめぐっていくつかの新たな発見もあった。パリの下水道網の歴史を実際の下水道を見せながら示す「下水道博物館」では、薄暗がりの中すぐ下を流れる下水の轟音とともに、水道事業の難しさと危険、水道鉱夫たちの奮闘、また「下水道の英雄」ベルグランの肖像を見学した。下水道事業に情熱を賭し、死してなお下水のそばのじめじめした暗がりに銅像が建つというのも不思議な運命である。
トゥールから小さな支線の各駅停車の終点シノンで下車してリシュリューに向かう際には、駅前になにもなく、駅の窓口すら閉まっていてタクシーも呼べず途方に暮れた。一時間待ってタクシーに乗りこみ、三〇分かけてリシュリューの街の入口に着いたときには、見事なまでに左右対称の市門からの眺めに感歎した。リシュリューは街の対称性に比して城の庭園は部分的に方形と半円との組合せが見られるものの、それほど技巧的ではなく、どこまでもつづく芝生は広々としていた。庭園の入口に肖像画でよく見るのと似た顔のリシュリューの立像がある。半身を夕陽に輝かせていたこの立像もまた、なにを思って高いところから寂れた翳りある街を見渡しているのだろう。
ナントでは暗渠となった運河のあとをトラムが走り、往時の栄光を伝える旧フェイドー島のブルジョア邸宅群の傾きに、この土地の地盤の弱さと砂地であったことが思い出された。ナントには二〇一二年にヨーロッパではじめて作られたという「奴隷制廃止記念館」があり、この街の富の薄暗い起源を記憶にとどめようとしている。右岸に見られる伝統的な建物や城そして石畳の街並と、ナント島から左岸に広がる二〇世紀的な建築との異質性が、街の発展史を物語るようであった。
圧巻はグルネーの故郷サンマロで、海にそびえ立つ市壁とその中にひときわ高い教会の塔、そして石造りの建物と石畳の舗道は、街全体が軍事要塞あるいは空母のように美しかった。西側の城壁の外に広がるひなびた漁港と、東側の長い海岸線を埋めるドーヴィルにも似たマリンリゾート地の全体が、街の色彩を変化に富んだものにしている。それらが一体となって、威厳に満ちていながら開放的な街を形づくっていた。第二次世界大戦で壊滅的な打撃を受けた都市を再建したとは思えない、時間が止まったかのような市壁内の都市風景だけでなく、かもめが飛び交う港の情景は、やはりこうしたところから商業の自由の思想が海風に乗ってやってくるのだと納得させられた。とりわけ夜には、満天の星と石造りの街の組合せに心を動かされ、グルネーのこだわりのない人づきあいやパーソナリティもまた、サンマロの気風から来たのではないかと想像した。
二〇一一年に書いた『連帯の哲学Ⅰ』のつづきを書くつもりで構想を練りはじめたのが、本書のはじまりである。最初の一章でフーコーを取り上げようとしたのだが、途中でそれが一冊の本の重さになっていることに気づいた。本書はそのようにして生まれた。
偶然生まれたと言っても、私がこれまで書いたどの本よりも長い経緯がある。大学院入学当時、修士論文に満足できなければ研究者を諦める以外ないと考えていた。約二年後の一九九五年一月に修士論文「ミシェル・フーコーの統治性研究」を東京大学大学院に提出し、そのテーマが今回の本のはじまりになっている。修論に満足したわけではないが、そこで長期にわたって考察すべき研究対象を見出した。その後はイアン・ハッキングの影響を受けて確率・統計史と現代の統治へ、また政治思想史そして社会連帯へと関心が広がっていった。そうした中でもフーコーについては少しずつ書き、考えつづけたが、結局博士論文としてまとめる機会をもたなかった。
今回思いがけず運が降ってきたため、私にとってこの作品は二〇年遅れで書いた博士論文のようなものである。研究は自由にやるべきで、修論から博論へと数年間で二つの大きなアウトプットを義務づけられるいまの大学院の仕組みにはずっと疑問をもっている。それなりに仕事をまとめることができても、その先に大きな構想を抱けないのではないかという思いからである。私はやりたいようにやってきて、今になってこの本をまとめられて幸運である。
寄り道に見えたこれまでのさまざまな勉強や興味関心、また大学での講義の準備なども含め、今回の本で役に立たなかったことはなに一つないように思う。それくらいフーコーの関心は広く、こちらが注意して読めば深く掘り下げうる可能性をいたるところに秘めている。一行一行読んでいきながら、その着想の豊かさと思わぬところを関係づけ全体を結びなおす思索の力に圧倒された。これまで二年の講義を誰よりも聞き、読んできたつもりでいたが、すべてが新しい発見の連続だった。私はまたフーコーに魅了された。そしてこんな長い本を読ませておいて恐縮なのだが、本書での読みはまだまだ雑だと思う。
博士論文を書かずにおいたのは、いつか統治性について書くべきときが来るという思いもあったからだ。書いてしまうのがもったいないという気持ちもあり、またフーコーだけを読んでも出てこない視野で、統治について捉えられる日がやがて来るだろうと漠然と考えてもいた。今回は想像していたのとは違ったきっかけがあった。というのは、本書での私の書き方を決したのは、自分の中のアイデアでも蓄積でもなく、資料収集が飛躍的に容易になった昨今のネット事情によるからだ。
フランス語の書籍や雑誌論文のネット上での検索の性能は、フランス国立図書館のプロジェクトであるガリカgallica などのおかげで、修論を書いたころとは比較にならない水準に達している(ガリカは一九九八年にはじまったフランス文化政策の一大プロジェクトである。服部麻央「フランス国立図書館の電子図書館Gallica の二〇年」『カレントアウェアネス』三三三号(二〇一七年)、五─七頁参照)。著作権が切れた古いものほど検索にかかり、いまでは一七世紀の貴重書の初版の数々をオンラインで読むことができる。ネット検索の充実ぶりは、家に大図書館を持つに匹敵するものになっている。日本語・英語を含めネット上で読むことができる資料はここ一〇年で急速に充実してきている。たとえば一六世紀の法王庁初の禁書目録が図像でネットに上がっているのには驚かされた。
こうした古い貴重な資料がアクセスしやすいのに対して、新しい著作の多くはネット上では読むことができない。それについては大学図書館ネットワークを活用し、日本中の大学が所蔵する著書や論文を閲覧することができた。明治大学図書館スタッフの方々には、この一年で百冊近くの本を全国の大学図書館から借りていただき、ほんとうに感謝している。閲覧した著作の中には、筑波大学に二宮宏之氏が寄贈された本がいくつもあり、他では手に入らないそれらの本に助けられた。
フーコーが言及したテーマやトピックのいちいちについて、関連文献を探索し紹介するという本書のスタイルは、こうした環境によって生まれた。しかし、読み物としての取っつきやすさと資料や情報としての価値との両立は難しい。本書では前者がある程度犠牲になったと思う。それでもやはり、フーコーの講義録を読む際の辞書のような著作というのはこれから先もあまり書く人はいないだろう。またこうした書き方でしか伝えられないおもしろさもあると考えている。
筑摩書房から出ているフーコー講義録を読むための著書を勁草書房から出版することになり、また勁草書房の『連帯の哲学Ⅰ』のつづきにあたるテーマの一部は、ちくま新書の『社会契約論』に書いた。ちぐはぐになってしまったが、予想外に書くべきときがやってきて、どちらも書いてしまった。こうした気まぐれなやり方を寛大にも許容し、前著以来七年間も続編を待ってくれた(そして続編にならなかった)勁草書房の関戸詳子さんには、ずっと世話になってきた。はじめて会ったときは編集者になったばかりだった彼女は、いまではどのような本をなぜ作るかに関して明確なヴィジョンをもつ優れた編集者となり、横道に逸れがちな私を軌道修正し、いつもあたたかく見守りまた後押ししてくれた。不思議なことに、関戸さんはとても几帳面なのに計画どおりにいかないことをいつも許してくれるのだ。計画することに窮屈さと恐怖を感じ、目次すら作らず作っても反古にして本を書く私の手法(とは言えなそうだが)でも、いつか大きな作品が生まれるとなぜか信じて待ってくれた。
また、そもそも明治大学から一年間のサバティカルを与えられなければ、こうした集中力のいる研究をまとめることはとうていできなかった。明治大学に奉職し一九年が経つが、つねに恵まれた環境を与えてくれることに感謝する。
本書をめぐってはさまざまな方にお世話になった。ヨーロッパの観念について、同僚の川嶋周一さんに文献をご教示いただいた。木村俊道さんはベイコンについて、大久保健晴さんは日本における国家理性の語について、突然の問いかけに親切に応じてくださった。また、人口の誕生については森政稔さんとの共同研究会で報告する機会をもった。そのとき森さんがマルサス思想を「裏返しのモラル・フィロソフィー」と評されたことが、人口学と神学について改めて考えるきっかけとなった。ルソー全集に人口についての断章があることは、卒業生の白根薫くんが教えてくれた。コンディヤック『商業と統治』とルソーにおける市民社会や文明についても彼に教わった。ルソー読解全般については、飯田賢穂さんからとても大きな刺激を受けた。同僚の前田更子さんは、日本におけるフランス近代歴史学研究の動向を教えてくださった。カントの「統整的」理念のイメージについては、網谷壮介さんから助言を受けた。また、ダランベールの確率への懐疑的態度や関連文献について、隠岐さや香さんから貴重な意見と文献についてご教示いただいた。安藤裕介さんからは、フランスでのエコノミーポリティーク研究の動向について教えていただいた。とりわけ隠岐さんと安藤さんの著書からは、関連部分について本書の構想自体が大きな影響を受けている。また、本書の刊行直前に西迫大祐『感染症と法の社会史─病がつくる社
会』(新曜社、二〇一八年)が出版された。同書は病、衛生、確率そして統治などをキーワードに近代パリを描いており、本書と重なるテーマを扱っている。とくに病の表象と統治をめぐって、本書で十分掘り下げられなかった点にも分け入っている。そして、非常に悩ましいアンシャン・レジーム期の官職や法律についての訳語は、高澤紀恵先生にご教示いただいた(個々の訳語について逐一うかがったわけではなく、思い違いや訳し間違いはすべて著者の調査不足によるものである)。他にもたくさんの人たち、とくに明治大学の学生たちとの熱く楽しい交流がつねに私を励まし、勇気を与えてくれた。
分厚く難解になってしまった本書を、できるだけ多くの読者に手にとってもらうため、財団法人櫻田会からの出版助成を受けた。学術書の出版事情が厳しい中、こうした援助の存在は心強い。
この本を、自由に考えたいと願うすべての人に捧げたい。自由奔放な一人の思想家と向き合い対話しながら、好きなように考えつづけることの喜びを、多くの人と分かち合うことが著者の第一の望みである。

