あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
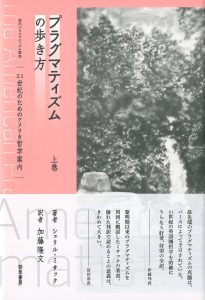

シェリル・ミサック 著
加藤隆文 訳
『プラグマティズムの歩き方 21世紀のためのアメリカ哲学案内(上・下)』[現代プラグマティズム叢書]
→〈「訳者解説」(pdfファイルへのリンク)〉
→目次・書誌情報はこちら:〈上巻〉/〈下巻〉
訳者解説
上下巻から成る本書は、Cheryl Misak (2013) The American Pragmatists (Oxford University Press)の全訳である。著者シェリル・ミサックの活動の詳細については、ぜひご本人のウェブサイト(https://www.cherylmisak.com)を確認してほしい。上巻に収録した「日本語版に寄せて」でも述べられているように、彼女は本書を上梓したのち、フランク・ラムジーの業績を、そのプラグマティズム的な側面に着目して解釈し直す研究をおこなっている。本書から直近のラムジー研究にまで通底して見られるミサックの態度は明快である。きわめて大づかみに言うと、リチャード・ローティをきっかけに人口に膾炙したようなプラグマティズム史観を問い直し、分析哲学と協働しながら発展してきた思想潮流としてのプラグマティズムの姿を世に示すという態度だ。
一九七〇年代から八〇年代にかけてローティが分析哲学からの離脱とプラグマティズムの再興を主張し、いわゆるネオプラグマティズムに注目が集まった。その傾向は、ローティの弟子であるロバート・ブランダムをはじめとする現代の論者たちに引き継がれ、二十一世紀に入った今、ある部分はローティ思想を受け継ぎつつ、ある部分はそれから距離を取りながら、それぞれに興味深い(ネオ)プラグマティズムの論考が展開している。ミサックは、こうした議論状況を把握した上で、ローティ的な思想傾向を踏襲する(とミサックが見なす)現代のネオプラグマティズムからあえて距離をとり、自身がコミットする立場を「ニュープラグマティズム」として打ち出している。ローティは、分析哲学が支配的である英語圏哲学の状況を憂い、プラグマティズムの復権を主張した。それとは対照的にミサックは、プラグマティズムと分析哲学の連続性を説得的に論じてゆくのである。
とはいえ訳者としてことわっておきたいのだが、ミサックが首肯するプラグマティズムの主張は、かなりの程度、ブランダムやヒュー・プライスといった面々がそれぞれに述べる現代のネオプラグマティズムの主張と重なる。ニュープラグマティズムとネオプラグマティズムを対比的に語るミサックの論法は、ローティ没後十年を経て新たな議論の展開が見え始めたプラグマティズムの研究状況をさらに盛り上げるかのごとく導入された、ある意味で「プロレス的」なものではないのか、というのが訳者の見立てである。つまりミサックは、あえて状況を対立的に描き出す(「マッチメイク」する)ことによって、プラグマティズム研究の「興行」に打って出ている。
訳者は、本書内での「フレー!」という言葉の用いられ方を踏襲した上で(第九章、第十二章参照)、「興行主」としてのミサックに「フレー!」という声援をおくりたい。つまり、ミサックのマッチメイクのおかげで、二〇一九年現在においても鮮烈な、ワクワクする哲学的議論を目の当たりにすることができ、訳者は幸せである。「フレー!」「いいぞ、もっとやれ!」という思いを、「哲学プロレス」ファンの一人として抱いている。だが、ウィルフリド・セラーズやミサック自身が述べている通り(本書下巻一五一ページ)、「〜べき」という規範的な判断や主張を「フレー!」という声援と同一視してはいけない。ミサックの「興行」の打ち方が妥当なのかどうか、とりわけ、善玉(ベビーフェイス)と悪玉(ヒール)の特徴付けが適正なものであるのかどうかは、試合の盛り上がりとは別に検討されるべきであろう。もちろん、試合が盛り上がったおかげで現代のプラグマティズムをめぐる議論が白熱しているのだから、ミサックの「興行」は政治的に有意義である、という主張はありうる。だが、この「興行」はネオプラグマティズム陣営を描写する上での誠実さを欠く、と判断する向きがあってもおかしくない。いずれにせよ、ミサックの「興行」の評価は、今後の議論に委ねよう。それよりも本書には、「プロレス的」な要素を差し引いた上でも、少なくとも三つの意義深い特色が認められる。訳者は、これらの特色があるからこそ、本書の邦訳が出るべきだと考えた。
本書の特色
以下、訳者が重要と考える本書の特色を三点指摘する。とはいえ、これらの特色は本書を一読すれば順当に看取されるものである。また、それぞれの特色に関連するミサックの主張については、本書内でミサック自身が明快に示してくれている。ここでは屋上屋を架す論述を控え、読者の便宜にかなうと思われる要素のみを手短に書きたい。
ミサックは、自身が編者となった論集『ニュープラグマティストたち』(The New Pragmatists)の序論において、次のように明言している。
本書に収録されている論文のうちのいくつかは、ある特定のプラグマティズム解釈から――つまり、手にすべき真理や客観性などというものは存在しない、あるのはただ、連帯、共同体内での合意、あるいは私たちがそれを言って済ませることを私たちの仲間が容認してくれる事柄だけなのだ、というリチャード・ローティの見解から――「プラグマティズム」という銘柄を取り戻すということをあからさまに試みている。然るに、〔本書収録の〕全ての論文は、ローティに言及していないものであっても、人間的な探究(human inquiry)の客観的次元を適正に取り扱おうとする立場を明確に述べる努力をしているという点で結束している。[Misak 2007a: 1]
ミサックが『プラグマティズムの歩き方』でおこなっていることも、まさにこの言葉通りのことである。すなわちミサックは、プラグマティズムの歴史を語り直すことで、ローティとは一線を画す、新たなプラグマティズム像を示そうとしている。そしてそのプラグマティズム像とは、「人間的な探究の客観的次元を適正に取り扱」う思想としてのプラグマティズムである。こうして、本書の第一の特色は、『ニュープラグマティストたち』において示唆されていた新たなプラグマティズム像追求の試みを、ミサック自身が存分に展開しているところに認められるだろう。
第二の特色は、本書が古典的プラグマティストの中でも特にチャールズ・サンダース・パースを高く評価していることである。前述のように、ミサック自身の打ち出すプラグマティズムは、ある意味での客観性を志向する。そして、そうした主張をなす際に彼女が拠り所としているのが、他でもないパースの「探究(inquiry)」概念である。ローティは、ウィリアム・ジェイムズととりわけジョン・デューイのプラグマティズムを高く評価し、プラグマティズムの復権を主張した。しかしその一方で、ネオプラグマティズムをめぐる議論が熱を帯びる中、パースのプラグマティズムは不当に見過ごされてきた、とミサックは考えている。こうした捉え方が妥当か否かはどういう議論の文脈に注目するのか次第であろうが、少なくとも昨今、生命記号論、生態心理学、あるいは人工知能開発といった様々な経路から、パース思想への関心が高まっていることは確かだ。そうした中で本書は、パース・リヴァイヴァルを主張する際の哲学史的根拠を提供する素材として、出色のものである。
第三の特色としては、本書が近年の分析哲学史研究の成果を伝えるものとなっていることが挙げられる。二〇一九年現在にあって、今まさに、分析哲学史関連の新たな史料が次々と発見されている。ミサック自身も分析哲学史研究者の顔を持ち、前述の通り、今はラムジー研究に力を入れている。今後、日本においても分析哲学史研究が盛んになってゆくことが予想されるが、本書を読めば、分析哲学史の現代の一般的議論の概要を非常に手っ取り早く把握することができる。この点から本書は、プラグマティズムに限らず、広くアメリカ哲学(あるいは英語圏哲学)の歴史を知っておきたいという読者一般に、自信を持ってお勧めできる。さらに第九章で明言されている通り、本書は、デューイの死後にプラグマティズムが凋落し、分析哲学がそれに取って代わった、というようないわゆるプラグマティズムの「凋落史観」に真っ向から反対する。プラグマティズムはむしろ、論理経験主義と手を取り合いながら発展してきた。そうした歴史認識に立ち、ミサックは、近代的な様相論理の確立者であるC・I・ルイスや、統一科学運動の牽引者でありその後の分析哲学に多大な影響を及ぼしたルドルフ・カルナップの思想に認められるプラグマティズム的な側面を、生き生きと描き出している。こうした記述は、新たなプラグマティズム像の提示の一環であるとともに、分析哲学史の問い直しをも含意している。すなわち、プラグマティズムとの間に密接な影響関係を結びながら展開してきた思想として、分析哲学の歴史を語り直している。この点もまた、本書の意義深い特色であると思われる。
読書案内
本書には、『プラグマティズムの歩き方』という少しフランクに響く邦題を付けた。ここには、本書が、これからプラグマティズムの世界を散策してみようという関心をお持ちの読者にとっての旅行案内書のようになればという思いを込めたつもりだ。散策の際には、本書とともに携えると良いかもしれない本がいくつもある。本書の文献表を参照しながら旅のお供を選ぶのも良いだろう。ただ、邦訳がない、内容が専門的すぎるなどの理由から、多くの本には手が伸びにくいかもしれない。そこで、ここでは、日本語で読めて(あるいは近日中に読めることになる予定で)比較的とっつきやすい本をいくつかご紹介しておきたい。
(1)伊藤邦武著『プラグマティズム入門』ちくま新書、二〇一六年。
(2)加賀裕郎、高頭直樹、新茂之編『プラグマティズムを学ぶ人のために』世界思想社、二〇一七年。
(3)冨田恭彦著『ローティ――連帯と自己超克の思想』筑摩書房、二〇一六年。
(4)リチャード・ローティ著、冨田恭彦編訳『ローティ論集』勁草書房、二〇一八年。
(5)Richard J. Bernstein, The Pragmatic Turn, Polity Press, 2010.(リチャード・バーンスタイン著、廣瀬覚、佐藤駿訳『哲学のプラグマティズム的転回』、岩波書店、二〇一七年。)
(6)Cornelis De Waal, Peirce: A Guide for the Perplexed, Bloomsbury, 2013.(コーネリス・ドヴァール著、大沢秀介訳『パース哲学について本当のことを知りたい人のために』勁草書房、二〇一七年。)
(7)Christopher Hookway, The Pragmatic Maxim: Essays on Peirce and Pragmatism, Oxford University Press, 2012.(クリストファー・フックウェイ著、村中達矢、加藤隆文、佐々木崇、石田正人訳『プラグマティズムの格率』春秋社、二〇一八年。)
(8)植木豊編訳『プラグマティズム古典集成』作品社、二〇一四年。
(9)Robert B. Brandom, Perspectives on Pragmatism: Classical, Recent, and Contemporary, Harvard University Press, 2011.(邦訳が「現代プラグマティズム叢書」として近日刊行予定)
(1)は、何をおいても真っ先に読んでほしい。書名が示す通り、プラグマティズムの思想に入門するにはうってつけの本である。本書著者のミサックを、おそらく本邦で初めて一般の読者向けに紹介した本でもある。(2)は、古典的プラグマティズムから現代のプラグマティズムに至るまで、あるいは教育学や社会科学の分野でのプラグマティズムの応用など、非常に幅広い話題に触れている点が魅力だ。
(3)と(4)はローティの思想を知るための最良の手引きとなるだろう。本書では半ば斬られ役として登場しているローティであるが、ミサックの「興行」が妥当であるのかどうかを、ぜひ読者自身でローティの思想と向き合った上で考えてみてほしい。(5)は、ローティと個人的な親交の深かったバーンスタインが、長きに渡るプラグマティズムの潮流を自身の観点から描写している。ミサックが描き出すプラグマティズムの姿と対比してみてほしい。
本書で最も高く評価されているパースの思想についてより詳しく知りたいならば、まずは(6)を読まれることをお勧めする。さらに、本書でたびたび言及されているフックウェイのパース研究をまとめた(7)にもぜひ目を通してほしい。ミサックは「人間的な探究」にこだわるが、パース思想はいささか人間離れした超越論的とも言える志向をドイツ観念論から引き継いでいる。フックウェイの研究は、そうした微妙なバランスの上に成り立つパース思想を丁寧に描き出している。
古典的プラグマティストたちの著作そのものに触れてみたくなったら、(8)が便利である。パース、ジェイムズ、デューイの最も基本的な著作が一冊にまとめられている。巻末の文献案内も役に立つ。
(9)は、手前味噌ながら、訳者を含む四人で目下翻訳を進めている書である。著者のブランダムは、ローティの弟子で、現代のネオプラグマティズムの旗手といえる人物。彼は「分析プラグマティズム」という考えを提示しているが、これとミサックの提示するプラグマティズムをぜひ対比してほしい。先に述べたプロレスの比喩をここでまた用いてみる。ニュープラグマティズムの代表選手として、ミサックはブランダムとどう対峙するのだろうか。試合の行方はいかに。いや、もしかしたらそもそも、取り組みが成立しないかもしれない。両者の対立点など無いことが分かるかもしれない。いずれにせよ、近日中にこの試合を見られる環境が整う予定である。乞うご期待、と口上を述べておこう。
謝辞
最後に、本書の出版に際してお世話になった皆様に感謝を述べます。
まず、本書の装丁チームの皆様に。ブックデザインを手がけてくださった大西正一さん、作品画像を提供してくださった三宅砂織さん、そして装丁チーム内の調整役として奔走してくださった上原徹さん、ありがとうございました。今回、装丁を全て訳者サイドでやらせて欲しいとわがままを言いました。本邦訳書が実現する運びとなった際、二〇一七年の春先に大阪の画廊で見て印象に残っていた三宅砂織さんの作品が本書のイメージにぴったりだと思い浮かんだのです。本書下巻の表紙に使用させていただいたものがその作品です。スマートフォンを手にした女性がパリのルーヴル美術館のピラミッドのモニュメントの前を歩く姿は、アメリカン・プラグマティズムの思想を携えて現代の社会を颯爽と生きてゆくさまを、まさに「プラグマティズムの歩き方」を、象徴しているように思われました。さらに後から知ったことですが、この作品は《The Missing Shade》というシリーズに属するもので、このシリーズはデイヴィッド・ヒュームの言った ‘the missing shade of blue’ という逸話から着想を得て開始されたとのことでした。経験したことのない青の色合いの観念を、経験したことのある青の色合いの観念から想像力によって導き出すことはできるのか、というヒュームのこの逸話は、本書で描かれるプラグマティズムの思想史と絶妙に符合するようにも思われます。とはいえ、ここは美術批評を展開する場ではないので、三宅砂織論については稿を改めましょう。上巻に使用させていただいた作品画像も《The Missing Shade》シリーズのもので、こちらは二〇一九年初夏に銀座の画廊で発表された作品です。三宅さん、上原さん、大西さんという理想的なチームによって、素晴らしい装丁が実現しました。本当にありがとうございました。
さらに邦訳にあたって、様々な方々からお力添えをいただきました。特に、上巻では「訳者はしがき」で述べさせていただいた皆さんに、下巻では三木那由他さん、佐々木崇さん、田中凌さん、松永伸司さん、朱喜哲さんに、訳稿の下書きを読んでいただき、貴重なご意見を賜りました。ここに記して感謝を申し上げます。また、ここに全員のお名前をあげる紙幅はありませんが、個別のポイントでさらに様々な方々のお知恵を借りました。ありがとうございます。とはいえ、思わぬ誤解や誤訳が、本書のところどころに残っているかと思います。それらは全て訳者に責任があります。お気付きの点があれば、どうか忌憚なくご指摘ください。本邦訳書は、版を重ね、その都度誤訳箇所などの訂正を重ねながら、長く読み継がれる価値のある本であると確信しています。読者の皆様も、どうか本書の至らない点のご指摘を通して、本邦におけるプラグマティズム研究を盛り上げていただければ、訳者としてこれにまさる幸せはありません。
そして、訳者の拙い提案に真剣に耳を傾けてくださり、本書の企画を実現させてくださった、そして出版業界の慣行などもあまり分かっていない訳者を辛抱強く導いてくださった、勁草書房の山田政弘さん、ありがとうございました。これから「現代プラグマティズム叢書」は積極的に展開してゆきます。読者の皆様、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
加藤隆文
※傍点は省略しました。pdfファイルにてご覧ください。

