あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
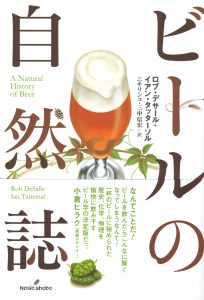 ロブ・デサール、イアン・タッターソル 著
ロブ・デサール、イアン・タッターソル 著
ニキリンコ、三中信宏 訳
『ビールの自然誌』
→〈「はじめに(冒頭)」「解説 枝葉を広げるクラフトビール──ドレスデンの街角から」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報はこちら〉
【小倉ヒラクさん(発酵デザイナー)による本書帯文】
なんてことだ! ビールを飲んだらこんなに賢くなってしまうなんて!
一杯のビールに秘められた歴史、化学、物理を愉快に飲み干すビール学の決定版だっ。
はじめに
あまたある酒のうち、ビールが世界最古かどうかははっきりしていませんが、歴史的に最も重要であることは確実です。また、社会的な格の高さではワインに後れをとってきたとはいえ、よくできたビールならば人の五感や美意識にうったえる力でワインに劣ることはありません。それどころかビールはワインにくらべ、発想も製法もより複雑であるばかりか、造り手の意図を反映しやすいともいわれてきました。
だからといって、私たちがワインを軽視しているわけではありません。前著『ワインの自然誌(A Natural History of Wine)』をご覧になった方にはおわかりいただけることでしょう。ワインは人の体験に、そして人生に重要な位置を占めています。でもそれはビールも同様です。両者が互いに補いあう、まったくちがった飲み物であることは疑う余地がありません。ワインを自然誌の観点から考察する価値があるなら、ビールだって同じでしょう。
そんなわけで本書が生まれました。しかも刊行は今、世界のほぼ全域のビールファンにとって黄金時代といえるこの時期です。たしかに、昨今のクラフトビール熱は工業生産ビールの退屈さへの反動ですから、背景には巨大多国籍企業が画一的な製品を大量生産、大量販売していることがあります。それでも市場には幅があるもので、大量生産ビールと反対側の極を見れば、今ほど多彩な、創意工夫を凝らしたビールが造られていた時代はありません。
独創的な新製品が数多く登場したことにより、ビール界は楽しくもなりましたが、同時にややこしい場所にもなりました。消費者がとても把握しきれないくらいあふれかえっているのに流通は昔のままなので、高評価でありながら入手困難な銘柄も少なくありません。でもそんな混乱も、度を越さなければ時にはちょっぴり痛快なものです。
この混沌とした世界で旅の助けになる本はたくさんありますが、あまりに展開の早い業界だけあって、一日じゅう張りついていなくてはついていけないほどです。いっぽう本書では、まったく別の道を目指しました。私たちの狙いは、ビールはその正体からしてこんなに複雑なのですよとお見せすること。そのためには、はじめに歴史や文化の観点から、続いて自然界におけるビールについてお話ししましょう。ビールの原材料も、ビールを造って飲む人間も、自然から生まれたのですから。そのため、進化学、生態学、霊長類学、生理学、神経生物学、化学、さらにはほんのちょっとだけ物理学にも触れましょう。みなさんの目の前のジョッキに湛えられたすてきな一杯、淡いものなら淡黄色から、濃ければ黒褐色まであるこの多彩な液体を、あらゆる角度から楽しんでいただこうというわけです。執筆という旅の過程で私たちは多くのことを学び、謎もいろいろ解けました。読者のみなさんにとってもそうであれば嬉しく思います。(以下つづく)
解説 枝葉を広げるクラフトビール──ドレスデンの街角から
現在、クラフトビールブームはますますの盛り上がりを見せ、書店にはかつて想像もつかなかったほどたくさんのビールに関する書籍が並んでいる。本書はビールを題材とした本ではあるものの、これらの類書とは大きく変わった特徴を持つ。それには本書の執筆者のふたりが、系統進化生物学を専門とする世界トップレベルの科学者であることが大きく関連している。特にビール本にすでに親しんでいる愛好家の方にとっては、科学啓蒙書のスタイルで執筆され、科学の言葉でビールに関するあらゆることが語り尽くされた本書は、かなり特異なものに映るだろう。
一方で、文化の進化や、進化的手法の文化への応用に興味を持つ読者であれば、それらのビール本としての特異性はそれほど気にならないだろう。しかし、もし特にビール自体には興味がなく、とりあえず一杯目に飲む「シュワシュワした黄色い液体」という認識であれば、本書で語られるビールの多様性に驚くことであろうし、本書がクラフトビールの世界へ入るきっかけになるかもしれない。
解説者は、本書の著者ふたりと同様、昆虫の分類や系統進化を専門とする研究者で、かつクラフトビール歴二十年ほどのビール愛好家という立場から、異なるタイプの読者を橋渡しする役割として、この解説をお引き受けした。
さて先にも述べた通り、本書ではビールの起源からその材料と製造法、さらにはビールの栓を抜くときの音の物理的特性から、それが脳に伝わるまでの解剖学的・生理学的特性に至るまで、ありとあらゆることが、最新の研究成果も引用しながら、科学の言葉で微に入り細に入り語られている。趣味の世界に対して、科学という道具を使って全力で取り組む様は、科学者という人種のヒューマンウォッチングとしても興味深い。そしてビール本としての本書の特異性を際立たせる最大のポイントであり、そしてやや理解しにくいのが第14章であろう。他の章とは異なり、14章では著者らが独自にビールの特徴をデータに変換し、生物進化の解析に用いられる方法で系統解析を行い、さらにはチェコやドイツへのフィールドワークまで敢行して書き上げた、完全にオリジナルな一科学論文とも言える章だからである。
さてそのようなオリジナルな解析を行っているにもかかわらず、そこからもたらされた結論は、よく知られたビールの分類とほぼ一致している。とりわけビールを良く知る読者であれば、「手間がかかってる割には大した結果になってないね」と思われるかもしれないが、その認識は大きな間違いである。この間違いを理解するために、まずは「分類」と「系統」という、二つの異なる体系の理解が必要となる。
生物の例を使って説明したい。爬虫類という分類群は私たちにとって馴染み深いもので、そこにはヘビやトカゲ、カメやワニが含まれることを多くの方がご存知と思う。この爬虫類を認める分類体系では、生物の中に(ヘビ・トカゲ、カメ、ワニ)から構成される、一つの集合を認めていることになる。
一方、系統という視点からこれらの生物を見ると、異なる体系が見えてくる。爬虫類および鳥類の系統関係は図のようになっていることが知られており、これを集合として表すと、(ヘビ・トカゲ(カメ(ワニ、鳥類)))となる。つまり、まずワニと鳥類からなる集合があり、その上位の集合としてカメ、ワニ、鳥類が、さらに上位にヘビ・トカゲ、カメ、ワニ、鳥類の集合が、という具合に、どの集合にも必ず鳥類が入ってくる。系統樹上にはいわゆる爬虫類(ヘビ・トカゲ、カメ、ワニ)の集合は存在せず、実際、現在では爬虫類のような分類群を、生物学的に意味のあるまとまりとしては「認めない」とする意見がほとんどである。
このように、分類と系統はまったく異なる観点に基づく物事の体系化であり、時には両者に矛盾が見られるということを理解していただいた上で、話を進めていこう。14章では系統という観点からビールの体系化が行われているにもかかわらず、その結果は他の書籍でも見られるようなビールの分類、例えば、
下面発酵=ラガー類
ピルスナー
シュバルツ
上面発酵=エール類
ペールエール
スタウト
といったものとよく一致している。生物の場合でも爬虫類のように分類と系統が齟齬をきたす例ばかりではなく、異なる体系化の結果が一致することも多い。
しかし、たとえそれらが一致したとしても、系統と分類が異なる視点に基づいた体系化であることは注意すべきである。系統推定は実際に起きた歴史を客観的に推定する行いである一方、分類は主観に基づく類型化であることが多く、あるものをどこに分類するかは、どの特徴に注目するかによって異なりうる。例えば、ビール、発泡酒、リキュール(第三のビール)といった分類は完全に日本独自のものである。二〇一八年の酒税法改正で大幅に改善されたが、かつては副原料にスパイスや果物を使った途端、それ以外はビールにほかならない液体が、ビールとは異なる発泡酒というカテゴリーに入れられてしまっていた。また、アルコール度数三〇%超のビールが日本に輸入された際、そのアルコール度数からビールではなくスピリッツとして輸入されたこともあった(アルコール度数二〇%未満が日本の酒税法上のビールの定義)。日本の酒税法に基づいて先のような分類がなされたとしても、三〇度超のビールや副原料を加えたビールが「ビール」にほかならないことは、「系統」という観点から見れば明らかなのである。
生物学者は、現在手に入る生物の情報を用いて、過去に起きた進化の歴史をひもとこうと奮闘している。タイムマシンを持たないわれわれは、「真」の生物進化の歴史を実際に見ることはできず、系統解析の結果は「推定」の域を出ることはできない。
一方でビールの進化に関しては、さまざまな記録からその「真」の進化史をある程度はうかがい知ることができる。さらにビールの進化は、現在むしろ加速しながら進行中で、私たちはその進化を実際に体感すらしている。したがって、本書で示されているビールの系統関係を、それらの証拠に基づいて検証するという、生物や文化の系統推定では通常困難な作業を行うことが可能になる。そのような観点から見てみると、いくつか面白い点が見えてくる。
一つは、ビアスタイルガイドラインに準拠して得られたデータから、私たちが知っているビールの進化史とよく一致した系統樹が得られているという点である。生物の系統解析では、新しく進化した形質に基づいて系統関係を推定する。たとえば、鳥の観察から、前足が進化した「翼」という新しい形質がデータに加わり、それに基づき鳥綱が系統的なまとまりであることが推定される。
ビアスタイルガイドラインは系統推定を目的に作られたものではもちろんないが、おそらく、新しいスタイルのビールが登場すると、それを表現する新たな形質が加わる、という過程を何度も繰り返してビアスタイルガイドライン自体も進化してきたのだろう。これはまさに、新しく進化した形質を新たな形質データとして付加する過程にほかならず、このような新たな形質レイヤーの積み重ねを繰り返す過程を通して、ビアスタイルガイドラインがビールの系統推定のための優れたデータに進化したと考えられる。
ガイドラインが系統推定上いかに優れたデータであるかという点は、著者らがチェコ・南ドイツでのフィールドワークの際に記録した、フレーバーホイールデータを用いた「系統解析」の結果と比較するとよりはっきりする。フレーバーホイールで評価される形質自身や、それぞれがどのような評価を得たかという点はビールの進化を表したものではなく、そのデータに基づいて推定された「樹形ダイアグラム」(著者らもこの樹形が系統樹ではないことを理解したうえで、本文やキャプションで「系統樹」の用語を避けている)は、ビールの進化ではなく、著者らの好みを反映したものとなっている。
また本書では、ビールの進化を表す図として二分岐的な系統樹(すなわち、ある祖先が二つの子孫に分かれることを繰り返すことで生じる進化)が示されている。しかし、実際のビールの進化がこの通りでは「ない」ことも、私たちは真実として知っている。IPL(インディアペールラガー)やブラックIPA(Black IPA)、ベルジアンIPAなど、エールとラガー、ペールエールとスタウト、アメリカンとベルジアンなど、異なる系統に属するビール同士のハイブリッドと言えるビールも数多く登場している。このように実際のビールの進化は、生物学で言うところの網状進化の過程を経ている。本書では最節約法による系統解析に加え、STRUCTURE というソフトウェアを用いた集団構造解析により、異なるビアスタイル間の交絡の存在を検討している。
STRUCTURE 解析の結果では、まずビアスタイルが大きく五つのグループに分けられている。ビール愛好家であれば、たった五つと感じる方が多いとは思うが、この五つという数は恣意的に決められたものではなく、「これ以上細かく分けても、分ける煩雑さほどには情報量が増えない」という上限が統計的に決められている。つまり統計的に言えば、とりあえずこれら五つのグループの違いが認識できれば、おおよそビールをグルーピングする入り口としては上出来と言えるわけである。そしてこれら五グループを見ると、互いに別のグループの要素が含まれるビアスタイルが存在すること、つまり異なるビール同士のハイブリッド進化が実際に生じていることが明瞭に示されている。
さてビールを対象とした厳密な系統解析は本書のオリジナルとはいえ、14章でも紹介されているように、ビールの系統史を表したポスターは以前から複数存在する。このようにビールの多様性を視覚的に認識しやすくする試みが繰り返し行われているのは、それだけビールの多様性が高いからにほかならない。近縁なグループであるワイン(14章でも外群として用いられている)と比較しても、そのスタイルや味わいの幅は圧倒的で、一般には苦いと認識されているビールだが、甘さや辛さ、しょっぱさや酸っぱさが際立つビールも数多く存在する。本書でその登場が予言されている「うまみ」を生かしたビールも、国内の複数の醸造所によってすでに造られている。
他の醸造酒や蒸留酒の場合、その香味は原材料とその発酵や熟成過程でもたらされるものがほとんどであろう。一方でビールの場合、ホップという、醸造という観点から言えば副原料ともみなされるものが必ず使用されているし、第9章で紹介されているようにそのホップ自体、新しいアロマをまとった新品種が次々と誕生している。そのほかにも、麦芽(モルト)のローストの深さを変えたり薫香を付加したりと、主原料の加工方法も多様である。さらにはビールに用いられる副原料は極めて多様で、フルーツ、スパイス、コーヒー、紅茶、チョコレートなど、挙げていけばきりがない。
このように、ビール造りというのは単なる醸造ではなく、原材料の加工から副原料の利用に至るまで、料理を作るような自由度があり、これがビールの多様化を許容してきた重要な要素になっていると考えられる。
日本ではドイツこそがビールの本場と認識されているように思うが、ドイツビールの多様性はむしろ低い。ビールの原料を厳格に定めた純粋令の存在が、多様化を阻害する進化的制約になっているように思われる。そして現在、ビール進化のホットスポットとなっているのはアメリカである。ありとあらゆるスタイルを独自の解釈を加えながら取り入れているうえ、自家醸造も盛んであり、それだけ多くの系統に分岐していける素地が整っている。そのような自家醸造者の中から大人気の醸造所に発展した例も多い。
そうしてアメリカで生み出された新たなビアスタイルの影響は極めて大きく、本場のドイツ、ベルギー、イギリスにも波及している。昨夜見つけた、ドレスデン旧市街の中心地のクラフトビアバーでは、一四本の自家醸造ビールのうち、実に一〇本がアメリカの影響を受けたスタイルで、ドイツ本来のビールと言えるのは、メルツェン、シュバルツ、ラオホの三本だけであった(あと一本はベルギースタイルのセゾンだったが、これはアメリカでも流行っており、そちら経由での影響を受けている可能性も高い)。ピルスナーももちろんあったが、一本は大手のものだったし、もう一本の自家醸造のものは明らかにアメリカの影響を受けたIPLスタイルのものであった。ちなみに、オクトーバーフェストを迎えたビアバー前の広場には数多くの屋台が並び、ドイツ伝統のピルスナー、ヴァイツェン、シュバルツ、そしてフェストが湯水のように消費されていたことも事実ではある。
我が国に目を向けると、一九九五年ごろに一度「地ビール」ブームが巻き起こり、早々に衰退した。しかし二〇〇〇年初期ごろから第二のブームが立ち上がり始め、現在では「クラフトビール」は完全に定着し、さらにその人気は加速度的に広がっている。造られるビールも欧米の模倣から、それをさらに磨き上げつつオリジナリティを追求する段階に移っており、独自の系統進化が進んでいる。地元で採れた材料だけを使った真の意味での「地ビール」や、茶、山椒、わさび、ハスカップ、菖蒲、トウキ、ゆず、昆布、鰹節等々、日本独自の副原料を使った、多種多様なビールが誕生している。大手の造るビールでは、米はむしろ口当たりを軽くする目的で加えられるものだが、米の味を積極的に生かしたビールもある。そのようなビールを口にすれば、大手がプレミアム系ビールの売り文句に使う「モルト一〇〇%」ばかりが良いビールの基準ではないんだぞ、ということがはっきり理解できる。
ビールの多様性を歴史的観点から語っている本書では、ビアスタイルやスタイルごとの香味の説明などはほとんどなされていない。日本や世界のクラフトビールをスタイルごとに紹介した書籍はたくさんあるので、本書でビールに興味を持たれた方は、それらを合わせてひもとくのも良いだろう。
しかしビールの多様性を知るうえで一番良いのは、実際にビアバーに足を運び、多様なビールを自身で味わうことである。ワイワイ飲むビールも楽しいが、カウンターで一人静かにビールに向き合うのも良いし、店主や隣の客とビールの知識を交換し合うのも楽しいものだ。ビールの多様性に対して新しい観点をもたらす本書は、そんな話題づくりの格好の虎の巻となるだろう。
二〇一九年九月二二日
吉澤和徳
(図は省略しました。pdfをご覧ください)

