あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
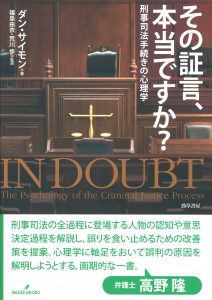 ダン・サイモン 著
ダン・サイモン 著
福島由衣・荒川歩 監訳
『その証言,本当ですか? 刑事司法手続きの心理学』
→〈「監訳者はじめに」「第1 章 はじめに(冒頭)
」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報はこちら〉
監訳者はじめに
本書はアメリカの法心理学者,ダン・サイモン著のIn Doubt: The Psychology of the Criminal Justice Process( 2012) の翻訳である。In Doubt という言葉は直訳すると「疑わしい,不確かな」という意味になる。では,何が本書では疑わしいとされているかというと,被疑者の特定から裁判に至る刑事司法手続きとその仕組みが保証する正確性である。そして,その論拠として膨大な心理学的知見を利用し,各章では刑事司法制度が抱える問題をつまびらかにしたうえで,改革に向けた提案を行っている。
これまで,日本では目撃証言や虚偽自白など,個々の問題に関する書籍はすでにいくつか出版されているが,刑事司法手続きの始まりから終わりまでを俯瞰し,段階ごとに問題を検討した書は他にないように思う。本書には,目撃証言や虚偽自白はもちろん,虚偽検出,陪審員評議,事実認定にまつわる問題に対する検討も含まれている。したがって,これらの問題に関わるほぼすべての当事者(被疑者,被害者,目撃者,警察官,弁護人,検察官,裁判官,陪審員)に生じうる心理学的問題,すなわち認知的バイアスや問題検討能力の限界について述べている。
本書の特徴の一つはその情報量の多さである。本文だけでなく,100 ページ以上にわたって詳細に記述された注には目を見張るものがあり,最新の心理学的知見だけでなく過去の判例,統計調査など,様々な疑問に答えてくれる辞書のようでもある。したがって,アカデミックに携わる心理学者や法学者だけでなく,これらの分野に関心がある初学者の見識を広める手助けにもなれば幸いである。
一方で,本書はアメリカの刑事司法制度を前提としているため,日本の刑事司法制度に与える示唆は少ないのではないかという指摘をされるかもしれない。しかし,この制度を支えているのが人であり,人が同様の認知能力の限界を抱えている限り,文化差や制度の違いは本書の指摘する問題や提案の重要性を矮小化するものではないと考える。
ただし,制度の違いによる混乱を避けるため,日本の読者に配慮して翻訳した部分についてはここで明記しておく必要があるだろう。日本では,警察活動を行う法執行機関に勤める人々を指す言葉として,警察官(police officer)あるいは刑事(detective)といった言葉が一般的に使用されるが,アメリカの司法制度では連邦レベルや州レベルごとに管轄する法執行機関が異なれば,そこで働く人々の呼称も多様である。たとえば,law enforcement agent, law enforcement officer, responding patrol officer などが挙げられる。そこで,読者の混乱を防ぐために,日本でいう警察官に当たる人々の呼称については一律に「警察官」と訳した。アメリカ連邦捜査局(FBI)の捜査官(FBI agent)のように「捜査官」という訳が一般化しているものや,刑事(detective),文脈的に捜査官と訳すことが適切だと判断した場合はこれに当たらない。
また,原著が最初に出版されてから時間が経っていることもあり,引用として注に記載されているホームページのURL には,いくつかリンクが切れているものが散見された。そこで,翻訳段階でリンク切れが確認され,代替ページが判明したものについてはできる限り新しいURL に置き換えたことも明記しておく。
本書を刊行するにあたっては多くの方にご協力いただいた。訳者のみなさまにはご多忙の中,翻訳を分担してくださったことに深謝したい。また,出版スケジュールに合わせるために忙しない作業となったことをお詫びする。高野隆弁護士には第一線で活躍される実務家として,解説を書いていただいた。日本の刑事司法の問題点と本書の内容を照らし合わせた丁寧な解説で,本書を日本の読者にとってより有意義なものにしていただいた。甲南大学法学部の笹倉香奈教授には法律用語の翻訳について相談に乗っていただいた。重ねてお礼を申し上げたい。そして大変辛抱強く,丁寧に編集してくださった勁草書房,永田悠一氏にこの場を借りて厚く御礼申し上げる。
2019 年9 月
訳者を代表して
福島由衣
第1 章 はじめに
刑罰は,国家が社会秩序を維持する手段としてもっともわかりやすく,世界中で用いられているものである。しかし,その刑罰を執行する前に,国家は人間のどの行動が犯罪事件に結びついており,だれがそれを実行したのかを確信をもって決定しなければならない。この行為は,刑事司法手続きを定める複雑な法制度に則っている必要がある。この手続きの機能とその結果生じる判断の正確性が,この本の主題である。
以下の3 つの事件から,刑事司法手続きの実務を垣間見ることができる。カリフォルニア州在住のピーター・ローズは,13 歳の女の子をレイプした罪で起訴された。証言台で,被害者はローズが加害者で100% 間違いないと証言し,目撃証人は,犯人はローズ以外にはありえないと証言した。ペンシルベニア州のブルース・ゴドショックは,2 度の侵入強盗と強姦の罪で訴えられた。ゴドショックの事件は,彼の有罪を示す証拠にあふれていた。被害者の1 人は彼を犯人だと識別し,留置場の情報提供者は,彼が罪を認める発言をしていたと証言した。そして,法科学者は血液型が一致したと報告した。決定的だったのは,33 分間にわたってゴドショックが自白し,一般の人は知りえない具体的な詳細情報について話している録音テープを検察官が提出したことである。その自白の中で,ゴドショックは,犯行は自分の飲酒問題のせいだと主張し,「被害者である2 人の善良な女性に私がしてしまったことを本当に申し訳なく思っている」とつけ加えた。カーク・ブラッズワースは,メリーランドの9歳の少女に対する強姦と殺人の罪で死刑を求刑された。裁判でブラッズワースは,5 人の目撃証人から犯人として識別された。また,検察は凶器として使われた石について彼が話していたという証言を提出した。さらに,法科学的捜査の担当者は,殺人犯の靴跡がブラッズワースの靴と一致したと証言した。
これら3 つの事件の有罪証拠にはとても説得力があり,彼らは合理的な疑いを超えて有罪であると認定された。ローズは27 年,ゴドショックは10 年から20 年の服役,ブラッズワースには死刑の判決がそれぞれ下された。長い間,この判決はなんら特別なものではなかった。彼らは刑を科された犯罪の真犯人ではない,とDNA 検査が示したそのときまでは。これらの事件で証言した証人たちは,特に,犯行を行った人物を識別するという決定的な点についてほとんど誤っていた。ローズは釈放されるまでの8 年間を刑務所で過ごし,ゴドショックは14 年半,ブラッズワースは8 年間服役していた。後者の2 人は,死刑囚用の監房に入れられていた。
これらの事件は,刑事司法手続きにおける捜査段階と裁判段階両方の機能に関して多くの難題を提起している。証人に誤った証言をさせたものは何か? なぜ警察官や検察官,陪審員は証人を信じたのか? 誤りに気付くことは可能であったのか? 最も重要なことは,将来同じようなことが起こるのを防ぐために何ができるのか,ということである。
実験心理学からの視点
刑事司法手続きのわかりやすい特徴の一つは,そのほとんどが証人,刑事,被疑者,弁護人,裁判官,陪審員といった人の手によって運営されていることである。この制度は,このような人たちの,道徳的判断や情動,動機づけに結びついた記憶,認知,評価,推論,社会的影響,意思決定といった心の働きによって運用されているのである。刑事判決は,その手続きに関わった人々の心の働きの組み合わせの結果に過ぎないともいえよう。そのため,心理学的観点から刑事司法手続きの機能を検討することが重要である。幸運なことに,われわれは膨大な実験心理学的研究の成果を利用することができる。ここしばらく,法心理学者は,刑事司法手続きの中で役割を担う人々がその役割をまっとうしやすい状況とまっとうしにくい状況についての研究に真剣に取り組んできた。同様に,認知心理学や社会心理学,意思決定科学といったさまざまな関連領域も,刑事司法手続きの機能に必然的に含まれる心的過程について大量の知識を蓄積してきた。
この本の主たる目標は,実験心理学の膨大で多様な研究の一部を,刑事司法手続きの運用のより良い理解のために応用することである。これらの研究を通してわかったのは,この手続きの中で行われている作業は,極めて複雑で繊細なものであるということである。見知らぬ人物を識別することや,ある出来事の特定の詳細を思い出すこと,そして,このような証言の正確性を見定めるといった,日常当たり前のように行われている作業は,見た目ほど単純ではない。これらの課題の正確性は,多くの要因に依存し,その要因の多くは不明で,とらえどころがなく,犯罪捜査の厳しい現実と,その後の司法手続きの中に容易に埋没してしまう。
このような理解は,この本の中心にある2 つの主張につながる。第1 の主張は,重大な刑事事件において,捜査段階で得られた証拠,特に人証は正確な証言と誤った証言が合わさった弁別不能な混合物であるため,被告人の有罪を常に示すものではないということである。以下の4 章は,刑事捜査に誤りが混入する可能性について知見を与えるものである。第2 章は,警察捜査の機能,特に捜査において誤った結論を促進しうる,あるいは誤った結論を導き出させる条件に焦点を当てる。第3 章では,目撃証人による犯人識別の問題を扱う。第4 章は,事件についての証人の記憶を検証する。第5 章では,被疑者の取り調べについて扱う。
第2 の主張は,現在の裁判過程は証拠の正確性を検討するのに十分とはいえず,罪を犯した被告人と無実の被告人とを高い信頼性をもって見分けることができないということである。裁判手続きが持つ診断能力の限界は,その後に続く2 章の主題である。第6 章は,裁判で提示された証拠から真実を見つけ出そうとする中で事実認定者が直面する問題について検討している。第7 章は,この問題に立ち向かう事実認定者の手助けとなるよう作られた法的な仕組みの有効性について検討する。
ようするに,これまでの研究が示していることは,刑事捜査は誤りを多く含んだ証拠を作り出す傾向があり,裁判手続きは,一般的にそれを修正できないということである。捜査段階で生じる正確性の問題と裁判段階が持つ診断能力の限界という問題が合わさると,刑事司法手続きは,裁判がもたらす重大な結果にふさわしい正確性に達していないという結論が導き出される。この正確性の欠落は,一般的にこの制度の設計と管理を委任された人々,特に警察関係者,検察官,裁判官,立法者によって見過ごされるか否定されるかしており,学問的議論や一般の人々の議論においても,適切に理解されていない。第8 章では,今日における正確性の問題が示唆するところを検証し,裁判過程の正確性を高める制度的方法のいくつかを模索する。(以下つづく)

