あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
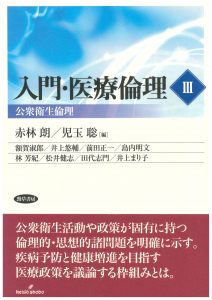 赤林 朗・児玉 聡 編
赤林 朗・児玉 聡 編
『入門・医療倫理III 公衆衛生倫理』
→〈「第4章 公衆衛生の歴史:日本(2)主な関連法規」(第1節、第2節)(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*2021年1月現在、新型コロナウイルス感染症への対応をめぐって新型インフル特措法や感染症法の改正の議論が続いていますが、政府レベルでも感染症法の歴史についての認識が深まっていないように思います。ハンセン病の隔離政策と差別の問題への反省ということだけでなく、戦前戦後の感染症対策の流れを踏まえて、現在の問題を考える必要があります。2015年刊行の本書『入門・医療倫理Ⅲ 公衆衛生倫理』第4章では、日本の公衆衛生の歴史と関連法規をコンパクトに紹介しており、類書はほとんどありません。公衆衛生に関する政策立案者やメディア関係者の方、このテーマについて理解を深めたいすべての方たちに今こそお読みいただきたいと考えて、特別に公開することにしました。以前に公開した同書の第9章「感染症対策」とあわせて、ぜひご覧ください。
》特別公開Ⅰ『入門医療倫理Ⅲ』「第9章 感染症対策」はこちら→【あとがきたちよみ/特別公開Ⅰ『入門・医療倫理III』第9章】
第4 章 公衆衛生の歴史:日本(2)主な関連法規
井上悠輔
本章の目的と概要
公衆衛生をめぐる法体系は,労働衛生や学校保健などの特定集団に関するものを除き,一般集団への保健衛生上の危害を防止することを主眼としている[1].個々人には社会の共通目標の達成に向けた協力や貢献が求められ,また前章でも触れたように,公衆衛生事業はしばしば警察法規とも一定の親和性を持って運用されてきた.生活環境の変化や国際化の進展,または再興した疾患や新たに浮上した疾患への対応など,個人や集合体への脅威は様々な顔をのぞかせ,それに合わせて公衆衛生の名のもとに社会が個々人に求める「参加」「貢献」も変化してきた.疾患に苛まれて苦境にある個人や家族の「生」が,その当時の国家や社会の利害に照らして極めて軽く扱われ,虐げられてきた歴史もある.本章では,こうした「社会防衛」と政策に関する倫理上の論点に関わりの深い話題として,感染症,予防接種,優生政策,精神保健の関連法規の展開を検討する.
1.感染症に関連する法規
前章でも触れたように,明治初期は伝染病(感染症)が公衆衛生における最も重要な政策課題であった.明治30(1897)年に成立した伝染病予防法はその代表的な法規であった.その後,急性の感染症の猛威が次第に鎮静化する中で,結核やハンセン病などの慢性的な感染症対策へと施策の重点は移ったが[2],今日の再興・新興感染症対策を考える上でもこの法規のたどった経緯を知ることは重要である.また,こうした感染症政策における患者保護のあり方について大きな転換点となったエイズ予防法とハンセン病をめぐる議論もあわせて紹介する.
(1) 旧伝染病予防法と感染症法
1) 伝染病予防法の成立とその特徴
我が国の近代衛生行政にとっての最初の試練は,幕末から明治期にかけてのコレラ流行であった.内務省衛生局は大流行のたびにこの対応に追われ,「ほとんど他の事業を拡充整理するの暇なし」[3]という状況であった.明治10(1877)年の流行の際,内務省は「虎列刺(これら)病予防法心得」を示し,海港検疫,避病(ひびょう)院[4],届け出,交通遮断,消毒などの詳細な規定を設け,各府県に通達した.明治12 年の流行の際には,他の伝染病をも含めた包括的な予防規則を起草中であったが間に合わず,窮余の措置として虎列刺病予防仮規則を制定した.避病院や患者・死者の運搬の際に黄色の標旗が用いられたのはこの規則による.[表4─1 本章で検討する主な法規](省略)
この仮規則を引き継いで翌年に示された伝染病予防規則(明治13 年)が,各種伝染病の予防に関する統合的な法規としては最初のものである.この規則は,コレラのほか,腸チフス,赤痢,ジフテリア,発疹チフス,痘瘡などの疾患を対象とし,医師の届け出,避病院の設置,患者の収容,患家の標示[5]についての一般規定,および疾患別に排泄物などの焼却,死体の埋葬処理,交通遮断,検疫委員の設置などについての規定を設けた.この規則については「近代医学上必要とされる事項を網羅」「近代的伝染病予防法規がようやく成立するに至った」との評価がある[6].なお同年,同規則の附属法規として伝染病予防心得書が示され,改定を重ねつつ,疾患ごとの清潔法や消毒法等の規範となった.
明治10 年の上記「心得」,同13 年の伝染病予防規則を踏まえ,同規則の同19 年の改正は「第三の心得書」,同23 年の改正は「第四の心得書」と位置づけられる.但し,両者は対照的であり,同19 年の改正では,衛生警察(前章参照)の強化が謳われ,警察力の動員への傾斜が見られる一方,同23 年の改正では,自治衛生の受け皿としての衛生組合の設置を規定し,「警察的武断攻略」からの脱皮がめざされた.但し,こうした組合組織は日常の予防運動に関するものであり,流行が発生した際は警察機能が前面に出ることになった(前章で述べた通り,府県では明治26 年の官制改革によって衛生事務は警察に移管された).
明治20 年を過ぎてコレラ流行が一段落し,一方で海外との往来の活発化による将来の新たな伝染病流行に備える目的から,防疫の基盤となる伝染病予防法(明治30 年)が制定された.同法では,コレラの流行に対処して各地に自主的に組織されていた衛生組合が法制化された点が重要である.
制定当時,同法の対象疾患は,八法定伝染病(コレラ,赤痢,腸チフス,痘瘡,発疹チフス,猩紅熱,ジフテリア,ペスト)であったが,後に日本脳炎や流行性脳脊髄膜炎などが加わった.症状,細菌学的検査の結果などによって疑いはあるが断定に至らない「疑似症」についても,広く法の適用が認められ(第2 条),患者でない病原体保有者についても患者と同様の措置の実施が認められるなど(第2 条ノ2),疾患の防圧を優先する多くの規定が備えられていた.後に,病原体保有者に関する規定は緩和されたが,コレラについては例外的に維持された.伝染病の発生の探知については,医師や,人が集まる場所や輸送に関連する者(寺社や病院,会社,船舶,集会所,興行場などの管理者や代表者)による届出のほか,行政官による積極的な探知が認められていた(職権探知).「市町村長」「検疫委員または予防委員」は感染者の発生に関する情報を把握することとし,これには患者や死者の発生にとどまらず,該当者の転出入も制限された(同施行令第4 条).伝染病患者発生の場所を管轄する市町村長(保健所を設置する市においては保健所長)または予防委員は,コレラ,天然痘,発疹チフスまたはペストの場合は原則として,その他の伝染病の場合には必要と認める場合において,患者を伝染病院,隔離病舎その他伝染病予防上適当な場所に収容しなければならなかった.また,感染の疑いがある者を事前に収容する「隔離」については,個人に加え,市街・村落などの特定地域を対象とする措置も認められた(第8 条).
2) 感染症法
旧伝染病予防法は,後藤新平(前章参照)らの関与のもとに制定され,以来,明治から平成までの伝染病対策の基本法であり続けた.特に急性感染症の防圧が念頭に置かれ,隔離を含む,患者の管理による感染拡大の制御など,各種の予防措置の法的根拠をなした.しかし,今日の視点からすれば社会防衛の性格を色濃く有し,感染症の拡大阻止を最重要事項と捉え,一方で罹患した個人の人権への配慮に欠けるものであった.後述するらい予防法廃止(平成8 年)やエイズ予防法をめぐる議論に後押しされて,平成に入ってからこれらの規定の見直しが本格化し,その結果,性病予防法,エイズ予防法との統合による「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法 ,平成10年)が成立し,翌年施行された.後に,明治37(1904)年の「肺結核予防に関する内務省令」を引き継いで結核予防対策の根拠となってきた結核予防法がこれに統合された(平成19 年).
感染症法には,国会における法案修正の過程で前文が設けられ,医師・獣医師による都道府県知事への所定の期日内の届出を土台とした「感染症への迅速かつ的確な対応」をめざしつつ,「人権尊重」「良質かつ適切な医療の提供」を確保することが明記され,規定も充足された.例えば,まん延防止措置は最小限度にとどめること,患者への入院に関する手続保障に関する規定などに特徴がある.前者については,消毒や媒介生物の駆除,死体の移動制限,立ち入りや移動の制限が規定されている.後者については,危険度の極めて高い特定の疾患について,就労の制限のほか,説明と同意に基づいた入院勧告制度,勧告に従わないときに都道府県知事(保健所長)が72 時間に限って患者を指定医療機関に入院させることができる応急入院制度,72 時間を超えた入院の必要性やさらに10 日毎に入院継続の必要性を判断する際には,感染症の診査に関する協議会の意見を聴いた上で行うこと等を法定化している.さらに,30 日を超える長期入院患者からの行政不服審査請求に対しては,厚生(厚生労働)大臣が審議会等の意見を聴いた上で5 日以内に裁決を行わなければならないといった行政不服審査法の特例を設けている(第25 条).一方,患者やその保護者は退院を要求できること,医療機関は入院させた患者から病原体が確認されない場合にその旨を知事に通知すること,知事は病原体を保有しない個人を退院させなければならないこととする規定も置かれている(第22 条).
また,感染症の予防その他のために必要を認めたとき,都道府県知事は職員に調査を命じることができ,一方の患者等はこの調査に協力するよう努めなければならない,と規定されている(第15 条).この点について,アフリカの一部の地域を中心としたエボラ出血熱の流行を背景として,平成26 年に規定が追加され,各都道府県知事は,「まん延を防止するため必要があると認めるとき」(厚生労働大臣の場合はさらに「緊急の必要」があると認めるとき),危険性の高い特定の感染症の「患者」「疑似症患者」「無症状病原体保有者」および当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又はその保護者に対し,検体(血液試料など)の提出や採取に応じるべきことを勧告し,これに従わないときは,必要な最小限度において当該検体を採取させることが可能となった(第16 条の3,検体の採取等).関連して,主に外国からの来航者について急性感染症流行時における隔離の規定を有する法律に検疫法がある.検疫の実施は幕末から長く試みられてきたが,我が国が主体的に行う検疫が本格的に始動したのは,欧米諸国との不平等条約の改正以降である.それまでも大規模なコレラ流行の度に緊急の防疫対策の一部として実施されていたが,明治30(1897)年の伝染病予防法の成立に伴い,その特別法として海港検疫法が制定されることで,常時検疫が始まった(さらに昭和2 年に航空検疫規則).大正11 年の改正により,病原体の保有者(無症状保有者)も患者とみなすこととなった.戦後の国際社会への復帰に伴い,昭和26 年に検疫法が制定された.検疫所長には,感染症法にもとづく特定の疾患(「一類感染症」,「新型インフルエンザ等感染症」)に掲げる感染症の患者を隔離する権限が付与されている.引き続き「患者」には「疑似症を呈している者」「病原体を保有している者」も含まれていたことから(第2 条ノ2),平成21(2009)年の新型インフルエンザ(インフルエンザA/H1N1)の流行時は,これらの解釈と運用が問題となった.入管法(出入国管理及び難民認定法)には,感染症法の規定による特定の感染症の患者(患者とみなされる者を含む)や新感染症の所見がある者の入国を拒否する規定が置かれている(第5条,上陸の拒否).
(2) 旧エイズ予防法
この法律(後天性免疫不全症候群の予防に関する法律)は,ヒト免疫不全ウイルス(HIV)の感染による後天性免疫不全症候群(エイズ)を対象とするものであった.厚生省による昭和60(1985)年の第一例の患者認定以来,患者とされた個人が社会およびメディアによる好奇の目や誹謗にさらされるなど,差別的な扱いを受けた事例が全国で続いた.東京弁護士会(人権擁護委員会医療問題研究部会報告,平成元年)によると,エイズ予防法が施行された平成元年の段階で,エイズ患者に関する人権問題が全国で数十件確認され,同様の事件はさらにその後も続いた.「エイズのまん延の防止を図り,もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与すること」(第1 条)を目的とするエイズ予防法は,こうした中で平成元年に成立した.この法律には,国民,国や地方公共団体の責務として「人権が損なわれることがないよう」「人権の保護」についての規定を示しつつ,「予防」「まん延の防止」に重点を置いた構成となっていた.例えば,医師や都道府県は感染者の把握と情報収集[7],防止のための措置を担い,一方,感染者には「人にエイズの病原体を感染させるおそれが著しい行為」をせぬこと,「医師の指示を遵守すること」を「感染者の遵守事項」として求めた(第6 条).医師はその責務として,国や地方公共団体の施策に協力し、予防に寄与するよう努めることとされ(第4 条),感染者を診断した場合には,本人又は保護者に対して「エイズの伝染の防止」に関する指示をすると共に,年齢,性別などを知事に報告しなければならないとされた.こうした指示に従わず,感染者が他者に感染させる「おそれ」があると判断した場合,医師は当該感染者の氏名及び居住地その他厚生省令で定める事項をその居住地を管轄する都道府県知事に通報しなければならないともした(第7 条).また,都道府県知事は,「エイズの伝染の防止」の観点から,感染者やその保護者に対する指示を発することができた(第9 条).
エイズ予防法は,前項の伝染病予防法の規定の影響を受けつつも,「国及び地方公共団体の責務」のほか,「国民の責務」「医師の責務」,そして上記の「感染者の遵守事項」など,伝染病予防法でも言及されていなかった各当事者の責務や遵守事項にも踏み込むものであった.このように患者本人よりも二次感染の防止に重点を置いた制度のあり方が,患者の人権を侵害しているとして問題視され,平成10(1998)年の感染症法の成立に伴い,エイズ予防法は廃止された.後続の感染症法には,これら「国及び地方公共団体」「国民」「医師等」の部分は基本的な構成を維持して盛り込まれた一方,「感染者の遵守事項」は踏襲されず,代わって,人権への配慮や医療の提供,医療についての適切な説明と患者の理解を得ることなどが加えられた.
(3) 旧らい予防法
1) 明治から戦前までの政策
らい予防法は,らい菌によって起こる慢性の感染症であるハンセン病(らい,癩)に関するものである.適切な治療を受けない場合は皮膚に重度の病変が生じることがあり,これと関連して患者は古くから差別の対象となってきた.明治中期に至っても,存在した療養所の大半は来日した外国人宣教師によるものであった.
明治35(1902)年には衆議院において「癩病者取締に関する建議案」が議員提案され,可決に至っている.当時の状況としては,明治30 年にベルリンで開催された第1 回国際らい会議において,ハンセン病は感染症であり,その特性に応じた患者管理が必要であるとされた[8].また,明治32 年に日本と欧米諸国との間での不平等条約が改正されたことにより,欧米人が日本国内において自由に行動できるようになった(内地雑居).そこで,「放浪患者」を欧米人に見られることは国の威信にかかわることであり,回避したいという意識が働いていた可能性も指摘されている[9].専門家の間では,上記のようにハンセン病は感染により伝播する疾患であることが共通認識となりつつあったが,一般市民の間には遺伝を疑う者も多く,明治33 年の内務省の調査により患者数が3 万人を越えたことが報告されると,潜在的な患者数の存在への懸念もあって,患者の特定と収容を支持する世論が醸成された.
日本にはすでに伝染病予防法が成立していたが,急性感染症を主に想定していた隔離規定に合わないとの判断からこの疾患への適用の拡大はなされず,代わって明治40 年に法律第11 号(癩予防に関する件)が制定された.この法律は,医師が患者を診断した場合には警察当局への届け出を義務付け,近親者などの身近な者による患者の保護・監督が困難な「下層」「浮浪」の患者を収容できること,これに対応すべく療養所を全国各地に創設することを定めた.法案をめぐる議論では,居住が定まらない者が感染源となることの防止,「厭うべき」外観の取締りであることが強調される一方(明治40 年2 月16 日,衆議院本会議における内務省衛生局説明),医療体制の整備や療養所からの退所についてはほとんど言及されなかった.続く大正5(1916)年の法改正では,通常の司法手続きが取れないとの理由から,療養所の所長に入所患者に対する懲戒検束権が与えられた.後に監禁のための「特別病室」(監房)の設置や,患者の虐待の事例も報告されている.
前章でも登場した衛生局の保健衛生調査会における検討では「癩」が主要課題の一つに挙げられていた.調査会は,放浪する患者の隔離から全患者を対象とした生涯隔離への転換を支持した.昭和6(1931)年の癩予防法は,国公立の療養所のもと,収容の量的,質的な管理強化を進めるものであった.感染者は他者に感染させる恐れがある職業に就くことが禁止される一方,従来は患者や扶養義務者が負担してきた収容の経費負担や家族への生活費補助などを自治体が担うこと,患者情報に関する守秘義務の規定など,患者を広く対象として収容を円滑に進めるための環境整備が図られた.以降,収容患者数は,収容の徹底を目指した無癩県運動もあって,急増した.昭和16 年には公立の療養所が国に移管され,国立らい療養所11 か所,私立の3 か所における入所者は一万人を超えた.当時日本の統治下にあった韓国や台湾,南洋諸島でも療養所が設置された.
昭和18 年にアメリカで治療薬プロミンの有効性が報告され,日本にも戦後紹介された.治療薬の効果に関する期待が高まる一方,治療の機会を提供するためにも全患者を療養所に収容するべきとする論調も目立つようになった.また,戦中・戦後の混乱により,多数の患者が「未収用のまま散在している」として,療養施設の拡張による「伝染源」の速やかな収容を求める主張も根強く存在した(例えば第12 回国会参議院厚生委員会,昭和26 年11 月8 日).厚生省は,警察行政を引きついだ都道府県に宛てて「無癩方策実施に関する件」を発し,「癩の予防撲滅は文化国家建設途上の基本となる重要事項」「今一段の努力によって無癩国建設の成果を」と強調し,収容の強化を求めた(第二次無癩県運動).
2) 戦後のらい予防法
これまで扶助の対象にある者として選挙権を持たなかった入所者が,昭和22(1947)年にこの制限の撤廃により参政権を手にしたことは,自身らの不当な処遇への抗議行動へとつながる大きな契機の一つとなった.昭和28 年,癩予防法が全面的に改正されて成立したらい予防法が,収容による隔離および所長による患者を拘束する権限を強化した上,医師の診察を拒んだり,所内の規律に反して療養所を離れたりした者に対する罰則規定(第27 条)を盛り込んだ点について,全国々立療養所ハンセン氏病患者協議会(全患協)は激しく抗議した.
その後も,患者の収容方針は継続された.翌年(昭和29 年)の法改正により,患者家族のうち生活困窮世帯に対する生活援護が強化されたが,このことは家族と患者との生活基盤を完全に分離し,患者の収容と隔離をより円滑に進める効果を有した.併せて,病床数の大幅な拡充が図られ,入所者数は戦中期の1 万人をさらに超えて推移し,全患者の収容はこの時期にほぼ達成された.また,こうした措置の対象となる「伝染させるおそれがある患者」(第6 条)が広く解釈され,退所基準が厳しく運用された結果,退所はほとんど認められなかった[10].
これらの取り組みは,戦前の政策を継承し,またその貫徹をめざした結果であり,社会に根付いた偏見や無関心からも支持されたものであった.同年には入所者家族の非感染児童の登校を拒否した龍田寮事件が発生しているが,こうした事例は,「本人や家族のために」隔離を維持するべきとの主張を補強することにもなった.らい予防法が成立した年には,インドにおける国際会議において在宅治療への転換,治癒者の社会復帰が決議されており,またその3 年後のローマ会議においても社会復帰の促進を謳った決議が示されるなど,国際的な動向と日本における論調や認識との乖離は大きな問題点として指摘されるべきであろう.当時占領下にあった沖縄では,立法院において,感染させるおそれがない患者の在宅予防措置,軽快患者の退所規定を明文化したハンセン氏病予防法(昭和36 年)が成立していた.
3) 優生政策との連動
ハンセン病問題と後述する優生政策との連動も注目すべき点である.本来,感染症について検討される公衆衛生上の措置は,当該個人の回復と他の共同体成員への感染制御を目的とするものであり,次世代への特定形質の遺伝を阻止しようとする不妊処置が検討される必要はない.しかし療養所では,医学的な根拠が曖昧なまま[11],主に療養所運営上の都合や生まれてきた子どもが「かわいそう」などとする理由のもとこれらの措置が実施され[12],官民共にこれを黙認してきた.当時は,法的根拠のない不妊処置が傷害罪を構成する可能性について,本人らの「任意」による承諾を得ることにより違法性が阻却されるとする運用が図られた.戦後成立した優生保護法は,「癩病者」を優生措置の対象に追加することで,患者への不妊処置の法的根拠となった.この優生保護法のらい条項は平成8 年に廃止されるまで存続した.
4) らい予防法のその後
ハンセン氏病患者への隔離措置を批判する動きが国際的に主流になり,また全患協などによる差別的対応の撤廃に向けた取り組みも粘り強く続けられた.しかし,運用面での改善が図られたものの,制度としての患者および元患者の隔離政策は継続された.
平成7(1995)年には日本らい学会の「反省表明」(「らい予防法」についての日本らい学会の見解)が示されたことに加え,厚生省に設置された検討会において,法の廃止と患者および元患者の生活保障を盛り込んだ法案が作成された.これは患者および元患者の高齢化と隔離生活の長期化が進む中,すでに生活基盤となっている療養所体制を廃止するのではなく,こうした人々の権利を回復しつつ,これまでの生活や医療体制を維持し保障する途を目指すものであった.この法案は「らい予防法廃止に関する法律」として,平成8 年に成立した.元患者らは隔離政策について謝罪と賠償を求めて国を相手取って訴訟を起こし(国は控訴を断念し終審),平成13 年には「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」(ハンセン病補償法)が,平成20 年には「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」(ハンセン病問題基本法)が成立している.国は「ハンセン病の患者であった者等に,いたずらに耐え難い苦痛と苦難を継続せしめた」(補償法,前文)と謝罪し,入所者等の被った精神的苦痛を慰謝するための補償金を支払うことが盛り込まれた.
予防法が廃止された平成8 年には,優生保護法が改正され(母体保護法に改称),旧法における「癩疾患」の条文と「優生手術」の項が削除された.また,上述の感染症法には,その前文に「過去にハンセン病等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め,これを教訓として今後に生かすことが必要である」と記された.多くの患者および元患者は現在も療養所にとどまっており,今なお「国の隔離政策に起因してハンセン病の患者であった者等が受けた身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる被害の回復には,未解決の問題が多く残されている」(基本法,前文).平成15 年には熊本県で元患者への旅館宿泊拒否(ハンセン病元患者宿泊拒否事件)が発生している.
2.予防接種に関連する法規
(1) 種痘法,戦後の予防接種法
明治新政府にとって天然痘は大きな脅威であったが,すでに幕末から試行されてきた種痘があることもあって,その対応策は他の感染症への対策と異なり,専ら予防接種行政を中心に展開してきた.新政府は,早い段階で,種痘を全国的に展開するべく,大学東校(のちの東京大学医学部)に種痘館を設けるとともに,各府藩県に通達して種痘の普及を促した(明治3 年,太政官).当時の当局であった文部省医務局は,明治7(1874)年の種痘規則にもとづき種痘医による接種を指導した.続いて衛生行政を所掌することになった内務省衛生局により,各地方政府に対して種痘義務を指導する天然痘予防規則が示された(明治9 年).これは強制種痘の先駆けであり,生後70 日から一年以内に必ず種痘すること,その時期に種痘ができなかったときは医務取締又は区戸長に届け出ることとされ(第1 条),遵守しない者への罰則規定も設けられた.また,「種痘濟ノ證書」(種痘を受けた証明書)を導入し,各自保管することも定められた.しかしその後も天然痘はしばしば流行した.明治42(1909)年には種痘法が成立し,特定の年齢に至った小児に対して種痘を行わせることが,保護者など(ほか,学校長,育児院など)の「義務」として明確化された.種痘法による強制接種制度は,以後40 年間にわたり天然痘予防の基盤をなし,戦後の予防接種法に引き継がれた.法定予防接種は種痘のみであり,他のワクチンについては,たとえば大正時代のスペイン風邪流行時のワクチン接種,軍部での腸チフス予防接種の利用の事例などが散見されるものの,一般に制度化されて運用されることはなかった.
戦後の混乱の中,種痘事業の停滞によって天然痘の流行が急速に拡大したことを受けて,GHQ は,チフス対策等とともに,大規模かつ強制力のある予防接種を指導しつつ,その基盤となる包括的な法制度の整備を政府に求めた.成立(昭和23 年)当初の予防接種法は,強制接種の対象となる疾患を大幅に拡大(ジフテリア,百日咳,腸チフス,パラチフス,インフルエンザなどを加えた全十二種)し,また罰則規定によって履行を担保する強力なものであった.ただ,罰則の積極的な運用は予定されておらず,実質的にはGHQ による強制力が接種を支えていた.そのため,GHQ の占領政策が終了すると,市町村の大きな負担となっていた接種証書の運用が廃止されるなど,予防接種の性格は見直されることになった.
(2) ワクチンによる健康被害
制度の見直しをめぐる議論の中で,特に論点となったのが投与したワクチンに関連する健康被害である.感染症対策としての予防接種は集団免疫の獲得を目指して実施されるが,一方で投与を受けた個人にワクチン自体に伴う害が生じうる場合がある.こうしたワクチン被害は,その作為過誤の側面を強調して「ワクチン禍」(予防接種禍)と呼ばれ,戦前においても,種痘を受けた者の一部に特有の脳炎が発生することが知られていた(種痘後脳炎).戦後,一時中断していた種痘事業が再開される中,事態の急速な好転を期待して強力痘苗の導入が推進され,天然痘の犠牲者は激減する一方で,種痘後脳炎による犠牲も顕著となった.予防接種法の施行に伴い接種の対象となる疾患は大きく拡大されたが,接種の効果自体が詳細に検討されていたとはいえず,むしろ不作為への批判の回避という消極的な動機が先行していたことも指摘されている[13].接種対象が新生児を含む小児である場合が多いこと,接種が強制であるにもかかわらず救済制度がないことが,被害の認識を一層際立たせた.昭和23 年には,ジフテリア予防接種において,京都や島根で接種を受けた幼児に多数の健康被害が発生した「ジフテリア予防接種禍事件」が起きたが,この事件は主に製造販売業者の責任と検定制度不備の面から処理された.事故補償や救済制度の在り方について一時的には争点になったものの,事態が鎮静化すると共に,こうした害の発生を例外的な個人の「特異体質」に因るものとして処理することが当時は多かった.
昭和43(1968)年,厚生省の伝染病予防調査会は伝染病予防法と予防接種法の見直し作業を開始した.調査会の結論では,従来救済されてこなかったワクチンの被害者に対する無過失救済制度の導入が謳われた.昭和45 年の種痘禍事件による種痘中止により,予防接種禍が改めて社会問題化しはじめたこともあり,厚生省は従来の路線を変更して,同年,初めての救済制度を導入した.それまで主に重視されてきた予防接種に関する不作為過誤の回避(必要な予防接種を実施する国の責任)に加え,本来実施すべきでなかった予防接種を実施した国の責任(作為過誤)も注目されるようになり,以後の予防接種を巡る議論に大きく影響した.昭和50 年の伝染病予防調査会の答申を経て,翌年に予防接種法が改正された.主たる内容は,予防接種の拒否に関する罰則規定の廃止,暫定措置であった被害者救済の制度化,そして日本医師会が強く求めていた医師の免責への対応(一部の重過失を除いて,国が賠償責任を引き受けることとなった)であった.接種義務規定は維持されたが,この改正で新たに法定接種に区分されたインフルエンザの集団接種の有効性が疑問視される中(代表的な事例研究として前橋スタディ),運用面で徐々に個人同意方式が重視されるようになり,実体として任意接種に近づいた.一方,この時期には,予防接種による被害の回避に関する国の不作為責任を問う判決が続いた(平成4 年の東京集団訴訟判決など).[表4─2 予防接種制度について](省略)
(3) 予防接種法の改正,新興感染症対策
公衆衛生審議会は平成5(1993)年,予防接種の目的について実質的に社会防衛重視から「個人防衛重視」への転換,義務接種から「勧奨接種」への転換を勧告した.勧奨接種とは,市町村が接種対象者やその保護者に対して,接種を受けるよう勧奨することを指す.国民は予防接種を受ける義務に関する規定は,緊急時を除き,従来の義務接種を支えた「受けなければならない」とするものから「受けるよう努めなければならない」とする努力義務(接種努力義務)に改められた.国民の自発的接種や医師の協力を確保するために,義務接種でなくなったのちも救済制度が維持されることが提案された.平成6 年の予防接種法の改正は,おおむねこれらの方針に沿うものであった.公的事業としての性格が薄れることで,接種の可否判断についての接種医師の責任も高まったが,例えば接種の対象となることの多い子どもについては,判断者としての保護者の役割がより際立つこととなった.平成13 年の法改正では,勧奨接種がさらに集団予防目的に比重を置いた「一類疾病」と個人予防目的に比重を置いた「二類疾病」に類型化された.二類疾病は被接種者に予防接種を受ける努力義務が課されておらず,被接種者が各自の判断に基づいて接種を受けるものとされ,高齢者を対象としたインフルエンザが指定されていた.
平成21 年の新型インフルエンザ(A/H1N1)の流行は,こうした個人への恩恵,個人の選択を基調とする予防接種体制のもとで発生した.従来の議論に加え,ワクチンの害,とりわけ安全性や有効性などについての国内での審査の時間を確保できない「特例承認」のワクチンの使用に伴う責任や救済,世界的に希少なワクチンの確保と優先配分の設定など,種々の論点が複合して生じた.国内生産で不足するワクチンを確保しようとして政府が交渉した海外のワクチン製造業者は,ワクチン使用に関する副作用についての免責を求めた.一方,こうしたワクチンの使用に不安を持つ医療者も,生じうる害に関する免責を主張した.政府は,これらの免責の設定自体は退けたものの,当該予防接種を国の事業とし,国が健康被害の救済責任を引き受けることを規定した「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法」を制定した.一連の議論は,国内外で利用できるワクチンの格差,いわゆる「ワクチン・ギャップ」が注目される機会ともなり,平成25 年の予防接種法改正に伴う定期接種の対象の拡大・再編につながった.これにより従来の「集団」「個人」に着目した区分は崩れ,国が自治体を介して勧奨し,対象者に努力義務が生じる予防接種の対象として,集団予防を目的とする場合のほか(従来の一類),重篤な症状やそのおそれがある疾患の予防を目的とする場合が加えられた(あわせてA 類に統合).従来は社会防衛から論じられることが多かった予防接種の利害をめぐる議論に,個人の症状の重篤化の予防についても法が勧奨し,また個人が努力義務を負う対象が加わったことになる.なお,このA 類の一つである「ヒトパピローマウイルス感染症」(子宮頸がんワクチン)については,接種を受けた者の間で健康被害が発生したことを受けて,同年のうちに勧奨接種から外された.
同じく平成25 年には,「新型・再興型インフルエンザ」「全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症」を対象とした新型インフルエンザ等対策特別措置法が施行され,国民の生命および健康の保護,生活や経済への影響の最小化を目的とした,国および地方自治体の措置に関する法的根拠の明確化が図られた.この法律には,生活基盤の維持に従事する事業者や公務員などへの予防接種に関する「特定接種」制度(第28 条),検疫制度,知事や厚生労働大臣は医療関係者に患者の治療に対応するよう要請・指示できること(第31 条),緊急事態宣言下での特定の施設の使用や催物の開催制限など(第45 条ほか)が盛り込まれた.(以下、本文つづく。傍点は割愛しました。表はpdfファイルでご覧ください)
[1]河角泰助,1961,『衛生行政法』,良書普及会,1 頁.64 Ⅰ 総論
[2]大正年間から昭和初期にかけて,大正8 年に「結核予防法」と「トラホーム予防法」(昭和58 年廃止),昭和2 年に「花柳病予防法」(後の性病予防法,平成9 年廃止),昭和6 年に「寄生虫病予防法」(平成6 年廃止)と「らい予防法」(後述)の制定をみ,ほぼこの時期に予防衛生の基礎が確立された.
[3]衛生局第三次年報の記述による(厚生省医務局,1976,29 頁より引用).
[4]後の「伝染病院」.当初は主にコレラ患者の隔離を想定し,居住地から離れた場所に建設され,医療者以外の敷地への出入りは制限された(虎列刺病予防仮規則,明治12 年).
[5]「患家の標示」についての規定は,患者隠ぺいを防止する観点から明治15 年に廃止された.当時,漢方医による患者隠ぺいも懸念されており,同年,患者の届け出に関する要件が強化されている.
[6]厚生省医務局,1976, 131 頁.
[7]情報収集の対象となる感染者には,いわゆる「薬害エイズ事件」により健康被害を受けた血友病患者は含まれていない.詳細として,泉真,1990,「「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」の制定について」,『北大法学論集』,41(1),259─308 頁.
[8]この疾患の感染力が微弱であることも確認されたため,容態の悪い患者を治療施設に隔離し,改善の後に家庭に復帰させる部分隔離(「ノルウェー方式」)が支持され,隔離絶対的な隔離を行う「ハワイ方式」は退けられた.しかし,日本にはこの会議への参加者によって隔離の部分のみが強調して伝えられたとされる(ハンセン病問題に関する検証会議,2005,『ハンセン病問題に関する検証会議最終報告書』,財団法人日弁連法務研究財団,610 頁).
[9]ハンセン病問題に関する検証会議,同上,53 頁.この点は,明治32 年に成立した精神病者監護法(後述)とも共通するだろう.
[10]ハンセン病問題に関する検証会議,同,112 頁.
[11]厚生省が患者を対象とする断種措置を肯定する説明として,遺伝や,胎内感染のほか,直接の病因ではないものの発症しやすい遺伝的な体質が関係しているとする可能性も指摘されていた(例えば,第74 回帝国議会貴族院職員健康保険法案特別委員会における厚生省の説明,昭和14 年3 月25 日).いずれの見解も,遺伝的な理由による断種措置を規定した昭和15 年の国民優生法の適用を肯定するには至らなかったが,患者を対象に実施された断種措置の経験は,優生関連法規の運用に活用された.
[12]ハンセン病問題に関する検証会議,2005,147 頁.
[13]手塚,2010,『戦後行政の構造とディレンマ』,藤原書店,76頁および103頁.

