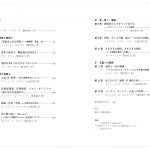あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
 スーザン・バンディズ 編/橋本祐子 監訳・訳、小林史明・池田弘乃 訳
スーザン・バンディズ 編/橋本祐子 監訳・訳、小林史明・池田弘乃 訳
『法と感情の哲学』
→〈「序論(冒頭)」「監訳者あとがき」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「監訳者あとがき」本文はサンプル画像の下に続いています。
序論
スーザン・バンディズ/橋本祐子訳
感情は、法のすみずみにまで行き渡っている。これは必ずしも驚くべきことではない。証人が法廷に感情を持ち込むことや、法廷ドラマが人の心を強く揺さぶることはよく知られている。最近では、証人の生(なま)の感情が、法的フィルターによってかろうじて抑えられている様子を目にする機会が多かった。オクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件では、被害者やその家族の悲痛な証言を耳にし、悲しみや同情が広く共有された。ルイーズ・ウッドワードの裁判では、彼女がベビーシッターとして世話をしていた赤ん坊のマシュー君を殺害した罪に問われたが、そこでは、マシュー君が傷つけられたときのウッドワードの精神状態や、マシュー君の母親が彼に十分な愛情を注いでいたかどうか、裁判官が正しく冷静であったかどうか、検察官に思いやりが十分あったかどうか、さらに、行為、評決、判決に対するアメリカ国内・国外での人々の感情(この事件では、同情、悲嘆、強い反感、激怒というようにめまぐるしい変化があった)の役割について問題が提起された。O・J・シンプソンは裁判で、元妻ニコールとその友人ロン・ゴールドマンを謀殺した罪に問われたが、この裁判によって、法廷から感情を排除する難しさについて、私たちが望む以上のことが明らかになった。ゴールドマンの両親の怒りを目の当たりにし、シンプソンが元配偶者に対して過去に怒りを抱いていたという報告を聞き(陪審がそれを考慮できるかどうかについて不安もあった)、そしておそらく、警察の戦術や評決に対する怒りといった私たち自身の強烈な感情がわきあがったであろう。さらに、4 人の警察官がロドニー・キングを殴打した罪に問われたものの無罪判決となり、それをきっかけに広がった憤怒は、法的な選択が時に感情的に難しい問題を含む領域で行われることを明確に示したのである。(以下、本文つづく)
監訳者あとがき
本書は、Susan A. Bandes (ed.), The Passions of Law(New York University Press, 1999)の全訳である。「法と感情」(Law and Emotions)研究という新たな法学研究の存在を広く知らしめることとなった記念碑的な論文集であり、「法と感情」研究を知るうえで必読と言ってもよい重要著作と評されている。ここで本書の意義を説くにあたり、日本ではまだなじみの薄い「法と感情」研究について、簡単に紹介しておく必要があるだろう。
人間の営みはさまざまな感情で彩られており、それゆえ、わたしたちの社会生活を秩序立てる役割を担う法が人々の感情を取り扱うのは、ごく当たり前のことのように思われる。一方で、法と感情の関係について私たちが思い浮かべるのは、例えばホッブズが優れた裁判官が備えるべき要件の1 つとして、「判決にあたって、すべての恐怖、怒り、憎しみ、愛、共感を捨てることができること」(加藤節訳『リヴァイアサン(上)』筑摩書房、2022 年、439 頁)を挙げたように、法の担い手や法実践は決して感情に動かされてはならず、できる限り感情を排すべきである、というイメージではないだろうか。これは、「法は理性が支配する領域であり、感情的なものはそこから排除されるべきだ」という法学の主流派的な見方にも通じている。つまり、必然的に法は人の感情を取り扱わざるをえないが、それにもかかわらず、法と感情とはそもそも相容れないものと捉えられてきたのである。
こうした見方の根底にあるのは、理性ないし法を感情と二項対立的に捉えたうえで、感情より優位にあるものとみなす考え方であった。1980 年代から1990 年代にかけて、この二項対立的な捉え方の克服を目指しアメリカを中心に台頭してきたのが、「法と感情」研究という新たな研究領域である。その背景には、認知科学の発展があった。認知科学によって感情メカニズムの解明が進んだ結果、「感情とは、反応的で主観的なものにすぎない」という従来の考え方が覆され、心理学、神経科学、哲学、経済学、社会学、人類学、歴史学、政治学など、さまざまな学問分野でも「感情」に関心が注がれることとなった。そして、遅ればせながら法学も、こうした領域横断的な潮流に加わることとなったのである。ここからもわかるように、「法と感情」研究は、自然科学、社会科学、人文科学の諸領域を横断する学際的研究であると言うことができる。
では、「法と感情」研究の魅力とは何だろうか。バンディズらによれば、それは次のように法の理解を豊かにする点にあると言われている。⑴ 合理的な熟慮と法的推論に関する標準的な説明を問い直す。記述のレベルでは、感情に動かされない合理性というフィクションを拒絶し、感情と認知との相互作用を明らかにする。また、規範のレベルでは、法規範の同定ないし運用や、裁判官や陪審らの討議プロセスにおいて感情がどのような役割を果たすべきかを明確にする。⑵ 感情が行動にもたらす影響や、望ましい意思決定を導出するための感情の方向づけについて、特定の法原理が依拠する想定を解明する。⑶ 内面的で個人的な現象としての感情のみならず、社会や制度を動かす原動力としての感情にも焦点を当てる(S. Bandes and J. A. Blumenthal, “Emotion and the Law,” Annual Review of Law and Social Science 8, 2012)。したがって、「法と感情」研究の企ては、法の客観性や中立性に疑念を呈す、リアリズム法学、フェミニズム法学、批判的人種理論と問題関心を共有するものとして評価できるだろう(本論文集が、批判的人種理論の代表的論客リチャード・デルガドとジーン・ステファンシックが編集するCritical America シリーズの1 冊として刊行されたこともこの証左と言えよう)。
さて、日本における「法と感情」研究はどのような状況であろうか。日本では、例えば裁判員制度をテーマとして心理学的アプローチを用いた実証研究や、神経科学の知見を用いて特定の感情と法との関わりを分析する研究(「法と心理学」や「法と神経科学」)には一定の広がりが見られるものの、「法と感情」研究の受容はこれからであるように見受けられる。もちろん、刑事法の分野では感情が考察の対象とされてきた伝統があり、刑罰の非難表出機能や、保護法益としての感情といった重要論点に関する研究が蓄積されているが、法の中の感情的次元に照準を定めた法理論としては、「法と感情」研究はまだその緒に就いたばかりであると言わなければならない。
とはいえ、日本法哲学会2021 年度学術大会が「法と感情」を統一テーマに開催され、それと併せて「『法と感情』をめぐる諸思想」と題するワークショップも実施されたことは特筆に値する。また、日本語で読むことのできる英米圏の「法と感情」研究として、本書の寄稿者の1 人でもあるマーサ・C・ヌスバウムの『感情と法:現代アメリカ社会の政治的リベラリズム』(河野哲也監訳、慶應義塾大学出版会、2010 年)の存在も重要である(本書第1 章の内容の多くは同書と重なっており、本書でも訳出の参考にさせていただいた)。
本書の概要に関しても、ここで簡単に触れておきたい。本書では、怒り、嫌悪感、羞恥心、復讐心、後悔、ロマンティック・ラブ、臆病、正義への情熱などといった、さまざまな感情が幅広く取り上げられるとともに、刑法、刑罰制度、婚姻制度、軍事司法、法理論、裁判官の伝記など、法に関連するさまざまな主題が取り扱われる。執筆者の面々も、錚々たる顔ぶれである――哲学者のロバート・C・ソロモン、マーサ・C・ヌスバウム、チェシャー・カルフーン、著名な法学者であるリチャード・ポズナーやマーサ・ミノウ、刑法哲学のジェフリー・G・マーフィーや法史家ウィリアム・イアン・ミラーなどなど、実に多彩である。心理学をはじめとする認知科学の専門家が執筆陣に含まれていない点を指摘する評価もあるが、すでに日本では心理学や神経科学からの研究が多く存在するため、法学者と哲学者の論考を集めている点は、むしろ本書の魅力ともなるだろう。
多くの言及が刑事法についてなされているが、それ以外の法分野の研究者にも、法と感情の関わりについて多くの示唆を与えてくれるに違いない。また近年では、法学教育における感情の役割についても盛んに議論されているところである。もちろん、哲学をはじめ、感情に着目する人文科学、社会科学、自然科学など各分野の研究者にとっても少なからぬ示唆がもたらされるだろう。さらには、ブラック・ライブズ・マター(BLM)運動や、# MeToo 運動などにおけるように、不正義を告発する憤りや被害者たちへの共感の広がりから社会を変革しようとする動きが見られる現代にあっては、一般の読者の方々にとっても、本書は興味深い内容になっているのではないだろうか。
訳出にあたっては、emotion に「感情」の語を当てることとした。心理学や哲学では、emotion は「情動」と訳されることが多いが、よりなじみ深い日常語として「感情」とした。作業の進め方については、論文集ということもあり、池田、小林、橋本が各々の担当部分を訳出した後、それぞれの文体を最大限尊重する方針の下で橋本が整理を行った。
刊行にあたっては、編集者の鈴木クニエさんに大変お世話になった。本書の出版についてご相談して以来、当初の予定通りには進まない訳出作業を辛抱強く待っていただいたほか、的確なタイミングでの励ましや貴重なアドバイスをくださり、刊行にまで導いてくださった。心よりお礼を申し上げたい。
最後に、本書が広く読まれることにより、法のすみずみにまで行き渡るさまざまな感情が照らし出され、法をめぐる議論がさらに豊穣なものへと発展してゆくことを心より願っている。
2023 年3 月
橋本祐子
(傍点は割愛しました)