あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
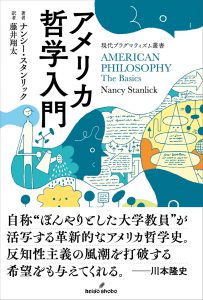 ナンシー・スタンリック 著
ナンシー・スタンリック 著
藤井翔太 訳
『アメリカ哲学入門』
→〈「日本語版への序文」/「訳者解題」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「訳者解題」本文はサンプル画像の下に続いています。
日本語版への序文
私が『アメリカ哲学入門』〔の原著〕を執筆した二〇一三年のアメリカ社会を振り返ってみると、現在の、あるいは二〇一六年以降のアメリカ社会とは、かなり異なったものだったように(私には)思われる。二〇一六年以前の数年間、「希望〔hope〕」という言葉は単なる流行語(バズワード)ではなく、アメリカやアメリカ国民が目指すべき理想を表現するものだった。もしかしたら、〔このように感じられるのは〕私の認識でしかなく、現実はそうではなかった、という可能性もあるだろう。自分の視点や物事の理解が他の人と一致しないことがある――こうわきまえているという意味で、私はこの見解について、他の多くの事柄についてと同様に、非常に謙虚だと自負している。哲学の訓練・教育を受けた者の特徴とは、先入観、議論を構築する際の前提、そして到達した結論について、知的謙虚さを保った上で〔決定的なものではなく〕暫定的な言明をなすにとどめる――そして、それに従って行為する、という態度である。それに従って行為するということは、次のようなことを意味する。進んで他者と協力すること、他者の考えに耳を傾けること、他者の立場を理解しようと努めること、時には考えを改め、自らの可謬性〔過ちを犯しうる性質〕を認識すること、そして妥協を厭わないこと。妥協とは、自分とは異なる考えや行為を選ぶ他者と共通の基盤を見つけることである。そしてそれは、本書のいたるところに登場する、最も尊敬されるべき哲学者・思想家たちによって表現された偉大なアメリカの実験を自ら生き続けることを意味する。アメリカのプラグマティストたちは、慎重に練られた観念や議論の力を示す優れた例である。それによって彼らは、現実の理解、知識の獲得、そして善き生を送らんとする企図において、人間性の向上を導いたのだ。そしてその営みは多くの場合、価値のある目標を達成するために、観念と議論を修正することを意識したものだった。
例えば、一七八七年に開催された〔フィラデルフィア〕憲法制定会議で交わされた、合衆国憲法批准にまつわる賛否の議論を見てみよう。ベンジャミン・フランクリンはそこで、聴衆に向けて次のように提案した。「私は、次のことを願わずにはいられません――この文書にまだ異論を持っている会議メンバーの誰しもが、今回ばかりは私とともに、自らの無謬性〔過ちを犯すことがないという性質〕を僅かばかりでも疑い、私たちの間の〔見解の〕一致を明白なものにするために、この文書に自らの名前を〔署名という形で〕加えてくれることを」。フランクリンは、憲法制定者の間に意見の相違があるにもかかわらず、彼がこの文書に対して自信を抱いていることを表明し、その場にいた人々に対してこのような要求を呼びかけたのだった。「私はこの憲法に賛成します――たとえそれが欠点を有しているとしても。なぜなら私は、一般〔中央〕政府が私たちにとって必要であると考えており、そしていかなる形態の政府であろうと、うまく運営されれば人民にとって祝福となるはずだと信じているからです。さらに私は、〔私たちの新たな〕政府が何年にもわたってうまく運営されるだろうとも信じています。それでも、これまでに他の形態の政府がそうなったように、私たちの政府が暴政に陥る可能性もあるでしょう。そうなってしまう状況とは、人民が腐敗し、他の政治体制を選ぶだけの能力を失った結果として、暴政を必要とするような場合です」。
フランクリンが懸念としていたアメリカ合衆国の人民の腐敗、そして、〔現代の〕私たち〔の社会〕が自覚的かつ自発的に、ある種の暴政に陥りつつあるということ――私が憂慮しているのは、こうした事態にほかならない。米国には、極端な立場をとった上で、自分とほとんど、あるいは完全に同じ考え方をする人たちとだけ同調している人たちがいるように思われる。そうすることで、彼らは「他者」を理解し尊重する可能性を排除しているのだ。つまり、極端な右派や左派は、他者と対話し、誰もが納得できる妥協点を見出すことができないでいる、いや、そう試みることすらしないのである。彼らは自分たちの考えや生き方こそが端的に正しく、他者もそれと同じように考え生きるべきだと主張し、断固として譲らない(時には、人の自由を拡大するどころか、自由を制限する法律を制定するほどの極端に走る)。そして場合によっては、ミルが「世論の精神的強制」と呼んだ手法さえ用いたりする。しかしながら、これはアメリカ(合衆国)が理想としてきた国家のあり方ではない。だからといって、生き方、あり方〔being〕、振る舞い方に関して、これまで常に合衆国の政党の間で平和的・協力的な関係が続いていた、というわけではない。私たち〔アメリカ国民〕の間では、常に意見の対立が存在していた。〔実際、〕一八六一年から一八六五年にかけての南北戦争は、アメリカの連合〔union〕を引き裂いたのであって、それを元に戻す作業は今日まで続いている。南北戦争の大義や理由については、アメリカ国内でも意見が分かれている。ある者は州の権利のため〔の戦い〕だったと主張し、またある者は奴隷制度を終わらせるのが目的だったと述べる。私たちの意見の相違は、時に根深く、着実に、そして長く続くものなのである。
しかし、二〇一六年頃に何かが起こったように思われる。不和と憎悪が日常を規定するようになった、とでも言おうか。個人崇拝に起因する政治的な分断が定着し、長い間アメリカの思想と行為を特徴づけてきた観念や理想を支持する人々よりも目立つようになっていった。その結果、数々の相違点を克服するという、私たち〔アメリカ人〕がいつも持ち合わせていた能力は阻害されるようになった。この点についても再び、ベンジャミン・フランクリンの知恵ある言葉が、今日のアメリカ社会が抱える問題の一端を捉えているように私には思われる。彼は憲法制定会議で次のような発言もしている。「私は長く生きてきた中で、自分が一度は正しいと考えた重要な事柄について、後によりよい情報を得たり、より周到に考察したりすることによって、あとで自分が間違っていたことに気づき、見解を改めざるをえなくなった、という経験をたくさんしてきました。ですから、年をとればとるほど、私は自分の判断を疑い、他人の判断に敬意を払うように変わっていった、ということです。多くの人は、たいていの宗教の宗派と同様に、自分が真理を完全に握っていると考え、他人が自分と異なるところはすべて誤りであると考えるものです」。さらに、彼はユーモアをたっぷり交えて次のように続けた。「ですが、多くの人は自分自身の正しさを、自らの所属する宗派の無謬性と同じくらい高く評価しているにもかかわらず、そのことを自然に表現する能力ということに関しては、とあるフランス人女性に勝る人はほとんどいません。その女性は、自身の姉にこう言ったのでした――『お姉様、どうしてなのか分からないのですが、正しい見解を持っているのはいつも私の方で、他に正しいことを言っている人を見かけたことは一度もないのです』、と」。簡単にいえば、フランクリンは賢明にも、自分自身の可謬性を認識していたということだ。それに加え、〔第一に〕自分が正しい・真であると信じている事柄や、自分が「正しい」と考える生き方に人々が夢中になっていること、〔第二に〕意見や生き方は真理や虚偽の問題ではなくてむしろ選好〔preference〕の問題だという事情を人々が捉え損なっていること、そして〔第三に〕ある人や宗派が持つ選好は、もしそれが他者の選好の邪魔になったり害を与えたりしないのであれば、それを法律や社会的・個人的な制御の対象とするのは不適切であること――これらについても、彼はよく理解していたのである。
アメリカの建国者の一人であるトマス・ジェファソンは、『ヴァージニア覚え書』において、支配者や政府が個々の人間の問題に干渉する権限について次のように述べている。「支配者の権限は、われわれ人民が彼等に委託した自然権についてのみ、及びうるものなのである。良心の権利を、われわれは決して彼等の手に委ねはしなかったし、また委ねることもできない。良心の権利については、われわれは神に対して責任を持つのである。政府の合法的な権限というものは、他人を害するような行為に対してのみ及ぶものである。しかし、たとえば私の隣人が神は二十もあるといっても、あるいは神は存在しないのだといっても、私には少しも害を及ぼすことはない。それは、私の財布を奪うこともないし、私の脚を折るようなこともない」。この点でジェファソンは、イギリスの〔哲学者〕ジョン・スチュアート・ミルの『自由論』を先取りしていたといえる。ミルが同書で表明していたのは、「危害原理〔harm principle〕」の範囲を超えては、他者の行為を制限することはできない、という主張だった。危害原理については、次のように簡潔に説明されている。「文明社会のどの成員に対してであれ、本人の意向に反して権力を行使しても正当でありうるのは、他の人々への危害を防止するという目的の場合だけである」。そしてミルは、「個人は、自分自身の身体と精神に対しては、主権者である」と結論づけている。別の言い方をすれば、ある人の行為がその行為者当人に害をもたらすものであるとき、そのようなことをするべきではない、とその人を説得することや、ある宗教の信者に対して、そのような教えや教義を信じるのは誤っている、と説き伏せること――私たちは当然ながら、これらを試みる権利を持っている。一方で私たちには、他人が自分の思うように生きることを止めるような権利があるわけでは全くない。ニューイングランドのトランセンデンタリストであるヘンリー・デイヴィッド・ソローは、著書『ウォールデン』において、個人主義というアメリカ人にとっての健全な精神を表現するものとして、おそらく最良といえる言葉を残している。「ある男の歩調が仲間たちの歩調とあわないとすれば、それは彼がほかの鼓手(ドラマー)のリズムを聞いているからであろう。めいめいが自分の耳に聞こえてくる音楽にあわせて歩を進めようではないか。それがどんな旋律であろうと、またどれほど遠くから聞こえてこようと」。
私たちは、〔アメリカという国家の〕建国者や、リベラルな伝統に属する哲学者たちの知恵を失い、それを騒音(ノイズ)に置き換えてしまったのではないか――そして、新たに招き入れられた不協和音のような喧噪が、音程・音量を高めていき、自身に同意しない者〔の声〕をかき消そうとしているのではないか。建国者たちの知恵に取って代わったもの、それは「五分で読める」Facebook の投稿、TikTokの動画、そして、あまりにも多くのアメリカ人が書籍や〔宗教の〕教説に書かれている言葉を信じていると言いながら、それを読んだことすらなかったり、そうした文献を誰かに解釈してもらうことを求めたりするという、驚くべき傾向である。私が愛するアメリカの考え方においては、このような有様は、アメリカがいかなるものであるか、あるいはアメリカはどのように経験されるべきか〔という理念〕からは、かけ離れたものだ。私たちの歴史、そして私たちの観念の歴史は、これよりもずっと豊かである。私たちの未来が有する価値は、政治的ハッカーや自己愛に満ちた権力闘争、独善的な活動家(アクティヴィスト)、あるいは人種差別主義者や性差別主義者、同性愛嫌悪者、外国人嫌悪者などに任せられるほど、小さなものではない。こうした輩たちは、過剰なまでの確信とともに発言・行動し、そのせいで彼らと意見をともにしない人々を沈黙させて、私たちを千々に分断するのである。
私は、穏健な精神と冷静な頭脳が最終的には勝利を収めることを望んでやまない。
ナンシー・A・スタンリック
フロリダ州オーランドにて
二〇二三年六月一三日
(訳注は割愛しました)
訳者解題
本書は、Nancy A. Stanlick, American Philosophy: The Basics (London: Routledge, 2013)の全訳に、日本語版の序文を付したものである。人文・社会科学系の大手出版社ラウトレッジを版元とする原著は、「当該テーマを初めて学ぶ学生を読者層として、その分野の基本事項を導入し、発展学習に向けた理想的な踏切り板となることを意図」した「The Basics(基礎)」シリーズの一冊として出版されている。題名に違わず、本書はアメリカ哲学史における重要人物の思想を概観することを趣旨としており、特定の学派に焦点を当てたものではない。しかし、そこで採用されている視座と問題意識を鑑みて、この日本語版は勁草書房の「現代プラグマティズム叢書」の一書として位置づけられている。
著者について
著者のナンシー・スタンリックは、アメリカ合衆国の哲学研究者である。一九八一年にサウス・フロリダ大学哲学科を卒業後、同大学で修士号(一九八三年)と博士号(一九九五年)をそれぞれ取得している。博士課程では、社会科学の哲学の専門家として知られるスティーヴン・ターナーを指導教員とし、ホッブズの政治哲学についての博士論文によって学位を得た(ちなみに、彼女は同大学から哲学の博士号を得た史上初の女性だという)。職歴としては、セントラル・フロリダ大学を含むいくつかの大学で非常勤講師として教えた後、二〇〇一年に同大学の専任教員に着任し、現在に至るまで教育・研究・大学行政にあたっている。二〇一五年には同大学で正教授に昇進し、副学部長等の要職を経て、二〇二三年八月には哲学科の学科長に就任している。
スタンリックは倫理学・社会哲学、近代哲学史(特にアメリカ哲学とホッブズ)等を専門としており、関連する業績として次がある。
1. Philosophy in America (Volume I): Primary Readings. Upper Saddle River, NJ: Pearson,2004. (Bruce S. Silver との共編)
2. Philosophy in America (Volume II): Interpretive Essays. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2004. (Bruce S. Silver との共著)
3. American Philosophy: The Basics, London: Routledge, 2013. (単著〔本書〕)
4. Asking Good Questions: Case Studies in Ethics and Critical Thinking, Indianapolis: Hackett Publishing Company, 2015 . (Michael Strawser との共著)
5. The Essential Leviathan: A Modernized Edition. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 2016 . (Thomas Hobbes 著、Daniel P. Collette との共編)
6. Understanding Digital Ethics: Cases and Contexts, New York: Routledge, 2019. (Jonathan Beever とRudy McDaniel との共著)
上記のうち、1から3がアメリカ哲学に関するもの、4と6が倫理学・社会哲学に関するもの、そして5が近代哲学史に関するものである。また著者はこれ以外にも、オンラインの無料哲学百科事典として知られる『インターネット哲学百科事典(Internet Encyclopedia of Philosophy, IEP)』のアメリカ哲学関連記事の責任編集者を務めていることも、注目に値するだろう。
本書の特徴
本書は一見、実に穏当な大学生向けの教科書のような顔をしている。第一章で予告されているように、アメリカ哲学史に登場する代表的な思想傾向が時代に沿って大まかに分類され、それぞれの章では一定の傾向を共有する論者たちの思想が簡単に解説されていく。重要な哲学的概念は太字で示され、それらの意味は巻末の「用語解説」で説明される。また、各章の結論部の前には、当該の章で紹介された議論に対する批判的考察がなされる節がもうけられている。これは、本書を教科書として用いる学生や一般読者が各テーマを授業内外で討議し、深い理解を得られるようにするための工夫だろう。実際に、原著に寄せられた複数の書評において、本書の教科書としての質は概ね高い評価を得ている。
一方で本書は、誰を「アメリカの哲学者」として扱うかについては、必ずしも多くの伝統的な哲学(研究)者が同意するとは限らない、挑戦的な選択を行っている。すなわち、ヨーロッパ系の白人男性哲学者だけではなく、女性、黒人、ネイティヴ・アメリカンといったアイデンティティを持つ論者についても、本書は積極的かつ大々的に取り上げているのだ。全体の概要を示す第一章に続いて、第二章で神学者のジョナサン・エドワーズを最初のヨーロッパ系アメリカ人哲学者として位置づけるのは「実のところきわめてオーソドックスな哲学史観」だし、第三章でなされているようにアメリカ建国の父たちの議論と思想を「哲学」として扱うことも、これまでに例がないわけではない。だが、続く第四章では前章で扱われたトマス・ジェファソンらの奴隷制度をめぐる言説が批判的に検討された上で、フレデリック・ダグラスやグリムケ姉妹らの議論が紹介されているが、こうした名前が主題的に登場するのは哲学書としては珍しいだろう。また、第五章ではトランセンデンタリストのエマソンとソローに加えて、一般には黒人社会学者・思想家として知られるデュボイスや政治活動家のゴールドマンが紹介されている。プラグマティズムを扱う第六章の人選と内容は標準的なものだが、アメリカ哲学の最近の展開をまとめた第七章では、認識論と科学哲学の議論に続いてネイティヴ・アメリカンの哲学が、そして第八章では、政治哲学に続けてフェミニスト倫理学と黒人神学の議論が概観される。このような構成の哲学史は管見の限り(この原稿を執筆している時点で)本邦では例がなく、哲学(のみ)に馴染みがある読者にとっては初めて見かける名前も少なくないだろうと思われる。
本書の特徴は、同様のテーマを扱った類書と比較するとより明白になるだろう。アメリカ哲学(史)を主題とする日本語の書籍の数はそもそも少なく、そしてその多くは書かれてからかなりの時間が経ったものだが、そのいずれにおいても、例えばダグラスやデュボイスのような黒人思想家や、グリムケ姉妹に紙幅が割かれることはない。また、執筆時期が比較的最近で、内容面でも(この原稿の執筆時点で)最も包括的な範囲をカバーするものだといえるブルース・ククリックのアメリカ哲学史についても、残念ながら事情は大きく変わらない。実際、同書日本語版には訳者らが作成した「主要人物表」が付録として収められており、そこには実に六二人の名前が挙げられているが、女性哲学者のルース・バーカン・マーカスがかろうじてリスト入りしているものの、それを除いては全員が男性であり、黒人やネイティヴ・アメリカンをルーツとする論者は一人もいない。
それでは、なぜこれまで書かれてきた多くのアメリカ哲学史では、もっぱらヨーロッパ系の白人男性ばかりが取り上げられてきたのだろうか? 哲学史家たちはみな、人種差別主義的・性差別主義的な偏見をもって、意図的に女性や有色人種の論者を排除してきたのだろうか? 高名な哲学者の著作においてすら極端な主張が確認できる以上、そのような傾向を有した人々が一定数いたことは確かだろう。しかし、哲学とは何であるかについては、必ずしも明示的・意識的な悪意を介在しない仕方で、特定の人々の思弁や活動を指す特殊な営みとして理解されてきたという事情も少なからずあったと考えられる。つまり、「哲学的」とされる問題群に何が含まれるかについては、知的コミュニティにおいてある程度の共通了解があり続けたであろうし、社会的・具体的な実践を従、それに対する理論的考察を主とする優先順位も、古代から続く基層的価値観として影響力を持っていたと思われる。また、哲学が大学を中心とする学術制度の中に組み込まれて以降は、そのシステムの中での正統的なトレーニングや学位の有無・種類、また議論の形式や文体についても、一定の様式が整備されていった。このようにして経路依存的に引き継がれてきた議論環境においては、標準とされる問題設定・論述様式、あるいは専門家たちの哲学的議論のサークルに参加するために求められる諸々の要件(例えば学位とそれを裏づける学術的訓練)を満たさない思想家たちやその言葉は、哲学ならざるものとしてみなされてきた。
スタンリックはこうした傾向に抗い、(アメリカ)哲学を保守的・硬直的・静態的な定義から解放することを提案する。ここで彼女が採用するのが、プラグマティスト的な視座である。すなわち、哲学の特徴は「人間の理解や行為に対して観念が影響を与えること」であり、哲学的観念は「現実、知識、そして善き生についての人間の理解や行為を駆動する知的原動力」(本書二頁)だとして捉え直すのである。この拡張された定義においては、理論を主、実践を従とする枠組みは転倒され、力強い思弁に基づく活動によって社会変革を目指す行為をも、「哲学」という営みの一つの相貌として理解することが可能になる。また、制度的な不正義によって高等教育を受けることができなかった女性や黒人の思想家のみならず、学術論文に代表される書き言葉を通じた形式的コミュニケーション手段によってではなく、口承によって知的伝統を表現・維持してきたネイティヴ・アメリカンも、哲学者として正当に名指されることになる。
本書の意義
本書のように、これまで見過ごされてきた人々にも光を当ててアメリカ哲学を辿り直すことの意味は何か? 一つは単純に、これまでに提出されてきた多くの哲学史が採用する視点の恣意性と偏向性、ひいては不正確性を暴く、という点があるだろう。つまり、それらは「アメリカ哲学史」ではなくて、「ヨーロッパ系白人男性哲学史」だったのではないか、という問題提起をなすものだということである。本書のような小著においては、議論の質や影響力の観点から見て取り上げられるべき哲学者が網羅されうるわけもないし、現に扱われている人物にしても、そのそれぞれについて思想史的な観点から見て必ずしも厳密な論述がなされているとはいえない――これらは著者自身が自覚している本書の限界ではある。だが、本書はそういった課題を抱えてなお、古いアメリカ哲学史に欠けていた(しかし含まれるべきだった)人種的、性別的、文化的グループ(の少なくとも一部)による知的貢献を正当に評価するものであり、その意味で、アメリカ哲学の系譜に対するより包括的な把握に向けた前進、あるいはそれに向けた提言として価値あるものだといえるのではないか? そして本書の二つ目の意義とは、このような哲学史の再記述は、それ自体が倫理的な行為として捉えられうるということである。現代認識論においては、知識の担い手が帯びる権力の高低や社会的立場によって、その人物の証言の信頼性が不当かつ恣意的に低く見積もられるという事象に注目した、認識的不正義というアプローチが注目されている。その顰みに倣っていえば、(アメリカ)哲学史において特定のカテゴリーに属する人々の議論に特権的立場が与えられ、それ以外が(意図的・非意図的の別を問わず)排除されるという事態も、まさにそうした不正の例なのではないか? 不当に冷遇されてきた哲学者たちにしかるべき尊敬を向けることは、その意味で正義にかなった行為だといえるのではないだろうか?
本書の打ち出す哲学観とそこから紡ぎ出されるアメリカ哲学史は画期的なものである。そしてそうした試みの常として、異論・批判を免れる術はないだろう。「本物の」哲学からの逸脱、理念とすべき真理や客観性を蔑ろにする哲学の政治化、プラグマティスト的哲学史観に合わせた人物や議論の恣意的選択(チェリー・ピッキング)――こうした疑義は当然ながら寄せられるだろうし、すべてではないにしてもその一部は妥当な指摘だろうとも思う。ただ、そうした議論も含め、読者が本書の功績と課題を批判的に考察することはむしろ歓迎すべきことであり、それは本書の美点である明快にして簡潔な筆致が喚起するものなのだと、私は考えている。アメリカ哲学、ひいては広く哲学や思想の歴史の叙述・認識において、誰がいかなる視座をとり、それを引き受けていくのか――こうした議論や思索の契機を提供することこそが、訳者である私の願いである。
謝辞
本書を完成させるにあたり、次の方々から重要なご支援・ご助力を賜った。ここに厚く御礼申し上げる。原著者のナンシー・スタンリック氏は、Zoom で本書について議論する機会を作ってくださり、寛大にも日本語版序文を執筆いただいた。「アメリカらしさ」を哲学者たちのリベラルな理念の中に見出そうとするこの力強い文章からは、対話の喪失と社会的分断に特徴づけられる現代社会に対する彼女の強い懸念と同時に、アメリカ哲学に対する生きた希望が表現されている。勁草書房で編集を担当してくださったのは山田政弘氏である。彼は哲学書を中心として同社から出された数多くの名著を手掛けた編集者として知られている。その評判に違わず、怠惰な私にも無理なく遵守可能な出版スケジュールを提案してくださり、意味の取りにくい文章に対する的確な修正提案もいただいた。また、業務連絡に際してメールではなくMicrosoft Teams を利用することに同意いただけたことを、とりわけありがたく思っている。同じく勁草書房の鈴木クニエ氏の名前もここで挙げない訳にはいかない。かつて私は、哲学関連の文章を英語で読むオンライン講座を開いていたことがあるが、それにたびたび参加してくださっていたのが鈴木氏だった。彼女が私を山田氏に紹介してくださることなしには、本書の企画は現実のものになることはなかっただろう。哲学関係の語彙を中心に本書全体をチェックしてくれたのは、哲学研究者の飯泉佑介氏である。訳文・訳語に対する彼の指摘のおかげで、本書の質は間違いなく向上した(そして当然ながら、本書に何らかの問題が残っているとしたら、その責任は私にある)。キャロル・ギリガンや正義論を主題とする川本隆史先生の大学院ゼミに共に出席していた飯泉氏の協力と励ましによって、その授業の精神に通じたアメリカ哲学の作品を仕上げられたことを感慨深く思っている。
藤井翔太
(※注は割愛しました。上記pdfでご覧ください。)








