あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
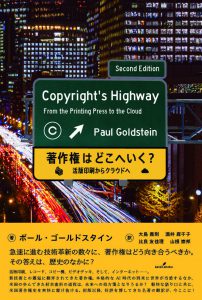 ポール・ゴールドスタイン 著
ポール・ゴールドスタイン 著
大島義則・酒井麻千子・比良友佳理・山根崇邦 訳
『著作権はどこへいく? 活版印刷からクラウドへ』
→〈「日本語版への序文」「訳者あとがき」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「日本語版序文」「訳者あとがき」本文はサンプル画像の下に続いています。
日本語版への序文
学術書の書き手にとって、自分の作品が他の言語に翻訳され、新たな読者の目に触れることほど名誉なことはない。これは、本書のように、そのテーマが文学的・芸術的表現制作と世界的流通を取り巻く法的環境の理解に捧げられたものである場合には、尚更そうである。本書の翻訳に強い情熱と学術的な配慮をもって取り組んでくださった大島義則専修大学教授・弁護士、酒井麻千子東京大学准教授、比良友佳理京都教育大学講師、山根崇邦同志社大学教授には、心から感謝申し上げたい。
本書は、日本の著作権法を明示的には取り上げていないが、日本法が堅持する大陸法系の著作者の権利の伝統に関する広範な議論を通じて、その実質を明らかにしている。英米法系のコピーライトの伝統に学んだ法律家は、表向きロマン主義的な著作者観や作者という地位にこだわりをもつ大陸法系の伝統よりも、功利主義的で実用主義的な英米著作権の優位性を主張することがある。しかし、これほど見当違いな批判はないだろう。第五章で説明したように、著作者の権利の法であっても、制度設計次第で、その範囲を真に作者の個性が発露した作品に限定したり、日本の著作権法のように、工業製品の保護を隣接する法領域に促すこともできるからである。実際のところ、著作者の権利の法が結果として生みだす柔軟性には、英米法系のコピーライトよりも実用主義的な面がある。
この点は、一九八〇年代の知的財産権によるコンピュータプログラムの保護という難問に対する日本の対応を例にとれば、よくわかるだろう。諸外国がコンピュータコードを自国の著作権法の体系に当てはめることに苦慮していた当時、日本の通商産業省は、ソフトウェアの技術的・経済的特性に特化した特別なプログラム権法を提案した。この提案は、著作権法や特許法の概念を借用しつつも、日本の著作権法におけるコンピュータプログラムの保護を明確に否定するものであった。日本は最終的に、国際礼譲という最も現実的かつ最優先の理由から、コンピュータプログラムの著作権による保護という新たな国際規範に落ち着いたけれども、今日、世界各国がソフトウェア著作権に関して、著作権というラベルの下で、かつて通産省が提起した懸念に対策を講じているのは偶然ではない。たとえば、EUコンピュータプログラム指令は、著作権に関して特別な条項を置いているし、米国著作権法も、コンピュータプログラムに関して、著作権の範囲を制限し、システムの互換性を確保する目的でコピーを作成する行為を免責している。
現在では生成AIが、著作権のルールに新たな、さらに大きな挑戦を突きつけている。AIをサポートする大規模な言語モデルの学習は、トレーニングセットを形成する多数の作品の著作権を侵害するだろうか。生成AIを利用して生みだされた成果物は、著作権保護の対象となるだろうか。日本の立法者はすでにこれらの疑問に答え始めており、その継続的な取り組みは、ソフトウェアの保護に関する問題の解決と同様に、国際的な影響を与えずにはいられない。本書の読者が、著作権と新技術の織りなす歴史の教訓のなかに、生成AIという著作権制度に対する最新技術の挑戦を上手く解決するための指針を見つけだしてくれることを、切に願っている。
二〇二三年九月二八日
ポール・ゴールドスタイン
カリフォルニア州スタンフォード
訳者あとがき
酒井麻千子
1 はじめに
本書は、Paul Goldstein, Copyright’s Highway: From the Printing Press to the Cloud (2nd ed.), Stanford University Press, 2019 の全訳である。著者はスタンフォード大学ロースクールStella W. And Ira S. Lillick 寄付講座教授で、著作権法の講義を担当している。自身の名を冠した著作権法の学術書をはじめとして、現在は版を重ね共著となっているが、国際著作権法の教科書や知的財産法のケースブックなど、多数の専門書及び学術論文を公表している。また著者は法律を題材にした小説家としても有名で、二〇一三年には三作目の小説で法廷小説に与えられる文学賞も獲得した。著者のウェブサイトを拝見すると、本書は多彩な著作のうち一般向けの書籍に位置づけられるようだが、法律の専門的な内容が多数含まれ、読み応えのあるものとなっている。
米国を中心とした著作権の歴史(コピーライト・ハイウェイ)をたどる本書は、一九九四年に初版、二〇〇三年に改訂版が出版された。初版及び改訂版は、‘From Gutenberg to the Celestial Jukebox’ という副題がつけられていが、第二版の本書は‘From the Printing Press to the Cloud’ に変更されている。章構成も変化していて、初版は六章構成、改訂版は初版の六章の部分を大幅に書き改めつつ一章拡張して七章構成、そして本書は七章に新たな事象を書き加えつつ八章をほぼ書き下ろした形で八章構成となっており、より現代に近い技術を取り上げた章を拡張・新設している(もちろん、他の章も最新の事情を踏まえた修正が適宜なされている)。第二版の副題変更はこれらの変化を踏まえたものであろう。いわばハイウェイの延伸である。
以下では、本書を読み進めるにあたって有益と思われる思考の補助線を示しつつ、本書の学術的意義に触れることにする。
2 いくつかの補助線
⑴ 本書における、著作権の歴史の取扱い方について
本書は著作権の歴史をたどるものではあるが、歴史的事実を列挙するものではない。著者は、きわめて現代的かつプラクティカルな問題意識から、歴史を取り扱っている。すなわち、著作権が対象としてきた情報・娯楽市場の構造は、技術革新に伴い劇的に変化しており、世の中の大抵の情報や娯楽はほぼ無料で手に入れることができるようになった。そのような中で、著作権は創造的な作品の創作・流通・享受に対して適切な役割を果たし、「新たな情報・娯楽環境がもたらす挑戦に対応できるのだろうか」(二六頁)、より端的には、著作権の役目は残っているのだろうか、という問題である。
著者はこの問いに対して、新たな技術との遭遇に立法や司法を通じて対処し続けてきた著作権の歴史こそが、方針の手がかりを与えてくれる、と考える。そこで、コピーライト・ハイウェイを一気に駆け抜け、その道程から「実用的な教訓」(二八二頁)を得て、立法への「処方箋」(同頁)を引き出し、道半ばのハイウェイのその先を予想するのである。
したがって、本書で取り扱う歴史の事象は、「著作権がその時々の新技術とどのように対峙してきたのか」という観点からピックアップされ記述される。著作権法誕生の契機となった活版印刷技術に始まり、写真、映画、レコード、ラジオ、ビデオテープ・ビデオデッキ、そしてデジタル技術とインターネット。加えて、筆者は単に関連する立法・判例・学説を記述するだけでなく、特に戦後以降の関係当事者に行った綿密なインタビューを元にして、当時の議論をまとめている。本書が読み物としても面白く感じるのは、えてして長くつまらなくなりがちな歴史の話を、鮮やかに、そして軽やかに走り抜ける爽快感があるからであろう。
⑵ 「天空のジュークボックス」について
本書に頻繁に登場する言葉の一つに、「天空のジュークボックス」がある。第二版では副題から削除されたこの言葉は、もともと筆者が一九九四年の初版において、デジタル技術とインターネットがもたらす未来の可能性を示す技術イメージを指す言葉として考案したものだった。それは、ユーザーが瞬時にかつオンデマンドに、大量の情報・娯楽の宝庫へアクセスできるようになる技術やサービスが近い将来提供される、というものである。そして本書七章にもあるとおり、この「天空のジュークボックス」という言葉は一九九五年の米国政府の白書に採用され、広く知られることとなった。
「天空のジュークボックス」は、二〇二三年の現在においてはほぼ達成できていると言えなくもない。アイチューンズのように曲単位で音楽やMVをダウンロード・視聴できるサービスにとどまらず、スポティファイのようなストリーミングサービスも日常的に使われている。音楽だけでなく、映画、書籍も含め、膨大なコンテンツに即時アクセスし、享受することができるようになった。しかしながら、筆者の当初の予想と異なったのは、このイメージを最もよく想起させうるユーチューブなどのオンライン・プラットフォームが、コンテンツ提供の対価に五セント硬貨を求めるジュークボックスではなく、広告収入モデルを通じて無料でコンテンツをユーザーに提供したことである。包括ライセンスの締結や収益の分配を通じて権利者に一定の金額を支払う、コンテンツモデレーション技術を用いて適切に侵害コンテンツを管理する、といった対応によって状況は変わりつつあるが、いわゆるバリューギャップ問題(ユーチューブ等が音楽配信から得る利益と権利者に還元される利益が不均衡であること)への懸念も根強い。
⑶ 「著作権のコップ」について
「天空のジュークボックス」と同じくらい高頻度で登場するのが、「著作権のコップ」の比喩である。著者はこれを、著作権楽観論者と著作権悲観論者との対立を示すために用いている。著作権楽観論者は、著作権は創作を行った著作者に対して、著作者の利益を害しうる著作物のあらゆる利用に及ぶ支配権を認めるものだと捉える(自然権論)。したがって、「著作権のコップ」に入る水は多ければ多いほど良いと考えるのである。他方、悲観論者は、著作権は著作者のインセンティブを与えるのに必要な限度に限るべきで、著作者と利用者のニーズのバランスを図ることが重要だと考えている(功利主義)。したがって、「著作権のコップ」は半分空であるのがよい、と考える。
本書でも示されるように、両者の対立は著作権法上よく知られており、実際立法や司法の場で火花を散らしてきた。しかし著者は、五章において、歴史上両者は対立するだけでなく、しばしば肩を組んで著作権の保護を担保してきたことも指摘する。これは、両者が「著作権のコップ」の水量を問題にしていても、コップが空であることは想定していない点からも明らかである。
3 本書の学術的意義
本書から得られた知見をまとめると、以下の二点になる。
⑴ 歴史から得られる「実用的な教訓」と立法への「処方箋」
やはり最も注目されるのは、歴史から得られる「実用的な教訓」と立法への「処方箋」であろう。これは八章で詳述される。
まず前提として、著者は立法の重要性を強調する。米国の著作権政策において、議会(立法)だけでなく裁判所(司法)もしばしば新たな技術と対峙する役割を担ってきたこと、特に二一世紀に入ってからは、立法活動の事実上の停止を背景に司法の役割が高まったことを確認する。しかし、司法の判断は、ユーザーの利便性を確保しつつ権利者にも一定の利益還元を行う、といった中間的な解決策を示すことが難しい点を指摘し、より良い制度づくりのためには立法が必要であると考えている。
その上で、新技術に対処するための立法作業について、著者は著作権の歴史から得た二つの具体的な「処方箋」を――初版から変わらず――提示する。第一に、新技術によって新たな著作物候補となりうる素材が現れても、著作権の範囲を直ちに拡張せず、著作権の歴史的な価値観から慎重に判断すべきである点、第二に、新技術によって新たな技術的利用が現れた場合、つまり新たな侵害態様が生じた場合は、克服できない執行コストが立ちはだからない限り、これを捕捉するように迅速に著作権を拡張すべきである点である(二八二頁)。
著者の見解は、2⑵で挙げた「著作権のコップ」をめぐる対立――つまり自然権論と功利主義という相反する立場から生じる、それぞれの著作権のあり方――のどちらが望ましいのか、といった視点から結論を引き出すのではなく、著作権の歴史を振り返りながら、どちらの立場でも許容しうる方針を提示するという点で、一定の実務的な価値を有し、新たな技術と対峙し続ける著作権政策の方向性に示唆を与えるものである。しかし、著者の提示する二つの「処方箋」自体には、疑問なしとしない。特に第二の処方箋については、新たな著作物の技術的利用が、公平性の観点からユーザーに認められるべき場合であっても常に禁止されてしまうのではないか、といった懸念が生じうる。こうした懸念に立法が具体的に(後述する「道徳的な輝き」(二八四頁)でもって)対応する必要性を著者は認識しているが、にもかかわらずデフォルトを新たな利用の禁止に置くのは、著者が歴史から得た「実用的な教訓」が関係していると考えられる。その教訓とは、昔も今も「ただ著作権制度が機能している」(二八二頁)こと、著作権が長い間、「増大し続ける創造的な作品の数々を、どんどん低廉なコストで社会が入手することを、決して妨げなかった」(同頁)ことである。つまり著者は、「昔から今まで続く」著作権制度が果たしてきた機能をおそらく是と捉えており、新たな利用はこの状態を崩すので捕捉されるべきである、と考えているように思われる(これは同時に、新たな素材を著作権の対象とすることに消極的な要因にもなる)。
しかしながら、このスタンスに対しても批判が生じうるだろう。例えば、著者の立場はただ現状を追認しているだけで、いわゆる「現状維持バイアス」を強化してしまうのではないか、という批判である。この点について深く掘り下げる紙幅の余裕はないが、著者はこの批判に対しても一定の回答を用意しているように思われる。それが⑵である。
⑵ 著作権の役割と倫理あるいは道徳的議論の重要性
著者は、最初の問題意識(現代における著作権の役割)を、⑴での議論を踏まえて示している。すなわち、著作権法が著作物利用のすみずみまで網羅すべきであるという「処方箋」を実践するためにもっとも効果的な役割は、著作権が「自力執行力のある規範」(二八七頁)となることである。他人の家の芝生をわざわざ横切って近道をする人がいないこと、他方で緊急時に芝生に踏み込むのを躊躇う人もいないことを挙げた上で、二一世紀の著作権の至上命題は、「制限と許可の原則を、不動産の規範と同じくらい道徳的に説得力のある行動規範として確立すること」(同頁)である、と著者は主張する。これは著作権侵害とすべき、あるいはすべきでない、という判断を誰もが守ってくれるようにするためには、合理的な説明とともに直感にも訴えかける必要がある。さらに著作権が永続的な規範として深く承認されるためには、「作者の顔」(二八八頁)を見せ、作者とユーザーがつながる必要がある点も指摘している。
このような主張を、歴史的に裏付けることができるのが著者の一番の強みであろう。特に第二章では、出版社が、自身の利益ではなく著者の利益を前面に出して様々な主張を行い、立法にも取り入れられたことが示されていた。またホームズ判事の新たな著作物利用に対する判断も、理論的な正しさ・精密さはもちろんのこと道徳的観念に強く訴えかけるものだった。このように著作権法はかつての「道徳的な輝き」を取り戻し、自力執行力のある規範となることが必要である、と著者は主張している。
4 おわりに
以上のように、本書は読み物としても面白いが学術的にも興味深い内容を含むものである。このような書籍を翻訳する機会をいただけたことは望外の喜びである。
最後になるが、本書の企画経緯について。本書の翻訳企画は、二〇二〇年一〇月、酒井が勁草書房の鈴木クニエ氏からメールをいただいたのがきっかけ……とつい先日まで思っていたのだが、実はそれよりもずっと以前に、同社の別の編集者の方に「『コピーライト・ハイウェイ』面白いですよ」と酒井が飲み会で話したのが真のきっかけで、第二版の出版を契機にお話を頂いたようである(大変恐縮だが本人は全く覚えていなかった)。その後、鈴木氏との相談を通じて、知的財産法がご専門で、既に同社で知財関連の翻訳書を手掛けておられた山根崇邦先生に企画参加をご快諾いただいた。そして「八章構成なので四人で各二章分担はどうだろうか」というアドバイスをいただき、同じく知的財産法がご専門で、本書のテーマに関連した論文も発表されていた比良友佳理先生、鈴木氏曰く「原著者は小説家の一面もあるので、ラノベに強く翻訳相性が良さそう」な大島義則先生にもお声がけして、豪華なメンバーで翻訳を進めることになった次第である。
翻訳作業は、担当章についてそれぞれ暫定訳を作ったのち、相互レビューを通じて訳語の調整もできるだけ綿密に行った。当初相互レビューはグーグルドキュメントのコメント機能を使ってクラウド上で作業する形にしたものの、なかなか捗らない訳者もいた。この状況を打破すべく、鈴木氏のご提案で、Zoomを用いたオンライン相互レビュー会を連日開催して一気に進めたのも今となっては良い記憶……である。なんとか刊行にこぎつけることができて、ほっとしている。
また著者であるポール・ゴールドスタイン先生は、本書の日本語版序文を書いてくださっただけでなく、訳者からの翻訳に関する質問にも快く答えてくださり、誠に感謝している。
出版にあたっては、鈴木氏に加え、同社の中東小百合氏に大変お世話になった。編集や校正では、特に中東氏に丁寧なチェックをいただいた。訳者の事情により、当初の予定よりも出版がかなり遅れてしまったにもかかわらず、辛抱強く待っていただき、また折に触れお気遣いをいただき、心から感謝申し上げる次第である。
書籍は制作過程もさることながら、何よりも、読者のみなさまが手に取ってくださることで完成する。本書が、著作権に関心のあるすべての人々にとって、楽しいドライブの時間となりますよう。
二〇二三年九月








