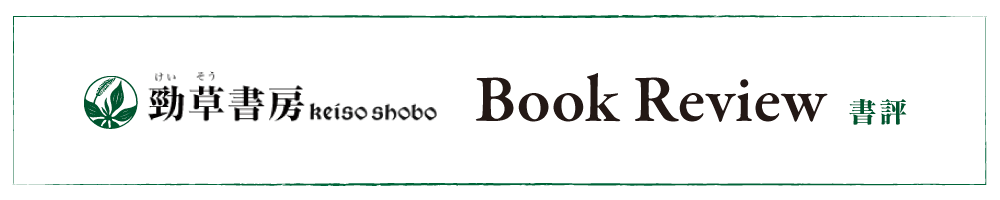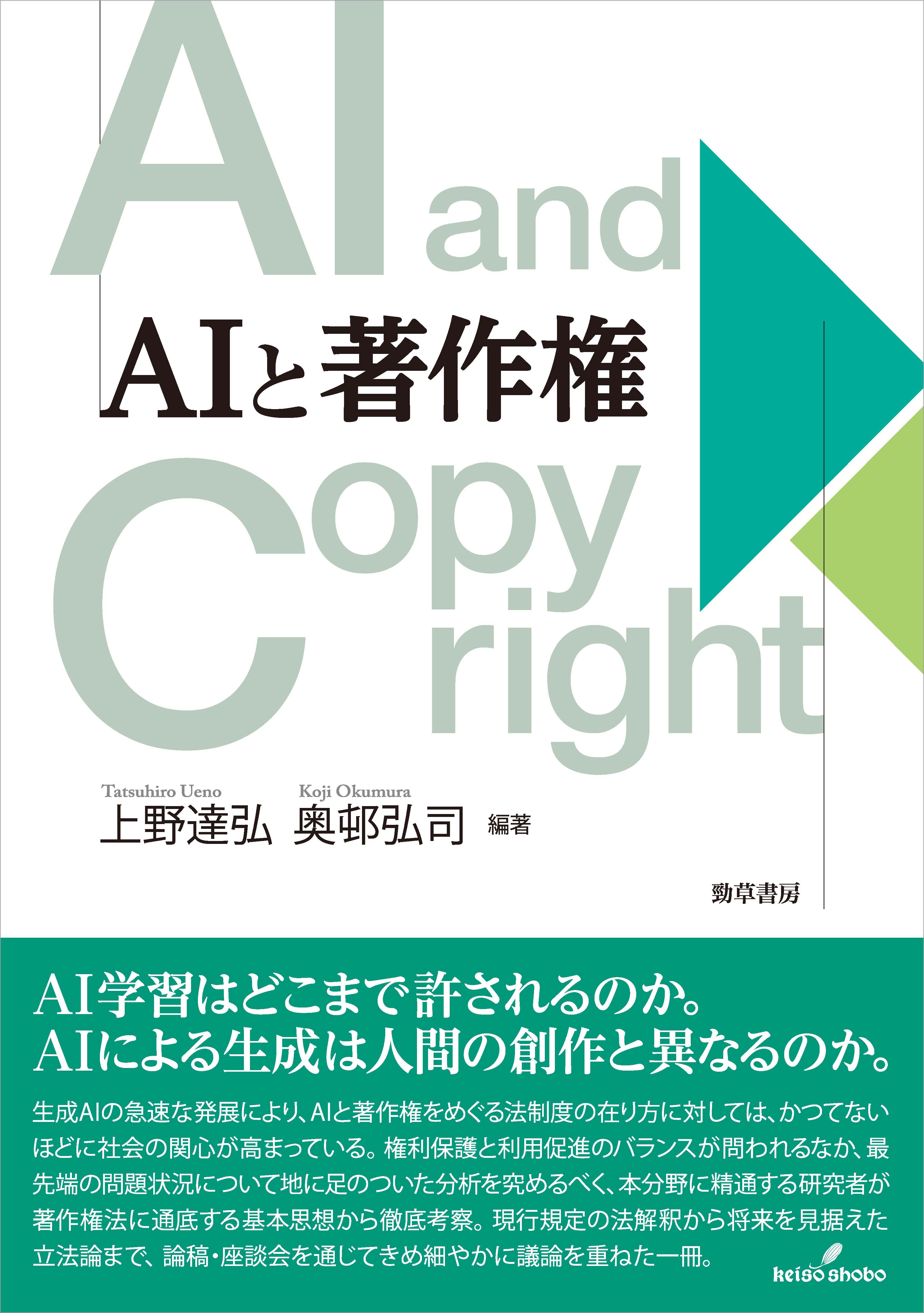
書評 「AIと著作権」のバイブル
評者 池村 聡
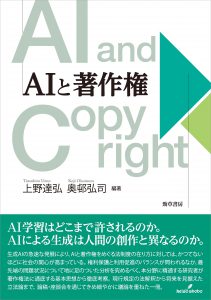
本書は、そのものズバリのタイトルが示すとおり、ここ数年、著作権業界を大いに賑わせている「AIと著作権」について網羅的に分析した書籍である。
もっとも、「書籍」といっても、本書はいわゆる法律実務書ではなく、現在の学会を代表する研究者たちによる最新論文が収録された珠玉の論文集である。
本書には、上野達弘教授による「『AIと著作権』の過去・現在・未来」と題する序論(PartⅠ)に続き、PartⅡとして、「日本法における権利制限-著作権法30条の4を中心に」(愛知靖之)、「諸外国における情報解析規定と日本法」(上野達弘)、「アメリカにおけるフェア・ユース該当性」(奥邨弘司)というAIによる学習段階における侵害の成否に関する論文が、続くPartⅢには、AIによる生成段階における侵害の成否に関する論文として、「類似・依拠」(奥邨弘司)、「行為主体と準拠法」(横山久芳)が、PartⅣには、AI生成物の著作権保護に関する論文として、「AI生成物の著作物性」(前田健)、「イギリスの著作権法におけるコンピュータ生成物の保護」(今村哲也)が、それぞれ掲載されている。
これら論文タイトルと執筆者名を見ただけでも、「このテーマならこの先生!」と言いたくなる、まさに垂涎のラインナップであり、刊行時期との関係から、文化審議会法制度小委員会が本年3月15日に公表した「AIと著作権に関する考え方」に関する記述こそないものの、本書は、同考え方に盛り込まれた内容を含め、AIと著作権に関する論点や最新の議論状況、海外の立法や判例の最新動向を正確に理解するための決定版、そして現時点におけるこれ以上ない最良の教材といえよう。
残念ながら、与えられている字数の都合上、本書に掲載された論文全てについて感想を述べる余裕はないので、ここでは実質的なトップバッターである愛知論文についてのみ、簡単に触れておきたい。
愛知教授といえば、AIと著作権という文脈では、何といっても、今ほどAIが世間で注目されていなかった2020年に発表した論文「AI生成物・機械学習と著作権法」(パテント73巻8号、2020年)が、よく知られているところである。愛知教授は、同論文において、「ディズニー映画風の新しい映画を作るAIを開発するために、ディズニー映画全てをコンピュータに入力して機械学習させる行為」を例に挙げ、こうした作風模倣のための学習行為につき、いち早く30条の4但書該当性を肯定し、著作権侵害に該当するという見解を表明しており、AIブームが到来したここ数年で一気に注目を集めるとともに、AIと著作権を巡る一連の議論においては、愛知教授の但書該当性肯定説を批判する見解が多く公表されている。本書に掲載された愛知論文では、30条の4の解釈に関し、様々な角度から事細かな分析がなされるとともに、前論文に対して寄せられた批判について丁寧に反論し、改めて但書該当性肯定説の支持を表明しており、非常に読み応えがあるものとなっている。
その他の掲載論文も、執筆陣の気合いが感じ取れる、いずれ劣らぬ素晴らしい仕上がりとなっており、非常に読み応えがある一方で、読み手の側にも相応の気合い(?)が求められるといえよう。
本書の大きな目玉は、上記論文集部分に続くPartV・座談会部分であり、ここには、上記各執筆陣及び谷川和幸教授により行われた、PartⅡ~Ⅳにおいて取り上げられた各テーマに関する議論の様子が収録されている。いずれのテーマに関しても、上野教授のスマートな進行とともに、和気あいあいとしながらも白熱した議論の様子が臨場感あふれる形で文字化されており、極めて刺激的な内容となっている。
座談会部分は、こと読みやすさという観点からは、論文集部分よりも読み手に優しいものとなっているため、論文集部分が難しいと感じた場合は、(奥邨教授がXで推奨していたように)まずは座談会部分から読んでみると良いだろう。ただ、座談会部分には、論文集部分における各執筆者の見解を前提にしたやり取りも少なくないため、時間と気合いがあるのであれば、やはり論文集部分から読み進め、その後座談会部分に入った方が、理解が深まると思われる。
本書を通じて、はからずも、自分がかつて文化庁で経験した立法作業のことを思い出し、今さらながら、その責任の重大さに身震いをした。本書では、30条の4を始めとするAIに関係する著作権法上の条文につき、細かな文言の使い方や他の条文との関係、改正の経緯(旧条文との関係)、主張立証責任の分配などの観点から、実に様々な解釈論が展開されている。私は、平成21年(2009年)から3年半、文化庁著作権課に出向し、平成21年改正、同24年改正に立法担当者の一人として関与し、内閣法制局審査等を通じて、様々な角度から、様々なケースを念頭に、様々な議論を繰り返し、一つ一つの条文を作り上げていく貴重な経験をした。立法作業は、様々な大人の事情や予期せぬ事態の影響を受けることもあり、必ずしも理屈だけで成り立っているものではないし、理屈の面に関しても、立法時において、全ての論点につき漏れなく正確な検討できているとは限らず、将来起きるあらゆる事象を見通した検討を行うことも不可能である。他方で、ひとたび立法が行われてしまえば、そうした立法時の事情などとは無関係に、その時代に応じて様々な解釈論が展開されていく。仮に自分が30条の4等の立法担当者だったとしたら、どんな気持ちで本書を読んだのだろう。本書は、そんなことを思わずにはいられない深い記述で溢れている。
つらつら述べてきたが、本書は、弁護士としてAIと著作権に関して日々様々な相談を受ける私にとって、常に参照するバイブルとなることは間違いない。だからというわけでもないが、思わず編著者の上野教授、奥邨教授から書籍にサインをして頂いたのであった。
三浦法律事務所 弁護士(第二東京弁護士会)。専門は、知的財産法。主著として、『はじめての著作権法』(日経文庫、2018年)、『実務者のための著作権ハンドブック(新版)』(共著、CRIC、2022年)、『著作権法コンメンタール別冊平成21年改正解説』(勁草書房、2010年)、『著作権法コンメンタール別冊平成24年改正解説』(共著、勁草書房、2013年)など。
『AIと著作権』
- 著者
- 上野達弘・奥邨弘司 編著
- ジャンル
- 法律
- 出版年月
- 2024年2月
- ISBN
- 978-4-326-40435-3
- 判型・頁数
- A5・352ページ
- 定価
- 3,300円(税込)
高機能生成AIは著作権の夢をみるか? 世界各国の最新動向と我が国における議論状況を踏まえ、今後の法規制の在り方を検討する。
勁草書房ウェブサイトへ https://www.keisoshobo.co.jp/book/b640472.html