あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
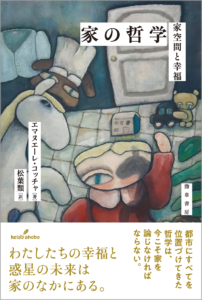 エマヌエーレ・コッチャ 著
エマヌエーレ・コッチャ 著
松葉 類 訳
『家の哲学 家空間と幸福』
→〈「訳者あとがき」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「訳者あとがき」本文はサンプル画像の下に続いています。
訳者あとがき
本書は、Emanuele Coccia, Philosophie de la maison: L’espace domestique et le bonheur, traduit par Léo Texier, Paris, Rivages, 2021 の全訳である。原著であるイタリア語版はFilosofia della casa: Lo spazio domestico e la felicità, Torino, Einaudi, 2021 だが、著者自身がフランス語で著述でき、訳にもみずから目を通していることと、元のコラムや講演がフランス語であること、仏伊語版がほぼ同時に出版されていることからも、原著との異同や解釈不一致の類はほぼないと思われる。
エマヌエーレ・コッチャは一九七六年生まれ、イタリア出身の哲学者である。農業学校出身で、ラテン・アヴェロエス主義やジョルジョ・アガンベン、ブルーノ・ラトゥール、ダナ・ハラウェイなどからインスピレーションを受けつつ、現在まで多岐にわたる分野――とりわけ生態学、美学――にかかわる著作を世に問うてきた(くわしい略歴は『メタモルフォーゼの哲学』(勁草書房、二〇二二)の訳者あとがきを参照のこと)。最新の単著は『ヒエラルキー――天使たちの社会』(二〇二三)である。彼のテクストへの注目度は高く、すでに本書も続々と各国語訳されており、彼自身も国や地域を問わず飛び回り、講演活動を盛んに行なっている。
*
本書のテーマは「家」である。一般向けに書かれたテクストということもあり、各章はコンパクトで読みやすく書かれているが、その内容は幅広く、また独自の着想に導かれている。あとがきでも述べられるように、家の哲学として始まるものの、いつのまにか世界についての議論へと接続している。理論書のように問題提起に対して一直線に答えを求めるのではなく、寄り道をしていると気づかないうちに元いた所とは違う場所にいるようなテクストである。読者は、彼の残した「インクのしみ」とともに小旅行へと誘われる。
全体を俯瞰してみれば、本書でのコッチャの手法はおそらく現代の人類学とでもいうべきもので、それを虚心坦懐に自分の日常的経験に適用している点がユニークである。住み慣れた自分の家において、ふいに「他者たち」と出会い、変様しあうとき、コッチャは記述と分析を開始する。そこで、いかなる「他者たち」が描かれているのかに着目しながら、以下では各章の内容について素描したい。
都市の哲学を論じる、J=F・リオタールの小編「場末(ゾーン) 」を思わせる序文に続き、彼が1章から2章において戸口をまたぐのは、まだ見ぬ「未来の家」である。「内見」と「引っ越し」は幸福の場でありうる家との出会いであり、さらにはそこに住んでいた「誰か」、いずれ住むであろう「わたし」、そして家を共有する別の生との出会いである。それはたんに住む空間を選ぶことのみならず、家のなかの細々とした日用品を介して家をつくることを意味する。
3章と9章ではトイレや浴室、寝室の独自の機能を通して、家の「間取り」について論じられる。部屋は、その性質によって身体や所作を限定するが、さらに精神を規定するものでもある。たとえば浴室は、その機能上、他の部屋から隔離されていなければならないが、その結果として性的な身体を閉じ込めてしまう。なお、ここでマルクスの「類的存在」への言及があるが、これは「類」と「社会的性=性別」が、フランス語で同じgenre という語を用いることからくる。コッチャはこの二重性を介して、近代的思考は労働のみならず性をも問題にすべきだったと主張している。9章では、不安定な存在感をもつ廊下と対比されながら、かつて子供部屋であった寝室の安心感が強調される。寝室で与えられる眠りとはたんに休息を与える時間ではなく、覚醒状態を差し止め、別の覚醒状態へと繫ぎあわせる心理的な外科手術である。
4章から6章で、コッチャは家のなかの物と出会う。4章では、それは「家財道具」である。家は抽象的な面積や空間ではなく、物を介して住まうことのできる場所である。物は互いに、そしてわたしたちに対して力を行使しており、磁気的または電気的ともいいうるネットワークを構成する。この力の出どころはわたしたちの人格であり、身体的接触を介してわたしたちは物に人格を与えつづけている。家とは、精神を宿した物たちが活動するアニミズム的空間なのだ。5章では、キャビネットのなかの「衣服」と出会う。服は防寒や日よけなどの機能をもつ防護用品であるのみならず、わたしたちのアイデンティティそのものである。かつてのように身分によって着る服が限定されていないのであれば、それはブルデューのいう差別化(ディスタンクシオン)ではなく一種の自己表現であり、外へ着ていける家である。6章で出会うのは彼自身の「家族写真」である。この写真に写るのは彼とその一卵性双生児の兄弟であり、彼ら自身にもどちらがどちらか見分けがつかなかった。いわばこの写真は彼らにとって、ラカンのいう「鏡像」をずらしつづけるものであり、自分の隣の存在は、つねに「そうありえた自分」として世界の理解可能性を与える。同様に、あらゆる生きもの同士は、ただ一つの同じ生を介して「双子」である。
7章から8章は、家のなかから生まれるコミュニケーションが描かれる。7章で出会うのは「言葉」である。どの国にいても窓にブラインドをかけて書き言葉と向きあうコッチャは、言葉が観念を載せ、書き手と読み手の思考を混ぜあわせる、麻薬的な媒体であることに気づく。8章では「ソーシャルネットワーク」が扱われるが、それは集合住宅をモデルとした新しい家である。そこでは虚構と現実との境界があいまいになり、登場人物でありまた著者でもあるような、新たなアイデンティティが生み出される。
10章から最終章は、人間とは異なる種や界の存在と出会うのだが、これまでのコッチャの著作で扱われたモチーフの変奏としても読むことができる。10章では、それは「動物」である。エピメテウスとプロメテウスの神話によれば、人間は他の動物のうちで最も弱く、武器をもたないがゆえに、物質と実在を操る技術を与えられ、他の動物たちを統べるようになり、それ以来、人類と他の動物たちとの関係とは闘争と分離でありつづけてきた。他方、家が与えるのは、他種との共生であり、種を越えうる愛である。11章では「植物」と出会う。著者は、植物をまとう現代的な建築「ボスコ・ヴェルティカーレ」に滞在した経験から、都市はつねに森を辺境の異邦と見なしてきたこと、反対に、家とは植物によって、つまり庭や農地、観葉植物によって土地に根を張ることで存在しているということに気づく。最終章である12章は、そうした共生とは別の仕方での他種との混淆としての「食」が描かれる。台所は生と生の出会いの場であり、互いに自分を料理することによって他者へと変様する場である――余談だが、本章を訳しながら思い出したのは、去る日本講演の夜の会食時、コッチャが家庭料理についてしきりに尋ねながら、好き嫌いなく食べていた場面である。
結論部分は、全体部分の要約というよりは、本論からさらに思考を延長して、「石」と出会う。家は石材でできているし、家電、乗り物、携帯電話、パソコンも石なら、惑星もまた石の塊である。そう考えると前章までで論じてきた「生」との関係は、石とのアニミズム的な関係に転用されるかどうかが試されなければならない。
以上のように本書の議論の射程は広大だが、どの章でもこれまでの思考枠組みを外れるような新たな他者との出会いが描かれている。生を営む場である家は、通常そう捉えられるように、たんに「雨風を防ぐもの」「所有された空間」ではない。そうではなく、家とはさまざまな他者――家族、過去/未来の自分、動物、植物、石、道具、衣服、等々――と生を混ぜあわせながらメタモルフォーゼを繰り返す、幸福の実験場である。
他方、本書では家の不幸についての考察は限定的である。家父長制や、家庭内の身体的・精神的抑圧は、ときに言及されるに留まる。この観点からのコッチャの議論は、日本講演の翻訳「All We Need Is Love」(松葉類・樋口雄哉・宇佐美達朗訳『立命館大学人文科学研究所紀要』一三六号、二〇二三年、五─二六頁)を参考にされるとよいだろう。
コッチャの思想的遍歴に還元するなら、彼が本書で新たに提起する問題とは、生とそれを取り巻く物との相互関係である。これまで彼が論じてきた「ただ一つの同じ生」のメタモルフォーゼを可能にする媒体である物は、生との交わりにおいてのみ語られるのではなく、もはや生に対してある種の行為性(エージェンシー)を伴った主体としても描かれているように思われる。すでに彼は『植物の生の哲学』において惑星などの天体、『メタモルフォーゼの哲学』において原子、ウイルス、プレートについて論じたが、それを一挙にすべての物へ敷衍するのではなく、家財道具や人形、絵、パソコンなど個々の物へと適用している。コッチャはこのことの哲学的意義について、本書では明確に語っていないが、これまで以上にたとえば倫理や政治的観点から問題になってくるのは言うまでもない。いずれさらに論じられるべき問題である。
*
さて、訳文全体についての補足をしておきたい。コッチャは言葉と思想の流れを意識して書いていると思われるため、とくに日常的な経験にかんする部分は、研究者向けに逐語的に訳すより、できるだけ開いて平易に読みくだせるように訳した。語彙にかんする説明や、文の対比などを読みやすくするための語句は文中〔 〕に示した。本書で初めて彼の思想に触れた読者諸氏にも親しみをもって読んでいただければ幸いである。
最後になるが、温かさと不穏さの混淆する魅力的な絵を提供してくださったきたしまたくや氏、前作『メタモルフォーゼの哲学』に続いて適切な鉛筆を入れてくださった勁草書房の関戸詳子氏、丁寧な装丁を施してくださった大村麻紀子氏にも感謝したい。彼らの手によって、訳者の家のなかで生み出された訳文が増殖し、重なりあい、新たな色調を帯びたのは間違いない。そして、わたしの家のなかを縦横に駆けまわり、多大なインスピレーションを与えてくれた、娘と息子にも。彼らの想像力が未来を切り拓いてゆけるように願っている。
新緑の眩しい季節に
松葉 類







