あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
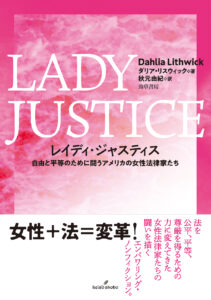 ダリア・リスウィック 著
ダリア・リスウィック 著
秋元由紀 訳
『レイディ・ジャスティス 自由と平等のために闘うアメリカの女性法律家たち』
→〈「第1章 始まり」「訳者あとがき」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「第1章」「訳者あとがき」本文はサンプル画像・推薦のことばの下に続いています。
【推薦のことば】
女性やマイノリティの尊厳と平等のためにたたかってきたアメリカの女性法律家たち。
彼女たちが切り拓いた道の先で、それでも時として私たちは、なにも変わっていないと打ちのめされ、たたかいを続けている。
声をあげる女性たちと、ともにたたかう法律家、そしてそれを支える市民。
法によって社会を前進させようとするすべての人に、レイディ・ジャスティスの物語が勇気を与えてくれる。
――亀石倫子(弁護士、「LEDGE」代表)
アメリカ社会の変革を求めて果敢に挑戦した女性ロイヤーたちの姿に、目を見張りました。「女性に法を足すと魔法の力が生まれる」という著者の言葉に勇気づけられる、感動の一冊です。
――髙部眞規子(元裁判官・弁護士)
これはアメリカの話だが、日本の話でもある。日本もアメリカも、女性やマイノリティの平等からはほど遠い点では同じ。本書で描かれるのはアメリカで女性法律家たちが闘っている物語だが、日本でも世に知られざる多くの女性法律家たちが古い制度に挑戦し、社会を変えてきた。そんな先人たちに憧れた私は、法と制度を変えることをミッションとする弁護士になった。『レイディ・ジャスティス』は、よりよい未来の実現を望む若い人たちや、法の力を信じて弁護士を目指している人たちへのインスピレーションになるだろう。
――土井香苗(ヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表)
「法は男の領域」。そんな時代にもレイディ・ジャスティスたちは見抜いていた。法は女性に変革の力を与えること。女性たちが連帯すればいかに偉大な変革が成し遂げられるかを。「最強」と呼ばれた女性判事ルース・ベイダー・ギンズバーグの死。揺らぐ中絶の権利。トランプ再選の可能性――バックラッシュに立ち向かうための勇気と戦略がここに詰まっている。
――三牧聖子(同志社大学大学院准教授)
『レイディ・ジャスティス』は、人が最高の状態や最悪の状態にあったときの、そしてその人たちがこの五年間でアメリカ合衆国をどのようにかたち作ってきたかについての、心をつかみ、感動させ、わくわくさせる物語である。ダリア・リスウィックほど、深い知識とすぐれた報道、それに鋭いウィットを織り交ぜながら、法についての文章を生き生きとしたものにできる人はいない。本書は、トランプ時代の嵐の中で人権や真実のために立ち上がった勇気ある女性ロイヤーたちについての作品である。そこに書かれている歴史も重要だが、本書は非常におもしろく、迫真力をもって書かれた、あの時代を駆け抜けるような一冊でもある。
――レベッカ・ソルニット(文筆家)
ザ・ニューヨーカー誌ベスト・ブックス2022の1冊、ニューヨーク・タイムズ紙ベストセラー、LAタイムズ紙の時事部門賞受賞。ワシントン・ポスト紙、ボストン・グローブ紙ほか各紙絶賛。
第1章 始まり
……略……
アメリカの法や憲法の分野での前進はどれも、一直線に暗いところから明るいところへと向かったのではない。そういう話のほうが好まれるけれども、アメリカの法の前進は昔からずっと、主として男性が、男性のために、男性の運命の向上を主な目的として設計した法制度の中を通る、明暗ある歩みだった。そんな男性主体の流れに反して職業人生の中心に法を据えることを選んだ女性たちの経歴は、フェミニストの学者であるキャロル・サンガーの言葉を借りれば「断続的な前進と限定的な成果の物語となる可能性が高い」。しかし、マリーの経歴は断続的な前進でも限定的な成功の物語でもない。その前進をマリー以外の人が自分の手柄にしてしまい、その成果の多くを目にする前にマリーが亡くなったというだけのことである。そんな話も、法制度内にいる男性ではなく女性について語られることとしてより現実に近いと言えるかもしれない。トランプ政権時代の女性による法的レジスタンスについては確かにそんなことが言えた。これから先についてはそうはならない。
そう考えれば、法の歴史が自由や権利の拡大と縮小との間で揺れる振り子のようなものであるだけではない。湖を横切っていくマガモのように、男性が軽々と水上を滑っていくのが常に見えている一方で、女性は水面のすぐ下で猛烈に働いているのである。ということは、この本が語るのは、すべてを後回しにし、針路を変え、減給を受け入れ、子供の発表会を欠席し、ドナルド・トランプが大統領だった二〇一七年から二一年までの四年間に、立憲民主主義を守るために猛烈に水をかいていた女性たちの物語である。そして最初に登場するのはポーリ・マリーという、英雄なのに英雄ではない、スターなのにスターではない、エリートなのについにはエリートたちにあまりに失望し、人生最後の一〇年間は神と信仰と社会奉仕に専念していた人である。マリーは私たちが今日暮らす憲法下の世界の大部分を、岩壁を素手で彫るようなことをして作り出した。たった一人の女性がこれだけのことをできたのは、当時は世界が今よりも小さかったからでも、問題が今ほど途方もなかったからでもなく、世界や国にどう思われようが自分にその仕事をする能力があるのがマリーにはわかっていたからである。連邦議会議員のエレナー・ホームズ・ノートンはポーリ・マリーの自伝『疲れ切った喉にある歌(Songs in a Weary Throat )』の序文で、マリーは「歴史の先端で生き、歴史を自分と一緒に引っ張っていたようだった」と書いた。
この表現は、マリーよりも前にいた女性たちを描写するのに使うこともできるし、本書に登場する女性の一部についても使うことができる。マリー同様、彼女たちはそれにもかかわらず歴史を変えてきた。これらの女性ローヤーたちが、トランプ政権中に根を下ろして生い茂り、二〇二〇年大統領選挙でトランプが負けた後もまだ勢いのある人種差別や男女差別、トランスフォビア、ゼノフォビア、汚職、偶発的暴力を食い止めるために戦った理由は、マリーが戦ったのと同じ理由、つまりより民主的な未来という夢のためだった。暗いときも明るいときも、マリーはルース・ベイダー・ギンズバーグのために道を開き、ギンズバーグは本書に登場する女性たちのために道を開いた。暗いときも明るいときも、本書で描かれる女性たちは私たちの子供たちのために道を開いている。
本書が印刷に回ろうとしていた二〇二二年六月、連邦最高裁判所がロー対ウェイド事件判決を覆す判断を下した。多数意見は、まだ生まれていない子や州議会議員の権利にたいへんな気配りを示した。多数意見を書いたサミュエル・アリートには妊娠した人の生が見えていないも同然で、アリートは魔女の火炙りに賛成していた十七世紀の法律家を幾分うれしそうに引用した。この判決が正式に出る前から、そして書き直しの可能性があった時期にも、州によっては中絶を犯罪化する法律を急いで通し、私人にその法律を執行する権限を認めた。救急処置室は流産している女性の受け入れを断り、オハイオ州では十歳のレイプ被害者が妊娠中絶のために他州に行かなければならず、診療所は中絶を禁じる州から来た女性の処置を拒んだ。妊娠した女性がよりよい選択をするのを助けるためだとかいう話は消えた。あっという間に、複数の州が「投獄せよ」の別の形である法律を制定した。トランプ政権の四年間に親子分断政策〔不法に入国した親子を引き離す政策〕や投票抑制を止めようと活動していた女性たちが、今度は女性が無視されないようにし、平等を確保し、女性の票の価値が失われないようにする任務を負うことになる。
女性と法との間には特別な関係があるというのが私の主張である。理由をあまり手短にまとめるのはよくないが、法というものがラディカルな変化を起こすためのもっとも確実な方法だからかもしれない。以前、私が本書を執筆中だと聞いたある著名な憲法学の教授が、なぜ「法についてのピンク色の本」なんかを書いて時間と信用を無駄にしようと思うのか、と尋ねてきたことがある。でも、いうまでもなく法こそが、女性がなれるものやできることや望めることを常に左右してきたのである。法は男性によって書かれたというだけで、常にピンク色の本だった。記者として裁判所に取材していた二〇年間で、私は女性が司法制度や憲法、また平等という課題と深いつながりを持っていて、その関係は実に何世紀も前からあったと考えるようになった。それはいわば秘密の情事で、歴史を書く男性によって必ずしも記録されてこなかったというだけのことである。乱暴な権力や乱暴な金、それに言ってしまえば乱暴な乱暴さを利用できないなか、法は長らく、女性にとっての公平や平等や尊厳を推進するのに最適な制御力だった。アメリカでは、女性やノンバイナリーの人たち、貧しい人びと、移民、マイノリティの男性や白人以外の男性は、分割された画面の中、二重意識の中に生きていて、自分たちがこれまでにどれくらいを確保できて、それがいかに容易に取り上げられえるかを絶えず意識している。
女性が弁護士として活動することを認められるよりもずっと前から、女性は法の体制と深く絡み合っていた。そして女性が権力を持つようになるずっと前から、女性は司法を利用することもできた。『ヴェニスの商人』でポーシアがいちばんいいセリフを与えられているのはそれが理由である。ポーリ・マリーが、それが準備書面で使われるよりもはるか前にロースクールで書いた論文で、ブラウン対教育委員会事件判決となる人種隔離撤廃の方策を考え出したのもそれが理由である。有名になる女性のローヤーはめったにおらず、それは文学でも同じである。聖書に出てくるデボラは裁判官だったが、当時の裁判官は冷静に法的な決定を下す者というより「戦士の頭かしら」を意味していた可能性が高い。シェイクスピアのポーシアが、表向きには情けというものの本質について感動的な演説をするために男性の弁護士に扮したのは有名な話である。正確を期すために述べておくと、ポーシアは実際には華麗な令嬢で、夫を手に入れるというもっと大きな計画のために弁護士に扮したのだった。つまり『ヴェニスの商人』こそ本当に最初の、法についてのピンク色の本なのである。
女性は合衆国の建国当初から、この国で女性が果たす役割を法律家が左右することを知っていた。アビゲイル・アダムズは、一七七六年の大陸会議で頑張っていた夫のジョンに、女性にも配慮するように助言した。「そしてついでにもう一つ」とアビゲイルはジョンへの手紙に書いた。「新たな法典を作ることが必要になるのでしょうが、そこで女性たちのことをお忘れにならず、女性に対してあなたの先祖たちよりも寛大で好意的になってくださることを望みます。あれほど無制限の権限を夫らに握らせないでください。男性は誰でも、それが許されれば暴君になることをお忘れなく」。手紙の形で語られる「投獄せよ」の話である。
合衆国では、女性はロースクールに行ったり司法試験を受けたりする権利を確保した後も、法規と固定観念のせいで、弁護士として活動することは認められていなかった。一八七三年にマイラ・ブラッドウェルが弁護士として開業することを求めて連邦最高裁にまで行くと、最高裁は女性を開業認可から除外するイリノイ州の法律を合憲と認めた。ジョゼフ・ブラッドリー裁判官が同意意見で次のように書いたことはよく知られている。「民法、そして自然自体が、男性と女性それぞれの領域と運命とに大きな違いがあることを常に認めてきた。男性は女性を保護し守る者であり、そうであるべきである。女性が有する自然でふさわしい臆病さとひ弱さによって、女性は市民生活における多くの職業に明白に不適格となる」
実はアメリカの女性は弁護士になることを認められるよりもかなり前に医者として開業することを認められていたが、それは一つには治療することが女性に生まれつき備わっている世話する機能の自然な派生物と見なされていたからだった。他方で弁護士としての活動は荒々しい男性の仕事だと見なされていただけでなく、本物の権力への入り口だとも見なされていた。バーバラ・J・ハリスが書いたように、「女性の医者は、その職業が、女性が家庭で果たす育み癒す役割の自然な延長であり、自分と同じ性に属する人を世話することで女性の慎ましさを守っているのだと主張することができた。対照的に女性の弁護士は、明確に男性専用だった公的領域に明らかに侵入していた」。つまり、女性が医者になることを認められたのは、女性が看護師や教師、子守り、料理人になるのを認められたのと同じ理由だった。それに対し、女性が民主主義や統治そのものの機構をいじるのを認めれば、制度を変える力を与えすぎることになる。十九世紀末のアメリカで、女性の参政権運動と女性が弁護士になることを認めさせようとする運動とが密接に連動していたのはまったく偶然ではない。本書が示すとおり、勝訴することは女性弁護士の仕事のうちだが、長続きする変化を起こすには法そのものを変えることが唯一の方法なのである。
権力や名声がなくても、アメリカの女性は奴隷制廃止から平等参政権や人種とジェンダーの平等まで、すべての公民権闘争の最前線にいた。しかし、女性がついに法律事務所や公民権関連事業を率い、裁判官にもなっている時代には、最前線にいることの意味が変わってくる──新しい物語になる。女性のローヤーはトランプ時代の有害な政策や取り組みのなかに道を切り開いただけでなく、トランプ時代の終了の準備も整えた。トランプが就任した二〇一七年一月にはすでに、全国の女性ローヤーたちが、互いを知らないまま、トランプに対する法の面での抵抗の背骨になるために態勢を整えていた。女性の怒りは、それだけでは人を無力に、孤独にすることがある。しかし女性の怒りとローヤーとしての活動とが合わさると、目覚ましい何かが起きる。
とにかく何よりも、トランプに反対する人たちの主要な目的の一つは、恐ろしい不正を受け入れてそれを正常化するのを何が何でも拒むことだった。その点で女性のローヤーたちは、ほぼ毎日新たに起きるひどいことに直面しながらも恐怖を忘れずにいる、他の人にはない能力があった。本書に登場する女性は全員がある時点で、過剰反応しているとばかにされた。しかし法は私たちに、規範が次第に蝕まれていく様子を記録し歴史にとどめ、責任を問う手段を与えてくれる。法はゆっくりと前進するので、過去を忘れて先に進もうという衝動に逆らう。そして、許して忘れることをお家芸にできそうなこの国で、これらの女性たちが起こした訴訟は記憶と責任追及を求めた。基準点としての「ヒステリア」の状態を四年間も維持するのは不可能に近い。しかし正義そのものが極悪を正常化するのを拒むことを求めるのであり、女性は芝居じみていると退けられることを男性ほどいやだと感じないようである。そんなのは気にしすぎなのだと何百年にもわたって言われ続けてきたので、私たちは笑って前に進むことを学んだのかもしれない。
トランプは自分の政権を白人男性や──そのうちの一部は女性を虐待していたことがのちに判明した──白人男性の裕福な妻たちでいっぱいにし、連邦裁判所の裁判官にも白人男性を圧倒的に多く採用し、連邦検事の大多数にも白人男性を指名しながら、自分の周りの女性のほとんどにはシフトドレスやキトゥンヒールを身につける役をあてがった。そんな事態になるや否や、アメリカの女性たちは自分たちの声をもっと大きくし、女性がもっと目立つようにし、政治への関与を強め、より組織的に行動しならなければならないことを悟った。これが起動力となり、二〇一七年一月二一日に「女性の行進(ウィメンズ・マーチ)」が行われた──一日に行われたものとしては合衆国史上最大の抗議行動である。そして法制度がトランプ一家や外国の大富豪や金持ちのドナーたちがますます裕福になるために使われるようになると、あからさまに標的にされるか単に置き去りにされた貧しい人や移民、子供や弱者を守るのは女性の役目になった。幸い、女性がトランプ政権にとって見えないものになればなるほど、私たちは互いによく見えるようになった。トランプ政権がついに二〇二一年一月六日の惨事〔連邦議会議事堂襲撃事件〕に至ると、このときもまた、トランプにもっとも忠実だった側近のうち抗議の意を込めて辞任したのが女性だったのは偶然ではなかった。教育長官のベッツィ・デヴォス、運輸長官のイレイン・チャオ、ファーストレディの首席補佐官のステファニー・グリシャムなどである。ある時点で、そこにある対称性に向き合わずにいることができなくなったのだ。トランプは就任したときにも暴力の動因であり、退任を拒んだときにも暴力の動因だった。多くの女性にとって、その暴力や無法ぶりが我慢の限界になった。
連邦最高裁が二〇二〇年に新型コロナウイルス感染症のために閉まる直前に、私はルース・ベイダー・ギンズバーグ裁判官をインタビューした。そのときギンズバーグは私に、自分はハーヴァード・ロースクールの同級生のなかで二番目に優秀な女性だっただけだと言った。ロックスターのように扱われるようになっても、ギンズバーグは自分を特別というよりは、ただ勤勉で頑固だったのだと考えていた。本書に出てくる女性たちも、どんなことをし、それをどうやってしたかという点で同じように並はずれているのだが、彼女たちに先立つRBG同様、自分を非凡だとは考えていない。本書に出てくる女性たちは、異なる分野で同じようなことをした、または似たような分野で異なることをした何百、何千もの女性ローヤーや活動家のうちの数少ない例にすぎない。私がその女性たちの訴訟や組織や機関に光を当てるのは、彼女たちが、ドナルド・J・トランプが二〇一六年に当選してから辺りを見回し、しなければならないたくさんのことがあり、まさに自分にそれをする能力があることに気づいたからである。それに取り組むにあたり、彼女たちは同僚の弁護士やインターン、調査官、パートナー、ボランティアなどの力を借りた。アメリカにおけるトランプとトランプ主義に抵抗する取り組みについて名を残すことになる女性が一人いれば、その裏には名を残さない女性が何千人もおり、私たちがうっかり忘れてしまった女性もたくさんいる。
トランプ時代がその後も長く残す教訓は、法とは規範や勧告や規則の脆弱な組み合わせにすぎないということである。法は放っておいても自動的に執行されるものではないことを私たちは学んだ。連邦議会からの召喚状を無視しても、司法長官を意のままに操っているなら何も問題ないらしい。ハッチ法〔公務員の政治活動を制限する法律〕に違反しても、みんなただ肩をすくめるだけかもしれない。召喚状なんてものはばか正直な人のためのもので、大統領による恩赦は側近のためのものである。そんな体制がいかに危ういかは毎日のようにあらわになったし、実のところ今でもあらわになっている。それでも、知名度やブランディングが重んじられる文化の中でさえ法がこれほど強い勢力である理由の一つに、条件が整えば法は確かに全員を気にかけ尊重する、少なくともそうしようと努力するということがある。裕福なら、または有力なら必ず勝つわけではない。トランプが大統領だった四年間、法は混乱状態にあったが、法的な手続きはきわめて堅苦しく、多くを要求するものである。雑な文書作成や判断は命取りになる。本書で見ていくとおり、トランプ政権は法的手続き上の精密さを無視したために、好意的な裁判官の前でも何度も負けた。裁判でも選挙でも、トランプが結局は法と民主主義の勢力のもとで崩壊した理由の一つには、誰も──大統領であっても、どんなに金持ちであっても──アメリカにおける法の支配をいつまでも避けることができないことがある。少なくとも、今のところはそうである。必ず、誰でも、永遠にできるとは限らないが、法的責任というものはまだ追及することができ、私たちがそれを求めて戦わなければならないものである。収入、権力、ジェンダー、人種の相違にかかわらず自由と平等を保障する国には権威ある法典が一つだけある。それは権利章典である。そして少なくとも今のところは、どうにかそれで事足りている。
法は、忍耐と説得が報われることが証明される場である。私たちが、裁判所そのものでの変革を起こすためにゆっくりと計画的に人を説得していくやり方を活用することを学んだのは、ギンズバーグ裁判官と、法の世界での彼女の仲間だったサンドラ・デイ・オコナー裁判官からだった。弁護人席に着くことは裁判官席に着くことへの一歩であり、それが国の最高裁判所の裁判官席に着くことへの一歩でもあることを私たちが学んだのもこの二人からだった。また、権力というものは常に劇的で荒れ狂っているわけではなく、型にはまっていて長続きする場合もあることを学んだのもこの二人からだった。
誤解してはいけない。トランプ時代に出されたきわめて有害な命令を実行するために働いた女性ローヤーもたくさんいた──親子分断政策から若年時不法入国者救済措置(DACA)の撤回やトランスジェンダーの入隊禁止などである。トランプが権力を失ってからも、女性の弁護士が二〇二〇年大統領選挙の結果を争う勝ち目のない裁判を起こすのに重要な役割を果たしてきたし、無党派の選挙管理役員に嫌がらせをして退職に追い込んだり、二〇二一年一月六日の暴力的な反乱を扇動したりもした。しかし二〇一六年以降にトランプ主義を倒すのに女性がきわめて重大な役割を果たしてきたことに疑いの余地がないのとまったく同じように、女性のローヤーは女性とトランプと法の支配の物語に欠かせない存在だった。ポーリ・マリー同様、彼女たちは評価されなかったかもしれない。マリー同様、彼女たちの努力は小さな行動やつながり、目覚め、対決、そして変化がかたち作る見えない網となり、他の人たちが国を引き裂こうとしていたときに国をまとめていた。
というわけで、私が本書をポーリ・マリーで始めるのはこれが理由である。フェミニストの政治思想家のレベッカ・ソルニットが述べたように、アメリカ人は社会変革における「偉人(グレイト・マン)」理論に、その偉人が女性である場合でも、あまりに容易に屈することがある。私たちはトランプ時代のあまりに長い期間、ロバート・ムラー、次にアダム・シフ、次にジェイミー・ラスキン、さらに誰か別の人がカウボーイふうの武勇を発揮して独力でみんなを救ってくれると信じていた。しかしそうするうちに、自分たちのあいだにいるありふれた英雄たちを見失っていた。ソルニットは二〇一九年のエッセイ「その英雄こそが問題であるとき」でこう述べている。「私たちは単独の非凡な英雄や、暴力がもたらす興奮と腕力のすばらしさを好む。いずれにしても私たちに繰り返し与えられるのはそういうもので、そうするうちに、変化がどう起きるかや、その中で私たちが果たしうる役割、そして平凡な人びとが重要であることをよく理解できずにいる」
もちろん、ポーリ・マリーは「平凡な人びと」の正反対だった。しかしアメリカの社会変革における単独英雄理論でさえもマリーの貢献を無視し、マリーの後から出てきてマリーの業績を足がかりにし、マリーがずっと前にしていたことをした人のほうを評価することを選んだ。マリーがアメリカの憲法史と公民権史からほぼ完全に消されている事実は二つのことを示唆している。歴史と社会変革についての「偉人」理論は、人と人との深いつながりや耳を傾けること、組織すること、集団で行動すること、物語を語ることが広範な変化をもたらしうるさまざまな方法をすべて無視するだけではない。そのような理論は、ほぼ独力で本当に世界を組み替える、まさに英雄らしい偉大な個人のことも認めないのである。
本書は、ローヤーたちを互いにだけでなく、尊厳、平等、正義、法、真実、道理という憲法上の不変の価値基準とも結びつける見えない網についての物語である。法務というものは慎重に行うほうが報われることが多いにもかかわらず、大事なときに思い切って立ち上がった強い女性たちの物語である。多くの場合、自分の能力についてあきれるほどの疑いを持っていたけれども、つい数十年前には女性を排除していた法制度に無限の信用を置くことを厭わなかった女性たちの物語である。恐怖にかられた人もいれば、楽観していた人もいた。思いついたことについて相談したり、大胆な行動をとることで自分のキャリアにどんな影響が出るかを考えたりする時間のあった人はほとんどいなかった。本書は、女性が考えずに思い切って行動に出るために必要な網についての物語かもしれない。それは法規や規則や慣例によって作られた網で、あまりに重みと実質があるので、悪条件がそろっていてもぎりぎりのところで破れずにいられそうに見える。
王女様や王様や魔法使いの物語から生まれた国では、すべての権力は権力者に備わっている。しかし立憲民主主義国では、長く続く権力は戦いに足を踏み入れる人びとのほうにある。そしてその尺度に基づけば、トランプ時代に憲法を守るために立ち上がり、今日も民主主義と平等のための戦いを続けている女性たちは、最高裁に上訴の受理を求める平凡な書面や、書式を徹底的に整えた付録によって前線を維持した。憲法の起草者たちが自由と平等という民主主義の核となる価値基準に基づく国を思い描いていたとき、約二〇〇年後にそれらの価値基準を守る戦いの中心に女性がいることになるとは想像もできなかったはずである。むしろ、彼らは──アビゲイル・アダムズはさておき──男性が全部の権利を持ち、女性は男性に保護されるようにすると固く決めていた。しかしある意味では、トランプ時代に平等と正義とプライバシーと尊厳を守るために戦った女性たちは、ジェイムズ・マディソンとトーマス・ジェファソン、そしてベンジャミン・フランクリンによって作り出されたラディカルな立憲主義の責任を引き継ぐのに申し分のない位置にいたのである。彼女たちは、たいへんな重圧を受けながらも破れなかった体制に自分をつないだ。
これらの問いは──誰が目立って誰が認められるか、誰が仕事をして誰がその仕事をしたことで名を残すかは──女性と法とトランプ時代についての本にとってその女性たちと同じくらい重要である。私はカウボーイも結構だと思う。でも変化は「帽子をかぶって何かした男」の伝記だけからは生まれない。したがって本書は突き詰めれば、民主主義がよろめき、もう少しで倒れそうになった時代にいた「偉大な男性」を、あるいは「偉大な女性」を称賛するというよりは、正義を表に出すことについての本である。その正義はみんなの双肩にかかって高まったり低まったりし、私たち一人ひとりによって日々、私たち全員の尊厳と人間性のほうに向けられなければならない。
訳者あとがき
本書はDahlia Lithwick, Lady Justice: Women, Law, and the Battle to Save America(2022)の全訳である。民主主義や法の支配を脅かすトランプ主義に立ち向かった女性法律家たちの奮闘を描くノンフィクション作品で、原書は発売されてすぐに『ニューヨーク・タイムズ』紙のベストセラーリスト入りし、『ニューヨーカー』誌の「二〇二二年ベストブックス」にも選ばれた。
著者のダリア・リスウィックは弁護士資格を持つジャーナリストである。オンライン雑誌『スレート(Slate)』で連邦最高裁判所をはじめとするアメリカの裁判所の動向や法に関するさまざまな問題について記事を書いているほか、ゲストとともにそうした問題を掘り下げる人気ポッドキャスト『アミカス』の司会を務め、テレビのニュース番組にも解説者としてよく出演している。
リスウィックはスタンフォード・ロースクール修了後、本書にもあるとおり第九巡回区控訴裁判所の裁判官の調査官を務めた。その後しばらくローファームで働いたが、離婚案件を扱う仕事が「あまりにつらかった」と語っている。一九九九年、創刊されて間もない『スレート』誌でマイクロソフト独占禁止法違反訴訟を取材する機会を得たのが転機となり、以後は記者そしてコメンテーターとして活躍している。
本書は、リスウィックが「封じ込められていた司法女子パワーの爆発」と表現する、連邦最高裁でのわくわくするような口頭弁論の話で始まる。二〇一六年三月のことである。その後六月末に出た判決は期待に違わず、アメリカの女性が妊娠を中絶する憲法上の権利をあらためて確認するものだった。数カ月後の選挙でヒラリー・クリントンが女性として初めて大統領に選ばれる可能性が十分ありそうだったこともあり、このときはアメリカの女性が真の平等を獲得するまであと一歩のところまで来ていたように思われた。
ところが大方の予想に反して二〇一六年の選挙でクリントンは勝たず、ドナルド・トランプが大統領になった(ただし一般投票では、クリントンはトランプに三〇〇万票近い差をつけて勝っている)。トランプは就任直後から、女性やマイノリティの権利を縮小する政策を繰り出し、そのような政策を支持する保守的な裁判官を連邦裁判所に送り込み、白人至上主義を容認する姿勢を隠さなかった。しかし、アメリカが謳う自由と平等がふたたび白人男性だけのためのものになるように思われたとき──リスウィックの言葉を借りれば「女性の前進が安物のセーターのようにほどけていくように思えるなか」──大勢の女性のローヤーたちがいち早く反応し、抵抗を始めていた。
「トランプ時代の只中、みんな落ち込んで弱気になっていて、自らを法に結びつけた女性たちが信じられないような変化を起こしていたことに誰も気づいていないようだった」とリスウィックは言う。「この本を書き始めた当初は、自分を励ますために書いているのだと思っていたけれど、結局は私たちみんなを励ますための本になった」。女性に法を足すと魔法の力が生まれる、とリスウィックは考える。女性ローヤーの大活躍はトランプ就任直後から始まった。まず、ムスリムが多数を占める国からの入国を禁止する大統領令に毅然として抗議した司法長官代行と、空港で拘束されていた渡航者を助けに駆けつけ、大統領令の無効を訴えて裁判を起こして勝ったローヤーたちがいた。その後も、十代の移民女性の合法な中絶を阻止しようとしたトランプ政権に抵抗してやはり勝訴した、自身も移民の娘であるローヤーや、暴力的な集会を企画した白人至上主義者の責任を追及する裁判を起こして勝訴したローヤーが続いた。
弁護士といえばドラマにでも出てきそうな裁判ばかりが注目されがちだが、真の変化を起こすには、法律を使って状況を変えるのと同時に、法制度の周りにある仕組みや文化も変えていく必要がある。女性はそこでも才能を発揮する。本書には、トランプ政権の差別的な諸政策に歯止めをかける勢力を組織したローヤーのほか、トランプ政権を含む保守派が推し進める投票抑制に抵抗して画期的な選挙結果を導いたローヤーや、マイノリティの回答を抑えるために国勢調査の方法を操作しようとしたトランプ政権に立ち向かったローヤーも登場する。本書ではまた、トランプの在任中に論議を呼んだ二人の裁判官のセクハラ「疑惑」も取り上げられ、それに関わったリスウィック自身を含む女性ローヤーたちの苦悩が描き出される。
本書に登場する女性ローヤーたちは、生い立ちや活動内容がそれぞれ異なるのはもちろん、法に対する考え方や向き合い方もばらばらである。難民支援をするベッカ・ヘラーなどは、積極的に訴訟活動をしながらも、裁判について「真実に到達するには二人の人が正反対の立場から議論して戦い抜くのがいちばんいいという考えが……あまりにもばからしい男性的なやり方」だとまで思っている。それでも法を使うのは「それしかないから」だとリスウィックは言う。「法がなければ権力と暴力だけが物を言うことになる」。法が女性を押さえつけるために使われてきたのはたしかだが、「法は女性の生存と繁栄のための手段」でもある。法は私たちにできることやできないことを規定するが、法と私たちの関係は一方的ではなく、私たちが法を手に取って状況を変えていこうとする選択肢もあることに本書は気づかせてくれる。
アメリカでは、司法試験に受かった人は実にさまざまな仕事をする。いうまでもなく大小のローファームに入っていわゆる弁護士業に従事する人が多いが、政府機関や大学や企業はもちろん、新聞社などのメディア機関や非営利団体やロビー団体にも弁護士資格を持った人がいるのは珍しくなく、それぞれの場でローヤーとしての知識や技能を生かした仕事をしている。私も、本書の登場人物で言えばベッカ・ヘラーやブリジット・アミリのような、弱い立場に置かれた人に力を添えることを日々の仕事とするローヤーに憧れ、ロースクール修了後はしばらくそんな活動をする非営利団体で働いた。連邦裁判所に提出する準備書面の作成を手伝ったり、連邦議会議員の事務所を回って状況説明をしたりしたことなど、今となってはいい思い出である。
現在は法的な手続きに直接関わる仕事はしていないが、翻訳家として、アメリカのいわゆる人種問題や、本書にも出てくる投票権の問題を取り上げる本などを引き受けることが多い。平等や権利といった事柄の性質上、そのような本には法案や法律、訴訟や裁判所、州や連邦の議会での手続きの話がよく出てくるので、少しは残っているローヤーとしての機能を働かせつつ、普段からアメリカの裁判所や議会の動向を追うようにしている。
リスウィックのポッドキャスト『アミカス』は、たとえばその週に最高裁が出した判決や進行中の話題の訴訟について、リスウィックやゲストが笑えるコメントを交えながら鋭く的確な分析をしてくれるのがおもしろく、いつからか毎回欠かさず聴くようになった。そのリスウィックが、正義のために闘う女性ローヤーたちについて書いた本を出すと知って、僭越ながら「これは私が訳す本だ」と思ったのが、日本語版作成の発端だった。
誰もが自由と平等を享受できる社会から遠のいているように感じられるアメリカであきらめずに奮闘する女性ローヤーたちの話を日本に伝えるプロジェクトに賛同してくださった、関戸詳子さんをはじめとする勁草書房のみなさんに心から感謝している。目の覚めるような「ピンク色の本」をデザインしてくださったミルキィ・イソベさんにもお礼を申し上げる。本書を読んでくださる方々に、法というものとどう関わるかについて本書がなんらかのインスピレーションになれば幸いである。
二〇二四年六月
秋元由紀










