あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
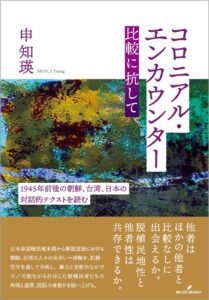 申 知瑛 著
申 知瑛 著
『コロニアル・エンカウンター 比較に抗して 1945年前後の朝鮮、台湾、日本の対話的テクストを読む』
→〈「はじめに─「比較」とは別のまなざしで」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「はじめに」本文はサンプル画像の下に続いています。
はじめに─「比較」とは別のまなざしで
暗黒が暗黒である以上、この狭い部屋のそれも宇宙にぎっしりと詰ったそれも質量に違いはないだろう。私はこの大小のない暗黒の中に横たわり、息づくものも労るものもまた欲しいものも何もない。ただ、どこまで行けば終わりが来るのかわからない明日、それがまた窓の外に待ち構えていることを感じながらぶるぶると震えているだけだ。(李箱(イ・サン)「倦怠」『朝鮮日報』一九三七年五月一一日)
比較は、劣等感を生むものとされている。しかし、比較によって生じるのは「非在感」、つまり自分自身が存在しなくなるという感覚だ。外部の尺度によって他と自分を比べ続けることは、自らが取るに足らないものだと感じさせる。いや、それだけではない。それは、存在をますます消すことになる。比較すればするほど、自分自身が消えていくのである。西洋によって東洋は、白人によって黒人は、植民地支配下において被植民者は、男性中心社会において女性は、異性愛社会においてセクシュアルマイノリティは、国民によって非国民は、人間中心主義において非人間は、存在しないものとされ、消されてきた。
しかし、そのように消され、いないものとされた者たちも、実際には生きているのであり、表現し、存在してきた。一体どうすれば、比較から離れて、彼/女/たちと出会うことができるのか。彼/女/たち同士はどのような関係だったのか。このような問いを抱えながら、筆者は植民地期から解放直後にかけての台湾と朝鮮の記録/文学に出会うことになった。不/可能かもしれない「比較から離れた関係」へと向かった身振り、視線、声を、もしかしたらそこに見つけ出せるかもしれないと思ったのである。
本書を書き終わる頃に観たドキュメンタリー映画「スラ(수라)」(ファン・ユン監督、二〇二三年)は、この問いに対する現在的な応答のようだった。韓国・全羅北道の黄海岸で、防潮堤を作り海を埋め立てた「セマングム干拓事業」(一九九一~二〇一〇年)が行われ、同地域の生態系と漁村共同体が破壊されるという深刻な結果をもたらした。ドキュメンタリーの題名である「スラ」とは、セマングムに最後に残った干潟の名前である。映画では、死んだものとされてきた干潟「スラ」にやって来る渡り鳥や海の生物を二〇年間記録してきた「セマングム市民生態調査団」の活動を描き出している。
セマングム干拓事業を計画した権力者にとって、セマングムの干潟は何(もの)も住まない「無居住地」に見えただろう。また、干拓事業に抵抗して干潟を守ろうと闘った人びとにとっても、最後の潮止め工事が終わった後、セマングムの干潟は死んでしまったように見えたかもしれない。しかし、生態調査団の団長であるオ・ドンピル(오동필)さんは、干上がった干潟に雑草と野草が生え、季節ごとに変化していく姿がとても美しいとしながら、こう述べている。「「干潟」という名を手放さなければ、いつかきっと干潟に戻るはずだから。誰がなんと言おうと、干上がっていたとしても、草だらけだとしても、干潟だったんだから干潟と呼ぶべきだ。そうしてこそ、干潟を生かすことができる」。彼の言葉からは、死んでしまったように見えるものの中にもあらゆる「微物」が生きていることを感じる力や、「死」も「生」だと言える力が感じられる。植民地下で比較され、いないことにされた被植民者も、確かにそこに生きていた。その身振り、視線、声を見つけたいと思っていた私に、オ・ドンピルさんの言葉は深く響いた。
しかし、比較が生む問題は、「非在感」「存在の消去」に留まらない。比較による支配と暴力は、より弱い他者へと連鎖する。比較が位階を生むのではなく、位階が比較を生むからだ。そこには、差別され、支配されることが怖くて、自分より弱い存在に対して差別・支配・暴力を繰り返すという構造がある。多くのものは、この構造から抜け出せない。「他者(マイノリティ)の居場所」を安全に確保しながら、同時にその弱い存在の間でさらなる「他者化された位置」を生み出す構造をなくすことは、いかにしてできるだろうか。
植民者と被植民者の関係だけではなく、被植民者同士、マイノリティ同士の間で作り出される関係に注目したのは、そのためであった。これは、植民地主義の中の人種主義・家父長制・人間中心主義を批判的に問うことでもあった。したがって、本書の中心には、人間と非人間の区別は絶対的ではないという認識がある。たとえば人種主義において黒人は人間でなく、植民地支配下で被植民者は人間ではなく、家父長制において女性は人間でなかった。しかしこうした認識を示すのは、彼/女/たちすべてを、支配権力が制度的に決めた「人間」という範疇に入れてほしい、入れるべきだと要求したいからでは決してない。むしろ、「人間」の範疇に入れられてこなかった彼/女/たちを「人間」と呼ぶとき、「人間」という範疇が破裂音を出して、破れる。そして、そこに多種多様な存在の場所や名前があらわれる。そもそも、人間ではないとされてきた非人間(動物・生物・植物・未生物)を、どのような名前で呼べばよいだろうか。
このような問いを通して、本書は読者を以下のようなものたちへとつなぎあわせたい。帝国日本の中央文壇によって比較されながらも、共に被植民地の現実を表現しようという気持ちから、台湾人作家・龍瑛宗(りゅう・えいそう/ロン・インゾン)に向けて手紙を書く朝鮮人作家・金史良(きん・しりょう/キム・サリャン)の「ふるへてゐる」手へ。朝鮮総督府の宣伝や圧迫に耐えられず、借金をしてまで博覧会を見学しに来たが、気を失い、道に迷い、さらに職まで失うことになった植民地朝鮮の地方民の鬱憤へ。台湾の本島人は「二枚舌」で語り、日本人は「三枚舌」で話すから信頼できないと不満を言う、台湾の原住民へ。台湾から日本の博覧会に移送されるときに、激しくもがきながら踏ん張っていた水牛へ。八月一五日に周囲の雰囲気が変わっていくことを敏感に感じていた、(大文字の歴史には記録されていない)在日朝鮮人少女の解放の経験へ。何が本当に「解放」を意味するかを問いながら集会に参加し、女工たちと暮らしながら日々の自己変革と悩みを記録するムンギョンの経験へ。もともとは強制動員された朝鮮人の妻だったが、炭鉱の事故で夫が死んでからは炭鉱の朝鮮人寮の女中になり、朝鮮人を強制動員するブローカーの「愛人」になり、最終的には遊郭に売られ産業「慰安婦」になったオクスンの沈黙へ。炭鉱周辺に位置しながらも、地図では不可視化されていた「アリラン峠」に住む流民・棄民・難民、そしてあひるが紡いでいた関係の中へ。
比較から脱した関係とは、いないことにされてきた存在の生の中に入り込み、その具体的な経験を尊重しながらそれぞれが存在する場所を作り、つながっていくところから始まるのではないか。だが、もちろんこのようなつながりや「共─鳴」の瞬間はまれであり、気づくことも難しい。比較から脱した関係を作り出すことや、その関係に気づくためには、険しい道程を経なければならないかもしれない。本書の序章は、そのような模索が持つ歴史的かつ理論的な難しさについて、多くのページを割いて論じている。比較され、いないことにされながらも「共─鳴」しつながっていく関係の具体的なあり方について知りたい方は、序章を飛ばして本論の第一章から読み始めてくださってもかまわない。
しかし、ここで立ち止まって、もう一度考えてみたい。なぜ、ほとんど目にすることがなく、到来もしないかもしれないような関係――位階化された比較から解放された関係――を模索しなければならないのだろうか。もちろん、それは苦痛を受け、苦痛を与える関係から抜け出すためである。しかし、それだけではない。さらに解放は、苦痛の解消にとどまらず、他者と「共─鳴」することで自らが別の存在になる可能性も生むからだ。
すべての生き物が死んだとされたセマングムの干潟「スラ」で、オ・ドンピルさんは二〇年もの間、生態系の記録を続けてきた。彼は自身が長年活動を続けることができた力について、こう語る。干潟への水が止められる前に、全羅北道・沃溝(オック)の塩田で十万羽の鴫シギの群舞を見たのだが、それがあまりにも美しかったと。だから、すべての生物が死んだと言われても、干潟を諦めることはできなかったと。あまりにも美しいものを見てしまったことの罪かもしれない、と。彼のこの言葉は、美しい生態系を保護しなければならない責任感について語ったものとして受け取られる場合が多い。しかし、私はその言葉は次のような意味をあらわしていると感じる。十万羽の鴫(シギ)が無数の羽ばたきと、その羽ばたきで数万の欠片になって輝いていた空が、あらゆる比較と位階を越え、どんな隠喩も媒介も必要なく、彼の中に入り込み「共─鳴」したのではないか。鴫(シギ)の羽ばたきと数万の空を抱くことになった「彼」は、以前には戻ることはできない、もう別の存在になったのではないか。たとえ干からびたセマングムの干潟で二度と十万羽の鴫(シギ)の群舞を見ることができなかったとしても、彼には十万羽の鴫(シギ)が飛翔する姿が今もずっと見えているのではないだろうか。
植民地下の朝鮮人作家と台湾人作家、被植民地の地方民、台湾の原住民、水牛、産業「慰安婦」、朝鮮人女工……。彼/女/たちは植民地/帝国が与えた位階によって比較されることで、自身の存在が消えるという経験をし続けていた。また、その位階化された比較を内面化し、自身が経験した苦痛をより弱い存在に与える構造からも一歩も抜け出せないでいた。しかし、このような状況においても、弱い者同士が「共─鳴」し、つながっていこうとした瞬間は重要である。たとえ、被植民者同士が「帝国日本」という媒介なしに互いに出会い、互いを植民地権力から解放された別の存在になるように導くことができなったとしても、鴫(シギ)の群舞に出会えて完全に別の存在になったオ・ドンピルのような経験が与えられなかったとしても、彼/女/たちは、ときには「ふるへて」いて、ときには気を失い、変改を敏感に感じ、自らを変化させ、お手上げの状況で沈黙して、「共─鳴」し、つながっていたのではないだろうか。したがって、抵抗すらできない状況に置かれていた被植民者やマイノリティの身振り・視線・声を、今からでも位階化された関係(比較・苦痛・暴力)から脱出させ、つなぎあわせてみたい。これは今日においても重要な課題であるはずだ。
冒頭に引用した李箱の「倦怠」の世界へ入ってみよう。李箱の遺稿であるこの文章が『朝鮮日報』に掲載された一九三七年は、日中戦争が勃発し、帝国日本による朝鮮の植民地支配が長期化していた時期だった。植民地主義というイデオロギーの外部を想像することが難しくなっていく状況の中、植民地(朝鮮・台湾)はその位階的システムによって、ますます暗黒や死、存在しないもの、マイナスを意味するようになる。そして、このような位階は、被植民者へのあらゆる暴力を正当化する根拠として作動した。李箱はこの苦しい状況の中でなんとか光に向かっていこうとするのではなく、暗黒の中でうつぶせになっている。李箱が語った暗黒は、光と闇を分ける境界線、つまり位階も比較も通さない。暗黒は「暗黒」である以上、狭い部屋と宇宙の差異もない場である。言い換えれば暗黒は比較を意識しなくてもよい場所になる。
しかし、李箱の「倦怠」は「明日」を恐れている文章でもある。植民地支配を受けない明日・希望・外部はあまりにも遠く、決して到来しそうにない。そのため、怖いのは暗黒ではなく、むしろ「明日」という希望である。明日には状況が好転するという希望がないままに、暗黒の外へと一歩を踏み出すことは可能だろうか。植民地支配が終わらないこと─いないとされる状態が終わらないことを知りながらも、自分の存在をあらわすことができるだろうか。位階を含んだ光にさらされることによる危険に耐えられるか。死んだとされるスラの干潟にいる生物のように。この問いの前で、私たちのふるえは止まらない。
告白すれば、ドキュメンタリー映画「スラ」を観るまでは、私もセマングム干潟は「すでに」死んでしまった場所だと思っていた。最後の潮止め工事が終わったばかりの二〇〇六年に訪ねた海倉(ヘッチャン)干潟は、マテ貝が突き刺さったまま干からびてひび割れており、竹蛤、白蛤などの名も知らない無数の貝の墓になっていた。セマングムが八〇〇〇年も前から形成されてきた干潟であり、また韓国の海の貝の八割以上がここで産卵し育ってきただけに、干拓地行によるエコサイド(ecocide 、大量環境破壊)の規模はものすごいものだった。
当時の海倉干潟では、絶え間なく「パキンパキン」という小さな音が聞こえてきた。私は、その音を海の貝が死んでいく声だと考えていた。その場から離れても、「セマングム」と聞くと、その「パキンパキン」という「死」の音が耳鳴りのように響いていた。しかし、ドキュメンタリー映画「スラ」を観てからは、それは「死」の音ではなく、枯れていく干潟で生きつづけている彼/女/たちの声だったかもしれないと思うようになった。白(ペク)蛤が、百(ペク)あれば百通りの形があるという意味で名づけられたように、暗黒や死、無居住地、存在しないとされる者たちの場にも、百あれば百通りに異なる存在の状態があるのではないだろうか。
植民地ではあらゆる存在が比較・位階化されるとともに、苦痛と暴力を内面化し、より弱いものを他者化する連鎖が構造として存在していた。そのような構造から完全に解放されることはなかったとしても、それが「死」の過程だと見なされたとしても、押し付けられたものではないさまざまな存在の状態が被植民者にあったことを、その声を確かに響かせていたことを、比較しあうのではなく「共─鳴」とつながりが作られようとしていた瞬間もあったことを、本書をとおして少しでも感じ取っていただけたら幸いである。
(注は割愛しました。pdfでご覧ください)





