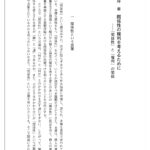あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
 野崎亜紀子 著
野崎亜紀子 著
『〈つながり〉のリベラリズム 規範的関係の理論』
→〈「はしがき」「序章 関係性の権利を考えるために――「関係性」と「権利」の関係(抜粋)」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「はしがき」「序章」本文はサンプル画像の下に続いています。
はしがき
本書は、自由について、筆者が法哲学を中心とする場に身を置き考えてきたことを論じている。自由について考えるといっても諸々の角度がある。法哲学的な視角で自由について考えるということは、「個人を尊重する」ということを、理論的かつ実践的に真剣に考えることである。そして、社会に生きるあらゆる個人の尊重を可能にする社会を作り、維持し、共存をはかるという基本的なものの考え方(理論)のもと、どのようにしてそのような社会が可能になるのかを、社会にさまざまに生じうる課題に対してどのように応答し、対処することができるかという実践的帰結と常にともに考える、ということである。
さて、社会は何もないところから創られるのではなく、その時点で「ある」ところからの改善改修をはかる、いわばノイラートの船である。改修の資材の変化はもとより、浮かんでいる海のありようの変化もそれなりに大きい。
社会のなかに生きる個人らによって構成される社会の環境は漸次的に、時に劇的に変化する。変化を起こす力にはさまざまな種類がある。なかでも、医薬開発を含む科学技術の進展はこれまで常に、人間の生に大きな影響を及ぼしてきた。なによりそれは「できないこと」を「できること」へと変化させる誘因であった。徐々にあるいは劇的に、そうした変化は起こりつづけてきたのであり、現代から振り返ってみれば近代はその連続であったというべきだろう。とりわけ前世紀の末から今日にいたる期間は、同時代に生きる当事者でさえも変化の大きさにおののくほどに、人間の生(life)のあり方に直結する課題が次々に生じ、社会はこれらに直面してきた。いかに生まれるか。いかに生を締めくくるか。これらのことがらが、広く自然の範疇の問題から自由(選択)の範疇の問題へとその位置づけを移してきたことは、変化の核心を構成している。そしてこのことは、社会における初期条件の変化と言いうる。
生まれる場面に視点を絞ると、生殖補助技術の展開は、生まれくる子どもの生にも、産む女性の生にも、そのパートナーの生にも、また当該技術にかかわるさまざまな人々にも直接・間接の影響(力)を及ぼす。締めくくりの場面では、人生の最終段階の迎え方、医療・治療の方針決定に関する制度設計の推進は、高齢者にとどまらないさまざまな個人、その家族や親密な人たち、これにかかわる(医療者を含む)人々にまで、同様の直接・間接の影響(力)を及ぼす。
そしてこれらの問題については多くの場合、公権力の関与が求められており、法・制度的対応が望まれている。そうした社会状況のなかで、個人の尊重という近代が見出した自由を基底とする普遍的価値を確保するためには、どのように考えればよいだろうか。
随分と壮大なテーマなのではあるが、この課題を理論的実践的検討の問題として捉え、制度設計のあり方を考えるという喫緊の課題が、眼前に存在している。筆者はこうした課題についてこれまで、具体的に考えてきた。この個別具体的取り組みと、理論的検討とを結びつけることこそが、真剣に考えること、なのだろう。
本書の基礎をなす論文は、非公表のものを含め以下のとおりである。いずれも今回本書を構成するにあたり、タイトルを含め大幅に内容を追記・修正している。ここにいたるまで随分と長い時間がかかってしまったこととともに、そのときそのときの具体的課題への取り組みとともに考えるという積み重ねであったことから、事実および文献等のアップデートが及んでいない部分があることは、大きな反省である。ただ筆者がそこに見出した課題、考える意図と方針については、変更がない。
序 章 「関係性の権利を考えるために――「関係性」と「権利」の関係」日本法哲学会編『法哲学年報二〇〇四』(有斐閣、二〇〇五)一三七―一四五頁
第一章 「〈個人の尊重〉と〈他者の承認〉――新型出生前検査から考える」『同志社アメリカ研究』五三号(同志社大学アメリカ研究所、二〇一七)一九一―二〇九頁
第二章 「ケアの倫理と関係性―― ケア関係を構築するもの」竹下賢・長谷川晃・酒匂一郎・河見誠編『法の理論 32』(成文堂、二〇一三)八七―一一四頁
第三章 「法的主体と関係性―― ケアの倫理とリベラリズムの論理」仲正昌樹編『叢書アレテイア15「法」における「主体」の問題』(御茶ノ水書房、二〇一三)二四九―二七三頁
第四章 「第一章 「平等」の議論と「差異」の議論」学位論文「法は人間の「生」をいかに把握すべきか――マーサ・ミノウの「関係性の権利論」を手がかりとして」(二〇〇一年九月、千葉大学提出)
第五章 「特別関係に基づく義務と責任」日本法哲学会『法哲学年報二〇〇〇』(有斐閣、二〇〇一)一八一―一八七頁
終 章 「規範的関係論・序説」『千葉大学法学論集』二九巻一・二号(千葉大学法学会、二〇一四)一四九―一七四頁
補 論 「ケアの倫理とリベラリズム――リプロダクション(生殖)をめぐる視角から」大阪府立大学女性学研究センター二〇一八年度第二二期女性学講演会「ケアの倫理とリベラリズム――依存、生殖、家族」における講演(二〇一八年一〇月六日大阪府立大学女性学研究センター)
本書の研究の始まりは、学部学生であった一九九〇年代前半にさかのぼる。
当時、わが国では脳死・臓器移植法の制定に向けた議論が進んでいた。三年次から所属していた家族法のゼミナール(中川良延千葉大学名誉教授)は、穏やかな雰囲気ながら、真剣かつ自由な発表や議論の場であった。筆者はこのとき、臓器移植法制化問題を取り上げることにした。発表する準備のために、この問題についての日本の状況と法制化に向けた議論状況および国外の制度等を知るべく、各所で開催されていた脳死・臓器移植問題および法制定にかかる問題について議論検討がなされる場に参加し、法整備に向けて議論する各種関係当事者の方々(ドナー、レシピエントの経験者、その候補者ともなりうると考えられた方々、ご家族やご遺族、医療者、有識者等)の姿を目にし、彼らの声を耳にした。立法に際しての課題は各種あったが、特に、脳死臓器移植実施要件としての意思の問題と、その正統性にかかる議論に着目してゼミ報告をおこなった。人間の生と死にかかわることがらが、誰かの――そしてそこに家族が登場する――意思によって決せられる仕組みを法律で作る、ということに対して、なぜそうありうるのか、そうあるべきなのかといった疑問を当時、きちんと言葉で論じることができないまま、報告を終えたことをよく覚えている。
(以下、本文つづく)
序章 関係性の権利を考えるために――「関係性」と「権利」の関係
一 関係性という言葉
「関係性」という概念は今日、法学に限らずありとあらゆる場面に登場し、語られ、多様な意味で使われている。多様な意味をもつ「関係性」をめぐって、いくらか検討すべき課題が浮上してきた。本書は、個人の尊重を支える環境という観点から個人と特定の関係を有する者とのあいだの「関係性」に焦点を当て、個人の尊重を基盤とする規範理論における関係性の位置づけを明らかにすることを目的とする。
ところで「関係性」という言葉は、「何か」と「何か」とのかかわりを表す語にすぎない。したがって、関係する者とされる者とが「誰」と「誰」であるのか、また、どのようなかかわり合いが「関係性」という言葉で表象されているのかを明らかにしないかぎり、「関係性」という言葉を用いたとしても、そこで問題にされている内容も論点も理解することはできない。
本書はこのような理解にもとづき、関係性概念を法学の領域において、規範理論のもとで論じることを課題とする。より具体的には、自由な社会が成立するための基本要素はなんであるのかという問題を、「関係性」という視角から論じる可能性を求めている。多分に文脈に依存する関係性という概念を、正義を基底として普遍性を標榜する法(哲)学の領域内、すなわち規範理論のなかで論じてみようという試みである。
ここでは、「関係性の権利」という多義的な概念を整理し、そのなかでも「関係性のなかの権利」に注目する。そしてこの権利が義務的内容をもつことを明らかにしたうえで、この理解に対する批判に応える。
二 「関係性の権利」分析
「関係性」とは、関係当事者を伴う状況で解決すべきさまざまな問題について、どこに問題があるのかを捉えるうえで、当該の問題を分節化する際にしばしば用いられる概念である。しかし、法理論上の概念として「関係性」を位置づけ理解すること、すなわち規範理論のもとで論じることは、この概念が非常に文脈依存的であるゆえに困難を伴う。関係性は、個人と個人、個人と集団、あるいはまた個人と国家など、人と他存在とのかかわり合い全般を指し、用いられる。そのため、おのおのの文脈における「関係性」によって表される意味は、文脈依存的・個別的であり、それぞれに応じて、内容や意味、機能は異なる。
さて本書では、リベラリズム法学を支える基盤を探究していく。そこで序章では関係性を論じるにあたっての基点を示しておきたい。筆者は関係性を、個人の尊重に不可欠な環境のあり方を問う視角を獲得するという観点から捉える。そのためには多様な関係性の、どの文脈を、どのように法が取り扱うことができるのか、取り扱うべきかについて、法のもつ普遍性という特性の観点から、検討を加える必要があるだろう。
(中略)
五 規範的関係論を構想するにあたって――本書の構成
以上のような観点にもとづいて本書は構成される。
本構想において、個人の尊重を考えるうえでの基点を、出生と死という「生の両端」におく。そこから法理論を構想することが筆者の主張である。加えて、従前の法理論上の思考方法に新たな視角を与える可能性があるとすれば、第一に、以下の点をあげることになろう。本書補論で論じるとおり、本構想では、従前の法理論がすでに内包してきたこと、そしてまた社会の実践のなかで機能していることの再検討を試みる。これまでそれらを論じる法的な言葉が十分にはなく、説明がなされないままになってきたように見えることがらに少しでも光を当てるべきである、またその必要性がまさに眼前にあるという理解にもとづき、論じるものである。
本書においては常に、理論と実践との相互交通を念頭においた論述をおこなう。理論と実践とのあいだで相互の反照をおこなう際には、規範理論上の義務と実践的な帰結とのあいだで、ただバランスをとることにはとどまらない必要があるだろう。私たちはあらかじめ、社会のあらゆることを知ることはできない(知識の不完全性)なかで、ものごとについて、こうあるべきだと判断し行動する。事実と規範とのあいだには、どこかに断絶がありながらもしかし、常に実践的帰結とあるべき思考とのあいだの接続を模索することが、法哲学的思考においては求められるものと考える。
こうした理解から、第一章は、喫緊の制度設計上の課題をはらむ出生前検査という実践的課題に取り組み、本構想が具体的にどのような思考と主張に接続しうるのかを示したい。生の起点としての生殖について、高度に私的でありかつ公共的な問題として位置づけたうえで、どのように個人を尊重することができるのか、私的な関係を取り結ぶ局面に立つ者としての課題と、生殖に対する公権力の関与(支援と介入)のあり方という課題とを接続するという視角を提供する。
第二章と第三章は、一対をなす内容となる。本書が構想する「関係性の権利」という考え方を基軸とする規範的関係論は、リベラリズム法学の範疇に位置づけられる。しかし従前のリベラリズム法学に対してはさまざまな批判もある。なかでも特に意義ある批判としてケアの正義論があげられる。ケアの正義論は、自律的個人が個人であるためのその前提となる、ケアしケアされる関係性を維持しこれを最良のものとすべきであるというケアの倫理を、規範理論として構築しようとする主張である。このケアの正義論からの批判を、二つの観点から検討していく。まず第二章では、ケア関係の構造の確認と評価を試みる。ケア関係は、ケアの正義論が依拠するケアの倫理がその核心を支えており、リベラリズム法学が依拠する正義の倫理はそれをあらかじめ排除する構造を有していると批判される。しかしその批判の意義は積極的に評価しつつ、一方で個人の尊重の観点から、ケア関係を基軸とする規範理論の困難を指摘する。次に第三章では、法的主体という観点にもとづいて、ケアの正義論とリベラリズム法学とを対比的に論じる。ケアの正義論における関係的な主体という捉え方の意義は認められる一方で、経験的事実にもとづく脆弱な主体を当該関係的な主体の基礎にすることによる規範理論上の困難があるのである。同時に、リベラリズムの主体の構成方法(抽象化という擬制)がもつ意義と困難を検討し、個人の尊重にむけた法的主体理解の可能性を論じる。
つづく第四章は、本構想の着想の基礎をなす「関係性の権利論」を展開したマーサ・ミノウの議論の骨格となる論点を取り上げる。つまり、従前のリベラリズム法学において取り扱いの難しい個々人間の差異と、リベラリズム法学を支える平等の理念とのあいだに生じるジレンマを示し、このジレンマを生み出す暗黙の五つの想定を明示する。ミノウが論じる「関係性の権利」のアプローチを支える正義の原理は家族法分野に最も現われ、このありようは近代法体系の再考を可能にする、との視角を獲得するにいたる。
第五章では規範的関係の基盤となる、特別(特定)の関係性のなかに認められるべき片務的負担という特性について論じる。ここでは、親子関係、介護関係といった相互に非対等な関係性に着目する。そのような関係性の内部に措定される、相互に対等ないわゆる契約的合意では説明のつかない、非対等なおのおのに独立の互酬的(片務的)な負担について、従前の積極・消極義務、完全・不完全義務の整理を見直す契機を得る。
以上を論じることを通じて、終章においては先の互酬的(片務的)負担を「関係性の権利」を基盤とする規範的関係の理論構想として発展的に提示した。
議論が行きつ戻りつし、重複が多いことは否めない。また本節冒頭に示すとおり、従前の法理論が内包し、前提としてきたこととも考えられ(そうであればこそ、現行法制度内に規定が存在する)、斬新な主張とは言いがたいのかもしれない。しかし、言葉の尽くされない部分が、本書でいくらか言及する、生と死という生の両端領域にかかる課題――そしてそれは医薬科学技術を伴う医療と、その制度設計にかかる課題である――に取り組むにあたり、大きな課題として立ちはだかっていることもまた、否めない。こうした実践的な状況を念頭において、本書は論じている。なお、講演の機会を得た際の内容を補論として加えた。講演にはあらかじめ一定のテーマが与えられていたが、終章にいたるまでの本書全体を内包するかたちで論じた内容であるため、補論とした。
(以下、本文つづく。注は割愛しました)