あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
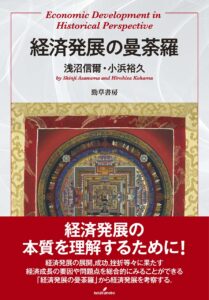 浅沼信爾・小浜裕久 著
浅沼信爾・小浜裕久 著
『経済発展の曼荼羅』
→〈「まえがき」「あとがき」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「まえがき」「あとがき」本文はサンプル画像の下に続いています。
まえがき
この本は,経済発展論,開発政策論を,われわれが比較的よく知っている国の歴史的事実を参照しながら,考えようとするものだ.
『経済発展の曼荼羅』と,書名に「曼荼羅」が入っているが,この本で経済発展のすべてを解き明かしているとわれわれが考えているわけではない.「曼荼羅」は仏教の言葉で,「本質を図解したもの」といった意味だ.われわれは経済発展の本質をすべて理解している,などと思っているわけではない.これまでの勉強のなかで,われわれが理解した経済発展の大切な要因を図解したものを「曼荼羅」と表現した.
学校を出てからかれこれ半世紀.一所懸命勉強したかどうかはともかく,発展途上国の経済や開発政策について考えてきた.とはいえ,途上国に住んだこともなく,それどころか,日本以外に住んだこともない.その時々,たまたまいくつかの国の調査研究をしてきた.パンナム1 便で羽田からニューヨークに行ったのは1970 年代半ばだった.その2,3 年後,マニラやクアラルンプールに出張したのが,途上国出張の始まりだったと思う.世界には200 くらいの国があるらしいが,行ったことがあるのは,5 分の1 くらいだろうか.小浜が教えたことがある商社マンはサブサハラ・アフリカの国全部に行ったと言っていた.外務省のある友人は,若くして死んでしまったが,95 か国に行ったと言っていた.
1980 年代に入るとメキシコに対する日本の経済協力に関する調査をやった.1982 年7 月,1 か月メキシコにいて,7 月31 日にメキシコを発って帰国,そのあと10 日くらいして銀行閉鎖,デフォルト.金融危機はマクロではよく書いていたが,カードでホテル代などを払って帰国したので,ミクロでも儲かった.その後,アルゼンチンの経済開発の調査や,1990 年代後半にはヨルダン,21 世紀に入って,バルカンによく行ったり,内戦終結後のスリランカにもよく行った.
忖度しないし,気配りもしないし,どこに行っても本音で誤解なく自分の意見を相手にぶつける.日本語も乱暴だし,英語もターザン・イングリッシュ.1980 年代半ばのブエノスアイレス.ホンダが,マナウスにあったオートバイ工場をベースに,ブエノスアイレス近郊に進出するという計画があった.アルゼンチン政府は,外国企業による直接投資を求めていたが,多くの国内のオートバイ・メーカーは,ホンダの進出に反対していた.小浜は工業庁長官(日本でいえば通商産業大臣,経済産業大臣)にも工業庁次官にも,「ホンダは,日本企業のなかでも海外進出に積極的な会社で,ほかの日本企業はホンダがアルゼンチンに進出してうまくいくか見ている.なんとしてもホンダの進出をアルゼンチン政府は支援して実現すべきだ」と何回も議論した.でも,工業庁長官も次官も言を左右にして決断しない.「国を発展させたいと思わないのかっ!」と机をたたいて迫ったが,結局,ホンダの進出計画は実現しなかった.戦後,日本のオートバイ業界でも同じような議論があった.でも,寡占だが国際競争力のある企業が生き残った.
ヨルダンでも最初は喧嘩.計画大臣が,あまりにも新古典派的な経済政策の考え方を主張したので,「国の発展局面,国の類型的特徴・差異(typological difference)によっては,市場に対する政府の介入も経済合理的な場合もあるんじゃないか」と反論したら,計画大臣は,「でも,IMF がそう言ってる」と言うので,「IMF の言うことが常に正しいわけじゃないっ!」と言い返した.彼女は計画大臣のあと経済担当副首相を経て,しばらくしてUNDP のアラブ地域担当局長に転出した.ニューヨークに行ったとき,えらく暑い日だったが,マンハッタンのきれいなレストランで彼女とランチをして,楽しい時間を過ごした.
経済発展を考えるとき,基本的経済のメカニズムは大事だけど,それだけで個々の国の経済発展を理解できるわけではない.基本的経済のメカニズムと各国の類型的特徴を組み合わせて考えなくてはならない.大きい国もあれば小さい国もある.たとえ国際環境も国内の経済環境が似ていても,インドのような大きい国とシンガポールのような都市国家では異なる経済発展経路を辿るだろう.自然資源の賦存度も国によって違う.産油国や鉱物資源豊富な国もあれば,アルゼンチンのように小麦,トウモロコシ,大豆,牛肉などの食糧輸出国もある.このように天然資源が豊かな国もあれば,日本や韓国のように資源稀少の国もある.天然資源の豊富さ稀少さといった類型的特徴以外にも,植民地支配を経験したかどうかといった歴史も国によって違うし,政治体制の違いも経済発展経路に影響する.
本文でも書くが,「ペティ・クラークの法則」は,経済発展のメカニズムをわかりやすいデータで説明したものだ.「ペティ・クラークの法則」は高校の教科書にも出てくるように,経済の重心が,「第1 次産業」から「第2 次産業」へ,さらに「第3 次産業」へ移っていくという経験法則だ.産業分類の議論はともかく,工業化の議論では製造業にピンポイントして考えるべきだ.でも第7 章で見るように,台湾のデータでは,「第2 次産業」の付加価値シェアが低下した後,再び上昇している.半導体工業の発展によると考えられる.経済発展を実証的(empirical)に考えるのは,なかなか難しい.
経済発展というのは庶民の暮らしが良くなることだ.貧しい国にとって所得が上がることは絶対的「善」だ.でも同じことを繰り返せば経済発展が持続するというわけにはいかない.不断の構造変化によって所得水準を高めることが開発政策の肝だ.1960 年代から70 年代にかけての韓国の経験は,わかりやすい構造変化だ.1950 年代は朝鮮戦争後の混乱期で,朴正熙のクーデター後,1962 年から第1 次5 か年経済開発計画がスタート.1960 年代は低賃金を活用した軽工業主体の工業化を目指した.1970 年頃,韓国は労働市場の転換点を超えると予想されていて,1972 年からの第3 次5 か年計画では重工業化を指向したのである.
上で書いたように,経済発展の分析には,歴史も政治体制も考えなくてはならない.1989 年,2 つの大きな出来事があった.6 月4 日には天安門事件が起こり,11 月9 日にはベルリンの壁が崩壊した.あれだけ世界中から批判されて中国はもうあからさまな民主化運動弾圧はしないだろうと思ったが,甘かった.
中東欧における民主化運動の高まり,ベルリンの壁崩壊で,世界は自由で民主的な体制が主流になるという楽観論があったが,これまたそれほど簡単ではなかった.その頃の雰囲気を知ろうとFukuyama (1989)を読み直した.前もそうだったが,なにしろカント,ヘーゲル,ニーチェ,マルクス,マックス・ウェーバーたちの議論がたくさん.もう50 年くらい読んでいない哲学者,思想家たちのオンパレード.フクヤマは,考え方が変わっているようだが,1989 年の論文の初めの方には,以下のような記述がある.
The triumph of the West, of the Western idea, is evident first of all in the total exhaustion of viable systematic alternatives to Western liberalism.
ベルリンの壁が崩壊し,1991 年12 月にはソ連が崩壊して,雪崩を打って自由で民主的な資本主義経済中心の世界になっていくという楽観論はあえなく潰え去った.その危機感がマーチン・ウルフにThe Crisis of Democratic Capitalism(Wolf 2023)を書かせたのだろう.
2024 年6 月
小浜裕久
あとがき:経済発展の謎─終わりなき探求
途上国の旅とその教訓
「経済成長のことを考え出すと,他のことが考えられなくなる.(“Once one starts to think about economic growth, it is hard to think about anything else.”)」そう言ったのはロバート・ルーカスで,ケンブリッジ大学に招かれて経済発展の理論の講義のときだ(Lucas 1988, p. 5).わたくしはこれを読んだときに,この感覚は,多くの開発に携わる者に通じると大いに共感したことがある.われわれの場合も,経済発展について考えることが職業生活の大部分を占めてきたと言っても過言ではない.これは以前にも書いたことだが,経済発展の動因や因果関係を考えるのは,玉ねぎの皮を剥くようなものだ.真相を見つけようと表面の皮を剥くと次の皮が現れる,それを剥けばその次の皮が……と限りがない(Stiglitz 2010, pp. xvii─xviii, p. 150).そこで多くの研究が「経済発展の近因(approximate causes of growth)」などといったタイトルになる.
わたくしは,途上国の開発課題について調査し,議論し,そして行動する過程で,実に数多くの途上国,主としてアジアの国々を訪ね歩いてきた.そのような途上国の旅から学んだ教訓は,ひと口で言えば次のようなものだ.
今日の途上国の多くは第2 次世界大戦後に政治的独立を遂げた後,今度は経済発展や貧困削減を第一義的な政治目的として掲げるようになった.ただ,その課題に対する向き合い方は,国によってさまざまだった.それぞれの国がおかれた地理的,歴史的環境が違えば,開発課題やそれにまつわる困難の性格も違ってくる.このように,それぞれの国の「地理と歴史」のために経済発展の軌跡もまた違った様相を示すようになる.地理は,農業に適した地形や気象の側面だけでなく,近隣の国々や経済大国のマーケットへのアクセスだけでなく,地政学的な関係にも大きな影響を持つ.また,歴史には,その国の成り立ちから始まって,現在に至る民族構成や近隣国からの文化的な影響,植民地時代の宗主国からの影響が含まれる.
このように,「地理と歴史」は経済発展の前提となる条件─これを初期条件と呼ぶ─を大きく変えるから,ある国がたどる経済発展の軌跡も変わってくる.政治状況が違い,歴史に根差す制度が違い,経済発展の初期条件が違えば,開発課題も経済発展の軌跡も変わってくることはよく理解できる.どの途上国も「地理と歴史」のしがらみを背負って,経済発展の途をたどっているのだ.
同時に,よく言われているように,歴史は繰り返さないが韻を踏む.それは時間的にも,あるいは空間的にも言えることだ.すなわち,ある一つの国で時系列的に同じような歴史的現象が見られるときもあれば,空間的に違った地点にある国々で,類似の歴史的事象が観察されることもある.現実に多数の国々の経済発展の軌跡をたどってみると歴史的に類似したパターンが現れる.これを歴史理論と呼ぶことも可能だ.もちろん理論といっても,普通われわれが理解するような,演繹的な論理展開をベースとする理論ではなく,歴史事象の構造的な比較研究から得られる理解のことだ.
「経済発展の曼荼羅」
比較史研究は,実は大変な作業だ.演繹的な理論研究の場合は,数少ない前提から始まって,数十個の変数間の因果関係を明らかにする作業だから,考察する対象の時空の範囲は限られている.しかし,歴史的な比較研究となると,比較の対象をどこまで広げるのか,例えば経済だけでなく社会や文化にまで広げるのか,あるいは理論の世界には現れない,時の政治指導者や政策担当者の性格や背景まで考慮するのか,そしてそこに何らかの因果関係を見出すのか,人を困惑させるような広がりを持った世界を扱うことになる.
ケインズは,かつて自らの経済学の師であるマーシャルに関してのエッセイの中で,「優れたエコノミストは,多面的な才能を持っていなければならない.……数学者,歴史家,政治家,哲学者の要素を合わせ持ち,同時に芸術家のように卓越しかつ純粋で,しかしまた時には政治家のように世俗的でなければならない」と述べているが,これは彼が,エコノミストが扱う世界の広がりをこのように多面的にとらえていたことを示している(Skidelsky 1992, pp. 410─411).
本書のタイトルに「経済発展の曼荼羅」という一見不可思議な言葉が入っているのは,経済発展の世界の広がりと多面性を示唆している.もともと仏教の密教に由来する曼荼羅にはいくつもの種類があるらしいが,一般的に日本では大日如来を中心に据え,周りにいろいろな仏,菩薩,明王を配置して,それによって宇宙の本質を映し出し,仏の悟りの境地を示している.いわば密教の世界観を一枚の絵に託したものだ.われわれが想像する経済発展の曼荼羅は,経済成長を中心に置き,それにまつわる要因,動因,制約条件,成立条件等々の事象をその周りに配したものだ.想像をたくましくすればするほど周りを取り囲む諸仏,菩薩,明王の数は多くなる.もちろん,われわれは非力で,われわれが経済発展の議論でカバーできる仏,菩薩,明王の範囲は限られている.とても経済発展の曼荼羅全図を描くことはかなわない.それは承知のうえで,われわれの志を示す目的で曼荼羅という言葉を使っているのだ.
歴史,その反復と踏韻
経済発展の歴史,そしてその反復と踏韻から浮かび上がってくる共通のパターンがある.それは極端に単純化するとおおよそ次のようだ.
まず,われわれが使っている新古典派の成長理論によれば,経済成長の原動力は,労働投入の増加,資本形成,技術進歩の3 つの要素に分解できる.最初の2 つはある程度「目に見える」,すなわち統計等によって可視化できるが,問題は第3 の要素,技術進歩だ.ミクロ的には技術進歩は観察できる.例えば,蒸気機関,内燃機関あるいは電力というような明らかに革新的な技術進歩は理解できる.しかし,もっと広義の制度や政策までも含む技術進歩となると数量的に把握するのが困難になってくる.例えば株式会社という企業形態の普及,銀行制度や証券市場の創設が長期の経済発展に与える影響は明らかに見えるが,それを数量化するのは難しい.そこで,現在の経済学では,この「技術進歩」を成長会計のうえでは剰余として計測する手法が定着している.そして,そうした手法による研究では,一般的に技術進歩の経済成長に対する貢献は非常に大きく,経済成長といえば技術進歩とほぼ同義と言っても過言でないほどだ.
実に悩ましいのは,これほどの大きな比重を持つ「技術進歩」の中身がはっきりしないことだ.宇宙物理学の世界では,宇宙全体に占めるダークマターやダークエネルギーの割合が非常に大きいことがわかっているが,さてそのダークマターやダークエネルギーの本体は何かとなると,よくわかっていないらしい.成長理論における技術進歩もまた一種のダークマターだ.その本体に迫るには,マクロの世界を離れて,経済や社会の構造とダークエネルギーの変化に─すなわちミクロの世界に─足を踏み入れる必要があるようだ.
ペティ・クラークの法則と「ルイスの転換点」
技術進歩というものの,技術の問題だけではないかもしれないので,いまでは「全要素生産性」という言葉を使うことが多い.途上国の経済発展の初期段階では,農業などの第1 次産業が経済に占める割合が圧倒的に大きい.そこに,産業革命が起こり,第2 次産業が成長すると,全経済の生産性は飛躍的に上昇するのは歴史的な常識だ.経済成長の過程で第2 次産業の比重が高まるのはペティ・クラークの法則と呼ばれるが,最も古くかつシンプルな構造的経済成長理論だといってもよい.もしこの法則が正しいとすれば,経済発展の軌跡は,即工業化の勃興,隆盛,そして停滞と衰退の歴史とほぼ同じで,その遠因,近因,動因,条件等々を解明することによって,経済発展の謎の解明に近づけることになる.
もっとも,この法則は歴史のパターンを問題にしているので,経済における第1 次産業と第2 次産業の因果関係を示しているわけではない.その因果関係は,1950 年代にアーサー・ルイスが定式化した工業化による成長モデルに示されている(Lewis 1954).彼のモデルによると,途上国の初期条件の一つは,農業部門に存在する余剰労働力だ.この廉価な労働力をベースに製造業が発展すれば,経済全体の生産と生産性は上昇する.製造業部門の生産性が農業部門よりも高い状態が続く限り,そして製造業部門の経済全体に占める割合が増加し続ける限り,仮に製造業部門の生産性が向上しないにしても,経済全体の生産性は上昇する.そしてそれは,農業部門の余剰労働力が枯渇するまで続く.
ルイス・モデルが描く工業化過程は実にシンプルに見えるが,このモデルを現実の経済に映してみると,実際には大変な経済・社会構造の変化を伴う成長過程であることがわかる.大規模製造業の産業立地は都市部だから,農村部から都市部への大規模な人口移動が起こる.「ALWAYS:三丁目の夕日」に描かれたような若者の集団就職が起こり,都市化現象とともに人々の生活パターンは変わってくる.表面的な消費パターンだけでなく,より社会の深層に達する文化的な変化も現れる.政府が提供する公共インフラやサービスに対する需要も増大し,政府自体の変化も求められる.近代成長の初期の経済成長加速は,ほとんど産業革命と同義と考えられるが,このような大規模かつ多面的な経済と社会の変化はまさに革命と呼ぶにふさわしい.
ルイスの工業化過程は,農村の余剰労働力が工業部門に移動し続ける限り続く.しかし,余剰労働力の供給には限りがある.その供給が途絶えたときに,何が起こるのだろう.この転換点を現実にピンポイントするのは容易でないかもしれないが,そのような「ルイスの転換点」が存在することは間違いない.
産業の高度化と「デニソン効果」
ルイスの転換点を通過した後,工業化はどこに行くのだろう.製造業内部の構造が変わらなくても工業部門の生産性が上昇するケースも十分考えられる.例えば,工業化の初期に盛んになる食品加工や繊維・縫製業内で,より資本集約的な機械化や自動化が起こるケースだ.これをノードハウスは「純粋な生産性上昇」と呼んだが,廉価な労働力を比較優位のベースとするこれら産業は,遅かれ早かれ後発国からのシビアな国際競争にさらされることになるから,ここにも限界がある(Nordhaus 2001).
そこで,工業化のモメンタムを失わずに経済発展を続けるためには,より高度な,すなわち技術水準の高い,より資本集約的な産業を育成し,拡大することが必要条件になってくる.このことは通常産業の高度化とか具体的には重化学工業化とかの標題で議論されるが,例えば繊維業が主力の製造業がより資本集約的な鉄鋼,造船,自動車や化学工業へと,さらに電気機器,エレクトロニクスへと発展していく過程だ.ノードハウスは,このような軽工業から重化学工業への移行から生じる生産性向上を,最初にそれを指摘したデニソンの名前をとって,「デニソン効果」と呼んでいる.
経済発展にとって工業化が重要なのは,農業などの第1 次産業と違って,製造業部門では「デニソン効果」の可能性が高いからだ.もちろん農業部門でもゴムの栽培からオイルパームに転換することによって生産性を上昇させるなどの例はあるが,製造業部門では,ルイス過程に特徴づけられる初期工業化で育成された労働力や経営資源が産業の高度化に容易に適用できるのがその理由だ.しかし同時に,そのためには適切な投資環境が整っていなければならない.これは非常に厳しい条件で,長期にわたってデニソン効果を実現するために,産業の高度化を継続的に進めるのは並大抵のことではない.廉価な労働力という強力な比較優位条件なしに,次々と新分野の産業に進出していかなければならないからだ.
ルイスの転換点以降の工業化過程を「デニソン効果のフェーズ」と呼ぶことにしよう.ルイスの転換点以前の工業化過程に比較して,このフェーズの工業化の進展はより困難だと考えられる.ルイスの転換点以前の工業化は,廉価な労働力という強力な比較優位をベースとする,いわば手の届くところにある果実をもぐような過程であるとすれば,それ以降の工業化の進展は,普段の人的資本のアップグレーディング,絶えざる新技術の導入,そのための直接および間接投資等々を必要とするからだ.そのためには,産業政策の名前で呼ばれるような,政府の介入が必要かもしれない.1975 年に出版された城山三郎の小説『官僚たちの夏』は,結局廃案となった「特振法」という産業政策をめぐる通産省と産業界の確執を描いている(城山1975).また,韓国ではすでに1960年代に機械工業,造船業,電子工業,石油化学工業などの育成のための個別の「工業育成法」が制定されている.典型的なインダストリアル・ターゲッティングを目的とした産業政策だ.
最近,多くの新興市場国で「早すぎる脱工業化」が起こっているという議論がある.そしてそれは,中所得国の罠の原因の一つだとする論者がいる.わたくしは,中進国の罠はすべての途上国が陥る可能性のある罠だと思う.初期の工業化過程が成功したからといって,それが先進国群の所得水準に達するまで自然に継続する保証はどこにもないからだ.第7 章で論じられている台湾の工業化過程の中弛み,すなわち製造業比率(対GDP)のピークアウトとその後の復活は中所得国の罠の典型的な事例で,台湾の製造業はいわゆるE & E 革命(電気機器とエレクトロニクス)の後にさらなる工業化の進展が滞ったが,半導体産業という新分野の開拓に成功することによって罠から抜け出した.「デニソン効果」が現れたのだ.なぜ台湾でそのような構造変化が実現したか,「今後の研究課題」としたい.
脱工業化と「ボーモル効果」
もう一度ペティ・クラークの法則に戻ってみよう.この法則によると,製造業を中心とする第2 次産業のGDP に占める割合は,経済発展の進展とともに高まるが,ある点でピークアウトして,それ以降は減少に転じる.同時にそれと並行して比重が高まってくるのが第3 次産業と呼ばれるサービス部門だ.どのような条件の下で脱工業化への転換点が現れるかは,それぞれの国の事情によって違ってくるが,今日までの多くの先進国の経験では,ほとんどの国が早かれ遅かれ脱工業化への転換点を迎える.ペティ・クラークの法則の第1 の工業化への転換点は,広い意味での技術進歩という供給側の要因によるものだった.これと対照的に第2 の転換点である脱工業化は,一人当たりの所得上昇に伴う需要構造の変化が主たる原因と考えられる.生活水準が高くなると,モノに対する需要が満たされて,限界的な需要は政府の各種サービスを含む公共財やエンターテインメント等の文化的サービスに向かうことは,直観的にもよく理解できる.その結果として,製造業は成長の限界に達する.また同時に,グローバライズされた世界では,先進工業国にキャッチアップしてくる新興国で製造業が盛んになり,先進国の製造業はシビアーな競争にさらされ,衰退の道をたどる.
脱工業化過程の問題点は,経験的にサービス部門の生産性上昇が,製造業部門の生産性上昇に比べて鈍いことだ.この傾向は,すでに1960 年代にそれを指摘したボーモルの名前をとって「ボーモル効果」あるいは「ボーモル病」と呼ばれる(Nordhaus 2008).サービス部門は,その名が示すように基本的に労働集約的だ.そしてまた,サービス部門の生産性の上昇率は製造業の生産性の上昇率に比較して低いことが知られている.その結果,サービス部門の生産物,すなわちサービスの相対価格はモノに比較して高くなる.このことは経済成長にとって大きな意味を持っている.なぜなら,サービス部門の相対価格の上昇は,サービス部門がGDP に占める割合を高めると同時に,サービス部門の低い生産性上昇率が足枷となって,経済成長率が低下するからだ.脱工業化は同時にまた経済成長率の低下あるいは停滞をもたらすというのがボーモルの結論だ.ボーモルは,高等教育,医療,文芸・工芸,ファッション産業,高級レストラン,等々の例を挙げてこの仮説を説得的に説明している(Baumol 1967).
経済発展の条件
経済発展の歴史は,工業化過程に注目して「産業革命」,「ペティ・クラークの法則」,「ルイスの転換点」,「デニソン効果」,「ボーモル効果」などのキーワードで図式的に理解できる.これらのキーワードは,工業化の始まりと隆盛,高度化,そして最後に脱工業化のフェーズの特徴をよく描いているからだ.このどのフェーズの変化をとっても,それは大きな経済構造変化を意味し,かつまた社会形態の変化を伴うまさに革命と呼んでよいような社会変動だ.新しい制度が作られ,新しい社会階層が生まれ,政治体制にも変化は及ぶ.経済的・社会的・政治的な勝者と敗者が現れ,それが原因で大きな政治抗争が起こる場合もあれば,また国際社会との紛争の原因になることもある.
これまでの経済発展の歴史の特徴的なことは,国よってはこのような変化が起こらない,いわば発展の挫折が見受けられることだ.どの国もがスムーズに産業革命を起こすことができるわけではない.発達不全の工業と低生産性の農業とが併存して,貧困がはびこる社会もある.ひとたび工業化の初動に成功したとしても,産業の高度化が進展せず,早すぎる脱工業化に陥る国もある.さらに,産業の高度化に成功した後,長期の停滞を経験する国もある.
ことほど左様に,どの国も独自の「地理と歴史」という初期条件から出発し,経済発展の次々に現れるフェーズに必要とされる構造変化や制度構築に成功したり,失敗したりしながら,独自の軌跡を残しながら発展を続けていく,終わりのないプロセスが経済発展なのだ.
それでは,工業化過程の変化の動因あるいは条件は何だろう.国によって差異があることを認めたうえで,何らかの共通項のようなものがあるはずだ.今までの膨大な研究から導きだされた経済発展あるいは工業化の条件を要約すると次のような項目になる.
(1)基礎的な教育を施された,よく訓練されたあるいは訓練可能な,健康な労働力の存在.
(2)基礎的な交通,港湾,通信などのハードなインフラストラクチャーおよび経済法制,企業制度,市場機構,金融制度,資本市場等のソフト・インフラが整っていること.
(3)政治的,社会的およびマクロ経済的な安定が確保されていること.
(4)海外市場との交流を可能にする開放経済体制がとられていること.
(5)発展の初期に一定の農業基盤が確立されていること(例えば「緑の革命」の成功),あるいは天然資源のベースが存在すること.
工業化の主役は民間の企業であることは疑いない.しかし,その活力が工業化のために方向づけられ,かつ効率的に活用されるために必要な条件がここに挙げられた条件だ.ここに挙げられたのは項目で,その内容となるとそれぞれの国とその発展のフェーズによって違ってくる.例えば,工業化の初期に必要とされる教育は,比較的単純な工場労働に必要な基礎教育だが,産業の高度化が進むほど,中等教育や高等教育が必要になってくる.ハードやソフトのインフラでも同じことがいえる.
重要なのは,ここに挙げられた項目はすべて政府が主体的に供給しなければいけないことだ.政府の能力自体が問題となってくるのだ.そこで,
(6)経済発展を志向する強い政府(いわゆる「開発国家(“DevelopmentalState”)」が存在すること,そのうえで,国家機構をよく機能させる官僚組織があること.
(7)政府とそれを支える官僚機構(テクノクラート)が確かな経済発展のビジョンを持っており,それが国民に共有されていること.
という追加的な条件が付け加わる.
これらすべての条件が経済発展のための必要条件かというと,その疑問に対する確たる答えはない.また,これが十分条件かという問いに対しても同じ答えしか与えることができない.しかし,これまでの研究の蓄積から出てきた経済発展のために重要な条件がこのように多数に上るということは,経済発展成功のマジック・フォーミュラ(魔法のような手法)は存在しないこと,経済発展に成功してきた国は,ここに挙げられたような課題に時間をかけて現実的な方法で,実践的に取り組んできた(“Doing the right things - taking time and pragmatically!”)ことを意味するのではなかろうか.
しかし,ここに挙げた複数の条件の中で,最後に挙げた政府についての追加条件(6)と(7)はことさらに重要だと思われる.なぜなら,経済発展のための条件は,放っておいて自然に成立することはまれで,その成立のためには何らかの政府の介入が必要になる.追加的に示した条件は,その政府自体が良く機能するための要件だからだ.(1)から(5)までの条件,すなわち教育と保健,インフラ,マクロ経済の安定,開放体制,農業基盤といった条件は,民間の企業や市場の力に任せておいて自然に成立するものではない.政治指導者あるいは指導者階級が,既得権益の反対を抑え込んででも経済発展の目的を追求するという政治目的に強くコミットしており,さらにその国の経済発展のビジョンが指導者層に共有されなければならない.そのビジョンは具体的な政策や制度に設計されて,実行に移される必要があるが,それを担うのがテクノクラートであり,官僚組織である.
民主制であるか否かにかかわらず,政権交代の可能性は常にある.上に述べたような国の経済発展のビジョンと戦略や政策が国の指導者層や有力者のグループに共有され,一定の政策努力が持続的に実行されるためには,理想的には政府の上層部に経済発展のビジョンを国是として定着させ,そのビジョン実現のための政策設計と実行計画を策定する部署があるのが良い.政府の首脳部に直結するは開発計画委員会(インド)や経済企画院(韓国)や開発計画庁(シンガポール,フィリピン)などがそれだが,現在ではこれらの機構の多くは多分に形骸化している感は否めない.
***
途上国の多くは─今日高所得国になっている国々を含めて─それぞれの「地理と歴史」を負って経済発展の途をたどってきた.それぞれの「地理と歴史」に特有の開発課題があり,またそれぞれの発展のフェーズに現れる問題もある.ある国はそうしたチャレンジを克服するのに成功し,またその他の国は挫折を経験してきた.経済発展の途は,すべての国がたどらなければならない過程で,その途に終わりはない.経済発展の軌跡を追い,その条件や動因を探る開発経済学の旅もまた同じだ.
長い間,わたくしは小浜さんに誘われて経済発展の謎を探す旅を続けてきた.途上国のいくつかに一緒に旅をしたことも数度にとどまらない.本共著はこれで5 冊目のその旅の結果だ.月1 回の原稿を議論する「昼の部」も,またそのあとの他の友人を交えた「夜の部」と称する夕食会も,実に想い出深い経験だった.原稿執筆の大宗を担ってくれた共著者の小浜さんには感謝のしようがない.また,すべての会合に参加し,われわれに激励と協力を惜しまなかった勁草書房の宮本詳三氏に深甚の感謝をささげたい.
2024 年6 月
浅沼信爾










