あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
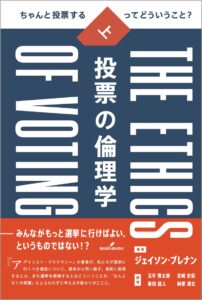
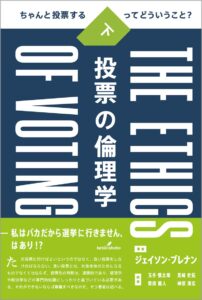
ジェイソン・ブレナン 著
玉手慎太郎・見崎史拓・柴田龍人・榊原清玄 訳
『投票の倫理学 ちゃんと投票するってどういうこと?(上・下)』
→〈「序論 倫理的問題としての投票」・「訳者解説」(pdfファイルへのリンク)〉
→目次・書誌情報はこちら:〈上巻〉/〈下巻〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「序論」「訳者解説」本文はサンプル画像の下に続いています。
序論 倫理的問題としての投票
なぜ投票が問題となるのか
票を投じるとき、我々は統治をより良いものにすることも、より悪いものにすることもできる。ひるがえって、我々の票は人々の生活をより良いものにすることも、より悪いものにすることもできる。
もし我々が投票において悪い選択をした場合、人種差別的であったり、性差別的であったり、同性愛嫌悪的であったりする法律がもたらされる。経済的な機会が消失したり、実現され損なったりする。我々は不正で不要な戦争を戦うことになる。我々は経済を刺激することも貧困を縮減することもほとんどないような、誤解に基づく景気刺激策や給付プログラムに多額の資金を費やす。よりうまく働くであろうプログラムに資金を投じ損ねる。いくつかの場面では規制しすぎ、また他の場面では規制が足りず、多くの規制は特別利益〔=自己利益〕のための不公平な経済的アドバンテージを守るだけの効果しかないものとなる。我々は不正義に苦しめられ、そしてまた不正義を存続させる。貧しい人々を置き去りにしていく。インナー・シティをゲットー化するような麻薬戦争を行う。刑務所にあまりにたくさんの人々を放り込む。移民政策及び経済政策を、ゼノフォビアや時代遅れの経済理論の上にしつらえる。
投票は道徳的に重要である。投票は統治の質、射程、形態を変えてしまう。我々の票の投じ方によって、人々が助けられることもあれば傷付けられることもある。選挙結果は有害なものでも有益なものでもありうるし、正しいものでも不正なものでもありうる。選挙結果によってマイノリティがマジョリティの利益のために搾取されることもありうる。ほとんど誰にも利益がないまま広範な危害がもたらされることもありうる。それゆえ、本書において私は次のように論じる。我々は、自分たちがどのように投票を行うべきかに関して、いくつかの道徳的な義務を負っているのだ、と。投票は何であれ道徳的に受け入れられるものだということはないのである。
この本は投票の倫理を取り扱う。とりわけ、政治的な文脈における投票の倫理に関心がある(MLBのオールスターゲームや全米アイドルコンテストの投票についてではない)。この本の目的は、そもそも市民は投票すべきなのか、また投票することを選んだならばどのように投票すべきなのかといった疑問に、結論を下すことにある。投票の倫理という学問領域は、例えば以下のような問いを投げかける。市民は投票するべきなのか、それとも棄権を選択するべきなのか? 選挙の結果について無関心である人は、棄権すべきなのか? 市民が投票するとき、どのようにすべきか? 投票先を決定するにあたって、投票者は自らの宗教的信念を持ち出しても構わないか? 投票者は誠実に、つまりは自らが最善だと考える候補や立場に対して投票しなければならないのか? 最善の候補に投票するということは何を意味するのか? とりわけ大事なこととして、投票者は自身の利益のみのために投票すべきなのか、それとも共通善(それが何であるにせよ)のために投票すべきなのか? 票を購入したり、売却したり、あるいは交換したりすることは果たして受け入れられることなのか?
〔これらの問いに加えて、〕政治哲学の観点から見て関連性を持つ、以下のようなトピックもある。政治参加を促進することに関して政府は何をすべきなのか? どのような人々が投票する権利を持つべきなのか? 選挙はどのように構成され、どれくらいの頻度で実施されるべきなのか? 政府は投票者を教育するよう試みるべきなのか、またそうするべきだとすれば、どのようにすべきなのか? 政府は市民に投票するよう強制してもよいのか? 投票は秘密であるべきかそれとも公開されるべきか? 有益な問いはいくつもあるが、しかし私はここではこれらの問いに関心を向けない。この本はあくまで市民の義務についてのものであり、政府の義務についてではない。投票をめぐって政府が何をすべきかに結論を下すためには、また別の著作にじっくりと取り組むことが必要だろう。
投票は何と区別されるか?
道徳的な観点からすると、投票は、メニュー表から料理をオーダーすることと同じではない。あなたがレストランでサラダをオーダーするとき、その決定の結果を引き受けるのはただあなた一人である。他の誰も、我慢してサラダを食べなければならないということにはならない。もしあなたが悪い選択をなしたとしても、ともかくあなたが傷付けることになるのはただあなた自身である。多くの場合、あなたはあなたの決定のコストと便益の全てを自分のものとする。
投票は違う。我々は投票するとき、言うなれば、全ての人々に対して一つの食事を強いているのである。もしあなたがディナーの皇帝――全ての人が毎晩のディナーに何を食べるかを決定しなければならない――に任命されたならば、あなたの決定が道徳的な重要性を有することは明白である。ディナーの皇帝として、あなたはあなたの決定のコストと便益のほとんどを外部化する〔=他人に負わせる〕ことになるだろう。そこには多大な責任が伴う。糖尿病患者には糖分を過剰に摂取させない方が望ましいし、ヴィーガンに肉料理を食べさせたり、ムスリムに豚肉を食べさせたりもしない方が良い。あるいは、もし仮にあなたがそういったことをする場合には、適切な理由があった方が望ましい。
現在では、投票に際して、〔その結果を〕自分で決められる人はいない。誰の票であっても数えられるが、一票以上に数えられることはない。我々は選挙結果を共同で決定する。重要なのは我々がどのように投票するかであって、あなたがどのように投票するかではない。しかしながら、共同の活動に参加するにあたって人々がどのように行動すべきかを律するいくつかの道徳原理が存在する。たとえ、大規模な選挙においては個人の投票が選挙結果に重大な影響を及ぼすことはほぼ全くないとしても、個人が義務から解放されるわけではない、と私は論じる。どのように投票するのかについて、投票者一人ひとりが道徳的な義務を負っている。
もちろん、政府がなす善と悪の、その全てが我々の投票のあり方に起因するわけではない。我々の投票行動は政治的結果に影響を及ぼす多数のファクターのうちの一つにすぎない。堅牢かつ確実な民主主義的監視があっても、官僚たちの気まぐれや政治家の堕落のゆえに悪い政策が実施されることはありうる。私の目的にとって重要なことは、総合的に見れば、投票はやはり違いをもたらすものなのだということである。〔例えば、〕それぞれの政党は政策的な偏りを――すなわち特定の種類の政策を他のものよりも優先して実施する傾向性を――有している。投票者が特定の政策的な偏りを持つ政党のメンバーのために投票するとき、そのような〔当該政党が好む〕種類の政策が実施される見込みは非常に大きくなる。
政治的結果を決定するファクターは投票以外にもある。このことが意味するのは、ただ投票者がより良い投票を行うようにすることのみによって全ての政治的問題を解決することはできない、ということである。要するに、より良い投票は〔あくまで〕より良い政府を導く傾向を有するものなのだ。
常識的見解に対する反論
投票は市民が統治の質に影響を及ぼすための第一の手段である。民主主義にとってこれ以上に象徴的な活動はない。投票を市民にとっての聖餐式と呼ぶ人もいる。多くの人々が、擬似宗教的な畏敬の念を持って民主主義に、とりわけ投票に参加する。
このことが意味するのは、人々にはいつ・どのように投票すべきかについて確固とした意見を有している傾向がある、ということである。彼らは、投票の倫理をめぐる諸問題に対する答えは明白であると考える傾向にある。投票に対する自分たちの見解を、人々は神聖な教説として取り扱う。自分たちの見解が挑戦を受けることを人々は嫌う。
(注と傍点は割愛しました。サンプル画像もしくはpdfをご覧ください)
訳者解説
柴田龍人・榊原清玄
はじめに:バカは選挙に行くな!
あなたは、自分がちゃんと投票している、と胸を張って言えるだろうか? 何はともあれ選挙のたびに投票しているから、特に問題ないだろう、と言うだろうか? ただ投票さえすればよい、そんなふうに考えていないだろうか?
ところが、とにかく投票さえすればよい、というわけではないのである。例えば、政見放送を観てみたら何やら面白いパフォーマンスをする候補者がいたので、その候補者に投票することにしたとしよう。あるいは、選挙でいつも票を入れる政党があるので、次の選挙でもその政党に投票することにしたとしよう。はたまた、質問に答えるだけで自分に合う投票先を教えてくれるボートマッチで自分の考えに近い政党を見つけたので、その候補者に投票することにしたとしよう。
このいずれも、ちゃんとした投票とはならない。本書『投票の倫理学――ちゃんと投票するってどういうこと?』の著者であるジェイソン・ブレナンはそう言うだろう。我々はただ投票さえすればよいというのではなく、良い投票をしなければならず、それができないならば棄権すべきなのだ。標語的に言えばこうだ。――バカは選挙に行くな!
ブレナンが述べる良い投票とは、少なくとも次のような諸条件を満たす。一つ目に投票は私利私欲のためでなく、社会全体(本文中では公共善という)を良くすることを目的としている。二つ目は、投票先の判断は、道徳的であり、経済学や政治学などの専門的知識にしっかりと基づいている。投票先の候補者がどんな人物か知っているだけでは不十分であり、その候補者が本当に社会全体のためになることをすると、投票者は正しく認識しているのでなければならない。
もう少し具体的に考えてみよう。例えば、減税を公約とする候補者がいるとする。減税が自分の生活を良くしてくれると思うからといって、それだけを理由にしてその候補者に投票してはいけない。また、減税が社会全体を良くすると論拠もなく考えて、その候補者に投票してもいけない。その候補者への投票が許されるのは、その候補者がもたらす減税が社会全体にとって良いものであると、論拠に基づいていえる場合のみである。これは減税に限らず、どの政策上の争点でも同じである。社会保障、軍拡・軍縮、産業の振興……、どんな政策を支持する候補者であれ、適切な論拠に基づいて、それが社会全体にとって良いものだといえないのであれば、その候補者に投票すべきでない、とブレナンは言うのだ。
確かに自分は経済学も政治学も知らないかもしれないが、投票は何はともあれ当たり前にしないといけないことじゃないか? そう思う人もいるかもしれない。だが、それは間違いであり、投票する義務などそもそもないのだ、とブレナンは主張する。その理由の一つは、一票の無力さである。選挙に行って投票すべきなのは、私の一票が何かを変えるかもしれないからだ。このような考えはよく見られる。だが、ブレナンはこの考えを徹底的に攻撃する。私の一票は私自身も社会も良くしない。なぜなら、全体の投票数を考えたとき、私の一票の影響力は消え入るほどに小さいからだ。実際、一票の期待値――私の一票が何かを変える確率とその何かを変えたときの効果の大きさを掛け算した値――は、0.000 ……と、ほぼゼロに等しい値である。だとすれば、あなたが投じた一票だけでは何も変えることができないのだ!
もし社会を良くしたいのであれば、そんな期待値がほぼゼロの投票に行くよりも、他のことに時間を使うべきではないのか? 社会を良くする手段は多様であり、普段の仕事に励むことによっても社会に貢献できるし、おそらく投票よりも期待値は高い。こうしてブレナンは結論する。あなたも私も投票しなくてよいのである!
しかしそんなに自分の一票が無力なら、別に好き勝手に投票してもいいんじゃないか? そう考える人がいるかもしれない。だが、そうではない。悪い投票が積み重なれば、社会にとってひどいことになる。悪い投票によって、有害な政策が実施され、豊かさも、平和も、命も、失われるかもしれない。悪い投票の一つひとつは無力だとしても、それらが積み重なれば有害となる。投票さえしなければ、悪い投票の積み重ねの一員になることを簡単に避けられる。だからブレナンはこう言うだろう。悪い投票一つひとつにほとんど力がないとしても、バカは選挙に行くな!
あなたはちゃんと投票しているだろうか? 投票は、(個々には無力であっても集合的には)他者の命と生活を左右する重大な政治的行為である。そんな行為をするのに十分な知識と判断力を、あなたは有しているだろうか? もしそうでないなら、あなたは選挙に行くべきではないのだ。選挙に行かなくとも、あなたが自分自身や社会のためにできることはたくさんある。ブレナンは我々にこう語りかける。
ブレナンの民主主義批判プロジェクト
本書を著したジェイソン・ブレナンは、現在アメリカのジョージタウン大学に在籍する政治哲学者である。「アメリカの政治哲学者」と聞くと、リベラルの一員かと思われるかもしれないが、そうではない。むしろブレナンは、リベラル批判の急先鋒と目されている。ブレナンは、財の平等や再分配を要請するリベラルに対して、より強固に経済的自由を擁護するリバタリアンの一人なのである。例えば、『資本主義でよいのでは?(Why Not Capitalism?, 2014 )』では、資本主義が社会主義よりも優れている理由を強く主張する。日本でよく知られているリバタリアンとしては、例えばロバート・ノージックが挙げられよう。しかし、ブレナンはより新たな世代のリバタリアンであり、ノージックのような旧来のリバタリアンよりも社会科学的な志向が強く、経済的な自由と社会正義の両方を重視している。ブレナンのより詳細なプロフィールについては、先行して二〇二二年に邦訳が出版された『アゲインスト・デモクラシー(Against Democracy, 2016 a)』の訳者解説を参照してほしい。(けいそうビブリオフィル https://keisobiblio.com/2022 /08 /10 /atogakitachiyomi_againstdemocracy/ でも読むことができる。)
さて、本書はブレナンの民主主義批判プロジェクトの一部である。以下では、このプロジェクトを概説することで、本書の目的や意義をより明確なものとすることにしたい。
ブレナンの民主主義批判プロジェクトには中核をなす三部作があり、本書はその第一作目にあたる。第二作目は『義務投票制――賛成論と反対論(Compulsory Voting: For and Against, 2014 )』(リサ・ヒルとの共著であり、義務投票制反対派のブレナンの論文と、賛成派のヒルの論文から構成される)であり、第三作目にあたるのが『アゲインスト・デモクラシー』である。この三部作を中核としつつ、その後もブレナンは民主主義に関する著作を公刊している。具体的には、二〇二一年にエレーヌ・ランデモアとの共著で『ディベーティング・デモクラシー――我々はより多く必要とするか、もしくは少なくともよいのか?(Debating Democracy: Do We Need More or Less?)』を、二〇二三年には『デモクラシー――ガイドツアー(Democracy: A Guided Tour)』を出版している。
三部作のうち本書以降の二作で、ブレナンの民主主義批判プロジェクトは次のように発展していく。『義務投票制』においてブレナンは、市民たちへの投票の強制に反対する。ブレナンによれば、投票の強制による市民の自由の侵害は、到底正当化できるものではない。なぜなら、市民たちへの投票の強制は、飲酒運転を強制するようなものだからだ、とブレナンは述べる。義務投票制によって普段は投票をしない人々も投票を強いられることになるのだが、これは普段運転しない人々にも運転を強制するのと同様だ、というわけだ(この説明から明らかなように、正確には、「飲酒運転」ではなく「無免許運転」と言うべきである)。言うまでもなく、そのような人々が良い投票をする見込みは低い。こうして義務投票制は選挙民全体の質を下げ、準じて統治の質も下げるだろう。それゆえ義務投票制は否定されるべきである、とブレナンは結論する。
続く『アゲインスト・デモクラシー』では、民主主義に対する根本的な挑戦が提示され、それに代わる政体として智者政(エピストクラシー)が提示される。ブレナンにとっての民主主義の問題点は次の点にある。すなわち、実際のところ有権者は統治に必要な能力を持たず、政治参加をすればその能力がもたらされるわけでもない。また、政治参加は人々に力を与えるものでもなく、選挙権は市民間の平等な地位を示すものでもない。我々は有能な政府に統治される権利があるのだが、民主主義がもたらす政府は有能とはいえないのが実態だ。それゆえブレナンは、民主主義の代替案として智者政を提示する。より具体的には、試験に合格した人にのみ選挙権を与える制限選挙制、一部の人に複数の票を与える複数投票制、人々に十分な知識と能力があった場合の政策の好みをシミュレーションする疑似信託、などである。
『アゲインスト・デモクラシー』とは異なり、本書では、民主主義に対する根本的な挑戦はなされていない。本書の議論の目的は、あくまでも、投票する義務などないことや、良い投票の本質とは何であるかを明らかにすることである。しかし、本書の議論は、市民全員が平等に投票権を保有する民主政の下でも、ブレナンが『アゲインスト・デモクラシー』で構想する智者政の下でも成立する。例えば、上述の制限選挙制を考えよう。この制度下においても、選挙権を持つ市民は好き勝手に投票することは許されない。彼らもまた良い投票をしなければならないのだ。
このように矛盾関係にないだけではなく、本書は、『アゲインスト・デモクラシー』を支える役割も果たしている。『アゲインスト・デモクラシー』では市民の典型的なあり方の一つとして「ホビット」が出てくる。ホビットは、「政治にかんして低い関心しかもたず、政治参加も低調な知識の乏しい市民」である(ブレナン 2022 上巻 p. v)。ブレナンは本書の第一章と第二章を、ホビットの道徳的擁護として位置付けている(ブレナン 2022 上巻 p. 122 )。
また逆に、『アゲインスト・デモクラシー』の議論が本書を支える役割も果たしている。本書の序章においてブレナンは、政治制度はハンマーのようなものであると述べる。すなわち、政治制度はそれ自体が持つ内在的価値ではなく、どれくらいよく機能するかに応じて道具的に評価されるべきだ、とブレナンは主張する。確かに、民主主義は手段以外の観点から――すなわち民主主義そのものの価値に基づいて――評価するならば、良いものといえるかもしれない。しかし、そのような価値は重要でない。このことの論証を、ブレナンは『アゲインスト・デモクラシー』で行っているのである。
ブレナンの目的:ファンダムとしての民主主義批判
そもそもブレナンはこれらの著作をどのような目的で出版してきたのだろうか? 先述のとおり、ブレナンは本書においては民主主義そのものの正当性を疑問に付すことはしなかったが、最終的には、『アゲインスト・デモクラシー』において民主主義の本格的な批判を展開する。ブレナンがそうするに至った経緯はどのようなものだったのだろうか? 本人の記述を手がかりにして、民主主義に対するブレナンの本心を推測してみたい。
意外なことに、ブレナン自身は民主主義の「ファン」であると公言している。ブレナンは『デモクラシー――ガイドツアー』において、こう述べている。私はこれまで、民主主義の様々な病理や欠点について多くのことを書いてきた。同時に、私はある意味で民主主義のファンでもある。(自分は民主主義の真のファンであるとよくジョークを言うのだが、なぜなら真のファンというのは、あるバンドには悪いアルバムがあることや、ある制度に欠点があるという事実を認めるものだからである。)民主主義は、おそらく我々がこれまでに試した中で最良の政治システムだが、深刻な問題を抱えている(Brennan 2023 p. vii)。
この発言が示唆するのは、ブレナンが「民主主義を本当に愛しているから」こそ批判しているのだ、ということではないだろうか? また、ブレナンは何が何でも民主主義を否定しようとするわけではない。『アゲインスト・デモクラシー』の「二〇一七年のペーパーバック版への序文」では、デモクラシーの利点を示す論考を発表したと述べている。「デモクラシーと自由」という論考で論じたのは、実際問題として、デモクラシーは多くの重要な帰結と正の相関を示しており、しかもそれは単なる相関関係ではなく因果関係と思われることである(ブレナン 2022 上巻 p. v 注番号は削除 cf. Brennan 2016 b)。
ここから示唆されるのは、民主主義をより深く知るために、ブレナンは民主主義の徳を示す場合もあれば、同時にその批判を鋭敏なものにする場合もある、ということではないだろうか? それを窺わせる箇所が『アゲインスト・デモクラシー』の序文にある。二、三年前に『投票の倫理学』を読んでくれた後、ジェフ〔=ジェフリー・ブレナン〕が私に「投票者がそれほどひどければ、一体なぜ民主主義を受け入れ続けるべきなのか」と尋ねてきた。その問いに応答する試みが、一連の論文や最終的に本書に結実している(ブレナン 2022 上巻 p. xvi)。
この引用文を見ると、ブレナンは民主主義の正当性を批判的な視点で徹底的に追求し、その集大成として『アゲインスト・デモクラシー』を世に問うたと推測できるのではないか? この推測に基づきつつ、以下、投票権の象徴的価値をめぐるブレナンの見解の変化を瞥見することにしたい。
『投票の倫理学』の原著が出版される前年の二〇一〇年に、ブレナンは自身の指導教員であるディヴィッド・シュミッツとの共著で『自由の小史(A Brief History of Liberty, 2010 )』を出版した。そこでは、平等な投票権は象徴的な価値を持つものとして好意的に扱われていた。その文章が、『アゲインスト・デモクラシー』の第五章冒頭でも引用されている。選挙権の価値は、[その道具的価値以外の]何かに存する。個々の票は大した実用性を持ちはしない。選挙権はむしろ平等な人格性のしるしなのだ。ナチスはユダヤ人に、劣位性のしるしとして、ダヴィデの星を身に付けさせた。選挙権は、平等の隠喩的なしるしである(Schmidtz and Brennan 2010 p. 189 ; ブレナン 2022 上巻 p. 187 )。〔[ ]内はブレナン 2022 上巻 p. 187 に記載されているもの。〕
この段階では、投票における手段的な価値は乏しいものの、投票権の等しい保有が象徴するものには価値があると(シュミッツとともに)ブレナンは考えていた。すなわち、投票する権利は平等な人格を示すしるしとして価値があるというわけである。
しかし、その後『投票の倫理学』の序論においては、この象徴的価値に疑念を抱いていることを窺わせる記述を残している。曰く、確かに投票権を等しく保有することは平等な地位の尊重や公的承認の観点から重大である。しかしながら、本書上巻の一三頁でブレナンは、「平等な投票権の象徴的な価値はそれを正当化するのに十分なものだとも考えていない」と述べるのである。『投票の倫理学』の時点で既に、投票権の象徴的価値に批判的になりつつあることがわかる。そして最終的に『アゲインスト・デモクラシー』の第五章にて、投票権の象徴的価値を否定するに至ったのだ。その具体的内容を知りたい読者は、実際に書籍に当たられたい。
『投票の倫理学』、『義務投票制』、『アゲインスト・デモクラシー』を含む一連の著作は、愛する民主主義に対してブレナンが送る長いファンレターなのかもしれない。これらは、民主主義を真に愛する者としてのブレナンなりのファン活動の産物だと捉えることができるのではないだろうか?
非合理性や政治的無知を認めつつ民主主義を擁護する議論
さて、本解説の冒頭で「バカは投票をしてはならない」と述べた。その理由は、簡潔にいえば、我々は正しい政治的知識や論拠に基づいた判断によって投票しなければならず、それができないならば、その投票はむしろ有害でさえありうるからだ、というものだった。我々に求められるのは、ただ単に投票するのではなく、良く投票することなのである。ブレナンは以上を正当化した上で、第七章で現実の投票者は実際に政治的に無知であり、あるいは非合理であることを実証的な政治学の知見を用いて示す。それによれば、人々は政治に関する知識をわずかにしか持たず、かつ政治において非合理的な振る舞いを見せるために、良い投票が現にできていないのである。このことは民主主義にとっては深刻な問題となる。なぜなら、民主主義の理念として重要な、各人の平等な集団的意思決定への参加が否定される恐れがあるからである。
しかし、投票者の非合理性を踏まえた上で民主主義理論を再出発させようとする議論が存在する。クリストファー・アーケンとラリー・バーテルスは、『現実主義者のための民主主義――なぜ選挙は責任ある政府を生み出さないか(Democracy for Realists: Why Elections Do Not Produce Responsive Government, 2016 )』と題した本の中でそれを試みる。その内容を簡潔に紹介したい。
まず二人は、二つの「民主主義における素朴理論」を否定するところから始める(これは本書の序論でブレナンが論じていた素朴理論とは異なる)。一つ目は、投票者は、選挙において争点となっている事柄に関して十分な情報を獲得し、かつ整合的な選好を形成した上で候補者を選ぶとする「争点投票の理論」である。二つ目は、選挙において現職の候補者か対抗候補者のどちらかに投票することによって、投票者は現職の公職者の職務遂行能力の評価や管理をすることができるとする「回顧投票の理論」である(Achen and Bartels 2016 pp. 14 -15 )。二人によれば、(少なくともアメリカにおける)投票者は政治の事柄をほとんど理解しておらず、また十分な情報を得る動機にも乏しい。それゆえ、一つ目の素朴理論である争点投票の理論は妥当ではない。また、何か悪い物事が起こったときにそれが現職の責任であるかどうかを投票者は適切に判断できない。したがって、二つ目の素朴理論である回顧投票の理論も妥当ではない。この本の中で二人はブレナンの『投票の倫理学』に言及していないが、今述べた議論は『投票の倫理学』の第七章の議論と軌を一にする。
民主主義の素朴理論に代えて、アーケンとバーテルスは「民主主義の集団理論」を支持する。この集団理論によれば、人々が政治に関して意見や価値観を形成する際には、人々の属する社会集団への忠誠心や党派的バイアスが大きく影響する。すなわち、ある人が政治に関して意見や価値観を形成する場合には、その人が属する集団がどのような価値観を持っているかに大きな影響を受けるということである。例えば、仮にその集団がリベラルな価値観を持っているとしよう。その場合、その集団に属する人々もリベラルな価値観を持つ確率が高まるのである。また、人々は自分の政治的意見や価値観に基づいてどの社会集団に属するかを決めるのではなく、自分が元々属している社会集団の考えに合わせて自身の政治的意見や価値観を形成し変容させていくことも指摘されている。この理論によれば、投票者は自身が属している社会集団や政党への忠誠心に基づいて投票を行う。つまり、人々にとっての良い投票というのは、自身が属する社会集団の価値観に合う候補者に投票することなのである。もちろん、全ての投票行動に以上の理論が当てはまるわけではないが、少なくとも素朴理論よりはもっともらしいと思われる。アーケンとバーテルスの二人は、民主主義の集団理論が示す事実に目を向けつつ、民主主義の正当化をするべきであると主張する。
ところが肩透かしなことに、その正当化自体を二人は積極的に行っていない。というのも、二人の目的は「民主主義の素朴理論を放棄することは、より高い知的明快さと真の政治変革の両方にとっての必要条件である」と示すことだからである(Achen and Bartels 2016 p. 328 )。ただし、一応の方針は提示している。それは、経済的及び社会的平等の程度を高めていくことである。二人が提示した理論によれば、人々は自身の社会集団の価値観に沿って投票(やその他の政治活動)をするのであった。ここで問題になってくるのは、それぞれの社会集団には政治的影響力の差があることである。例えば、高学歴層、富裕層、政治家との広い人脈を持つ層は、そうでない層よりも高い政治的影響力を持つ。他方で企業は労働者よりも高い政治的影響力を持ち、主要メディアは個人ブロガーよりも高い政治的影響力を持つ。二人は、特に経済的格差から由来する政治的影響力の差が最も重大であると指摘する。例えば、高い経済力があれば、政治キャンペーンやロビイングに多大な資金を投じることが可能になるだろう。こういった政治的影響力の差が存在する状況における政治活動(やそれによる統治)は、民主主義の理想からはほど遠いだろう。以上を踏まえて、焦眉の課題は「民主主義のプロセスにおいて、既存の貧富の差がもたらす最も直接的な影響を軽減する」ことであると最終的に二人は結論する(Achen and Bartels 2016 p. 326 )。
一票の影響力の小ささを認めつつ投票する義務を擁護する議論
他方で、政治的無知や非合理性があるとしても、投票する義務が正当化されると主張する人物がいる。ジュリア・マスキフカーは、『投票する義務(The Duty to Vote, 2019 )』において、投票する義務の規範的望ましさを主張し、その過程でブレナンが本書で示した議論を退けようとする。その内容は「投票の義務をめぐる議論の中で最も強力な擁護」であると目されている(Freiman 2022 p. 517 )。本解説でその全貌を述べることはできないが、以下、その重要な部分を確認しよう。
マスキフカーが主張するのは、単なる投票の義務ではなくて「注意深い投票をする義務」である。それは、「情報と公共的利害関心を備えた状態で」投票する義務のことである(Maskivker 2019 p. 4)。つまり、政治に関する情報を調べた上で、かつ共通善を促進する心構えを持って良い投票をする義務があるというのだ。そこで、マスキフカーはこの義務を支える二つの原理を正当化しようとする。
一つ目の原理は、「最低限利他主義の原理」である。この原理によれば、他者を助けるときにそのコストが重大ではない場合は、我々にはその他者を助ける義務があるというものである。ここで、マスキフカー自身が使用した例を見てみよう。あなたと松葉杖をついた友人がバスを待っているとしよう。バスが到着し、その友人が乗り込むのに手間取っている場合、あなたは例えば手を貸してあげるなどして助けることができるだろう。このとき、あなたは友人を助けるという善をなしたのだが、その労力はそこまで大きなものではないはずである。この例のように、投票によって共通善を促進することができ、かつそのコストが甚大ではない場合には、我々には(注意深い)投票をする義務があるのだ。しかし、ここで直ちに出てくる反論は、バスで友人を助けることはすぐに利益をもたらすが、投票はそうではないというものだ。なぜなら、本書で再三言われるように、一個人の票が持つ影響力は微小にすぎないからである。だとすれば、たとえコストが小さかろうと、利益をもたらす蓋然性がない行為を強制することはできないのではないか?
以上の反論に応答するために、マスキフカーは二つ目の原理を提示する。それは、「集合的サマリタリアニズム」である。これは、我々が集団として、望ましい帰結を生み出す努力をする義務があると述べる原理である。確かに個々の票が持つ影響力は小さいかもしれないが、むしろその投票が影響力を持つことができるように集団的な形で投票をするべきなのである。マスキフカー自身はこのようにいう。我々が投じる個々の票の価値は、注意深い投票というものが、我々が好ましいと思える十分な(客観的)理由がある集合的結果を多くの同様な行為とともにもたらすような行為であるという事実に存する。その理由とは、共通善と社会正義の推進である(Maskivker 2019 p. 50 強調は原文)。
この引用文が示唆するのは、個々の票が持つ影響力は乏しいとあげつらうのは、投票の本質を見誤っているということである。というのも、投票というのは、個々人の行為として見るのではなく、複数の人々がともに行う集合的行為として見るべきなのだ。現にブレナンも、悪い投票はそれ単体としては影響力がなくとも、それが積み重なれば悪しき帰結がもたされると論じているのである。最終的に、集合的サマリタリアニズムを第一原理(最低限利他主義)と組み合わせると、共通善の促進といった公共的な目的のために、甚大なコストがかからない範囲で注意深い投票をする集合的義務が我々にはあるのだ。
しかし、マスキフカーの議論に対してはまだ反論がある。それは、共通善を促進する手段は投票だけではないということである。例えば、自分の仕事に邁進することや、炊き出しのボランティア活動などをすることによっても共通善を促進することもできるし、そういった行為を投票のような集合的行為として特徴付けることも可能である。だとすれば、共通善を促進する手段として、なぜとりわけ投票が重要になるのだろうか?
この反論に対してマスキフカーは、公正な政府を生み出す重要な契機であるところが、他の活動と比べたときに投票が優位性を持つ理由だと述べる。もし悪い投票が積み重なった結果ひどい政府が生まれてしまった場合には、共通善が深刻な形で損なわれることになるだろう。政府という重要な主体に関わる行為であるゆえに投票は、共通善を促進する手段の中で重大な地位を占めるのである。
政治的無知や非合理性の原因に目を向ける
まだ話は終わらない。最後の反論として、投票者の政治的無知や非合理性を強調するものがある。注意深い投票をしようにも、何に注意するべきかが投票者にはわからないのである。それゆえ、結局のところ現実の投票者はまずい投票をしてしまう。だから投票を義務付けることはむしろ統治の質を下げることになる。『義務投票制』でブレナンはこのような議論を展開していた。この反論に対して、マスキフカーはそのような政治的無知や非合理性が生じる社会的原因に目を向けるべきであると応答する。政治的知識や政治に対する関心に影響を与える変数として構造変数、文脈変数、認知能力変数の三つがある。それぞれを順番に説明していこう。
一つ目の構造変数は、投票者を取りまく構造が与える影響である。例えば、エリート、政党、メディア、選挙法、行政などが投票者に大きな影響を与えることが知られている。例えばアメリカの共和党は、所得格差がある場合には自身の政党に票が集まる見込みが高いため、所得格差は問題がないと投票者に説得しようとする動機があると指摘される。実際に、共和党の言うことを一定の人々が信じてしまい、所得格差は何も問題がないと信じ込んでしまう事例があるとされる。また、メディアの報道の仕方、選挙法の複雑さ、人々の政治的活動に対する行政の無頓着さなどが要因となって、人々は政治に対して無力感を持つようになり、政治的知識を得る動機を失うとも指摘される。
二つ目の文脈変数は、人々の持つ政治的知識に対する社会経済的影響である。具体的には、人々が受けている教育のレベルや、人々の所得レベルがもたらす影響のことを指す。この変数に関しては、教育レベルの向上や所得格差の解消を通じて人々がより容易に情報へアクセスできるようになれば、政治的知識と政治的関心が中期的ないし長期的に改善されるとマスキフカーはいう。さらに、所得の平等を高い程度に達成している国々の投票者は、政治に対して比較的高い関心を持ち、また政治に参加する傾向にあるという論拠がある。
最後の変数である認知能力変数は、情報を論理的かつ意欲を持って使用する個人能力である。ブレナンが投票者の政治的無知や非合理性を強調するとき、焦点になっているのはこの認知能力変数のことである。マスキフカーが批判するのは、ブレナンが主にこの認知能力変数ばかりを強調することである。ただし、ブレナンも本書第四章の「なぜ代わりに投票者を教育しないのか?」にて少なくとも教育の重要性を認識している。もっとも、社会構造や所得格差による影響を明示的に考慮しているわけではない。人々の政治的知識や関心に対する社会的要素の影響力を考慮すれば、政治的無知や非合理性があるから「投票者は事実として賢明な結果を生み出すことができないと決めつけるのではなく、投票者の能力を向上させるよう努力するのが原則だと考える」べきである(Maskivker 2019 p. 117 )。
しかし、これに関してはブレナンからさらなる反論があり得る。それは、社会構造や所得格差を改善した上でも、なお「適切な投票ができない」人は投票してはならない、ということだ。まず、先述の社会的背景が修正されれば「全て」の人が十分な知識と合理性を持つことになる見込みは極めて薄いだろう。だとすれば、まだ「適切な投票ができない」人々は依然として投票すべきではない――たとえそれが注意深い投票であるとしても――のではないか。マスキフカーとブレナンの応酬はここで切り上げることにするが、注意深い投票をする義務が最終的に正当化されるかどうかはなお議論の余地があることがわかるだろう。とはいえ、マスキフカーの議論はブレナンに対する批判として重要であることは確かである。
終わりに:ちゃんと投票してますか?
本解説のはじめに、筆者たちは「バカは選挙に行くな!」と宣言した。読者の中には、自分と対立する考えを持つ人々の投票を抑制するために、本書の議論を用いる人がいるかもしれない。例えば、自分の意見に反対する人々こそがバカなのだから、その人たちは投票を差し控えるべきであると。だが、あなたはバカではない一方で、あなたと対立する人々のみがバカである論拠は一体どこにあるのか? あなたは様々な論拠を示すかもしれないが、それらが適切な論拠であることを本当に示せるだろうか? それができない限り、むしろあなたがバカである可能性を常に胸に留めておく必要がある。
ここまでの議論を踏まえると、本当に言うべきことは「ちゃんと投票せよ!」ということではないか? つまり、我々は投票を差し控えるという安易な方法に満足するのではなく、良い投票をするためには何をすればよいかを地道に考えた上で投票していかなければならないのではないだろうか? さて、ここで改めてあなたに問いたい。我々はどのようにすれば良い投票ができるようになるのだろうか? これに十全な答えを与えることは、我々には難しいかもしれない。ただ、それに向けた第一歩を踏み出すことはできる。本書の「ペーパーバック版のあとがき」で、ブレナンは上手な投票をするヒントを論じている。その内容をここで繰り返すことはしないが、ちゃんとした投票をする上で参考にすることができるだろう。ここまで読み進めてくれたあなたも、我々とともに良い投票を目指してみるのはどうだろうか?
※ 本解説で示した『アゲインスト・デモクラシー』の引用文は、邦訳されたものを使用したが一部修正を加えた。また引用する際には邦訳のページ数のみ示した。
謝 辞
本書出版のために尽力してくださり、また私たちをサポートしてくださり、さらに本解説の執筆を許可してくださった勁草書房の山田政弘さんに深く感謝申し上げます。本解説の草稿にコメントをくださった玉手慎太郎さん、見崎史拓さん、田畑真一さん、吉良貴之さん、福原正人さん、久保健太さん、小林卓人さんにも感謝申し上げます。また、柴田と榊原の民主主義読書会に参加してくださった田畑さんには大変お世話になりました。
(傍点と参考文献は割愛しました。サンプル画像もしくはpdfでご覧ください)












