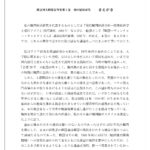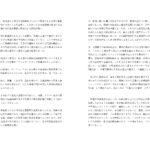あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
 渡辺利夫 著
渡辺利夫 著
『韓国経済研究 渡辺利夫精選著作集第3巻』
→〈「まえがき」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「まえがき」本文はサンプル画像の下に続いています。
渡辺利夫精選著作集第3 巻 韓国経済研究──まえがき
私の韓国経済研究を代表するものとしては『現代韓国経済分析─開発経済学と現代アジア』(勁草書房,1982 年)ならびに一般書として『韓国─ヴェンチャー・キャピタリズム』(講談社現代新書,1986 年)がある.本巻の「まえがき」では,これらの著作で記された私に固有な議論を二つにまとめて書いておこう.
私はアジア研究を韓国研究から始めた.1970 年代の初めのことである.大学院に席をおいていた当時,なけなしの金をはたいて韓国を訪れた.いまでは国内旅行と変わらない気安さで訪問できる間柄だが,当時の韓国は遠かった.「日帝36 年」の記憶が生々しく,韓国民の日本に対する怨嗟がなお強かったこの時期に韓国に出向くというのは,気の滅入ることであった.
しかし,2 週間ばかりの滞在を通じて私の胸を打ったのは,貧困の中にありながらも豊かさを求めて必死に働く人々の沸き立つ活気であった.ソウル南大門市場のあの唸りをあげるような活気に圧倒された.この国が何ものかにならないはずがない.日本が達成した経済的成果であれば,いずれこの国もそれを掌中にするに違いないと直感した.私は昭和14 年(1939 年)の生まれである.貧困からの脱却を求める執念をたぎらせていた闇市時代の感覚がまだ残っている.あの執念をもって日本が戦後復興を成し遂げたことを肌身で知っている.韓国を初めて訪れて得たあの直感が,私のその後の韓国論のスタイルを決定したように思う.
虚心に眺めればその成功は疑いのないものであったはずの1970 年代の韓国を前にして,日本の研究者の韓国論は韓国の現状をひたすら暗黒に塗りつぶして滅滅たるものであった.韓国はその後,1996 年秋にOECD(経済協力開発機構)への加盟を認められて名実ともに先進国の地位を掌中にしたのだが,このことを予想させるようなまっとうな議論は当時,何一つ用意されていなかった.
この国のことを少しでも実証的に分析してみれば,到底そんな結論になるはずもない臆面もない議論のオンパレードであった.イデオロギーというものの面妖さに腹が立ってしようがなかった.当時の日本の論壇では北朝鮮が「地上の楽園」であるかのような,まったくの偽りであったことがすぐ後で判明する,ほとんどデマのごとき報道が大手を振っていたのである.不可思議なことではあるが,イデオロギーとはそういうものなのであろう.
韓国の発展が誰の目にも明らかとなった時点でも,研究者たちは韓国の成功はこの国を取り巻く有利な国際環境の僥倖(ぎょうこう)によるものであり,そういう条件が失せれば韓国は崩落するといった議論が一般的でさえあった.韓国がそんなはずはない.朝鮮戦争を経てゼロから出発してここにまでいたった韓国は,実は開発途上国のモデルなのではないかとさえ当時の私は考えた.
その頃の私は韓国のことを論じる研究者たちと,孤立無援の論争を繰り返していた.「対外従属」「軍部独裁」「財閥支配」の暗鬱な韓国論に対して,そうした用語法で語られる韓国の現実は,発展の過程で通り抜けねばならない過渡的現象である.これらを克服して韓国はほどなく一人前の経済になるであろう,と当時の私は意固地なばかりに反論を書き連ねた.
なぜ韓国が私を惹き付けたのか.韓国は必ずや発展するという経済学者としての直感に導かれたのであるが,そればかりではない.退嬰(たいえい)に向かう当時の日本に対して何かアンチテーゼを突きつけてやりたいという思いが私にはあった.その思いの方が強かったようにも思う.第2 次大戦後の日本の「坂の上の雲」は昭和40 年前後であったと当時の私はみていた.その感は今も深い.この頃までの日本人は貧困からの脱却を求めて必死に働いた.働き詰めだった.勤労が卓越した価値であり,この価値が日本人の精神にある構えを作りだしていた.しかし,IMF 8 条国移行,OECD 加盟,東京オリンピック開催を経て自立国家としての国際的な認知を受けたその頃から,日本はあのひたぶるの勤労の時代を終え,あれやこれやと思い惑う国へと変身してしまった.国家意識を希薄化させ,勤労に重きをおかない若者が輩出し,そうした傾向をよしとする奇妙なるジャーナリズムの主張も加わって,日本人は方向感覚を失っていった.
日本経済が巨大化するにともない,積極的に国際的なフロンティアを開拓しようという攻勢は弱まり,守勢を強めた.何という志操の低さか.隣の韓国をみれば,耐えがたい飢えの時代から豊かな社会への道程をわき目も振らず駆け抜けているではないか.私は当時も今も「勤労」という言葉が好きである.「勤労の韓国」への私の思いはますます強いものとなっていった.
その頃の私は少々野心的に過ぎたのかもしれない.韓国の発展を整合的に説明するグランド・セオリーを探し求めていた.大学院の時代,欧米や日本の経済発展史に関心をもつ同学の士を集め,慶應義塾大学三田キャンパスの図書館の隣に建てられている,古びた「新」研究室の2 階の一室を借り切って,少なくとも週に二度ほどは勉強会を開き,その分野の代表的な英文図書をひたすら読みつづけた.その中で最も強い印象を私に与えたものがアレクサンダー・ガーシェンクロンの「相対的後進性の理論」であった.この議論が韓国経済発展の在り処を説明するのに大いに有用なものだと直感したのであり,その時の「あっ」と感じたあの感覚は今でも忘れることができない.ガーシェンクロンの議論をここで思い切って4 つにまとめてみたい.後発国の工業化がひとたび開始されるや,先発国のそれよりも急速なものとなる,その理由についてである.
⑴ 先発国は,みずからが成長するための技術や資本は,みずからの努力によってこれを開発し蓄積していかなければならない.しかし,後発国は先発国からの技術導入と資本輸入によって,その開発と蓄積に要する歴史的時間を圧縮し,また開発と蓄積のためのコストの相当部分を節約し得るという「後発性利益」を享受できる.
⑵ 後発国に導入される技術は,古い伝統をもつことなく,比較的新しい時代に発展した,しかも固定資本設備費の大きい,例えば鉄鋼業や造船業のような重化学工業部門である.いくつかの重化学工業部門の場合,その生産性は固定資本設備の平均年齢構成(ヴィンテージ)によって左右される度合いが強く,したがって後発国がいったんこの設備を導入することができれば,巨大な固定費用ゆえに設備廃棄を潔しとしない先発国に比較して,大きな優位性を一挙に獲得することができる.
⑶ この事実は,後発国の工業化の初期的時点において要求される企業の最低経営規模が相対的に大きいことを意味し,したがってまた後発国の場合には先発国に比較して独占的企業が早期に形成される傾向が強い.
⑷ 一国が経済的に後進的であるという事実は,急速な工業化の実現に要する資源動員能力ならびに産業組織が自生的には発達していない,という事実を意味する.したがって後発国の場合,工業化を開始するためには資源を動員し,工業部門そのものの形成を誘導し組織化する主体が新たに上から形成されねばならない.明治期日本の重要な工業化の主体は政府であった.
⑸ こうした後発国の工業化は,ある種の宗教的な国民的情熱によって支えられ,この情熱を体化した工業化イデオロギーによって推進されることが多い.
韓国の工業化の態様は,ガーシェンクロンが示唆する後発国の現代世界における一つの典型的事例なのではないか.私がそう考える理由が,以下であった.
⑴ 韓国の工業化は,鉄鋼,石油化学,造船を中心に,先進諸国から資本と技術を大規模に導入しながら進められ,これら産業部門が享受した後発性利益はまことに大きいものであった.
⑵ 韓国における重化学工業化の速度はめざましく,実際,ホフマン比率の変化をみるとその速度は先進諸国の重化学工業化の歴史的経験に比較して3 倍になんなんとするスピードをもった.
⑶ この高度経済成長とりわけ重化学工業部門の成長を担ったのは,新興の財閥を中心とする巨大企業群である.韓国の大企業はしばしば財閥という名で呼ばれるごとく,家族・同族による経営支配の色彩を濃厚にとどめており,所有と経営の分離も先進国の大企業のようには進んでいない.また自己資本比率が低く,導入外資への依存度も高い.
⑷ 財閥に強い保護と支持を与えたのが,経済自立化への激しい意欲をもった政府であった.韓国の経済成長と重化学工業化の過程で,資本ならびに熟練労働はつねに深刻な不足状態にあったが,これらの欠落要因の補填において政府が果たした役割は決定的であった.膨大な貯蓄・投資ギャップを埋めるための外資を含む貯蓄動員において,また戦略的重化学工業部門への財政資金の投下において政府が払った集中的努力にはまことに大きなものがあった.
⑸ 北朝鮮との軍事的対立は,韓国の政府ならびに国民の間に強国への志向性と,したがって重化学工業化への決意を固める求心力として作用した.1970年代に入って加速したアメリカの朝鮮半島における軍事的コミットメントの希薄化,在韓米軍の段階的縮小は,韓国軍民の間に経済,軍事の両面における自立化の緊急性を意識させ,これを支える重化学工業化への強い国民的支持を醸成した.「富国強兵」が明治期日本の工業化イデオロギーであったのと同様,「滅共統一」は現代韓国の工業化の重要な理念として機能したとみられる.
韓国の工業成長は,資本主義世界史上急速な発展を遂げてきた日本のそれを明らかに上回る速度をもった.韓国における工業化の非連続的スパートは,ガーシェンクロン世界のいずれより激しく,先発国の経済発展史がここでは強く「圧縮」して現れており,私はこれに「圧縮された発展」と名づけた.
韓国の経済成長は著しいが,所得分配などの社会的公正を実現することには失敗したかのような議論が,私が韓国研究を志していた頃に日本の韓国研究者や韓国人エコノミストの間で一般的だった.どうしてそんな経済学の理屈に合わない話が出てくるのか,不思議でならなかった.実際,所得分配の平等性を表す代表的な計測値,ジニ係数をはじきだしてみれば,韓国の急成長が分配の平等化をもたらしたことは歴然としていた.ことがそうなった因果的関係についての分析が,私の韓国経済論のもう一つの特色である.この点について次に述べておこう.
韓国の工業部門の雇用吸収力は強力であった.このことは韓国の輸出志向型工業化政策に由来する.1960 年代の中頃に,韓国政府はそれまでの保護主義的工業化を支持してきた諸政策を一挙に覆す,金利政策や為替レート政策の大幅な自由化,すなわち「市場自由化政策」を果敢に採用した.保護政策の自由化は労働過剰・資本不足という韓国における生産要素の賦存状態に適合する生産方法の採用を促し,労働集約財の比較優位を強化した.
韓国の工業化の雇用吸収力は強まり,その結果,農業人口の流出が開始され,1960 年代の後半期以降,農家人口,農家戸数の減少傾向は顕著なものとなった.かくして生まれた農村労働市場の逼迫化に応じて,農民の平均労働時間の延長,不完全就業率の減少,女子労働力率の上昇がみられるとともに,農業労働力の実質賃金は急速な上昇を始めた.
農業部門は,工業部門の労働需要に応じてその余剰労働力を継続的に引き出され,ついにはこれが失われて,その時点以降,農業賃金は上昇を開始した.他方,農業部門は工業部門の拡大によってみずからが利用する肥料,農業機械などの近代的農業投入財を豊富かつ安価に購入できるようになった.賃金は上昇する一方,農業投入財の価格は相対的に低下したのである.
労働力を集約的に用いた低生産性農業から,農業投入財を集約的に利用する高生産性農業へと転換していく条件がここに与えられた.このように工業部門の拡大は,農業部門の余剰労働力の吸収ならびに農業部門への投入財供給を通じて,この部門の生産性上昇をもたらした.農工間,あるいは都市・農村間の所得格差の縮小はその帰結である.韓国の発展は,このメカニズムを短期間に,しかも齟齬(そご)なく展開させてきた開発途上国の典型であった.