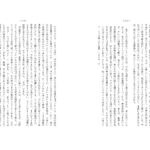あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
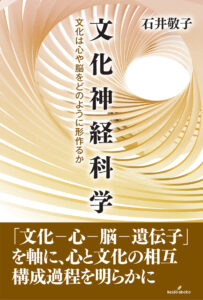 石井敬子 著
石井敬子 著
『文化神経科学 文化は心や脳をどのように形作るか』
→〈「はじめに」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「はじめに」本文はサンプル画像の下に続いています。
はじめに
2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻は、2年以上経ったこの原稿の執筆中にいたってもいまだ解決の見通しは立っていない。識者と呼ばれるさまざまな人たちがこの混沌とした情勢について解説するのを耳にしてきたが、個人的には、米原万里さんが生きていたらこの状況をどう評してくれたかとつい思いを馳せてしまう。ロシア語の通訳者としての活躍に加え、優れたエッセイストであった米原さんは、大の読書家であった。私自身、米原さんの存在を知ったのはその書評を通じてである。しかしその後に読んだ代表作『嘘つきアーニャの真っ赤な真実』(角川文庫)こそ、米原さんの別エッセイのタイトルを拝借するならば、私にとっての「打ちのめされるようなすごい本」である。
その書は、日本共産党の幹部の子女であり、それゆえさまざまな国の共産党幹部の子女が在籍していたプラハのソビエト学校に通っていた米原さんが30年ぶりに音信の途絶えていた3人の旧友に会いに行く3つのエピソードからなる。それぞれのエピソードの根底には、東欧の民主化と社会主義の崩壊の歴史がある。最後に出てくるルーマニア人のアーニャは、万人が平等であるはずの共産主義のもと(家のお手伝いさんを「同志」と呼んでいた滑稽さが何とも言えない)、共産党幹部の子女という特権階級を活かしてルーマニアからは離れ、現在はイギリスで所帯をもち暮らしている。学校で習ったロシア語はおぼつかない。米原さんはアーニャとプラハで再会し、昔話に花を咲かせるが、彼女に対する違和感は、本エピソードを締める以下の文章として表れる。
私たちの会話が成立しているのは、お互い英語とロシア語を程度の差はあれ、身に付けているからよ。あなたがルーマニア語でしゃべり、私が日本語でしゃべったら、意志疎通はできないはず。だいたい抽象的な人類の一員なんて、この世にひとりも存在しないのよ。誰もが、地球上の具体的な場所で、具体的な時間に、何らかの民族に属する親たちから生まれ、具体的な文化や気候条件のもとで、何らかの言語を母語として育つ。どの人にも、まるで大海の一滴の水のように、母なる文化と言語が息づいている。母国の歴史が背後霊のように絡みついている。それから完全に自由になることは不可能よ。そんな人、紙っぺらみたいにペラペラで面白くもない。(「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」188ページ)
「どの人にも、まるで大海の一滴の水のように、母なる文化と言語が息づいている。母国の歴史が背後霊のように絡みついている」ことは、当たり前のことに思えるかもしれない。しかし「井の中の蛙大海を知らず」といったことわざが暗示するように、井という当たり前の世界は、大海という比較対象の存在によって当たり前ではなくなる。そしていかに「井という世界」、つまり周囲の環境に私たちは縛られているのかを痛感する。さらにその反応として、時にはまたは人によっては反抗したり、むしろ縛られているがゆえにその世界に同調したりする。ここでの周囲の環境とは、家族であるかもしれないし、学校であるかもしれないし、友人関係かもしれない。または人々を取りまとめるような社会のルールや制度といったものを指すかもしれない。そうしたルールや制度に言語も含まれるだろう。中でも本書が注目するのは、「文化」である。
背後霊としての文化や言語、歴史といった存在が人に絡みつくのは、当たり前に思えるが、実際のところそれがどう絡みついているのかは自明ではない。日本共産党の幹部の子女として育ち、プラハのソビエト学校に通っていた米原さんには、その絡みつき方の独自のストーリーがあり、その一方でアーニャにも独自のストーリーがある。そして東京・牛込の一商人の子として育てられた私にもその独自のストーリーがある。無論、千差万別であるそれらのストーリーを丹念に追うことで、背後霊がいかに人に影響を与えているかを描き出すことは可能である。実際、民族誌的研究は、聞き取り調査や参与観察を通じ、その背後霊の存在を記述してきた。
一方、心理学は、心の法則を明らかにすることを目的とした学問である。個人の精神疾患や不調といった問題の解決を目指す臨床分野もあるが、その主流は、実証研究を通じて、人に普遍的に備わった知覚や感覚等の性質を明らかにすることにある。心理学研究では長年、文化や言語の影響はノイズを与えるものとして軽視されてきた。しかし民族誌的研究が明らかにしているように、その背後霊としての影響は決して軽視されるものではない。となれば心理学の立場に基づき、ストーリーの個別性を超えて、個々の文化に生きることで実践されるさまざまな文化的慣習がどう心を作り上げているのかを明らかにするのが重要な研究課題となる。過去数十年、この研究課題に取り組んでいるのが文化心理学である。本書は、文化心理学におけるさまざまな知見とともに、その文化による影響が脳や遺伝子にまで至る可能性を探る文化神経科学のアプローチを紹介する。