あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
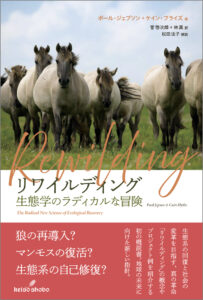 ポール・ジェプソン、ケイン・ブライズ 著
ポール・ジェプソン、ケイン・ブライズ 著
管 啓次郎・林 真 訳/松田法子 解説
『リワイルディング 生態学のラディカルな冒険』
→〈「訳者あとがき」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「訳者あとがき」本文はサンプル画像の下に続いています。
訳者あとがき
管 啓次郎
ある単語が人々の考え方を変えることは、たしかにある。変えるというか、それまではっきりとは意識されていなかった何かが、その単語を核として結晶し、だれの目にも明らかになる。理解のための触媒になり、さらには、将来の行動目標になる。本書がタイトルとして採用した〈リワイルディング〉という単語には、たしかにそんな力が秘められているのではないだろうか。
再野生化。「ワイルド」という英語の形容詞を「人の手が加わっていない」という意味だととらえるなら、ワイルドの状態を回復すること。生態系という枠組で考えるなら、人工・人為の部分をできるかぎり小さくし、人間が介入しない「野」のあり方を真剣に想像し、それに近づける方向で人間がその土地から「手を引く」こと。人間が文明civilization と呼んできたものの核にあるのは都市civitasだが、人間と人間が利用する物資の集積場である都市、あるいは人間のための生産の場である農地や山林のむこうにある「野」と今後いかにつきあっていくか、それを考えようではないか、という呼びかけの気持ちも、そこには含まれているだろう。
背後には、人間の活動が地球各地の環境を大きく破壊し、植物にせよ動物にせよ、他の生物種の生息域や生活環のあり方、現実の個体数に、大きな影響をあたえてきたことに対する反省がある。現代は多くの生物種の大絶滅時代だ。人間という単一の種が、定住革命・農業革命・産業革命・流通革命・情報革命といった激変を経験するごとに、ヒトの周囲の環境も大きな打撃をこうむってきた。他の種は、その影響を直接に、激しくうける。そして現在の単一のグローバル市場の時代にあって、ヒトの倒錯的な消費のパターンは、手がつけられないところまで反゠自然なものとなっている。
世界の行きすぎた都市化゠人間化。この反゠自然的世界に対する見直しをうながすのがリワイルディングという概念だ。ぼくが最初にこの単語をはっきりと意識したのは二〇一四年の夏、アラスカでのことだった。故・星野道夫の親友だった、写真家・作家・熊ガイドのリン・スクーラー Lynn Schooler の家で、数分の映像作品を見せてもらった。鮭の一生をみごとに描いたもので、水中撮影を含め、撮影者の技量には息を吞むものがあった。主題は明確だ。川で生まれ、海で育ち、ふたたび川を遡上して、そこで産卵・授精すれば一生を終える鮭という魚が、生態系において果たしている仕事。それはひとことでいえば海で育った自分が故郷の川に戻り、そこに住む熊やきつね、鳥たちや昆虫などの小動物に食われることで、海の養分を森に循環させていくということだ。
日本でも、たとえば三陸の牡蠣漁師である畠山重篤が、牡蠣の生育のために決定的に重要なのは彼が暮らす湾に川や湧水をつうじてもたらされる森の植物性プランクトンだということに気づき、川の上流での植林運動(「森は海の恋人」という取り組み)を成功させるといった例があった。人間による開発は、しばしばこうした自然の連関を無視して生態系を分断していくが、それをふたたび元来の姿に戻そうとする試みは、着実に行なわれるようになっている。たとえばそのような努力のことも、リワイルディングのひとつの姿と考えていいわけだ。
アラスカで見た短編はパウル・クラヴァーPaul Klaver という映像作家のものだったが、その彼が撮影チームに参加している長編映画のこともそのときに知った。オランダはアムステルダム近郊にある干拓地オーストファールテルスプラッセンを舞台に、人間が手をひいた土地がどのように自然の生態系を回復していくかを、驚異的な映像によって見せてくれる、すばらしいドキュメンタリー作品だ。動物撮影にかけては世界的に最高の技術をもった人々のチームが、途方もない撮影時間をかけて、この土地の姿を丁寧に描写していく。この映画『新しい野生』(De nieuwe wildernis. 二〇一三年)は本国オランダで大ヒットした。ぼくをアラスカに案内してくれた写真家の赤阪友昭とともに、二〇一五年にオランダの現地を訪ね、同時に映画の輸入準備にとりかかった。この映画はぼくの日本語字幕をつけて、二〇一六年秋には日本公開することができた。日本公開にあたってわれわれが選んだタイトルは『あたらしい野生の地 リワイルディング』。オーストファールテルスプラッセンにおける生物学者たちの試みに敬意を表するとともに、この映画が、人間が手放した、あるいは手放さざるをえなかった、土地の運命を考えるための指針になることを願ってのことだった。
リワイルディングには積極的なものも消極的なものもある。賛嘆すべき例も、手放しでは歓迎できない例もあるかもしれない。しかし最低限の了解として、地球は、その土地は、海は、人間だけのものではないという自覚があるはずだ。人間が独占していいものではないし、人間の都合で好きなように改造していいものでもない。人間の活動、なかでも利益を求めて歯止めのきかない増殖につながりがちな経済活動を、人間はみずから制御することを学ばなくてはならない。
少しだけ、立ち止まって考えてみよう。日本列島はまちがいなく、明治以後の百五十年で自然の多くの富を失ってきた。その速度が恐ろしいほどに加速したのは、いわゆる高度経済成長期以後の、この六十年ほどのことだ。その見えやすい指標として、海岸と河川の人工化があることも、疑えない。子供のころ楽しく遊んだ海岸が、四十年後、すべて消滅しているのを見て、愕然としたことがある。自然海岸は、護岸工事の名のもとにコンクリートで固められてきた。あるいは洪水管理の名のもとに、河川にはおなじくコンクリートでダムがつくられ、流れは単なる水路へと貶められた。そのような工事の何が問題かというと、もともとあった水と陸の「あいだ」を、すっかり破壊してしまうことだ。海でも川でも、水と土の中間地帯である岸辺は、つねに生命の鍵をにぎる場だった。多くの生物がそこで暮らすことができた。その場がつぶされる。近代がつくった余分なものは、これからたとえ百五十年かけることになっても除去しなくてはならないとぼくは考えている。いつのまにか全国の海岸に途方もない量が投げ込まれている消波ブロックは、生態系にとってどれだけの悪影響をあたえていることか。砂浜を失って、海亀にどこで卵を生めというのか。
しかし絶望するにはまだ早い。北アメリカの例になるが、たとえば二〇一二年のワシントン州エルワ川にはじまる、ダム除去による川の生態系の回復は、まだ端緒についたばかりだ。あるいはイエローストーン国立公園での例のように、オオカミの再導入による生態系の多様性回復という例もある。一方で、人間が居住をやめることで野生生物(植物であれ動物であれ)が旺盛に数を回復し、ヒトの歴史の痕跡すら消えてしまう土地も、現実にあちこちで生じている。確実にいえるのは、われわれは〈人為〉と〈自然〉のバランスの全面的見直しの時期に入っており、しかもその最後のチャンスに直面しているのではないか、ということだ。なすべきことは人間の自己収縮であり、それにより他の生物種のための空間をひらくことだと思う。「リワイルディング」という単語は、確実にこれからの百年の人間社会の課題となるだろう。そして本書はこの考え方の射程を知るための、最初の手がかりとして役に立つはずだ。ここから、議論をはじめよう。





