あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
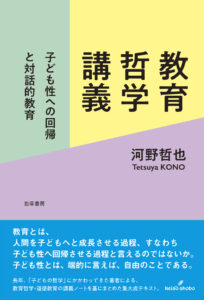 河野哲也 著
河野哲也 著
『教育哲学講義 子ども性への回帰と対話的教育』
→〈「序論 児童期への回帰としての教育」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「序論」本文はサンプル画像の下に続いています。
序論 児童期への回帰としての教育
本書はなぜ書かれるのか
本書は、教育についての新しい考え方を提示するために書かれた哲学の書である。筆者は、長年、「子どもの哲学」と呼ばれる活動を行い、その内容を大学の「教育哲学」という講義で論じてきた。その中で徐々に生まれてきた考えを、本書にまとめてみた。子どもの哲学とは、国際的には、「子どものための、子どもとともにする哲学(Philosophy for/with Children)」とか、「子どもとともに行う哲学探究(Philosophical Inquiry with Children)」と呼ばれ、子どもと大人が一緒に、あるいは、子ども同士で、哲学的なテーマについて議論する活動である。
この活動をさまざま地域、さまざまな年齢を対象にして重ねていくうちに、筆者は、従来から私たち大人が暗黙に想定している子ども観とその発達観を大幅に変える必要がある、こう感じざるをえなくなってきた。そして、教育がどうあるべきかについても、それに応じて、百八十度変えるべきではないかという確信に近い思いを抱くようになってきた。
本書が主張する内容は、かなり抽象的であるし、従来の常識を大きく変えるように迫っているものなので、すぐに教育政策や教育の方法に反映できるとは思われない。筆者の主張に仮に賛成できたとしても、それをどう実現していったらよいか、多くの人たちは戸惑うに違いない。
だが、まさに筆者は、大人たちに対して、その戸惑いから、子どもとその教育に関する考えを改め、むしろ、子どもたちからこそ学ぶべきことを本書で薦めようとしているのである。本書は、大人が子どもに教えるという意味での教育という営みを解体しようとして書かれている。本書の主張は、突き詰めれば、大人は、子どもと共に、子どもから学ぶべきだ、あるいは、大人は子どもに戻るべきだ、というものに尽きるものである。
この主張は、あまり斬新な響きをもっていないかもしれない。同じような響きの言葉を、読者の皆さんは、どこかで聞いたことがあるかもしれない。しかしその考えを本気で思っている人がどれだけいるだろうか。それを実現することがいかに困難であるか。いかにそれを実行できる大人が少ないか。いかにその貢献が理解されないでいるか。本書は、子どもであること(子ども性)の重大な意義を、真剣に教育の中に取り込もうとするものである。
筆者が、子ども性への回帰というアイデアの重要性に気づいていったのは、いま述べたように、子どもの哲学と呼ばれる活動に取り組んできたことに由来する。子どもと大人が一緒に哲学的なテーマについて議論したときに、いつも痛感させられるのは、子どもの柔軟な問いや独創的な発想に比較して、大人たちの発する問いがしばしば一定の型にはめられ、その発言が自分の社会的役割から逃れられていないことである。対話がクリエイティブになるには、参加者がそれまでの知識や経験を一旦放棄して、自分の現在の社会的立場を離れ、他者の考えに照らして己の考えを検討しなければならない。しかし、社会の中での自分の地位や位置から離れることを促し、「一人の人間としてどう思いますか」などと問いかけると、ただ首を傾げて沈黙する大人がいかに多いことか。
自分が社会の中で生きていくには、特定の地位が必要とされる。何かを語るのに、ポジションが必要とされるのだ。大人はこうした傾向にしばしばとらわれているが、そのことが、いかなることを招いているのかを、よく理解しなければならない。ただ発想に柔軟さが欠けていくというだけのことではない。
筆者は、子どもの哲学に関わるずいぶん前から、障害のあるお子さんたちの教育に携わってきた。いまだに、日本では、障害のある子どもは、その特性に応じて「通常の」子どもたちから分離して教育する方がよいと思われていることがある。障害のある子どもは、別の場所で教育を施して、一般の社会に参加できる素養と能力を育てるべきだと考える人が少なくない。分離教育を効率よく施した上で、障害のある人々を一般社会に迎え入れるべきだ。こうした考え方を持っている大人や教育者が、相当数いるのである。
しかし、これは、社会に参加するには資格が必要とされるという考えに基づいている。社会の中で優位な立場に立つ人たちの中には、受験という選別制度の中で勝者の側に立ってきたために、選別という仕組みが自分の体の中に染み付いてしまっている。そしてその恐ろしさに気づいてもいない。「一定の能力に達していない者は、社会に参加することはできない。そうした者は、社会からこぼれ落ちた者であり、生きているというよりも生かされているのだ」。このような考え方が暗黙のうちに多くの人に共有されている社会では、障害があるとレッテルを貼られれば、いつ社会から排除されてもおかしくない。「有能」ではなく、ただの人間でいるだけでは、「無用」のものとして社会から疎外される。最悪の場合、日本で起きた精神障害者施設での障害者の大量殺傷事件のように、生の領域から追い出されてしまいかねない。
もし社会がそうした傾向を持っているとすれば、誰も社会的な有用性や一定の役割を示すアイデンティティを自分から取り外そうという気持ちは起きないだろう。ただのひとりの人間であることは、社会のなかであってはならない状態だからである。こうして大人たちは、何者かであろうとして、その役割を身に染み込ませ、その制服をもはや脱げなくなっていく。それが、子どもの哲学で、大人が一人の人間として語ることができなくなっている原因である。そうした人のなかには、しばしば対話そのものを無用のものと考える人たちすらいる。そうしてますます自らの存在を社会での役割や立場へと還元していく。発想の硬い大人の多い社会は、かくも危険なのである。
これまで教育は、子どもを大人へと成長させる過程として理解されてきた。しかし、その大人になることが、自分を何よりもひとりの裸の人間として捉えることから離れてしまうことであるなら、それはどれほど危ういことであろうか。
本書では、それとは全く異なる考え、すなわち、教育を、人間を子どもへと成長させる過程、子ども性へ回帰させる過程として理解する新しい教育観を提示する。それは、人間が人間のままでいることができるような教育と言い換えることができる。実際に、子どもの哲学の分野では、児童期へ回帰という概念が注目され始めているのである。
(以下、本文つづく)




