あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
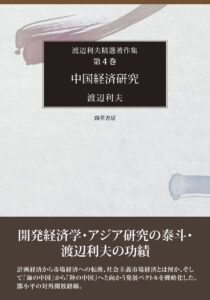 渡辺利夫 著
渡辺利夫 著
『中国経済研究 渡辺利夫精選著作集第4巻』
→〈「まえがき」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「まえがき」本文はサンプル画像の下に続いています。
まえがき
私は長い間、韓国をはじめ多くのアジア諸国を足繁く巡り、各国の経済発展の態様を観察・分析し、さらにはこれら諸国の経済発展の過程で生まれた東アジア全域に渦巻くダイナミズムについての考察を重ねてきた(このテーマは本著作集第5巻『アジアのダイナミズム』で扱う)。
中国という巨大な大陸国家の発展については、これを分析対象の中に組み入れなければ私のアジア研究が完成しないことはわかってはいたが、しかし、それにしても巨大で複雑なこの国の研究に入っていけば、そこから抜けでることは難しいのではないかという思いが強く、なかなか本気でここに関心を向けることはできないでいた。
しかし、1980年代の初め、中国の改革・開放が開始されて間もない頃、当時の経済企画庁の研究会の専門委員の一員として初めて中国を訪れる機会を得て、まだ残る人民公社、廃墟のような東北地域の国営重工業群をみて回り、さらに往時の中国第一級のエコノミストと数日にわたり議論する貴重な経験を得て、私の中国への関心はにわかに高まった。
私の研究のポイントは一つ、当時(今でもなおそうだが)最も重要なテーマであった、計画経済から市場経済への転換とはどういうことか、にあった。市場経済から計画経済への転換であれば、旧ソ連圏においてあまたの経験があるものの、その逆の、つまり計画経済から市場経済へ転換というのはどういうことか、トライアルの真意は何か。どんなメカニズムで中国はそれを行おうとしているのか、この一点を抑えることに努力の大半が割かれた。1990年代初期の3、4年の追究の結果、次のようなロジックが次第に明らかになってきた。研究成果は、一般書として一つには『中国経済は成功するか』(ちくま新書、1998年)、二つには『アジア新潮流─西太平洋のダイナミズムと社会主義』(中公新書、1990年〔『本著作集』第5巻所収〕)としてまとめた。本巻にはこの2つのうち前者を再録した。
中国は建国以来、長きにわたって国営重工業と人民公社を根幹とする集権的社会主義経済を営んできた。国営重工業と人民公社は、2つの独立した存在ではない。後者は前者の拡大のための蓄積源として位置づけられた。人民公社とは、工業化のための資源を確保すべく農業余剰を国家に吸引するための制度的機構に他ならなかった。農業余剰の吸引は国家が農民から購入する農産物の価格を定位におく一方、国家が農民に販売する工業品価格を高位に据えおくという、「鋏状価格差」(シェーレ)を固定化することによって実現された。
国家が低価格で買い上げた農産物は、やはり低価格で国営軽工業部門に原材料として販売され、ここで製品化された消費財、肥料、農業機械などの農業投入財が国営商業を経て今度は高価格で農民と都市労働者に販売された。それゆえ国営商業部門の利潤率は大きく、この利潤は工商税とともに国庫に上納され、これが国家財政収入の中核を形成した。国営工商業の高利潤に寄与したもう一つの要因は、都市労働者の低賃金であった。この低賃金を可能にしたものが、再び低価格で農民から買い上げられた食糧であった。蓄積された豊富な財政収入の多くは国営重工業に投入された。中国が低所得水準にありながらも、他の開発途上国に比較して一段と高い重工業化率を達成せし得たのも、こうした蓄積機構があってのことである。中国の「強蓄積メカニズム」と呼ばれてきたものの内実がこれである。
強蓄積メカニズムの欠陥はほとんど自明であった。国営重工業は蓄積源泉を自部門にではなく他部門の農業に求め、しかも統制経済下にあって競争的市場圧力を回避しながら拡大をつづけることができた。国営重工業が効率性向上への誘引を欠いた安易な拡大過程に堕していったのにも無理からぬものがあった。
強蓄積メカニズムは、農業においてより深刻な問題をつくり出した。中国農民はシェーレのもと、国家による収奪を余儀なくされた。価格体系がいかにみずからに不利なものであれ、人民公社から下達された生産目標は至上命令であり、農民はその達成に向けて無理やり増産に駆り立てられた。1970年代、農業生産は拡大しながらコスト割れによる欠損農家が全国に広範に観察されるようになり、この事態の深刻さは「増産不増収」という表現に象徴された。
強蓄積は、こうして一方に、拡大再生産への自律的メカニズムをもたない国営重工業と、他方には、人民公社制度により余剰を収奪され増産不増収に呻吟する低生産性農業という2つの部門が並立する「偏奇的」な二重構造を築いてしまった。
1978年の体制改革が画期的であるのは、実はこの改革が中国の農工両部門の間に初めて有機的な関連を創成し、旧来の二重構造にかわる新しい蓄積と循環のメカニズムを創成したからに他ならない。そのメカニズムの要に位置するのが「郷鎮企業」であり、私はこの企業を中国の体制改革が生んだ最も重要な経済主体だとみなした。
新農業政策により国家農産物買い上げ価格が引き上げられ、人民公社が解体されて農業生産の主役は個人農にかわった。これにともない農民の増産意欲は一挙に高まり、農業生産性と農民所得は急角度の上昇をみせた。意欲ある農民には非農業部門に投下可能な貨幣余剰が建国以来初めて生まれたのである。
また農業生産性の上昇は、余剰労働力をはっきりと顕在化させた。個人農システムの採用によって農村労働力の30%以上が余剰化したといわれる。加えて、都市・農村間の人口移動を制限していたかつての厳しい戸籍管理が次第に緩められ、1984年には「農民が集鎮(農村内都市)に入り、戸籍を移す問題に関する国務院の通知」が出された。配給食糧に依存しないという条件つきながらも、農民およびその家族の集鎮への移住が許可された。
新農業政策の採用によって農村に発生した貨幣余剰と労働力余剰がその吐け口を郷鎮企業に求めた。郷鎮企業とは、農村における郷(村)鎮(町)政府が経営する事業体であり、さらには農民が連合してその経営にあたる、企業や個人企業も含まれる。中核は工業企業である。経営形態は多様であり、農民が資金、労働力、技術をもち寄って経営にあたり、その収益を「股分」と呼ばれる一種の持ち株に応じて配分する企業形態さえ少なくない。郷鎮企業が体制改革下の中国に生まれた初めての本格的な「第三セクター」であるといわれる所以である。
郷鎮企業は食糧生産第一主義のもとで工業品の恒常的な不足に悩まされていた農村に、人民公社の制度的拘束を離れて自由にものを生産し販売する主体として生成した新事業単位である。郷鎮企業の生産性と収益率は農業より格段に高い。それがゆえに郷鎮企業は農業部門の貨幣余剰と労働力余剰を吸引して爆発的な拡大をみせた。対照的に、農業(播種農業)の生産拡大の速度は緩慢であった。農村における発展の主勢力はもはや農業部門ではなくなっている。中国農村で発生した郷鎮企業の強い労働力吸収は、土地に対する人口圧力を緩和し、農業生産性を上昇させ、農業部門の貨幣余剰と労働力余剰を郷鎮企業に向けて吐き出すという累積的経緯を創出している。
もちろん郷鎮企業の生産物は、農村の最終需要と直接的な結びつきをもつ。こうして郷鎮企業は自由な要素市場(資本・労働市場)と商品市場(財市場)を介在して、農業部門と工業部門との間に有機的なリンケージを作り出す新単位として生成したということができる。人民公社制度のもとで農業余剰を権力的に絞り取り、これを重工業投資に振り向けることによって形成されてきた旧来の歪んだ二重構造を是正する契機が、ここに生まれた。こうして農業部門は、かつてのような重工業部門拡充のための蓄積源としての役割を大きく減殺されざるを得ない。
もう一つ、改革・開放政策の開始以来の中国経済の活性化は素材産業、エネルギー運輸等のインフラ部門のボトルネックを深刻なものとした。このボトルネックが中国経済の成長を阻む由々しい問題要因となっていくのは間違いない。郷鎮企業の拡大とインフラ部門のボトルネック解消という、いずれも大きな蓄積基金を要する2つの課題を、しかも旧来の強蓄積メカニズムが崩壊したという現状の中で、同時に解決しなければならないという重大な局面にいたった。
新たな活路を求めて登場したのが王建氏の論文「正しい長期発展戦略を選択せよ─国際大循環経済発展戦略構想について」(『経済日報』1988年1月5日付)である。中国経済が直面する最大の課題に立ち向かう新しい方向性を示唆した、中国における初の本格的な開発戦略として、私はこれに高い評価を今でも惜しまない。改革・開放の必要性を論じた諸論文の中で異彩の論文である。
王建論文は、一つには農村人口の工業部門への移動、二つにはインフラの拡充という2つの要請の間で国内資源の「争奪」が深刻化している。このことを中国の当面の経済発展過程における主要矛盾として認識している。この認識は、すでに私が述べてきた論理からすれば、疑いもなく正しい。主要矛盾の解決を図るべく氏が導いたのは「農村労働力の移動を国際大循環の中に組み入れる」という構想である。労働集約的製品の輸出志向工業化を展開し、それがもたらす強い雇用吸収力を通じて農村の労働力余剰を解消し、次の段階として輸出により入手した外貨資源を素材産業・インフラ部門に振り向けて、その成長を促すという解決法である。
この論文をベースにして、趙紫陽氏は「沿海地域経済発展戦略」を表明し、王建氏の戦略の起点に位置する労働集約的製品輸出の担い手として沿海部の郷鎮企業に照準を合わせた(『人民日報』1988年1月23日付)。ここで趙氏は、郷鎮企業を中核とする沿海地域の労働集約的加工業は内陸経済との開発資源の「争奪」を回避するために、国際市場から原材料を輸入し、付加価値を高めた後に再びこれを国際市場に輸出するという「進料加工」(輸入原材料加工)を大々的に展開すべきだと主張した。すなわち沿海部加工工業は原材料入手と製品輸出の両端を「外」におく「両頭在外」を基本とし、「大いに入れて大いに出すべきだ」というのである。
同時に沿海地域郷鎮企業の競争力強化のために外国資本の積極的導入を図るべきであり、全額外資企業、合弁企業、合作企業の「三資企業」をその品質向上、技術の更新、企業管理技術の改善、製品販路の開拓に寄与させようとも唱えた。
王建・趙紫陽両氏の提唱する新戦略は、開発資源の制約状況を前提としたうえで膨大な農業人口の工業部門への移動を図るという、中国の経済発展において決定的な重要性をもつ傾向を持続させ、なおかつもう一つの基礎的な条件である基礎素材、インフラ部門投資の拡充という課題を同時に解決するためのほとんど唯一の可能性あるシナリオを示したのである。
そして実はこの新戦略は、中国を取り巻く東アジア地域に今日激しくも生起している構造調整と貿易・投資の新動向によく見合ったものである。再びいえば東アジア地域の構造調整と貿易投資の新しい動向についての記述が、本著作集第5巻の『アジアのダイナミズム』の課題となる。
毛沢東が死去し狂気と凄絶のプロレタリア文化大革命が収束して政治的安定性をようやくにして回復した1970年代の末年、気がつけば人民の胃の腑はなお満たされていなかった。建国以来、国の総力を上げて取り組んできた社会主義経済建設とはいったい何であったのか。社会主義建設はそれに投じられた努力に報いる成果をまるで残していないではないか。中国は周辺の資本主義国、日本は無論のこと、韓国、台湾、香港にはるかなる遅れを取ってしまった。東南アジアの国々に比較しても貧困は一段と厳しい。
社会主義経済建設のあまりのみすぼらしい成果への痛恨の思い、激しい危機意識が改革・開放への原動力となった。改革・開放を代表する指導者が鄧小平であり、彼の徹底した「生産力主義」であった。この生産力主義は、天安門事件という劇的状況に遭いながらも揺らぐことはなかった。むしろ天安門事件後の政治的危機を克服するには、思想上の工作だけでは不十分であり、実は成長加速によって生産力の発展、国力の増強、人民生活の向上を図ることが第一義であることを見抜いていたのが鄧小平であった。鄧小平は政治路線闘争に身を削ってきた毛沢東とはこの点において決定的に異なる。二人の政治思想、人間観を明らかにすることが本巻Ⅱのもう一つの目的であるが、これは渡辺利夫・小島朋之・杜進・高原明生著『毛沢東、鄧小平そして江沢民』(東洋経済新報社、1999年)のうちの私の執筆分である。
ところで、大陸中国を「海の中国」と呼ぶならば、台湾、香港、東南アジアの華人社会は「海の中国」である。中国が改革・開放の時代に入ってすでに相当の時間が経過した。この間、「海の中国」は「陸の中国」を塗り変えるほどの力量を発揮してきた。
中国が改革・開放政策を開始したのはプロレタリア文化大革命が収束して間もない1979年のことであった。この時期、中国の統治機構は機能不全に陥り、農業は疲弊し、国営企業はとてつもない非効率に呻吟していた。門戸を開いて海外の進んだ技術、経営ノウハウを導入しなければとは考えるものの、門戸を開けば入ってくる西側からの新しい「風」に脆弱な中国は耐えることはできない。さりとて、対外開放の挙に出なければ発展への端緒をつかむことができない。この身を切るような苦悩の中で、鄧小平のなした選択が特定地域の部分的開放であった。在外華人の出身地域である華南、広東省、福建省の窓を開き、ここに「海の中国」で鍛えられ蓄えられてきた中国資本主義のエッセンスの導入を図ろうとしたのである。華南に適用される政策措置は社会主義原則から離れた実に柔軟で大胆なものであった。「香港効果」を懐に招き入れて発展したのは華南であり、華南は中国の成長を牽引する最も重要な地域となった。
中華経済世界の図柄がこのようなものであるのは、その形成史を顧みて当然のことであった。国共内戦に勝利した共産党軍は往時の中国資本主義の精髄・上海企業─浙江財閥ならびにそれに淵源をもつ官僚資本系列企業の資産を没収し、身の危険を察知した企業家、管理者、技術者は大挙して香港に逃避した。無数の私営工商業者も「三反」「五反」運動などの残忍で暴力的な「社会主義的改造」によってその息の根を止められた。要するに共産党一党支配体制下の中国において、資本主義発展を担う主体は全土から姿を消したのである。中国資本主義の精髄がまず蝟集したのは香港であった。
香港ばかりではない。共産革命に先立つ50年ほど前、清国期の華南から植民地支配下の東南アジアに移り住んだ南洋華僑がいる。彼らは列強が経営するプランテーションや鉱山の労働者として雇用され、植民地経営が発生させた仲介商人(買弁)的機能を担う「東洋外国人」として刻苦精励した。南洋華僑はその過程で華南の商業主義の伝統を練磨し、これを東南アジアの地に蓄積していった。
南洋華僑社会の成立に、さらに200年先立つ17世紀後半期から18世紀にかけて台湾に移住し、この島の開発に挑んだのがやはり華南の貧農であった。台湾に流入した華南住民を待っていたのは、統治システムのまったく及ばない「化外の地」(中華の皇帝による教化の及ばない未開の地)であった。移住者は国家に頼ることのないベンチャーにより、台湾を東アジア有数の水稲耕作と砂糖黍栽培の地に変えていった。豊かさを求める激しくも厳しい労働が華南住民の起業家的才覚をこの島で練りあげた。
市場経済を担う主体が大陸中国には薄くしか存在しない一方、大陸の外縁に広がる東アジア海域世界にこれが厚く蓄積されていたというのが改革・開放政策が開始された時点における中華経済世界の構図であった。そうして「海の中国」から「陸の中国」へと向かうベクトルを戦略化したものが鄧小平の対外開放路線に他ならない。
この歴史的な図柄を記したのが、本巻に収録された、渡辺利夫・岩崎育夫『海の中国』(弘文堂、2001年)の私の執筆分である。






