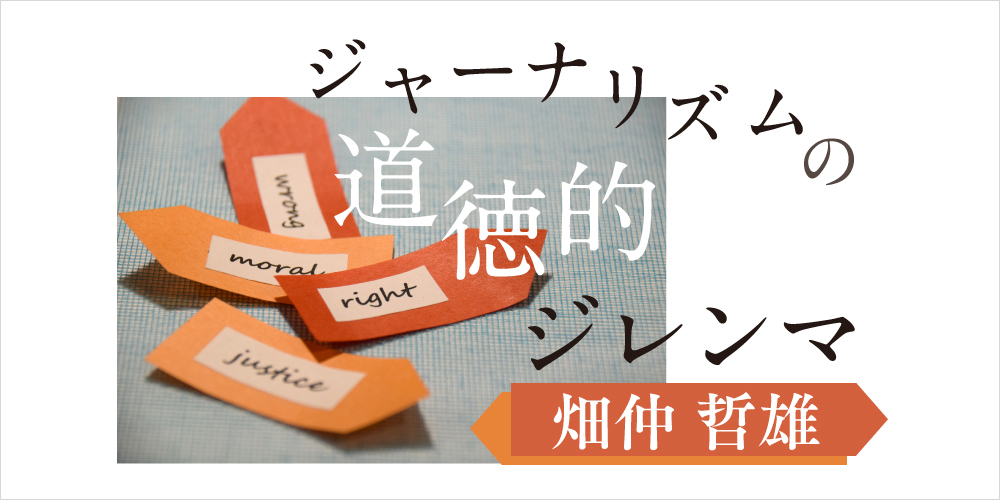※本書の「たちよみ」公開が書誌情報ページにあります。ぜひご覧ください。⇒<https://www.keisoshobo.co.jp/book/b10154377.html>
報道するために必要な取材。その取材方法として許される限界はどこにあるのでしょうか。[編集部]
記者ゆえのジレンマに直面したとき、なにを考え、なにを優先するのか? あなたならどうするだろう。
1:: 思考実験
法務室長は大きな溜息を漏らすと、机を叩いて声を荒げた。
「よそのコンピュータに侵入しただけで不正アクセス禁止法違反になるんだ。サイバー犯罪をしておいて『取材です』なんて屁理屈が通ると、本気で思っているのか!」。
「いや、権力を監視するには」と食い下がってみた。だが、外部から侵入された記録が当局に残っていないはずはない。早ければ、週末を待たずにわが社が家宅捜索され、パソコンや情報端末のほか、取材関係データを軒並み押収されるかもしれない。だから、今夜にも緊急役員会を開き、うちの社員が国のデータを不正取得したので社内処分した、という社告を公表して無難に事を進めるべきだと言う。
発端は、編集部にサイバーセキュリティの技術者を迎え入れたことだった。
オールドメディアも「編集部門の多様化」を喧伝するようになったが、わがネットメディアは設立段階から、さまざまな知識や属性をもつ人材を即戦力として仲間に引き入れてきた。彼女もそんな人材の一人で、わが社に転職してくるまではとある研究機関に在籍していた。彼女は日がな一日、コンピュータと向き合うだけで、記事は書かない。というか、書くのは得意ではない。だが、取材者としてのセンスは優れていて、彼女がネット空間で探索してきた断片的な情報を基に、編集部の記者たちが裏付け取材をしてニュースとして発信している。
当初は「なんかヤバそうなヤツだな」といぶかる声もあった。それでも、著名な学者が論文のデータを捏造しているという疑惑や、某国の軍隊が民間人を機銃掃射して殺害している映像など、彼女が入手した情報のいくつかは、大きな注目を集めるスクープになった。どんなふうに情報収集をしているのかは判らないが、いまでは編集部の記者たちからも一目置かれている。
そんな彼女が、けさの編集会議で示したのは、政府機関のデータが漏出しているという情報だった。
「理屈を詳しく説明するのは難しいのですが、あるソフトウェアを使うと、ダークウェブを経由して、ファイルが閲覧できたのです。これがその一部です」。彼女はそう言い、データらしきものをディスプレイに次々と映し出した。一目見ただけではよくわからないが、「政府が収集した国民の個人情報です。わたし自身のデータも含まれていましたから、間違いありません」と彼女は断言した。
目を疑った。「政府保有の個人情報流出」「セキュリティに重大な欠陥」「犯罪悪用への不安広がる」……そんな見出しになりそうな言葉たちが脳内を流れていく。だが、気にかかることがあった。はたして取材は合法的だったのか。それを尋ねると、彼女は首を傾げた。
「政府の情報流出という噂を知って以来、探索し続けていて、ある人物の協力を得て、ようやく核心のデータにたどり着きました。協力者というか情報源というか、その人物が何者かは判りません。最初は信用していませんでしたが、その人の助言に従うと、バックドアが開いちゃった……つまり、はからずも内部に侵入してしまったというわけです」
「つまり、きみは政府のファイヤーウォールを突破したということか?」
「はい、結果的に。でも、犯罪目的ではなく報道目的です。もし侵入できれば、大ニュースですし、お行儀良くしていたら権力監視なんてできませんから」。そう言うと彼女は誇らしそうな笑みを浮かべた。
会議室はざわめいた。「情報源の思惑が判らないと気味悪い」「よからぬ連中に利用されたのではないか」「わが社が摘発される危険性はないのか」……。そんな声もあったが、記者たちは、みな興味津々のようすだ。
つづきは、単行本『増補改訂版 ジャーナリズムの道徳的ジレンマ』でごらんください。
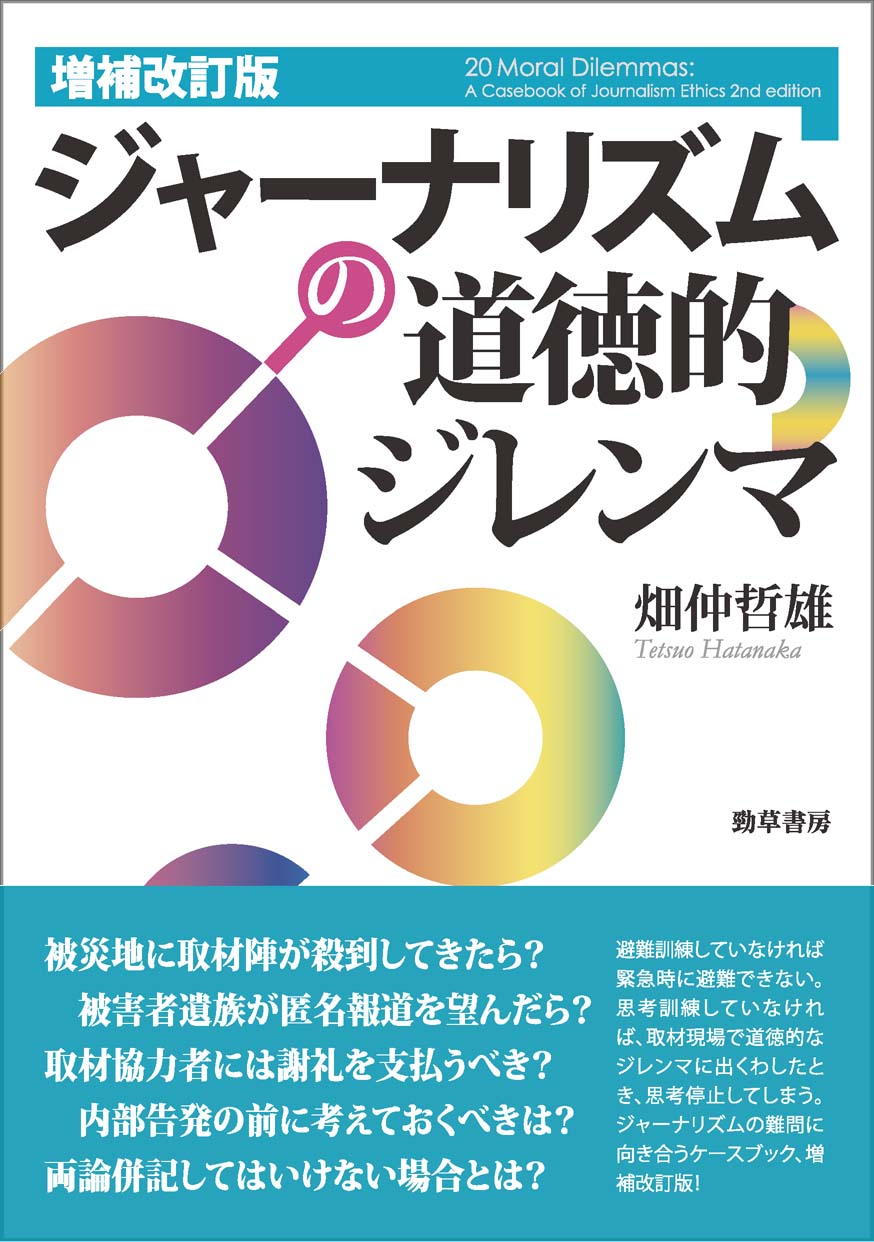 報道倫理のグレーゾーンへようこそ。ジャーナリズム現場で直面する20の難問を巡る思考実験に、さらなる理論的考察を加え増補改訂!
報道倫理のグレーゾーンへようこそ。ジャーナリズム現場で直面する20の難問を巡る思考実験に、さらなる理論的考察を加え増補改訂!
2026年1月17日発売
畑仲哲雄 著『増補改訂版 ジャーナリズムの道徳的ジレンマ』
A5判並製・256頁 本体価格2500円(税込2750円)
ISBN:978-4-326-60387-9 →[書誌情報]
【内容紹介】 フェイクやヘイトが跋扈する今、メディア不信を放置していいのか? 緊急時に避難するには訓練が必要なように、思考も訓練しなければならない。これまでにジャーナリストが直面したジレンマを徹底考察。旧版の事例を一部差し替え、理論解説を追加し、実名報道、取材謝礼、内部告発、オフレコ取材、性暴力報道などを倫理的に問い直す。
【目次】
はじめに――報道現場のグレーゾーンへようこそ
第1 章 人命と報道
CASE:01 最高の写真か、最低の撮影者か
CASE:02 人質解放のために報道腕章を警察に貸すべきか
CASE:03 原発事故が起きたら記者たちを退避させるべきか
CASE:04 家族が戦場ジャーナリストになると言い出したら
〈その先へ〉 物語の第二幕
第2 章 被害と危害
CASE:05 被災地に殺到する取材陣を追い返すか
CASE:06 遺族から実名を出さないでと懇願されたら
CASE:07 加害者家族を世間からどう守るか
CASE:08 企業倒産をどのタイミングで書くか
〈その先へ〉 不幸を減らす第三の選択肢はあるか
第3 章 約束と義務
CASE:09 オフレコ取材で重大な事実が発覚したら
CASE:10 記事の事前チェックを求められたら
CASE:11 取材謝礼を要求されたら
CASE:12 ジャーナリストに社会運動ができるか
〈その先へ〉 義務をはたす第三の選択肢はあるか
第4 章 原則と例外
CASE:13 「選挙ヘイト」とどう向き合うか
CASE:14 組織ジャーナリストに「自由」はあるか
CASE:15 事実の検証か、違法な取材か
CASE:16 その両論併記は大丈夫か
〈その先へ〉 専門職への長い道のり
第5 章 立場と属性
CASE:17 その性犯罪は、いつ暴くべきか
CASE:18 内部告発者の悲劇とジャーナリストの称賛
CASE:19 宗主国の記者は植民地で取材できるか
CASE:20 犯人が正当な主張を繰り広げたら
〈その先へ〉 善いジャーナリズムへの理論と思想
あとがき――ジャーナリズムはだれのものか
索引
■思考の道具箱■
傍観報道・特ダネ /メディアスクラム・合理的な愚か者 /犯罪被害者支援・サツ回り・発生もの /黄金律 /被疑者と容疑者・世間 /知る権利・取材源の秘匿 /ゲラ /小切手ジャーナリズム /地域紙 /倫理規程・良心条項 /DEI /コンプライアンス・マスコミ倫理 /ポストコロニアリズム