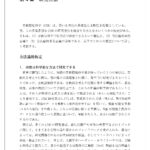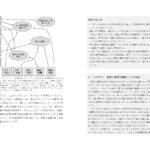あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
 クレア・ホワイト 著
クレア・ホワイト 著
藤井修平・石井辰典・中分遥・柿沼舞花・佐藤浩輔・須山巨基 訳
『宗教認知科学入門 進化・脳・認知・文化をつなぐ』
→〈「第1章 宗教認知科学とは」「訳者あとがき」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「第1章」ほか本文はサンプル画像の下に続いています。
第1章 宗教認知科学とは
宗教認知科学(Cognitive Science of Religion: CSR)は1990 年代に、認知科学の下位分野として創出された。今日では、さまざまな分野の研究者がCSR に加わっている。そこには宗教学、認知人類学、文化人類学、進化人類学、進化心理学、発達心理学、認知心理学、社会心理学、社会学、哲学、神経科学、生物学、行動生態学、考古学、歴史学などの分野が含まれる。宗教認知科学者はそうした分野それぞれの前提や方法を用いつつ、宗教的な思考と行動に人間の認知が果たす役割に焦点を合わせる。CSR 研究者は、認知科学の視点に沿い、人が宗教的表象に関わり反応する仕方は決してランダムではなく、認知プロセスの影響を受けそれに制約されることを認めている。進化心理学の視点に沿い、CSR 研究者はこの認知プロセスが私たちの進化史を反映するような構造によって形作られたことに同意している。そうした認知プロセスの多くは、祖先が暮らした環境に繰り返し現れる問題を解決するために進化したのである。
宗教はどのようにして生まれたのだろうか。宗教はなぜ世界中に見られるのだろうか。宗教的な思考や実践をうまく広める要因は何であろうか。宗教的な実践が参加者にもたらす影響はどんなものだろうか。CSR 研究者はこのような問いを扱い、回答しようと取り組んできた。中でも、CSR 研究者は(a)どの情報に注意を払うよう人の心は作用しているのか、(b)情報に注意が向くのはどのような文脈か、(c)宗教的な思考と実践が生じる際に、どのように情報が貯蔵され・処理され・作用するのか、これらを理解することに関心を持っている。彼らはまた、(d)宗教的な信念と実践が、それに関わる人に与える影響についても関心を抱いている。宗教認知科学の最終的な目標は、いかにして人類集団の中で宗教的な思考、信念、行動が生まれ、繰り返されてきたのかを、進化、認知、脳、行動に関する知識を用いて説明することにある。(以下、本文つづく)
第3章 解き明かすべき問い
宗教認知科学(CSR)が宗教研究の中でも特徴的なアプローチになっている理由の1 つは、CSR 研究者の立てる問いにある。例えば、宗教的な考えや行動(つまり、宗教に関連する概念や考え方、あるいは慣習、儀礼など)の中には、歴史や文化を通じて途絶えることなく現在も残っているものがある。なぜそうしたものは、途絶えることがなかったのだろうか。また、宗教的な考えを心に表象するには、特別な心・認知的基盤が必要なのだろうか。そうした心・認知的基盤はどのようにして生じてきたものなのだろうか。さらに、宗教が生まれるには、心と文化がどのように相互作用する必要があるのだろうか。こうした問いは、書籍や論文の中で、必ずしも明確に述べられるわけではなく、読者の目にとまらないことも多い。そこで本章では、こうしたCSR 研究者が立てる問いについて解説していきたい。
なぜある種の宗教的な考えや行動は途絶えることがないのか
ある種の考えや行動は、歴史を通じて、また文化の枠を超えて、比較的安定した形で絶えることなく存続する。それは一体なぜなのだろう。CSR はこの問いを解き明かすことに関心を向けてきた。このように、特定の考えや行動が時間や場所を問わずに繰り返し現れる(反復する)理由を説明することは、宗教の多様性を考慮すると、特に重要である。というのも、世界には、さまざまな異なる形態の超自然的行為者(の概念)がある。ということは宗教的な考えは文化によって多様である見込みが高い。それにもかかわらず、超自然的行為者が人間のような特徴を持つものとして表象される点など、共通点もある。つまりある種の考えが反復されている。これは、日々の経験が私たちの概念や思考を制約する部分があるためである。
いずれにしても、こうした文化を超えて繰り返し現れる考えと行動は多くの場合、分かちがたく結びついて、研究者が「宗教的」とラベルをつけるようなシステムを形成している。そこでCSR は宗教を、第2 章で論じたように、文化を超えて繰り返し現れる考えや行動の形に分解する。ここには、懲罰的神という不可視の行為者の概念や、死後も生命は継続するという考え方、儀礼的行動などが含まれる。そしてこうした考えや行動がなぜ生まれ、なぜ存在し続けるのかを解き明かすことが、「宗教」を説明するという言葉の意味である。さまざまな宗教で反復されている考えや行動を突き止めるため、CSR 研究者は、考古学、歴史学、民族学のデータを活用し、また自ら実験データを収集する。そしてこうしたデータの分析を通じて、反復するパターンについて検討を行う。
1. 日常的な宗教と神学的な宗教
CSR は、宗教的観念が文化の中でどのように伝達されるのか(文化伝達)を解明することに関心がある。その際、神学的な意味での宗教と、普通の人々にとっての日常の中にある宗教とを区別する。そしてCSR 研究者が特に説明しようとしているのは後者である。つまり、ほとんど教えられることがなくても比較的容易に生まれ、幼少期に確立されるような宗教的観念を説明することに関心がある。この種の考えは、直観的プロセス(すなわちシステム1)から生まれるものと言える。第2 章で取り上げたように、システム1 から生まれる観念は、素早く、自動的に、そして潜在的に進行する。哲学者のロバート・マコーリーは、このようなタイプの宗教的観念を「成熟に伴う自然(maturationally natural)」と呼んだ(表3. 1)。つまり、多くの普通の人々が素朴に理解する宗教とは、成熟に伴う自然的な観念であることが多いといえる(成熟に伴う自然的な観念を支える直観の詳細な例については、第7 章の表7. 1 を参照)。
では、神学的な意味での宗教が私たちの直観的プロセス(システム1)に反するとしたら、専門家が神学的教義をたやすく暗唱できるのはなぜだろうか。マコーリーはこれに関わる能力を「練習された自然的状態(practiced naturalness)」と呼んだ(表3. 1)。練習された自然的状態は継続的な訓練によって獲得されるものであり、通常の心身の発達から生まれたり、あるいは教えられることなしに生じたりするようなものではない。それは、例えば楽器の演奏や車の運転を学ぶのと同じで、自分のものにするには繰り返しの練習などの継続的な努力を必要とする。したがって、直観に反するような神学的な意味での宗教的観念は、顕在的に保持され、意識的にアクセス可能な(つまり、自分がそうした考えを持っていることをはっきり意識できる)ものだといえる。これは言い換えると、神学的教義を正確に暗唱できるのは思い出したり考えたりする時間があるときであるし、また練習した教義しか暗唱できないということでもある。
なおCSR 研究者たちは、神学的観念が形成されるのに必要な社会・文化的な条件に関心を持つが、その際には人間の認知機能の役割を重要視する。多くの神学的な考えは、複雑で人々の直観とは反する側面を持つというのがCSR 研究者の見解である。例えば、キリスト教の三位一体の教義では、神は3 つの異なる位格(すなわち父、子、そして聖霊)を持ちながらも同じ1 つの存在であるとしているが、この考え方は、個人は1 つの人格しか持たないという私たちの通常の理解(直観)とは反するものがある。そしてCSR 研究者は、こうした神学的観念が、大衆的・日常的には人々にどのように理解されているかを探ろうとしている。これにより、宗教的観念を理解しようとする際にどのような認知機能(直観やバイアスなど)が働くのかを知ることができるためである。
2. 神学的に適切な概念と不適切な概念
CSR 研究者が説明しようとしているのは、神学者たちが定義するような形式的な宗教というより、普通の人々にとっての日常的な宗教の中で絶えることなく存続している観念であるという点は、先述の通りである。ただし、普通の人々が持つ宗教的観念の中には、神学を拠り所としたものも多くある。例えば、仏教におけるカルマ(因果応報)の概念など、神学的な宗教に見られる考えを信じていると公言する人も多くいる。CSR 研究者はこうした概念を「神学的に適切な(theologically correct)」概念と呼ぶ(表3. 2)。なお、このようにある観念に「神学的に適切」とラベルをつけるのは、どのような教義の解釈が正しいか、真実であるかを決めるためではない。そうではなくこの呼び名は、人々が顕在的に、神学的な意味での宗教における考えを参照することがある、ということを意味している。もちろん、ある概念が神学的に適切であるかどうかについては(宗教・宗派などによって)さまざまな見解があり得るのだが、CSR 研究者にとって重要なのは、熟慮する時間が十分にあるときに、人々は自分が何を信じていると公言するのかという点である。
人が、さまざまな文脈を通じて、神学的に適切な考えを一貫して信じ続けるというケースは確かに存在する。こうしたとき、人々はよく、教えられたことを信じ続けているだけだと主張する。しかしながらこうしたケースばかりではなく、教えられたことを無意識のうちに、より直観的に理解しやすいものに(つまり、成熟に伴う自然的な概念に)変えてしまうことも、よくある。例えば多くの仏教徒は、彼らの信じるカルマの教義とは相容れないにもかかわらず、運の存在も同様に信じているとされる。CSR 研究者たちからすれば、これらの考えは「神学的に不適切」ということになるだろう(表3. 2)。
このような、公言された信念(例えば、カルマの信念)と実際に信じていること(例えば、運の存在)との乖離は、さまざまな状況で起こる。そして以下の2つの条件下では特に起こりやすいことが知られている。1 つ目は、答えを出すのに時間制限があるなど、短時間で認知的な処理を済ませる必要があるときである。例えばある研究によると、第7 章でも述べるように、キリスト教徒の参加者は「神は全能である」と顕在的には考えていても(神学的に適切)、時間制限がある場合には「神は(普通の人間と同じように)能力に限界があり、好みもある」と答える傾向があった(神学的に不適切)。
乖離が生じやすい2 つ目の条件は、苦境に陥るなどして、強い情動を経験しているときである。例えば、多くのキリスト教徒は、神に対して怒りを向けることは道徳的に許されないと考えるはずである(神学的に適切)。それにもかかわらず、癌の診断を受けるなどの予想外の苦境を経験すると(「なぜこんなことを」と)発作的に神への怒りを経験する人もいるという(8)(神学的に不適切)。繰り返しになるが、CSR 研究者が最も関心を持つのは、時と場合によって、人々が信じること・考えることが変わるという現象である。なぜこうした乖離が起こるのかを解き明かすことで、宗教的観念の処理にどのような認知機能が役割を果たしているのかを明らかにすることができるためである。
本章ではここまで、CSR のさまざまな側面を取り上げてきた。CSR には、心や文化を研究する他の学問分野と重なる側面があるが、異なる側面もある。例えば、宗教的な考えや行動を説明するために心理学の理論や方法を適用する点で、CSR は宗教心理学とよく似ている。しかしCSR 研究者は(宗教心理学者のように)個人の心を説明することを重視しない。例えば、「ある人物がなぜ宗教的になるのか」といった問いに答えることにはあまり関心を示さない傾向にある。むしろCSR の研究者は、人々がどういったものを信じやすいのかについての通文化的なパターンに関心があり、例えば、「なぜ人々は直観的に、神も(超常的な力を備えながらも)人間のような行為者であると表象するのだろうか」といった質問に答えようとしている。
宗教的な考え・行動を支える認知的・心理的基盤
人々の間で受け継がれる可能性のある考えや行動が数多く存在する中で、なぜある種の宗教的な考え・行動が特に繰り返し現れるのか、CSR はこの問いを、人間の認知的傾向に関する研究知見を援用することで説明しようとする。ここまで触れてきたように、人間の心や文化は無限とも思えるほどに多様な観念を生み出すが、途絶えることなく受け継がれているものはその中のごく一部にすぎない。例えば、なぜ多くの人々は、あらゆる出来事は偶然ではなく理由があって起こるのだと考えるのだろう。なぜ身体が滅びても生命は終わることなく続くと思うのだろう。なぜ幽霊のような超自然的行為者はよく、心を持たない非人間的な存在というよりも、心を持った、ただし目には見えない通常の人間として理解されるのだろう。なぜ神は、日々の生活で起きるさまざまな出来事の中で、特に道徳的な行いに関心を寄せる存在として描かれるのだろう。なぜさまざまな文化において人々は、宗教的儀礼には特に積極的に参加するのだろう。これだけに留まらず、さらに多くの問いが、この本で紹介するようなCSR 研究の原動力となっている。
(以下、本文つづく。表と注番号は割愛しました。PDFでご覧ください)
訳者あとがき
藤井修平
本書はClaire White, An Introduction to the Cognitive Science of Religion: Connecting Evolution, Brain, Cognition, and Culture( Routledge, 2021)の翻訳である。著者であるホワイトは米国の大学を卒業後、英国北アイルランドのクイーンズ大学で心理学を学び、2010 年に博士号を取得した後、米国カリフォルニア州立大学ノースリッジ校の准教授となった。彼女は、宗教認知科学の創立者であるE・トーマス・ローソンやハーヴィー・ホワイトハウスに教えを受けた第2 世代の研究者であり、米国の宗教学科で初めて宗教認知科学の専門家として常勤職に就いた人物でもある。彼女が専門としているのは生まれ変わりや葬送儀礼などの死に関する信念と行動であり、その研究内容は本書第6 章、第10 章において紹介されている。
宗教認知科学は、認知科学のみならず進化生物学、心理学、神経科学、人類学などによる宗教に関する多様な研究を統合し、2000 年に確立された比較的新しい分野だが、第1 章で解説されるようにその研究拠点は西洋諸国のいたるところに設立されており、関連する研究も増加し続けている。ホワイトの指導の下、カリフォルニア州立大学ノースリッジ校では学部生にも宗教認知科学のコースが設置されているが、本書はそうした学生のための教科書として執筆されたものである。
ホワイトは、宗教認知科学が既存の宗教研究といかに異なっており、どのような長所を有しているかについて、最初の4 章を費やして丁寧に記述している。第1 章「宗教認知科学とは」では、当分野が誰によって、どのような意図で成立し、どんな新しい視点を取り入れているのかについて解説される。宗教認知科学の初期の開拓者たちは、1990 年代当時の人文学において支配的だったポストモダニズム、文化決定論、極端な文化相対主義に批判的だった。その根拠は、1950 年代の認知革命に由来する、人の心に関する理解の転換である。彼らはこうした知見に依拠し、新たな認知的アプローチを打ち立てることで一致していた。第2 章「前提となる知識」では、宗教認知科学の視点からは、「宗教」および「信念」はどのように理解すべきかという根本的な問いが検討されている。とりわけ宗教の定義問題は長年研究者を悩ませてきたものだが、ホワイトは宗教の本質は規定せず、あくまでいくつかの特徴をもった現象を包括して呼ぶためのラベルとして、宗教という語を用いている。
第3 章「解き明かすべき問い」では、当分野がどのような問いを立て、解明を試みるかが語られる。重要なのは、神や儀礼、死後の世界など繰り返し現れる通文化的パターンを特定し、それらがなぜ信じられるのかという問いへの答えを、人類に共通の認知的傾向と、文化ごとに固有の要素の相互作用に求める姿勢である。第4 章「研究方法」では、当分野の研究方法が包括的に示される。ここではさまざまな分野の研究方法が用いられている様子が明らかになるが、とりわけこれまでに実施された27 の研究の方法や結果をまとめた表4. 1 は、宗教認知科学という分野をひと目で概観できる有用なものである。
続く6 つの章では、それぞれのテーマに関する最新の知見が紹介されている。第5 章「世界のあり方」では世界は何らかの存在によって創造されたという信念や、災難や病気についての超自然的な説明、天罰のような応報的思考について解説がなされる。第6 章「死後の世界」では、人々がなぜ死後に魂が存続すると考えるのかなどについて、さまざまな理論が検討されている。第7 章「超自然的行為者」では、神などの宗教上の存在がどのように信じられるかについての理論が概観され、第8 章「道徳」ではしばしば宗教と結びついているとみなされる道徳について、その起源や宗教との関わりが探究されている。残る2 章はいずれも儀礼を扱っており、第9 章は儀礼の特徴や伝達過程に関する理論、第10 章は儀礼は参加者にどのようなメリットを与えるのかに関する理論をそれぞれまとめている。これらの章の内容は、神や死後の世界、儀礼といった古典的なテーマに対し、認知科学や心理学、進化生物学によって解明を試みた成果が示されている。そして最後となる第11 章では、宗教認知科学の理論を受け入れると宗教は肯定されるのか、あるいは否定されるのかという哲学的な問いと、当分野に対してなされた批判、およびその批判を踏まえての今後の展望について述べられている。
こうした内容からわかるように、本書は初学者向けの教科書に留まらず、宗教認知科学の成立過程や長所、研究手法や代表的研究を網羅した当分野の基礎的文献と言えるものである。とりわけ文献情報は非常に充実しており、本書を一読するだけでテーマごとの最新研究を把握できるだろう。他方で、そうした徹底ぶりのために原著351 ページという大著となっている。また、各章には数段落ごとの要約や、授業で使用するための問いが細かく設けられていたが、紙幅や簡潔さの面を考慮して一部は割愛し、また授業で使用するための課題と文献案内については勁草書房ウェブサイト上での掲載とさせていただいた(詳細やURL は凡例を参照)。下記のQR コードからもアクセスできる。体験課題はアクティブラーニングの例としても参考になるので、授業で用いる場合はぜひ活用していただきたい。なお、注において未刊行の論文等が引用されている場合も、原文の表記のままで記載している。引用する際はその点に注意されたい。
本書の翻訳は、それぞれ藤井修平(第1 章、第2 章、第7 章、第11 章および序文等)、石井辰典(第3 章、第6 章)、中分遥(第9 章、第10 章)、柿沼舞花(第8 章)、佐藤浩輔(第5 章)、須山巨基(第4 章)が担当した。本書の出版にあたり、非常に込み入った内容を丁寧に整理、校正していただいた勁草書房の関戸詳子氏、その仕事を引き継いでいただいた永田悠一氏には大変お世話になった。この場を借りてお礼を申し上げたい。