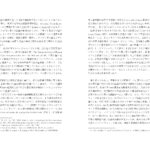あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
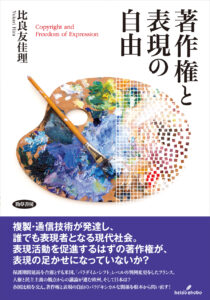 比良友佳理 著
比良友佳理 著
『著作権と表現の自由』
→〈「はじめに」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「はじめに」本文はサンプル画像の下に続いています。
はじめに
本書は、北海道大学大学院時代からこれまでの約10 年間、研究テーマとして取り組んできた、著作権と表現の自由に関する一連の研究業績を一冊の書籍としてまとめたものである。
はじめにこのテーマに関心をいだいたきっかけは、修士論文の研究テーマを検討していた際、1 つの候補として、パロディと著作権法の関係に興味を持ったことである。パロディに関しては、田村善之『著作権法概説』(第2 版・有斐閣・2001 年)241 頁が、「表現の自由という基本的人権に関わる」問題であることを既に指摘していたが、当時の憲法の教科書や概説書の表現の自由に関する箇所を開いてみても、名誉毀損やプライバシー権といったトピックは表現規制立法として位置づけられ、重要論点として扱われていたにもかかわらず、著作権や知的財産権と表現の自由の関係についてはほとんど触れられていなかった。インターネットやデジタル技術、SNS の普及に伴い、誰でも簡単にコピーや加工、共有ができるようになった今日では、他人の著作物を利用することが日常茶飯事となるとともに、利用態様も多様化している。パロディに限らず様々な場面で、著作権と表現の自由の緊張関係がかつてないほどに高まっているのではないか。人々が表現行為や情報発信を行う際、著作権侵害の可能性が頭に過り、表現行為そのものを控えたり、あるいは本来望んでいたのとは異なる形で(例えば元々利用しようと考えていた著作物を他のものに差し替えて)表現を行ったりするといった形で、多かれ少なかれクリエイティブな活動に支障をきたしているとすれば、それは著作権法の目指した帰結なのであろうか。著作権法が表現の自由に対して何らかの萎縮効果を与えかねない存在であるとすれば、憲法上の問題は発生しないのだろうか。このような素朴な疑問を抱いたことが、本研究の出発点となっている。
そこで米国法に目を向けてみると、古くは1970 年代の学説でNimmer らを中心とした議論が見られたが、その後1980 年代から2000 年代にかけて連邦最高裁判所が複数の判決を通して両者の関係性を徐々に明らかにしてきたという状況だった。特に、米国で著作権法保護期間延長法(Copyright Term Extension Act, CTEA)の合憲性が争われた2003 年のEldred v. Ashcroft 判決をきっかけに、改めて米国内で様々な議論が展開されており、日本でも数多くの紹介がなされていた。そこでまずは米国法を足がかりにこの問題について視座を得るため、米国法における判例、学説を調査・研究し、そこから博士論文「デジタル時代における著作権と表現の自由の衝突に関する制度論的研究」を2013年12 月に提出した。
米国法研究に一応の区切りがついたちょうどその頃、北海道大学法学部のBranislav Hazucha 教授から、欧州人権裁判所(The European Court of Human Rights, ECtHR/Cour Européenne des Droits de l’Homme, CEDH)で著作権と表現の自由に関する判決が下されたという情報を教えていただいた。これが2013 年のAshby 判決で、当時は著作権侵害訴訟が基本権・人権マターであるという認識が現在ほどにまで国際的に定着していなかったにもかかわらず、傍論とはいえ著作権が表現の自由の保護を理由に外在的に制約されうることを示唆した革新的な判決で、米国とは全く異なるアプローチに驚いたことを覚えている。
2015 年には京都教育大学教育学部に着任し、新たな環境で研究に取り組むことになった。上記の欧州人権裁判所判決を調べていく過程で、フランス国内でも2015 年のKlasen 破毀院判決を含む重要判決が相次いでいることが分かり、それらについて整理を試みた。
フェア・ユース規定のような一般的な権利制限規定を持たないという点で日本法とも共通点の多い欧州やフランス法への関心が高まり、より研究を深めたいと思っていた折、2018 年から2020 年にかけて、日本学術振興会海外特別研究員として在外研究を行う機会を得た。ドイツ国境にごく近いフランスのストラスブールには、ストラスブール大学の国際知的財産研究センターCEIPI(Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle)があり、知的財産権と基本権の研究で世界的に著名なChristophe Geiger 教授が当時のセンター長を務めておられた。在外研究を行うならばぜひGeiger 先生の下でという希望に対し、快く受け入れてくださったことに改めて感謝申し上げたい。
在外研究中の2019 年7 月には、欧州司法裁判所(Court of Justice of the European Union, CJEU)が著作権と表現の自由について待望の決定版ともいえる判決を下した。またフランス国内裁判所においても、前述のKlasen 破毀院判決の差戻控訴院判決が2018 年3 月に下され、著作権と表現の自由の関係が争われていた重要事件についての判決が一通り出揃ったという時期であった。欧州、そしてフランスで、立て続けに重要判決が下された絶妙なタイミングにフランスに滞在して、現地でいち早く多くの論考に接し、関連する国際シンポジウムを拝聴できたことは本研究を遂行する上で非常に意義があったと感じている。在外研究終盤の2020 年にはヨーロッパをはじめ世界中で新型コロナウイルスの流行が拡大し、フランスでも外出禁止令や飲食店の営業停止、大学の閉鎖が行われるという未曾有の事態に見舞われたが、CEIPI の同僚やスタッフが親身になって様々なサポートをしてくださったこともあり、当初期待していた以上の研究成果を得られた。
振り返ってみると、筆者が本書の研究テーマに取り組んだこの10 年は、まさに著作権と表現の自由の議論や判例が飛躍的に発展した激動の時代であった。2000 年代、米国のEldred 連邦最高裁判決を契機に、米国では著作権制度と憲法の関係性や、著作権法の立法過程が抱える構造的な問題とそれに対する違憲審査のあり方に関する議論が一気に花開いた。また、デジタル技術やインターネットの普及を踏まえた、現代のクリエイティブ環境における著作権の役割も論じられ、1970 年代には見られなかった新たな議論も展開した。さらに2010年代に入ると、欧州人権裁判所や欧州司法裁判所の判決が相次ぐとともに、フランス国内裁判所もこれらの欧州レベルの裁判所の影響を受ける形で「著作権のパラダイム・シフト」と呼ばれるほどのドラスティックな判例変更が行われた。かつて欧州では(特に2009 年のリスボン条約発効以前は)、知的財産権と基本権の関係性を論じる論考自体が少なかったが、現在では人権が「知的財産権の新しいフロンティア」と呼ばれ、学説や裁判例の発展のみならず、2019 年のデジタル単一市場における著作権指令などの様々な著作権関連のEU 指令で、今や必ずといってよいほどユーザーの基本権の保障が高らかに謳われているといった状況である。
本書は以上のような発展をできるだけ時系列に沿う形で整理し、博士論文と在外研究の成果を中心に、既発表の論考を再録した上で適宜加筆を行っている。内容を大幅に変更しないよう、論文発表時の情報を基本としているが、論文の趣旨が変わらない範囲でできるだけ新たな情報も付け加え、全体としても可能な限り一冊の書籍として一連の流れをもって読んでいただけるよう工夫したつもりである。
(以下、本文つづく。注は割愛しました)