あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
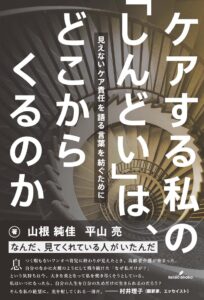 山根純佳・平山 亮 著
山根純佳・平山 亮 著
『ケアする私の「しんどい」は、どこからくるのか 見えないケア責任を語る言葉を紡ぐために』
→〈「エピローグ 「わからない」から始まる「ケア責任とジェンダー」論」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「エピローグ」本文はサンプル画像の下に続いています。
エピローグ 「わからない」から始まる「ケア責任とジェンダー」論
本書のテーマである「ケア責任とジェンダー」は、「陳腐」きわまりないテーマです。この世の中で誰かの世話をしているのはたいてい女性であること、その意味で、ケア責任に性別が関わっていることは、取り立てて目新しい話題ではありません。ジェンダーの問題に関心のある人にとってはなおさらそうでしょう。それなのに何を今さら、そのテーマで新たに語ることなんてあるのか、と思われる人もいるかもしれません。
しかしながら、わたしたちがこの「陳腐」なテーマであえて新しい本を世に送り出したのには、わけがあります。それは、ケアを考える上でいちばん大事かもしれないことが、これまできちんと言葉にされていないのではないかと感じていたからです。端的に言えばそれは「何がケアになるかなんて誰にもわからない」ということです。
ケアが誰か(の生)を支える行為であるということに、異論を唱える方はほとんどいないでしょう。もちろんわたしたちも、それに「異議あり」と言うつもりはありません。しかしながら、ここで難問が立ち塞がります。それは、何をもって「支えている」ということになるのか、どのようにして「ああ、たしかにそれはその人を支えているね」と判定することができるのか、という問題です。
これを難問たらしめているのは、「誰かを支える行為」にはそれをする側とされる側の、少なくともふたりが当事者となるという、ごくシンプルな事実です。たとえば、する側がいくら熱心に相手のことを思い、何かをしてあげても、される側にとっては自身の生を妨げるものでしかない、むしろ脅かすものにすらなりうることは、「あなたのためを思って」と自分の生活に干渉しまくる親に長年抑圧されてきた人には、直ちにわかることでしょう。
それなら、される側の受け止め方を第一に考えればよい、と言う声もあるでしょう。それはその通りですし、実際、多くのケアの議論は「される側が何をしてほしいか(してほしくないか)」を中心とせよ、と訴えています。
でも、それをどうしたら実行できるのか、どうしたら実行したことになるのかは実のところ不明です。「される側が何をしてほしいか」と言っても、される側が自分のしてほしいことを表明できる状態にあるとは限りませんし(というより、そういう状態にないからこそ、日々の生活に支えを必要としていることはままあるわけですし)、そもそもされる側自身が、自分は何をしてほしいのか、何をしたら自分にとって支えになると言えるのかをわかっていないことだってあるからです。
もうひとつ、それが本当に支えになっていると言えるかどうかを難しくさせるものは、時間の経過という要因です。する側が、そのときこれがベターだと考え、される側もそれに納得していたとしても、長い目で見た時に相手に不利益をもたらす結果となってしまった、ということはありえます。たとえば子どものために、「あのときはこれしかない、これがいちばん良い」と考えてした選択のはずだけれど、そのとき別の選択をしていれば、今この子はこんな状態にはならなかったかもしれないのに、と心のどこかで後悔を抱える親御さんは少なくないのではないでしょうか。また、子育ての「常識」が刻々と変わっていくことを考えれば、その当時の最善が後になってそうではないとわかった、となることを避けるのはほとんど無理とすら言えるかもしれません。
何を言いたいかというと、していることが相手(の生)を支えるものになっているかどうかは、誰が、どのようなタイミングで見るかによって変わりうるということ、そもそもされる側も含め、誰にもわからないことすら珍しくはないということです。ケアとは誰か(の生)を支える行為であるという定義自体は理解できるけれど、その定義に照らして、ケアと言える行為と言えない行為をきれいに区別することなど実はできないのではないか、ということです。
ちなみにこれは、ケアを広くとった場合でも同じです。ケアはいわゆる育児・介助・介護には限らないのだ、相手への配慮や気遣い、あるいはソーシャルサポート(励ましたり話を聞いてあげたりといった心理的なものから、何かを手伝ってあげたりといった具体的なものまでを含む、人々が互いにしてあげたりしてもらったりする何か)に当たることまでも、誰か(の生)を支える行為=ケアに含まれるのだ。このように、ケアを広くとる議論も珍しくはなくなりつつあります。
しかし、これもまた同じ困難を抱えていることは明らかです。する側が配慮し、励まし、手伝っているつもりでも、される側がそのように受け止めているかはわかりません。むしろ「やってくれないほうがまし」になってしまっていることすらありえます。だとしたら、(する側にとっての)配慮や励ましや手伝いは、される側(の生を)を支える行為=ケアになっているのでしょうか。
他方でわたしたちは、する側だけが支えているつもりでいる何かを「やってくれないほうがまし」なんていちいち言わないかもしれません。だとすれば、される側がそれをどう思っているかなんて他の誰にもわからない。このとき、そこで支えが行われているかどうかを、いったい誰がどのようにしてわかるのでしょう。
冒頭に述べた「何がケアになるかなんてわからない」とはそういう意味です。この「わからなさ」を前にして、多くのケアの議論、とりわけ既存の「ケア責任とジェンダー」をめぐる議論は、ケアになりうる行為が実際にケアになっていると仮定することで、この「わからなさ」を脇に置いてきたようにも思えます。つまり、子どもや高齢者といった「依存的な存在」に何かをしてあげることにしろ、ケアを広くとる議論における配慮や励ましや日々の手伝いにしろ、それがつねにすでにケアになっていると見なした上で【それが~上で:傍点】、それを誰がどれくらいしているか、そこには性別による差がどのように見られるかを分析し、なぜそうなのかを説明することが「ケア責任とジェンダー」を論じることである、と。要するに、その行為──たとえば、ごはんをあげることにしろ、見守りをすることにしろ、話を聞いて慰めてあげることにしろ──が本当に定義通りのケアになっているかどうかには、あえて突っ込まずにきたようにも思えたのです。
このケアをめぐる「わからなさ」ないしはややこしさを「うっちゃる」のではなく、その「わからなさ」そのもの(本編では「不確実性」と呼んできました)を中心テーマとしたのが本書です。ある行為が誰か(の生)を支えるものになるかなんてわからない。その意味で、これをすればケアになる・なっている、というような特定の行為はない。そのことをまず大前提とした上で、われわれはケアを何らかの行為ではなく、いわば「試みのプロセス」として考えることにしたのでした。
何が支えになるのか・それが支えになっているのかが不確実なまま、それでも相手の支えになるかもしれないことをひねり出し、あるいは選び取り、迷いながらも実際にやってみること。選んで実際にやってみたあとで、相手の様子を見てはまた、やり直してみること・やり直さざるをえなくなること。そして、それを繰り返し続けること。正解のわからない(そもそも正解なんてない)ぐるぐるループのそんなプロセスのただ中にわが身を置き続けることが、本書における「ケア責任を負う」ということでした。
このプロセス自体に目を向け、それをきちんと言語化しない限り、誰か(の生)を支えようとすることがなぜ難しいのか、なぜ大変なのかなんてわからないし、わかってももらえない。それに、このプロセスの取り組み難さとしんどさを理解し、このプロセスにともに入り込んでくれない限り、誰かとケア責任を分け持つなんてことはできない。わたしたちはそう考え、このプロセスをできるだけ細部まで「見える化」するために、本書を書き上げたのです。
わたしたちがこのプロセスを考える上で、SAという概念は不可欠なものでした。SAは拙著『介護する息子たち』で導入したsentient activity の略語ですが、このSAはまさに、相手を注視し、何を必要としているか、何をしてあげたらよいかを考えることでしたから。
他方、わたしたちにとってはそれこそがケアそのものとも言える「試みのプロセス」を「見える化」できるよう、わたしたちはオリジナルのsentient activity をずいぶんといじり倒し、あれやこれやの要素を付加して改変しています。それゆえ本書におけるSAは、オリジナルからだいぶ離れた、いわば「拡大版SA」とも言えるものです。しかしながら、相手を支えようと試みる際に駆使される感知と思案をその定義とする当初のSA概念がなかったら、そもそもこのように拡大することすらできなかったわけであり、それゆえ本書の分析は、SAの「元祖」である社会学者のジェニファー・メイソン氏の論文に多くを負っています(深謝!)。
ところで、ケアを「試みのプロセス」として考えた場合、「ケア責任とジェンダー」についてのよくある前提も改めざるをえません。それは「ケアは女性のほうができるもの」という前提です。なぜかといえばこの前提は、ケアがちゃんとできているかどうかを判定できなければ成り立たないからです。しかしながらここまで繰り返し述べてきたように、本当にそれがケアになっているかどうかを、誰の目から見ても確実にそうだと言い切ることなんてできません。だとすれば、「女性のほうができている」かどうかの判定もまた難しくなるはずです。
本書は、「ケア責任とジェンダー」をめぐる議論のなかでほとんど常識ともされてきたこの前提から、慎重に距離を置いてきました。なぜなら、「ケアは女性のほうができるもの」という前提から始めてしまえば、「何をどうすればケアになるのかなんて、女性だっていつまで経ってもよくわからない」という当たり前の事実から話を始めることができなくなるからです。
もちろん、女性のほうがケア責任を担っていること・担わされていること──「試みのプロセス」に身を投じざるをえなくなること──は事実です。でもそのことと、ケアができ(てい)ることは別のことでしょう。子どもを育てることを例にとれば、「こういうふうにして、この子はちゃんと育つのだろうか」といった疑問や迷いをどこかで抱えつつ、それでもそのときそのとき自分にできることをやって切り抜けてきたら、結果的に子どもが何とかここまで成長してこれた。それが、ケア責任を担ってきた、あるいは担わされてきた多くの女性の実感ではないでしょうか。
要するに、「これでいいのかしら」という不安を押しのけながら、そしてやってみた後も「これでよかったのかしら」という迷いをときに覚えつつ、正解もわからず走り続けてきた結果、自分のやっていること・やってきたことが、どうにかケアと見なされうるものになっていただけ。そうやって何とかやってきた、というより、何とかせざるをえなかっただけなのに、それをもって社会から「ほらほら、やっぱり女性はちゃんとできるじゃない」とまとめられてしまったらたまったもんじゃない。そういう思いが本書のきっかけのひとつにありました。
繰り返しになりますが、女性にだって誰にだって、依存的な存在をどうしたら支えられるのかなんてわかりません。女性のほうがケア責任を果たしてきたこと、つまりは「試みのプロセス」に身を投じてきたことは事実だけれども、それと女性のほうがケア責任を果たしやすいことはまったく別です。そして、そんな当たり前すぎるくらいの事実に軸足を置くことで初めて、わたしたちは「ケア責任とジェンダー」における不平等の原点、すなわち、この世の中が、いかに「ケアは女性のほうができるもの」という前提の上に成り立ってしまっているか、そしてそれがいかに問題であるかを議論することができるのです。
仮に女性が果たしてきたケア責任を「評価する」ためであっても、「ケアは女性のほうができるもの」という前提──その「できる」を「生まれ」で説明するものであれ「育ち」で説明するものであれ──をどこかで手放せない議論は、必ず足元をすくわれます。そういう議論は結局のところ、その前提を「真実」として改めて塗り固めてしまうことに加担してしまうからです。その前提を「真実」として無傷のままに留め置く限り、さまざまな社会制度の矛盾、すなわち、それが「真実」でないにもかかわらず、それを「真実」として社会制度が組み立てられているという矛盾にこそ、ケア責任を担う女性(だけでは必ずしもないけれど)のしんどさの根源がある、ということを問えなくなってしまうのです。
その意味において、「ケア責任とジェンダー」の問題を語るためには「なぜ女性ばかりがケア責任を担わされるのか」を問うだけではまだ足りない。「女性にだってどうしたらできるかなんてわからない」という事実をまずハイライトした上で、そこから「わからないにもかかわらず、なぜ女性ばかりが」を問うて初めて「ケア責任とジェンダー」をめぐる社会の矛盾と不平等があらわになるとわたしたちは考えてきました。そして、そのように考える上で、SAという概念は必要不可欠でした。なぜならこのSAこそ、依存的な存在を支えようとする際の感知と思案とその試行錯誤のプロセスを、目に見えるようにしてくれる概念だったからです。
そう、この社会はあまりにも「ケアは女性のほうができるもの」という前提でできすぎている。女性であれば「できるもの」あるいは「できるべきもの」とされているからこそ、女性たちは「試みのプロセス」を自らの創意工夫だけで潜り抜けることを求められてきたわけですし、また、「できていない」と見なされた際にはその結果責任をとらされてきたのです。だからこそわたしたちは、その「できるもの」という前提をいったんしりぞける必要があった。そしてそれをしりぞけた上で、つまり、女性にだって誰にだってどうすればいいのかわからない、という事実に真正面から向き合った上で、誰かの生を支えようとすること、すなわち「試みのプロセス」に身を投じることがなぜ・どのように難しいことなのかを言語化する必要がありました。同時に、その「試みのプロセス」における「寄る辺のなさ」がいったい何によって増幅され、あるいは何によってマシになるのか、要するに「試みのプロセス」に挑む上での資源となるものを明確にする。それを踏まえ、この社会がいかにその資源を与えないできたか、逆に、どのような資源をどのようにアクセスできるようになれば、「試みのプロセス」に身を投じる際の不安や惑いは今よりも緩和されるかを議論したい。それが本書のねらいでした。
ここまで書けば、わたしたちがなぜこんなにも「陳腐」なテーマで改めて本を出したいと思ったのか、そのねらいをわかっていただけるでしょうか。もちろん、ねらいは外れることもあります。読んではいただけたものの、やっぱり「陳腐」な話だったよね、と思われてしまうことだってあるかもしれません。
ただしそれでも、わたしたちはこう望むのです。何が支えになるのか、自分がやっていることはきちんと支えになっているのか、そんなことは誰にもわからない、わかることなんてできない。そのことから目をそらさずに、それでもケアないしは「試みのプロセス」に取り組むとしたらどうすればよいのかを考えることを。そしてそれこそが、「ケア責任とジェンダー」の議論の中心であり続けることを。
願わくば、わたしたちはもっと楽に、大切な誰かの生を支えられますように。支えなければ相手は生きられないかもしれない、でもどうしたら適切な支えになるかもわからない、そんな「目隠しの綱渡り」を進むことがケアですが、この「綱渡り」をもっと不安なく、誰かの手につかまりながら進められるようにしたい。そのために、わたしたちは「不確実性」を低減するような社会のあり方と資源の(再)配分にこだわってきたのです。
崇高な倫理観を身に着けた者だけが「綱渡り」に挑めるような社会はもううんざりです。わたしたちがほしいのは、そんな倫理観を身に着けられなくても、あるいはそこまでの倫理観を身に着けているといちいち評価してもらえなくても、大切な誰かの生を安心して支えていける社会のあり方です。だからこそ、支えるための資源に誰もがアクセスできるような、社会のしくみが必要なのです。その実現をまだあきらめないために、「陳腐」なテーマで書き上げたこの本を世に送り出します(平山 亮)。








