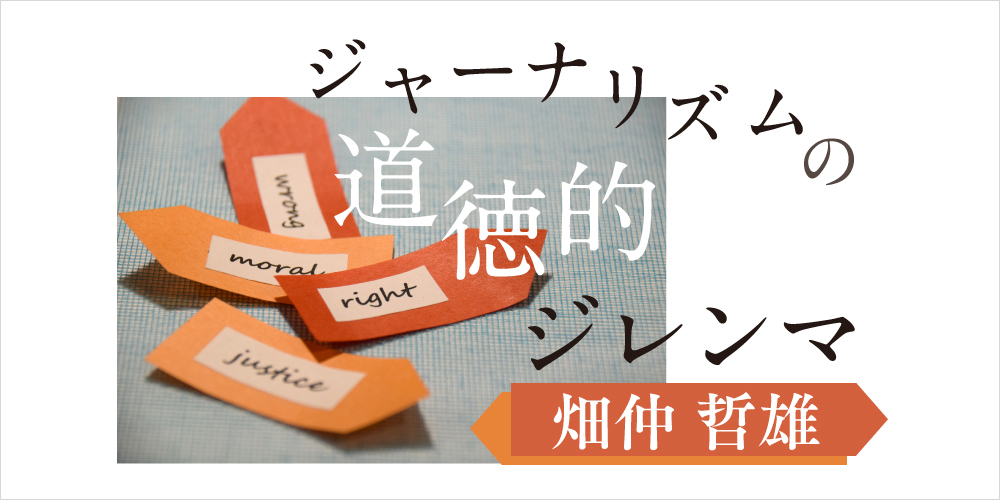3:: 実際の事例と考察
英語に「ホイッスルブローイング(whistleblowing)」という言葉がある。直訳すれば「警笛を鳴らすこと」だが、アメリカでは危機や不正を広く知らせることを意味する比喩として定着している。日本ではその行為を「内部告発」と呼んできた。
警笛を鳴らすという表現に比べると、内部告発という響きには、どこか重苦しく暗い印象がないだろうか。その言葉に近い表現として、「密告」や「告げ口」などがある。個人的な復讐や利得目的ではなく、国民の知る権利を守るため、止むに止まれず行動した人に対し、心ない誹謗中傷が浴びせられることは少なくない。
隠蔽されてきた犯罪や不正などの情報が報道機関に持ち込まれた場合、独占情報としてスクープになる可能性が高い。ジャーナリストは「情報源の秘匿」という職業倫理に従い告発者が誰なのかを明かさない。匿名だからこそ明らかにできる真実がある。その報道が国民の知る権利や公共の利益に寄与するなら、ジャーナリストは功績を称えられるが、告発者はどのような気持ちで人生を送るのだろう。
告発者が誰なのかわからない段階なら、組織の中で犯人探しが始まり、程度の差はあれ疑心暗鬼になる人が出てきても不思議ではない。組織では綱紀粛正を理由に従業員の管理が強化されることもあるだろう。不正暴露の影響は組織のすみずみに及び、「告発者憎し」というムードも醸成されやすい。
告発者が判明すれば、それまで一緒に働いていた同僚たちとの関係が変化する。仲間外れにされたり、露骨な嫌がらせを受けたりして孤立することは容易に考えられる。報復的な配置転換がおこなわれて退職を余儀なくされたり、名誉毀損や業務妨害で裁判を起こされたりした事例もある。
●――内部告発から公益通報へ
ジャーナリズムとの関連を論じる前に、内部告発に関する法整備のあゆみについて簡単に振り返っておこう。日本では2006年に公益通報者保護法が施行された。三菱自動車のクレーム隠し[1]や雪印食品の牛肉偽装[2]などの不正が内部告発によって相次いで明らかにされ、当時すでに法整備を求める世論が醸成されていた。この法律では「内部告発」ではなく「公益通報」という言葉が使われた。通報の形態は、内部通報(1号通報)、行政通報(2号通報)、外部通報(3号通報)に分類された。
法は、告発者にまず内部通報から検討することを促している。産業界ではコンプライアンスという言葉が浸透し始めており[3]、組織自体に自浄能力の向上を促進することに意義はある。研究者のなかには内部通報をめぐり「不祥事の早期告発は、裏切りではなく、会社の救世主」と期待する向きもあった[4]。
だが実際は法が施行された後も、日本社会に根強い「密告」「裏切り」というイメージは容易に払拭できなかったのか、通報者が報復的な攻撃にさらされる事例が続いた。法の実効性がほとんど認められないという批判の高まりを受けて、2020年にようやく法律が改正された。その2年後に施行された改正法では、従業員が300人以上いる事業者に内部通報の窓口設置が義務づけられた[5]。しかし、通報を理由にした報復的な解雇や降格に対する罰則の導入は見送られ、通報者が安心して「会社の救世主」になれる環境が整ったとは言えない。
消費者庁では「公益通報ハンドブック」を発行するなど制度の告知に努めてはいるが[6]、兵庫県では2024年に斎藤元彦知事が、自身のパワハラを告発する内部通報について「うそ八百」と非難し、通報者を「公務員失格」と貶める事態が生じた[7]。知事側は「通報者探し」をおこない、停職3か月の懲戒処分を下した。そのことが議会で問題視され、百条委員会が設置された。通報者は委員会で証言する予定だったが、その直前に自死するという前代未聞の事態となった。
●――過去の内部告発
広い意味で「内部告発」と考えられる事例は、雑誌やオンラインの掲示板などを含めると数限りなく、それらを網羅することは不可能だが、いくつかの有名な事例を振り返ってみよう。
1970年代のアメリカに二つの調査報道があった。一つはベトナム戦争に関する政府の機密文書[8]をニューヨーク・タイムズ紙が暴露したケースだ。政府系の研究所に勤めていたダニエル・エルズバーグが、政府が国民に嘘をついていることを広く伝えるため機密ファイルのコピーをニューヨーク・タイムズ紙の記者に託した。もう一つはワシントン・ポスト紙がニクソン政権の腐敗を暴いた一連の報道で、ニクソンは辞任に追い込まれた[9]。このケースでは内部情報が持ち出されたわけではないが、記者が取材を進めるヒントを与えた支援者がいた。この2例は調査報道による権力監視の成功例として語り継がれている。
1996年にはアメリカの大手タバコ会社副社長が、喫煙の健康被害に関するデータの改竄を暴露し、3年後に実話ベースの映画が公開され話題を呼んだことがある。作品では、副社長宅に銃弾が投函されていた場面や、副社長のインタビュー映像の放映をテレビ局幹部が妨害したことなどが描かれた[10]。
新しいところでは、2013年にアメリカの政府機関で情報活動に従事していたエドワード・スノーデンによる告発がある。スノーデンは中国・香港のホテルで身を隠し、複数の報道機関の記者に対し、アメリカ政府が非合法な手法で情報収集していることを暴露した。2015年には世界各国の首脳や超富裕層が租税回避地(タックスヘイブン)を使って課税逃れをしていることを告発する「パナマ文書」が話題になった。この事件は、各国の記者たちが連携協力して調査報道を展開したことで知られる。
日本の例も見ておこう。先述した三菱自動車のクレーム隠し事件は、2000年に社員が国交省に通報して発覚した。告発者が誰なのかについては報道されていない。雪印食品の牛肉偽装事件では、兵庫県の西宮冷蔵の経営者水谷洋一が報道カメラの前で不正の事実を証言し、雪印食品は廃業。西宮冷蔵も経営危機に直面した。
2002年には運輸業界の運賃不正を公正取引委員会に告発した社員串岡弘昭が勤務先のトナミ運輸を相手取って裁判を起こした。告発者は告発後26年にわたって報復的な扱いを受けていたことが注目を集めた。
2007年には北海道の食品加工会社ミートホープ社が偽ミンチを出荷していた疑いで農水省の立ち入り調査を受けた。当時の常務取締役赤羽喜六による通報が1年以上も放置されていたことが『朝日新聞』のスクープで判明した。同年には、精密機械メーカーのオリンパスの社員が社内の通報窓口に報告し、報復人事の扱いを受けている[11]。
●――ジャーナリズムの役割とは
2000年代には内部告発を勧める出版物がいくつも出版された。報道機関も自社ホームページには情報提供を受け付ける窓口を設けるようになった。たしかに勇気ある内部告発が社会正義を実現することもあるが、ジャーナリストが気をつけておくべきこともある。たとえば、内部告発問題に詳しい東京大学の松原妙華が2014年に発表した論文「内部告発を端緒とする報道のあり方」には、ジャーナリストに重要な視点を提供している。
松原は、内部告発報道にとって「権力監視」と「告発者保護」の両方が重要であることを法的、倫理学的に確認し、昭和から平成にかけて内部告発報道の後に争われた数十の訴訟について詳しく分析した。そのうえで、権力監視と告発者保護という二つの役割が衝突し、バランスを取るのが難しい場合が少なくないと論じる。
……ジャーナリストがどこまで告発者の保護や支援の役割を担うべきなのかについては議論があるところである。(中略)日本で、告発者の心情に共感し苦しみを引き受け、自分の責任として積極的に引き受ける報道姿勢をジャーナリストに求めるべきなのか、可能であるのかという問題は今後の課題となるが、組織不正を公の問題として公開することを決意した告発者の想いをどのような形で結実させるかは、ジャーナリストの報道に委ねられる部分が大きいであろう。[12]
「共感」「苦しみ」「想い」などの言葉から、松原は告発者が置かれた過酷な状況に思いを馳せることをジャーナリストたちに要請しているように読める。日々の特ダネ競争を競い合う記者たちには「スクープを放ちたい」という心理が働きやすい。内部告発はスクープにつながる可能性が高い。そのとき、ジャーナリストたちが情報源を秘匿すれば、「告発者保護」の義務を十二分に果たせたと胸を張ることができるだろうか。
内部告発の取材はジャーナリストと告発者との協働作業であり、両者には信頼関係が必要だ。しかし、報道が始まれば、両者の接触は困難になる。ジャーナリストはスクープ報道で称賛される可能性があるが、一方の告発者が称賛される例はそれほど多くない。それは告発者のその後に迫ったインタビュー記事やドキュメンタリー映像を見れば明らかだ[13]。このテーマを報道側の論理だけで捉えるだけでは不十分であることは論をまたない。内部告発者が取材者をどのように見ているかをジャーナリスト教育に組み込む必要性は大いにある。
4:: Move Forward 一歩先へ
思考実験と異論対論に続いて、もう一歩先の思考に挑戦してみたい。
内部告発の問題を考えるとき、ジャーナリストの倫理として「情報源(取材源)の秘匿」がたびたび言及されてきた。2006年には最高裁によって「原則として取材源に関わる証言を拒絶できる」という判断も示された[14]。表現の自由や国民の知る権利に関わる重要な法理であることは間違いない。だが、そもそも、報道のきっかけをつくった内部告発者の側に立って論じられることがほとんどない。
倫理学者の奥田太郎は「現在話題に上る内部告発は、ほとんどすべてジャーナリストや社会活動団体などの第三者の視点から語られているものばかりではないだろうか。それは、不正の告発といった「事件」を飯の種としていきる人びとのものの見方であって、事件の現場で働く人びとのものの見方ではない」と疑問を呈している[15]。ここでは奥田の議論の中身には立ち入る余裕はないが、ジャーナリストが告発者の側から考えてみる必要はあるだろう。
◆――功利主義と義務論に道徳的な葛藤はあるか
告発者の側から内部告発を考えてみよう。CASE24の「Move Forward 一歩先へ」でも触れたが、規範倫理学には大きく分けて三つの立場がある。ごく簡単に説明しておくと、一つは「最大多数の最大幸福」に象徴される功利主義(帰結主義)で、結果を最重視する。もう一つは、文字通り人間としての義務に従うことを命じる義務論という立場だ。三つ目は徳倫理学と呼ばれる立場で、結果や行為ではなく、有徳な人ならば判断するであろう行動を基準にする[16]。
もしも内部告発者が功利主義者だったら、社会の幸福量を最大化することを道徳的だと考えるだろう。告発によって食品アレルギーなどの健康被害という不幸を最小化できることは間違いない。会社は批判され苦境に立たされるかもしれない。また、告発したことで自分が組織から報復を受けることになるかもしれない。そうであっても、ある条件の下で内部告発はできる/すべきという結論が導かれる。
義務論者だったとしても、内部告発は否定されない。なぜなら、食品パッケージそのものが嘘をついているからだ。義務論の代表的な論者であるカントは、真実を言うことは絶対的な義務であると力説した。たとえ善意から語られたとしても嘘は許されない。不正を見て見ぬふりをすることは共犯者になることをも意味する。義務論者もある条件のもとで内部告発ができる/すべきと断じるだろう。
こうしてみれば、功利主義と義務論という規範倫理学の二大潮流は、内部告発を肯定しているように見える[17]。これに対し、第三の潮流である徳倫理学はどのように考えるだろうか。
◆――徳倫理学がいう「悲劇」と「汚れた手」とは
徳倫理学は、功利や義務という概念ではなく、人としての善さや美徳をもつ行為者を念頭に道徳性を検討する。能力を開花させ善い人生を送ることを理想とすることから、たとえ徳の高い人であっても、内部告発が選択肢に入った時点で、理想的な人生を送るのは困難になる。先述した奥田は「組織の中で不正の事実を知ってしまうことは、交通事故に遭うようなものである」と、内部告発者の心理を分かりやすく表現している[18]。
徳倫理学の代表的論者の一人ロザリンド・ハーストハウスは、道徳的ジレンマには解決可能なジレンマや解決不可能なジレンマのほかに、「悲劇」としか言えないジレンマがあると論じている[19]。今回の思考実験の主人公の行動を振り返ると、主人公は不意打ちのような形で組織の不正を知ってしまった。顧客に対して後ろめたい気持ちを持てあまし、確実な通報先として新聞記者を選んだ。だが、記者の言葉や態度を前にして気持ちがぐらついた。内部告発をしても、しなくても、ともに善き人生から遠ざかるという点で、悲劇的ジレンマに陥ったと言える。しかし、悲劇の当事者に対して徳倫理学が提示できる助言はなさそうだ。結局のところ「有徳な人柄にふさわしい仕方で正しい決断を下せるように、実践的知恵を身につけてゆくしかない」[20]ということになるのだろう。ハーストハウスの言葉を借りれば、そこから抜け出すには、「手を汚す」ことが不可避であり、「おびただしい後悔と痛み」が伴うことになる。
それに対して、ジャーナリストが内部告発をめぐる訴訟で、情報源が誰なのかと問われたとしても、「手を汚す」ことも、「おびただしい後悔と痛み」を覚えることもなさそうだ。むしろ、裁判で証言を拒否すれば称賛されることになる。そうした行為はジャーナリストとしての能力を開花させ、善い人生を送ることを可能にするように見える。しかし、それが内部告発者の悲劇の上に成り立っているかもしれないことを忘れてはならない。
[注]
[1]2000年7月、運輸省(現国土交通省)への内部告発から発覚した。
[2]2002年1月、雪印食品の取引先企業が西宮冷蔵による報道機関への内部告発で表面化した。
[3]Complianceは「法令遵守」と訳される場合が多いが、かならずしも法令だけでなく、社会規範や倫理に従うことも含まれる。
[4]阿部泰隆(2006)「不祥事隠し、なくせるか:中央大学教授阿部泰隆氏(今を読み解く)」日本経済新聞2006年05月07日朝刊。
[5]300人以下の場合は努力義務にとどまる。
[6]消費者庁「公益通報ハンドブック:改正法(令和4年6月施行)準拠版」(2025年4月18日取得、https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_220705_0001.pdf)。
[7]兵庫県西播磨県民局長だった男性は最初に報道機関など外部通報した後、県の公益通報制度を利用して同じ内容を内部通報したのち、自死した。
[8]アメリカ国防総省本庁舎の俗称から「ペンタゴン・ペーパーズ」と呼ばれる。2018年に公開された『ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書』(S・スピルバーグ監督、原題 The Post)では、ニューヨーク・タイムズ紙のスクープを後追いするワシントン・ポスト社の奮闘が描かれた。
[9]民主党選挙対策本部が入居していたビルの名前から「ウォーターゲート事件」と呼ばれる。詳しくは、ハヤカワ文庫の『大統領の陰謀』や同名の映画を参照されたい。1976年には同名の映画(A・J・パクラ監督、原題 All the President’s Men)が公開されている。
[10]マイケル・マン監督作品『インサイダー』(原題:The Insider)。
[11]奥山俊宏(2022)『内部告発のケーススタディから読み解く組織の現実:改正公益通報者保護法で何が変わるのか』朝日新聞出版。
[12]松原妙華(2014)「内部告発を端緒とする報道のあり方:その正当性を担保するジャーナリストの役割」『マス・コミュニケーション研究』84号、pp.129-149。
[13]日経ビジネスが2021年に「内部告発、その後を追う」というシリーズを連載し、西宮冷蔵、オリンパス、トナミ運輸などの告発者をインタビューした。2007年には柴田誠監督のドキュメンタリー『ハダカの城:西宮冷蔵・水谷洋一』が劇場公開された。
[14]奥田良胤(2006)「NHK記者の証言拒絶問題取材源の秘匿認める,最高裁が初判断」NHK放送文化研究所(2025年5月5日取得、https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/focus/106.html)。アメリカに本社がある食品会社の日本法人が所得隠しをした事件をめぐる民事訴訟で、NHKの記者が情報源に関する証言を拒んだことについて、最高裁判所第三小法廷(上田豊三裁判長)は、「取材源の秘匿」が「職業の秘密」に当たるという初の実質的な判断を示した。
[15]奥田太郎(2004)「内部告発」田中朋弘・柘植尚則編『ビジネス倫理学:哲学的アプローチ』ナカニシヤ出版、pp.174-201。
[16]「CASE24「選挙ヘイト」とどう向き合うか」の「4:: Move Forward 一歩先へ」を参照されたい(https://keisobiblio.com/2024/10/08/hatanaka24/2/)。
[17]功利主義と義務論がどのような条件で内部告発を認めるかについては、杉本俊介(2017)「内部告発問題に対する徳倫理学的アプローチ:ハーストハウスによる道徳的ジレンマの分析を応用する」『日本経営倫理学会誌』24号、pp.199-211を参照されたい。功利主義的な立場からは、内部告発すべき条件を定式化した「標準理論」が、義務論の立場からは「共犯理論」が、それぞれある。杉本によれば「帰結主義や義務論よりも、徳倫理学の立場から内部告発の正当化を捉えるほうが、第一に、内部告発の悲劇性や後ろめたさを説明でき、第二に、帰結主義や義務論に基づいた議論の問題点も明らかにする、という点で妥当」と結論づけている。
[18]奥田太郎(2004)「内部告発」田中朋弘・柘植尚則編『ビジネス倫理学:哲学的アプローチ』ナカニシヤ出版、pp.196。
[19]ハーストハウス、ロザリンド(2014)土橋茂樹訳『倫理学について』知泉書館、p.97ff。
[20]杉本前掲書 p.208。
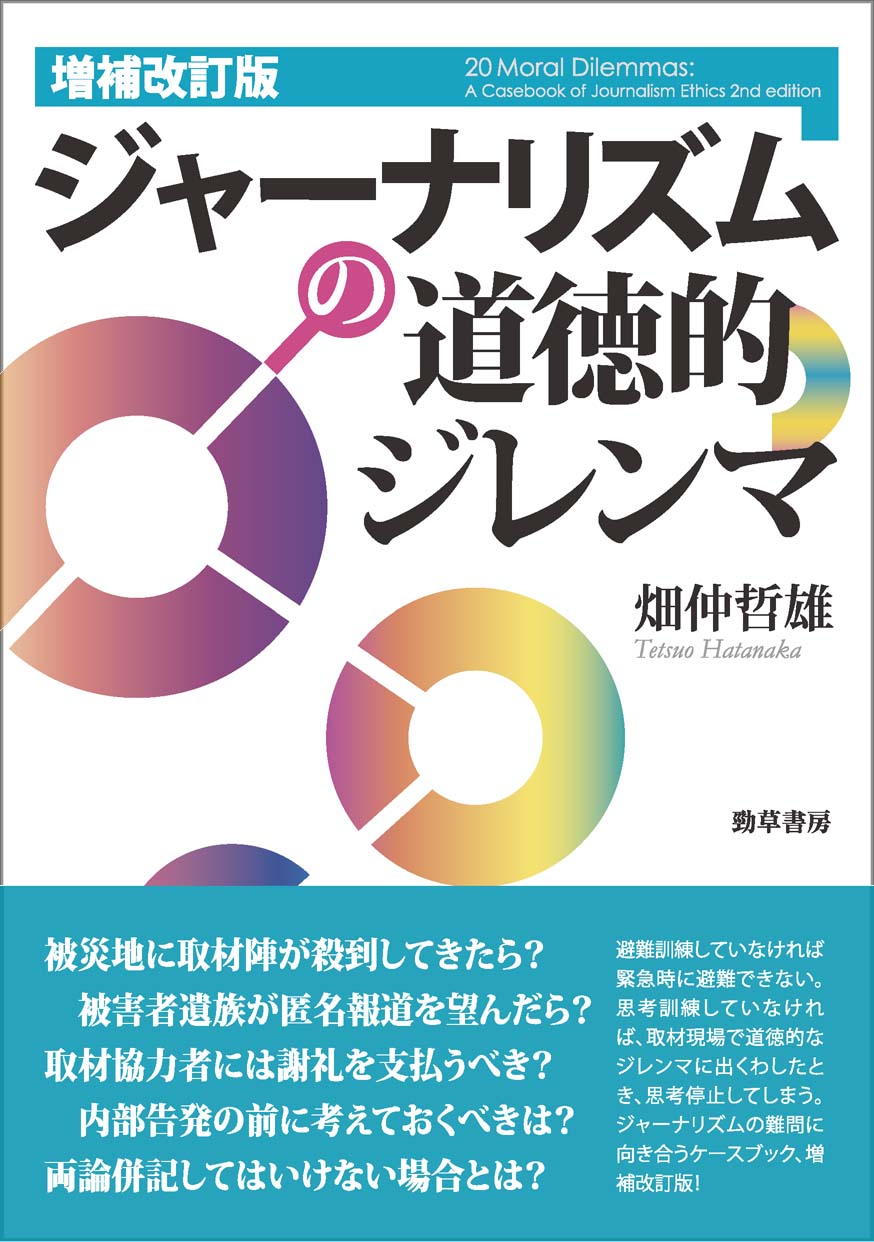 報道倫理のグレーゾーンへようこそ。ジャーナリズム現場で直面する20の難問を巡る思考実験に、さらなる理論的考察を加え増補改訂!
報道倫理のグレーゾーンへようこそ。ジャーナリズム現場で直面する20の難問を巡る思考実験に、さらなる理論的考察を加え増補改訂!
2026年1月17日発売
畑仲哲雄 著『増補改訂版 ジャーナリズムの道徳的ジレンマ』
A5判並製・256頁 本体価格2500円(税込2750円)
ISBN:978-4-326-60387-9 →[書誌情報]
【内容紹介】 フェイクやヘイトが跋扈する今、メディア不信を放置していいのか? 緊急時に避難するには訓練が必要なように、思考も訓練しなければならない。これまでにジャーナリストが直面したジレンマを徹底考察。旧版の事例を一部差し替え、理論解説を追加し、実名報道、取材謝礼、内部告発、オフレコ取材、性暴力報道などを倫理的に問い直す。
【目次】
はじめに――報道現場のグレーゾーンへようこそ
第1 章 人命と報道
CASE:01 最高の写真か、最低の撮影者か
CASE:02 人質解放のために報道腕章を警察に貸すべきか
CASE:03 原発事故が起きたら記者たちを退避させるべきか
CASE:04 家族が戦場ジャーナリストになると言い出したら
〈その先へ〉 物語の第二幕
第2 章 被害と危害
CASE:05 被災地に殺到する取材陣を追い返すか
CASE:06 遺族から実名を出さないでと懇願されたら
CASE:07 加害者家族を世間からどう守るか
CASE:08 企業倒産をどのタイミングで書くか
〈その先へ〉 不幸を減らす第三の選択肢はあるか
第3 章 約束と義務
CASE:09 オフレコ取材で重大な事実が発覚したら
CASE:10 記事の事前チェックを求められたら
CASE:11 取材謝礼を要求されたら
CASE:12 ジャーナリストに社会運動ができるか
〈その先へ〉 義務をはたす第三の選択肢はあるか
第4 章 原則と例外
CASE:13 「選挙ヘイト」とどう向き合うか
CASE:14 組織ジャーナリストに「自由」はあるか
CASE:15 事実の検証か、違法な取材か
CASE:16 その両論併記は大丈夫か
〈その先へ〉 専門職への長い道のり
第5 章 立場と属性
CASE:17 その性犯罪は、いつ暴くべきか
CASE:18 内部告発者の悲劇とジャーナリストの称賛
CASE:19 宗主国の記者は植民地で取材できるか
CASE:20 犯人が正当な主張を繰り広げたら
〈その先へ〉 善いジャーナリズムへの理論と思想
あとがき――ジャーナリズムはだれのものか
索引
■思考の道具箱■
傍観報道・特ダネ /メディアスクラム・合理的な愚か者 /犯罪被害者支援・サツ回り・発生もの /黄金律 /被疑者と容疑者・世間 /知る権利・取材源の秘匿 /ゲラ /小切手ジャーナリズム /地域紙 /倫理規程・良心条項 /DEI /コンプライアンス・マスコミ倫理 /ポストコロニアリズム