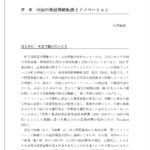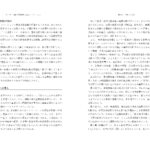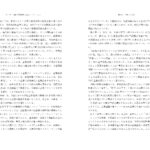あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
 大西康雄・科学技術振興機構アジア・太平洋総合研究センター 編著
大西康雄・科学技術振興機構アジア・太平洋総合研究センター 編著
『「自立自強」の中国 産業・科学技術イノベーションの現状と課題』
→〈「はしがき」「序章」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。本文はサンプル画像の下に続いています。
はしがき
本書は科学技術振興機構(JST)アジア・太平洋総合研究センター(APRC),の2024 年度調査研究会報告『「現代化産業体系」を目指す中国の産業・科学技術イノベーション』の成果を一書として刊行するものである。
アジア・太平洋総合研究センターは2021 年4 月,科学技術振興機構の研究センターとして設立され,アジア・太平洋地域における科学技術分野の連携・協力を拡大・深化し,わが国のイノベーション創出の基盤構築に貢献することを任務とする。この半世紀,アジア・太平洋地域では新興国が次々と台頭し,世界GDP(名目,ドル表示)に占める地域シェアはすでに2010 年代以来,北米,欧州を超えている。また,この地域はハイ・インパクト論文数の飛躍的増加にも見るように,科学技術イノベーションにおいても世界的中心の一つとなっている。
本センターはこれに鑑み,韓国,中国,台湾,ASEAN 主要国,インド,オーストラリア等における科学技術イノベーション動向の調査研究をその活動の大きな柱の一つとする。たとえば,2024 年度には「台湾における半導体人材育成施策と実態」,「新興技術政策の国際動向とアジア・太平洋における国際協力」,「インドのスタートアップ・エコシステムとディープテック・スタートアップ振興策」,「韓国における主要大学と企業の協力動向」,「中国の先進各国との共同研究に関する近年の動向」などをテーマとする調査研究報告をまとめている。
ところで,「経済安全保障(economic security)」が日米欧で重要政策課題として広く受け止められるようになったのは,ごく最近のことである。米国を中心に見ると,トランプ第1 次政権時代の2017 年12 月に発表された「国家安全保障戦略」が中国,ロシアとの「戦略的競争」を初めて公式に「中核的な挑戦」と位置付け,2018 年8 月には議会で「国防権限法2019」が成立,輸出管理改革法(ECRA),外国投資リスク審査現代化法(FIRRMA)が制定され,政府調達規制が強化された。華為技術(ファーウェイ)ほかの中国企業がエンティティ・リストに掲載され,これら企業への先端半導体と製造装置の供給が禁止されたのはこれ以降のことであり,この規制は2022 年以降,さらに強化された。また,バイデン政権下,2021 年11 月に「インフラ投資・雇用法」,2022 年8 月にはCHIPS 法とインフレ抑制法(IRA)が成立し,「新しい産業戦略」が本格的に開始するとともに,2023 年4 月にはサリバン大統領補佐官(国家安全保障)が,産業戦略の一環として,国家安全保障に関わる基盤的・先端的技術については「小さな庭,高い塀(small yard, high fence)」を原則として厳格に管理する方針を示した。
「経済安全保障」への取り組みは,日本でも欧州でも,こうした米国の動きと軌を一にして進展した。日本では2020 年4 月に国家安全保障局(NSS)に経済班が設置され,2022 年5 月には「経済安全保障推進法」が成立した。また,2023 年3 月には,欧州連合のフォン・デア・ライエン欧州委員長が経済安全保障政策の狙いを「リスク低減(derisking)」(実際には中国リスク低減)という言葉で提示した。2023 年5 月のG7 広島サミットの共同声明の一つ,「経済的強靱性及び経済安全保障に関するG7 首脳声明」に見るとおり,これ以降,「デリスキング」は経済安全保障に関わる人材育成,科学技術,通商・投資,産業政策等を広く包含する政策課題となった。
こうした日米欧の動向は,本来,中国とロシアの動きに対応したものだった。これは2017 年の米国の「国家安全保障戦略」,さらにはそれに先立ち,国防分野における先端新興技術のスタートアップ育成を目的として設立された国防省「防衛イノベーション・ユニット(DIU:Defense Innovation Unit)」などが,中国,ロシアの通常戦力強化,2014 年のロシアのクリミア占領,2015 年の中国による南シナ海における人工島建設,「軍民融合発展戦略」の国家戦略への格上げ,製造業高度化を目指す「中国製造2025」に対応したものだったことを見ても明らかである。
しかし,これはあくまで日米欧から見れば,ということである。2010 年代半ばに始まった「大国間競争」は,地政学,経済安全保障,宇宙,グローバル・サウス関与など,それぞれの競争領域において固有の作用・反作用を促し,その結果,戦略的競争はそれ自体のダイナミズムを持って進展するようになっている。
本書は習近平指導下の中国がこの戦略的競争にいかに対応してきたか,これを特に経済安全保障,あるいはもっと具体的に言えば,産業政策,科学技術政策,米国の対中競争戦略への対応,国防科学技術イノベーション政策などの分野について概観し,さらにAI,戦略的新興産業,自動運転技術,NEV の個別ケースについて検討するものである。習近平政権は2015 年の「中国製造2025」を踏まえ,第13 次5 カ年計画(2016~2020 年)で産業高度化・イノベーションを重視する「質の高い発展」を目的として設定した。しかし,米中の戦略的競争の激化するなか,2020 年には「科学技術自立自強」を強調し,「双循環戦略」に転換した。これは「国内循環」において「製造強国」を掲げ,核心技術の内製化を追求し,「戦略的新興産業」育成を目指すとともに,「国際循環」においては,サプライチェーンの強靱性強化と「一帯一路」の質の高い発展を目指すものである。また,このプロセスで,「総体国家安全観」の対象も大きく拡大した。
それがいま,中国,日米欧,アジア・太平洋,さらには世界全体にさまざまの影響をもたらしている。たとえば,「戦略的新興産業」育成には,「新三様」(EV,太陽光パネル,リチウムイオン電池)産業の急成長と輸出拡大に見るように,大いに成功した分野もある。しかし,同時に,この「生産力」主義政策は過剰投資・過剰生産をもたらし,国内的には過当競争,国際的にはダンピング輸出と中国の国際的孤立,さらに米国の過剰消費と相まって,世界経済の深刻な不均衡を生み出している。同じことは中国企業の迂回生産・迂回輸出についても言える。本書がこうした戦略的競争のダイナミックスを理解する上で読者の参考となることを大いに願っている。
科学技術振興機構アジア・太平洋総合研究センター長
白石 隆
序章 中国の発展戦略転換とイノベーション
大西康雄
はじめに:本書で論じたいこと
科学技術振興機構アジア・太平洋総合研究センターでは,長年にわたり中国の科学技術・研究開発に関する情報収集と分析に注力してきており,2021 年度以降は,産業技術分野をケーススタディとしたイノベーションの現状フォローと分析を継続してきた(科学技術振興機構2022,2023,2024)。本書では,その問題意識を踏まえ,中国が経済を含む全体的な発展戦略を転換していることを考慮しつつ,改めて「中国におけるイノベーションの現在地」の確認を試みている。序章となる本章では,主として習近平政権以降(第13 次五カ年計画以降)における発展戦略の模索を概観し,続く各章の分析につなげたい。
イノベーションの重要性に着目した産業政策の背景には,労働力と資本の投入増加に依拠した経済発展方式が限界に達し,成長率が低下して,今後の成長をもたらす主動力を生産性向上(全要素生産性向上)に求めるしかなくなったことがある。「国家中長期科学技術発展計画綱要(2006~2020 年)」(2006 年制定)はこうした認識に基づき策定された産業政策の嚆矢である(Naughton2021)。
習近平政権(以下,習政権)は,同じ問題意識から発足以来一貫してイノベーション駆動による経済発展を指向し強調してきたが,その後,米国のトランプ政権(第1 期:2017~2021 年)との間で経済摩擦が発生,長期化し,しかもその本質が技術覇権を巡る角逐であることが日を追うにつれて明らかになるに至った。また,これは中国に限らないが,コロナ感染症流行により世界に張り巡らしたサプライチェーンが麻痺状態に陥った。
内外錯綜する課題に直面した習政権が,それに対応して第14 次五カ年計画(2021~2025 年)の柱の1 つとして提起したのが「双循環」(二重循環)戦略だと考えられる。その後習政権は,「質の高い」経済発展の具体化を求め,「自立自強」のイノベーションを重要視するようになった。「自立自強」とは自前での持続的発展可能性を意味している1)。これに加えて現行国家体制維持を最優先とする考え方=「総体国家安全観」2)が強調されることになったことから,研究開発方式,研究開発の主体・システム,人材教育などイノベーションのあらゆる側面が影響を受けるようになっている。
本章では,中国共産党の重要会議での議論や関連する政策文書,法律に基づき,イノベーションを分析軸としつつ,習政権の発展戦略の変遷と今後の展望を試みたい。なお習政権においては「全面的改革」=あらゆる分野における改革,が強調されるようになっていることから,発展戦略についても特に必要な場合を除き「経済」を冠さないこととする。
第1 節 発展戦略転換の模索
1. 1 第13 次五カ年計画
習政権は,その初の自前の五カ年計画3)である第13 次五カ年計画(2016~2020 年)において,「新しい発展理念」を打ち出した。発展戦略転換模索の始まりである。理念は,「革新」,「協調」,「グリーン」,「開放」,「共有」(中国語は「共享」で,ともに享受する,の意)の5 つであり,革新=イノベーションが第1 位に置かれていることが注目される。
同計画では,「イノベーションは,発展をリードする第一の動力である」とし,理論・制度・科学技術・文化の刷新等各方面のイノベーションを不断に推進し,イノベーションを全社会の盛んな風潮としなければならない,と述べている。当時の李克強首相が強調していた「大衆による起業,万人によるイノベーション」を盛り込んだものであり,イノベーションの主体を民間に求める考え方である。
(中略)
第6 節 各章への導入
ここで,続く各章のポイントを紹介しておきたい。当然のことながら本章で記してきた論点と重複しており,また,複数の章で産業技術政策のレビューを行っているが,それぞれの筆者がその問題意識や視点から議論を深めたものであり,また産業別のケーススタディを行っている。
第1 章(大橋英夫)は,習政権におけるイノベーションの実態を産業・科学技術政策の生成,発展のプロセスに沿って詳細に分析している。まず,本章で指摘した「新質生産力」が提起された背景から説き起こされる。同概念は,ポスト高度成長期の中国経済の現実,従来型の投資主導の経済発展の時代が終わり,「量」から「質」を求める時代に変化するなかでこれに対応する習政権の問題意識を示すものであることが明らかにされる。
次いで産業・科学技術政策の展開を跡づけていく。そこでは,国際比較の視点を交えながら,政策の規模や内容(補助金,信用供与,優遇税制,政府引導資金など多様で中国独自の形式を有するものが多い)の評価とともに他国の産業政策との相違点(独自性)が示されている。こうした独自性の具体的内容は,以下の各章でも紹介,分析されている。
また,「総体国家安全観」という中国独自の国家安全重視が政策をいかに変容させていったかについて一節をあて,国家安全と各分野の政策の連携ぶり,そこから看取される「自立自強」の論理が分析されるとともに,それが抱えている課題,今後の展望が試みられている。
第2 章(白尾隆行・北場林)は,習政権の基礎研究強化の実態とそれが科学技術の「自立自強」にどう資しているのかに焦点を当てる。第1 節では,習演説や重要政策文書から,習政権が「4 つの志向」(①世界の科学技術フロンティア,②経済の主戦場,③国家の需要,④人民の生活と健康)を考慮しつつ「2 本足のアプローチ」(目標指向型と自由な探索型)を同時に追求する方針をとっていることが示され,主要な基礎研究振興政策が整理される。
第2 節では,研究開発費の具体的動向が分析される。基礎研究費の比率や企業・大学・公的機関別の負担比率が統計的に示され,国際的に比較される。当該分野での中国の追い上げは急ピッチであることが確認できる。
第3 節では,研究開発人材の現状が分析される。中国が大量の人材を育成していることが統計で示される。なお,厳しい対中政策のもとでも米国で理系博士号を取得する人材数で中国は突出した1 位であり,彼らが米国の研究開発を支えていることは容易に想像できる。米中対立のこうした一面も理解しておく必要があろう。
第4 節では,大学,研究機関,地方政府の研究開発費支出の実態紹介が,第5 節では,研究資金制度の特徴と資金配分機関による基礎研究資金支出の分析が行われている。中国式の「基盤的経費」と「競争的研究費」の二大カテゴリーで資金配分が行われているが,こうした資金供給の多元化・柔軟化が研究成果に結びつくためには課題が残されていると指摘されている。
第3 章(伊藤信悟)は,米中の経済摩擦の本質を「ハイテク競争(覇権争い)」だとし,両国の対応(闘い方)を分析している。第1 に,米国の対中国認識は,米国にとっての「唯一最大の競争相手」であるというものである。対応方針の基本は,米国内投資拡大と対中交流規制の併用であり,これは,トランプ政権第2 期においても変わらない。確実なのは対中圧力が強化されることであり,結果として両国関係の不確実性が高まることが予想される。
第2 に,中国の対応である。中国の対米認識は,国際情勢認識と自己認識の上に構築されている。すなわち,現状は「100 年に1 度の世界の局面の大きな変化」の時期にあり,米国を含む西洋の衰退のなか中国を含む東洋は興隆のチャンスがある。ただし,米国は混乱をもたらす源となっており,中国は米国の諸措置に粘り強く対応していく必要がある,というものである。
第3 には,中国の対抗策の効果と限界が論じられる。中国は,上記した当面の対応策をとりつつ中期的目標として「自立自強」型の経済,すなわち自己制御可能な産業チェーン,サプライチェーンを備えること,長期的には「科学技術強国」となることを目指している。現状を評価すると,「新三様」(新三大輸出製品)が示すように,国際競争力を備えた産業が勃興しているが,それだけでは不足であり,真の「自立自強」を獲得するためには「0 から1 を産むイノベーション」力を獲得しなければならないと指摘される。
第4 章(飯田将史)は,国防分野の科学技術イノベーションの実態について,現在展開されているさまざまな議論,政策に基づいて明らかにしようと試みている。第1 に,国防科学技術イノベーションの方向性は「新興領域の戦闘的能力を全面的に高める」ことである。新興領域としては,海洋,航空宇宙,ネットワーク空間,人工知能,バイオ,新エネルギーがあげられている。そして,これらの領域で戦略的能力を建設するためには,「新質生産力」と「新質戦闘力」の効率的な融合と相互の牽引作用を促進すべきである,とされる。
第2 には,国防科学技術イノベーションを推進する政策が分析される。基本となるのは「軍民融合」である。国家の主導下で,民間の企業・大学・研究機関などに存在する先端的科学技術や資金,人材などを軍事建設に動員することがその内容であり,中央レベルにおける指導機関「中央軍民融合発展委員会」(2017 年1 月設立。主任は習主席)のもとでのトップダウン方式の体制である。この体制下で,国家が所有・運営する資源,設備などの民間との共有,軍と民間による協同のイノベーション推進,軍と民間の各種標準の統一,などが推進され,併せて必要な人材の育成が重視されてきたことが確認される。
第3 には,中国軍の新しい作戦構想が分析される。それは現代の戦争形態が「智能化戦争」に向かうことを想定したものであり,情報通信技術と人工知能技術のイノベーションが武器・装備や作戦運用に応用され,作戦領域が拡大し,領域を超えた作戦が実行される,というものである。こうした「智能化戦争」のケースとして,ロシアによるウクライナ侵攻の戦訓を踏まえたドローンを用いた軍事作戦構想が紹介されている。
第5 章(金堅敏)は,第1 に,米国などを中心に発生した「チャイナショック」の内実の解明を手掛かりに,中国のイノベーション能力の実態分析を試みている。「チャイナショック」にはバージョンがあり,最初の「1.0」段階で米国の対中輸入が急増した際(1995~2010 年頃)の中国の優位性は,労働集約的産業における人件費コスト優位や改革開放政策による全般的な生産性向上に基づいていた。
それが,「2.0」(2020 年代~)になると,中国の特異な産業政策が注目されるようになっている。すなわち,経済低迷の打開策として輸出拡大が重視され,優位性をもつ製品(「新三様」)を中心に支援策が実施されたこと,国家安全保障最重視の立場から,半導体,産業用ロボット等の産業支援が強化されたこと,がその例である。
第2 に,以上の整理を踏まえつつ,産業高度化政策,産業競争力,企業のイノベーション能力についての分析を行っている。この部分は,第1 章の分析と結論を一にしているが,新たに国際的比較を可能とするさまざまなインデックスを用いて,産業・企業の現場により近い視点からの分析がなされている。
第3 に,ケーススタディとしてAI 産業を取り上げ,その競争力と可能性を分析している。当該産業では,ディープシーク社の例にみられるように,世界水準の破壊的イノベーションが出現して世界を驚かせたことが記憶に新しい。しかし,子細にみれば,投資環境・市場や人材育成やイノベーション成果の産業化等において,米国にはまだ一日の長がある。また,米国などによる半導体規制によるコンピューティング能力の制約,生成AI 応用人材の欠如,新規事業に関する規制環境の不安定性・予測不可能性,などが重大な課題として指摘されている。
第6 章(張紅詠)では,歴次の五カ年計画と産業政策の変遷を振り返りながら,特に2010 年の「戦略的新興産業」指定,2015 年の「中国製造2025」提示以降における政策の展開を跡づけ,その効果の客観的評価を試みている。
両施策ともに,優先的に発展をはかる産業を指定し,そこに補助金などの政策支援を集中する手法がとられた。それらの政策効果を計るために,直接的な財政支援,規制緩和,政府調達での優遇などの具体策を確認し,対象産業にもたらした効果については,「R&D 集約度」(R&D 支出/売上高),発明特許件数(有効発明特許件数/売上高)といった指標で定量的な分析が行われている。いずれも目標を上回る成果をあげていることが示されている。ただし,労働生産性の上昇目標については,未達成であり,効果が低い。
また,産業政策にはメリット=効果だけではなく,デメリットも存在することを意識する必要がある。たとえば,産業政策(=政府の介入)が資源の非効率な配分をもたらすことである。政府の補助金が投入された産業で,企業間格差が拡大した例がある。
本章では,さらに造船業とロボット産業のケーススタディを行い,産業政策の実態の具体的分析が試みられている。産業政策の今後の方向としては,①技術革新の深化を推進し,ターゲット産業で基礎研究と産業応用を両立させる,②補助金政策を見直し,競争を促進するような政府支援を優先する,③国際協調を推進し,先進国との技術協力を模索する,④地域の産業クラスターを活用し,持続的成長を促す,ことが必要だとしている。
第7 章(丸川知雄)は,中国における自動運転技術の開発と社会実装の現状について,同分野における政策の概要を確認したうえで,北京市,大連市,上海市などでの筆者の実体験に基づき報告している。
中国は,「一定条件下での自動運転が可能」という「レベル4」の実用化を目標しており,システムとしては,自動車が他の自動車や道路側の機器などと通信しながら動くICV(インテリジェント・コネクテッド・ヴィークル)の実証実験が進んでいる。実施主体をみると,基本戦略・法規を中央政府が定め,インフラ建設を含む実証実験・普及は地方政府が担う体制である。
技術開発主体である企業には,百度といったIT 大企業もいるが,自動車・建機等の大手メーカーと提携した小馬智行,文遠知行等のスタートアップ企業が主力をなしている。中国政府は,実証実験を積んだ企業に自動運転の営業許可を出す準備をしていると報じられているが,開発企業の先行きも含め不確定要因が残されている。
第8 章(高口康太)は,中国のNEV(新エネルギー車)産業政策を分析している。第1 節では,NEV 産業政策の歴史的展開が詳細に検討される。同政策の淵源は第8 次五カ年計画(1991~1995 年)に求めることができ,第10 五カ年計画(2001~2005 年)で多額の資金が投入されている,との指摘は興味深い。
同政策の本格的スタートは2009 年のことであり,その柱は,①「市場規模の目標」(設定),②「購入補助金と減税」,③「ダブルクレジット制度」,④「充電インフラの整備」,の4 つである。①は計画経済的手法であり,「省エネ・NEV 産業発展計画」で示された。②は,政策手段の中核をなす。公費投入により需要を喚起してNEV 普及を進めるという産業育成策である。③は,自動車メーカーに対してNEV 製造を強く促す施策である。内燃機関車メーカーはNEV 製造を拡大するか,NEV メーカーから「クレジット」を購入することが必要となる。さらに④で並行してインフラ整備を進めるとしており,NEV 産業政策はフルセット型である。
実際の政策実施過程では,本節冒頭に記されているような政策の不備を突く問題が次々と発生し,「NEV 冬の時代」と呼ばれる局面すらあったが,第2 節で分析されているように,2020 年のテスラの参入や独自のイノベーションもあってNEV 産業は飛躍を遂げる。この部分の記述は,長年にわたり何度も現場に足を運んでいる筆者ならではのものであり,示唆に富んでいる。
中国製NEV が世界市場を獲得するには多くの困難が待ち受けるが,本章が示すように,産業基盤を確立しつつある同産業の今後からは目が離せないところである。
(以下、本文つづく)