あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
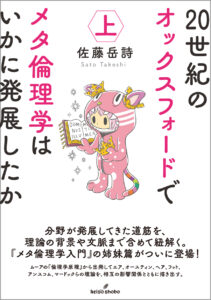

佐藤岳詩 著
『20世紀のオックスフォードでメタ倫理学はいかに発展したか(上・下)』
→〈〈「はしがき」(上巻)・〈「あとがき」(下巻)(pdfファイルへのリンク)〉
→目次・書誌情報はこちら:〈上巻〉・〈下巻〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「はしがき」「あとがき」本文はサンプル画像の下に続いています。
はしがき
本書(以下、上下巻を合わせて本書と呼ぶ)の目的は、第一に、二十世紀のイギリス、特にオックスフォードの地で「メタ倫理学(meta-ethics)」が発展してきた道筋を、G・E・ムーアが一九〇三年に出版した『倫理学原理』から現代までたどり直すことで、この間、英国の道徳哲学者たちはメタ倫理学において何を明らかにしようとして、何を論じてきたのか、そこで言われるメタ倫理学とは何なのか、ということの輪郭を描き出すことである。そして第二に、そこで抉出されたものと、その後の道徳哲学者たちの考え、そして特に読者自身の考えとを対比しながら相対化して捉え直すことを通じて、各自が自分自身のメタ倫理学上のスタンスについてより深く考えていくための手がかりを示すことである。
メタ倫理学とは
規範倫理学としばしば対比されるメタ倫理学は、前者が「現実のこの場面で私たちはいったい何をなすべきか」ということに具体的に答え、善悪の基準を示そうとする一階の倫理学であるのに対し、そもそもそこで言われている「「べき」とは何か」「「善」とは何か」を問う二階の倫理学であるとされる。メタ倫理学とは何か、ということも本書全体で問われる事柄の一つではあるのだが、暫定的な定義を述べておくとすれば以下のようになる。
道徳的・倫理的な営み(見方、思考、判断、行為、生活、生き方など)について、そこで使われている概念やその意味、前提されている事柄を明晰化したり、それらを成り立たせている世界、それらの営みに従事する私たち、さらに両者のかかわり合いについての事実を明らかにしたり、それらの事実についての理解を改善したりしようとする試み。
たとえば、私たちは道徳的・倫理的な営みにおいて、何が善いとか、正しいとかいう判断をすることがあるが、そこで使われている善という概念は何を意味しているのだろうか。また、私たちは何のためにそのような判断をするのだろうか。そうした判断は客観的な正解をもつようなものでありうるのか。そうした判断に私たちは何を期待しているのか。道徳は私たちにとって必要なものなのか。
メタ倫理学はこうした問いに答えようとして様々な議論を積み重ね、その際、認識論や意味論、形而上学などの伝統的な哲学の議論、あるいは心理学や社会学、生物学などの知見も活用してきた。これらは、規範倫理学的な問い――すなわち、典型的にはどんな行為が正しい行為かを尋ね、それに対して、「自らの立てた義務に従うこと」「最大多数の最大幸福をもたらすこと」「有徳な人がなすこと」などといった仕方で答えが与えられるような問い――とは異なっており、そうした問いが前提にする事柄を問題にしている。
メタ倫理学の二つのレベル
さて、本書で取り上げたいメタ倫理学の営みには二つのレベルがある。⑴道徳的概念にかかわるレベルと、⑵倫理学そのものにかかわるレベルである(以下、便宜上、それぞれを第一のレベル、第二のレベルと呼ぶことがある)。
⑴道徳的概念にかかわるものとしてのメタ倫理学
第一に、メタ倫理学は道徳的概念や性質、事実と言われるものの在り方の解明にかかわる。予め述べておくと、この百年の主流のメタ倫理学はおおよそ三つの立場に分類できると言われる。自然主義実在論、非自然主義実在論、反実在論である。
大雑把に言えば、ここで言う自然主義実在論は、道徳的な性質や事実はそれ自体が自然的な性質や事実であるか、それらに還元できるか、それらと同一であるか、もしくは別の自然的性質から必然的に導出できるとする立場である。伝統的には善と快を同一視する古典的功利主義が自然主義を前提にしていると言われることが多いが、性格特性としての徳を倫理学の中心に据える徳倫理学の多くもこの立場をベースにするものであり、本書で登場する自然主義はアリストテレス主義と重なるところも多い。
非自然主義実在論は、道徳的性質や道徳的事実は、自然的性質や事実ではなく、自然的性質や事実に還元することもできない、とする立場であり、プラトン主義に淵源をもつ。たとえば、先に挙げたムーアは、善は善であり、他の語で言い換えたり説明したりすることはできないと論じた。ほかにも義務や理由といったものが、還元不可能な道徳的(規範的)概念であると言われることがある。またその際、こうした性質や事実に言及する命題の真偽は、しばしば直観によって捉えられると主張される。
自然主義と非自然主義はいずれも何らかの意味で道徳的性質や事実が存在する、と主張する点で実在論と言われる立場であるのに対し、三つ目の反実在論は、そのようなものは存在しないと主張する立場で、根をたどればD・ヒュームやI・カントなどに関係づけられることが多い。典型的な反実在論的立場の一つである情動主義によれば、道徳的性質や事実は存在せず、善や悪は私たちの道徳的な感情や態度から説明される。私たちは何かを善いと呼ぶことで、自分たちの肯定的な態度を表現し、逆に何かを悪いと呼ぶことで否定的な態度を表現している、というわけである。
イギリスのメタ倫理学の歴史は、これらの三つの立場がお互いにぶつかり合いながら、それぞれに自分の主張を洗練させようとする過程だと考えることもできる。ただし、論争の中でそれぞれの立場は相手の良いところを取り入れようともするため、いつでも三者は明確に切り分けられるわけではなく、その主張は要所要所で入り交じっている。また、後の世代が常に前の世代よりも優れた理論を提出しているか、といえば必ずしもそうとは言えないところもある。
⑵倫理学そのものにかかわるものとしてのメタ倫理学
メタ倫理学には、こうした道徳的概念をめぐる議論とは別の位相にある議論もある。それは、そもそも倫理学はどのようなものであるか、どのようなものであるべきか、という倫理学そのものの在り方やその役割を問うレベルである。たとえば、倫理学とはしばしば「いかに生きるべきか」を問う学問だと言われるが、「この私はいかに生きるべきか」と「人(一般)はいかに生きるべきか」とでは、問いの意味もそれに対する答えも変わってくる。さらに、現代倫理学はしばしば価値観が衝突するいわゆるモラルジレンマの状況での「私はどちらを選ぶべきか」という問いに見られるような、個別の行為選択の場面を主たる問いの領域に設定してきたが、そうではなく、「私はどんな人になるべきか」とか、「正義に適った社会とはどのような社会か」と問うこともできる。倫理学とは何をどんな仕方で問う学であるべきなのか。これについても、ムーア以来の道徳哲学者たちは様々な答えを提案してきた。
また、この節の最初に、メタ倫理学は規範倫理学と対比されると述べたが、そもそも両者の関係はどのようなものであるか、あるいは、どのようなものであるべきか、ということもまた、このレベルでの議論に含まれる。一方には、メタ倫理学は規範倫理学からまったく独立に営まれる学問であるという考え方があり、他方には、両者を独立に展開することはできないという考え方がある。これらは、規範倫理学とは何か、メタ倫理学とはどのようなものであるかという理解抜きには成り立たず、本来はメタメタ倫理学と呼ばれるべきかもしれないような議論であるが、これもまた、メタ倫理学の中で論じられてきた問いである。
このように、メタ倫理学には二つの異なるレベルがあるが、両者は相互に関係し合ってもいる。たとえば、道徳的性質が行為のもつ性質であるなら、倫理学の問いが行為の是非に集中するのも自然である。他方、道徳的性質が社会のもつ性質であるなら、社会とは何か、というところから倫理学は出発する必要があるだろう。逆に、倫理学とは人の生き方を問うものであるなら、そこで焦点化される性質は、個別の行為の善し悪しよりも、もっと長い目で見た人の在り方であるかもしれない。
本書では、メタ倫理学がもつこれらの両位相を意識しながら、二十世紀のイギリス、特にオックスフォード大学において、メタ倫理学が様々な仕方で展開されてきた歴史を追いかけていく。これを通じて、冒頭に掲げたように、メタ倫理学において道徳哲学者たちはどんな背景のもとで何をしてきたのか、ということを、可能な限り明らかにしていきたい。
本書の方針
続いて、本書の方針について簡単に述べておきたい。基本的には世代で章を区切り、それぞれの章で数人の哲学者とその理論を紹介している。各章や節の冒頭では、時代状況を説明し、次いで、哲学者個人のバイオグラフィーを、なるべく他の研究者との関係性が分かるような仕方で記した。それぞれの章の最後には、取り上げた諸理論の対比、それぞれに対する批判や筆者による評価を盛り込んだ節を付した。以下に、本書で取り上げる道徳哲学者たちがどんな問いを立てたのか、ということを示しておきたい。第一章から第四章が上巻、第五章から第七章が下巻である。
第一章 「倫理学と直観」
この章で取り上げるムーア、H・A・プリチャード、W・D・ロスらは、一八七〇年代生まれで、前の世代であるH・シジウィックやT・H・グリーン、F・H・ブラッドリーらを批判対象としつつ、倫理学においてもっとも基礎的な概念とは何かを問い、さらに、それらを問う方法について論じる中で、倫理学とは何をどのように問うべきものか、ということを探究した。その際、「直観」が重要視され、それにともなって直観とは何か、それによって分かること、分からないことは何か、ということも論じられた。
第二章 「倫理学と言語行為」
この章で取り上げるA・J・エアとJ・L・オースティンは、一九一〇年前後の生まれで、ムーアらよりさかのぼって倫理学の意義そのものについて問うた。彼らは道徳の営みを言語行為の側面から捉え、道徳的発話とは何をすることなのかと問い、それが他の発話とどう違うのか、あるいは同じなのか、ということを論じた。特に、ここでは道徳判断は直観に基づいて道徳的命題の真偽を示すことではなく、主観的な態度や感情を表現することなのではないか、ということが論点となった。
第三章 「倫理学と道徳判断」
この章で取り上げるR・M・ヘアとP・フットは、一九二〇年前後の生まれで、戦争の体験を経て、倫理学が果たすべき役割を再考した。そして、道徳判断は発話者の主観的な態度の表現に過ぎないというエアらによる議論と正面から対峙し、言語の分析という枠組みにこだわりながら、道徳判断の客観性を追い求めた。そこでは、直観ではなく、理性や徳の役割が重視され、それらを通じてあらためて善とは何か、善が倫理学において占めるべき位置とは何かが問い直されることとなった。
第四章 「道徳判断を超えて」
この章で取り上げるG・E・M・アンスコムとI・マードックは、ヘアと同年の生まれだが、彼とは違って、既存の倫理学の外側から問いを立てた。たとえば「善い行為とは何か」を論じるなら、善だけではなく「行為」とは何か、さらにはその行為を駆動する心理学も論じられねばならないのではないか。あるいは、概念や言語のレベルではなく、存在のレベル、形而上学のレベルでも道徳は論じられる必要があるのではないか。これらを通じて、彼女たちは単なるモラルジレンマの解決とは異なる観点で倫理学を論じる可能性を問うた。
第五章 「道徳を超えて」
この章で取り上げるB・ウィリアムズは、一九二九年生まれで、ヘア世代の議論を総括し、倫理学あるいは哲学には何ができて、何ができないのか、を問うた。それらの限界を見定めた上で、「人はいかに生きるべきか」という問いに私たちはどうすれば答えることができるのかを問うことが、彼を動かした最大のテーマであった。
第六章 「再び、倫理学と道徳判断」
この章で主として取り上げる、J・マクダウェル、S・ブラックバーンは一九四〇年代の生まれである。彼らは前の世代、中でもJ・L・マッキーとD・ウィギンズの問題意識を引き継ぎ、道徳判断は客観的かというよりも、そもそも道徳判断が客観的であるとはどういうことかを問うた。価値や真理が世界のうちに実在しない限り、道徳判断は客観的でありえないのか、感情や態度が関係する道徳判断はすべて主観的なのか、ということを彼らは論じた。
第七章 「再び、倫理学と直観」
最終章で取り上げるD・パーフィットは一九四二年の生まれで、ブラックバーンらと同世代である。彼はブラックバーンらとは逆に、道徳判断から態度や感情の要素を徹底的に排除した形で、道徳判断を理解する可能性を問うた。そこでは倫理学におけるもっとも基礎的なものをめぐって、価値と理由の関係が論じられ、そしてそれらを理解するために、再び、直観という手法に焦点が当てられた。
こうした問題のいずれか(あるいはすべて)に関心がある方は、本書と共にメタ倫理学の歴史をたどり、メタ倫理学とは何なのか、自分のメタ倫理学上のスタンスとはどんなものなのか、という問いに解答することを試みてほしい。そして、それを通じてあらためて、自分自身にとって道徳的な問題とは何なのかについて考えてみてほしいと思う。
(注は割愛しました)
あとがき
下巻のあとがきである。謝辞は上巻のあとがきで記したため、ここでは割愛するが、本巻も多くの人びとのおかげで刊行の運びとなった。あらためて心より感謝を申し上げる。
上巻のあとがきで予告したとおり、ここでは本書の成り立ちについて簡単に述べておきたい。遡ること二十数年前、筆者の学部卒業論文はヘアを主題とするものであった。以来、最初の学術論文もヘアとウィリアムズに関するものであり、博士論文もヘアについて書き、最初に出版した書籍もそれを改稿したものであった。その後、さすがにヘア一辺倒から離れるべきだと感じ、十年ほど前からヘアと同時代のアンスコム、マードック、フットについて真剣に研究を始めた。後にして思えば、博士論文を書いた段階では、フットらのヘア批判の重要性などはまるで理解できていなかった。この段に至ってようやく、彼女らが何を言いたかったのかが朧げに掴めてきた。それによって、ヘアのこともまた別の角度から見られるようになり、新しい面白さが見えてきたのだった。
そうした自分自身の経験から、この時代のメタ倫理学に関心がある人びとが、少し違った角度からそれらを見る一つの契機を提供できればと考え、あるいはそもそもそれらをまったく知らない人にも少しでも関心をもってもらえればと考え、本書の執筆を開始した。当初は、ヘア、フット、アンスコム、マードックという一九一九年生まれ(フットは一九二〇年)の四人についてのみ書くつもりであった。しかし、構想を進める中で、彼・彼女らをそこに立たせたものが何であったのか、そして彼・彼女らが遺したものがその後どうなったのか、という点も知ってもらいたいと思いはじめ、結果として、ムーアからパーフィットまで、という構成になった。当然ながら字数は天井知らずに増え、分厚い一冊とするか、二分冊とするか、ということで編集担当の土井美智子さんの頭を大いに悩ませてしまうことになった。本当に申し訳ないと思うと同時に、最後まで根気強く伴走してくださったことに、深く感謝している。
通史のような形式での執筆は今回が初めてで、膨大な情報の取捨選択には、これまでにない苦労がともなった。自叙伝やインタビューなどで語られるエピソードは興味深いが、それなりに書き手・語り手・聞き手のバイアスがかかったものでもあり、どれを採用するか悩むところもあった。さらに、尊敬する研究者の先輩があるときに「あたかもこれが唯一の正史であるかのような哲学史を書いて人びとの見方を固定してしまうことには反対だ」と語っていたため、それに対する応答(言い訳)も考えながら執筆を進めるはめにもなった。
結果として、筆者の中で落ち着いたのは、これぞという哲学史を書くというよりも、上述のように、メタ倫理学の発展史の中で、自分が面白いと感じている一側面を切り取ると割り切って紹介するという方針であった。そもそもメタ倫理学の完璧な歴史を書くためには、オックスフォードに注目するだけでは足りず、その他のイギリス各地はもちろん、アメリカの議論もしっかりと記述せねばならないのは明らかである。注での説明に留めざるをえなかった哲学者たちもそれぞれに欠かせない役割を担っている。特に、ウィトゲンシュタインはヘア世代を中心に本書の登場メンバーの多くに絶大な影響を与えているため、本編で取り上げるかどうかかなり悩んだが、結局、力量の限界から断念した。また、伝記的な部分についてはなかなか一次資料にあたる機会がなく(ボドリアン図書館の深部には彼らの残したメモや未刊行の原稿のアーカイブが眠っているという)、多くがそれらを利用して書かれた伝記や評伝、会員の没後に英国学士院が発行する弔文、晩年の回想などに頼らざるをえなかった。哲学史を専門とする研究者諸氏から見れば、不満も多々あろうかと思うが、こうした点については今後の課題とさせていただきたい。
ただ、二十世紀が終わってから四半世紀が過ぎ、当時を振り返る文献の充実ぶりには本当に目を見張るものがある。個人の伝記・評伝では先頃邦訳が出版されたパーフィットのものをはじめとして、オースティン、マードックのものがあり、ムーア、エア、ヘアは自叙伝が残っている。本書では名前だけの登場となったが、ケインズ、バーリン、メアリー・ウォーノックやケニーらの評伝・自叙伝も当時の雰囲気をよく伝えてくれている。複数人を扱ったものとしては、アンスコム、フット、マードックにミッジリーを加えたオックスフォード・カルテットを扱った二冊(『オックスフォードの女性哲学者たち』、The Women are Up To Something)が出色の作品である。これらの充実した文献がなければ本書は単に学説を羅列するだけのものになっていた可能性も否めない(もちろん、そうした著作も重要である。哲学者たちの生きた背景を知ることの意義についてはマックール&ワイズマン『オックスフォードの女性哲学者たち』(木下頌子訳、青土社、二〇二五年)の解説で述べたので、そちらも参照していただきたい)。
また、本書の執筆にあたっては、日本で先人たちが連綿と紡いできたメタ倫理学研究の営みにも触れることになった。一九五〇年代後半にはすでに、「メタ倫理学」という言葉がいくつかの論文で使われており、プリチャードやロスの論文が含まれたホスパース編の『現代英米の倫理学』の翻訳も始まっている。その後も、決して倫理学のメジャー分野とは言えないものの、大陸系倫理学や規範倫理学研究のかげに隠れながら、その探究の系譜は脈々と受け継がれてきた。本書で取り上げた哲学者たちの主要著作もそのほとんどが翻訳されている。こうした先人たちの営みに最大限の敬意を表するとともに、本書が、彼・彼女らの積み上げてきてくれたものを次の世代へと受け渡していく一助となることを、心から祈るばかりである。
最後に、なぜ二十世紀のオックスフォードなのか。これは本書の草稿を読んでもらった際、研究者仲間の一人から問われたことでもある。メタ倫理学の最新の理論を知りたいのであれば、地域を問わず二十一世紀の文献を読むべきであるし、哲学的に定評のあるアイディアを得たいのであれば、古代以来の古典に目を向けるべきであろう。なぜ今更、この時代、この場所に目をやる必要があるのか。研究資料の充実、現代の理論との接続、未解決の問題、と様々なそれらしい理由を挙げることはできるだろう。特に、第二次大戦や社会構造の大きな変革を経験したオックスフォードの道徳哲学は、単に理論上の関心を刺激することを超えて、現代の様々な深刻な倫理的・社会的課題を考えるための示唆を与えてくれる。しかし、結局のところ、私にとって最後に残るものはどうしても、この時代、この場所、そこで生きた哲学者たち、そして彼・彼女らの議論が面白いから、ということに尽きてしまう。八百年以上もの間、学問の営みを見守ってきた街。そこで真理の探究に人生をかけた多くの研究者たち。彼・彼女らが倫理というただ一つの主題をめぐって繰り広げた数多の議論。それゆえに、上巻のあとがきと同じ言葉をもって、下巻のあとがきも終えることとしたい。本書を通じて、皆さんに少しでもオックスフォードの倫理学を面白いと思ってもらえたなら、それに優る喜びはない。
二〇二五年七月
佐藤岳詩













