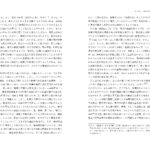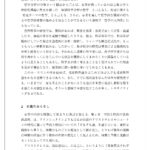あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
 ティム・モードリン 著
ティム・モードリン 著
ジミー・エイムズ 監訳/谷村省吾 解説
『物理学の哲学入門Ⅰ 空間と時間』
→〈「訳者まえがき」「はじめに」「解説」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。本文はサンプル画像の下に続いています。
訳者まえがき
本書は、Tim Maudlin, Philosophy of Physics: Space and Time(Princeton University Press, 2012)の翻訳である。全2 巻のうちの第1 巻であり、2 冊あわせて「物理学の哲学」と呼ばれる分野の主要なトピックを概観できる入門書となっている。第1 巻に当たる本書は、「空間と時間」を主題としており、現代物理学の標準的な時空の理論である相対性理論と、その前身であるニュートン物理学において、空間・時間がどのような構造を持つものとして定式化されているか、そしてその根底にはどのような哲学的な問題や論争が控えているかが解説されている。第2 巻に当たるPhilosophy of Physics: Quantum Theory(Princeton University Press, 2019)は、その表題の通り「量子論」を主題としており、標準的ないわゆる「コペンハーゲン解釈」に代わる量子物理学の理論がいくつか取り上げられている。
もちろん、物理学の哲学において研究されているトピックは、決して空間・時間と量子論に限定されているわけではない。熱力学・統計力学や物性物理学も、時間の不可逆性や創発といったさまざまな哲学的問題を内包しており、物理学の哲学者によって盛んに研究されているが、これらのトピックは第1 巻、第2 巻いずれでも扱われていない。また、量子重力も物理学の哲学で研究されているトピックの一つであるが、入門書には適さないため、これも扱われていない(相対論的な場の量子論については、第2 巻で一章が割かれている)。したがって、本書と続巻をあわせても決して「物理学の哲学」と呼ばれる分野を網羅するものではないが、現代物理学の二本の柱である相対論と量子論を入り口として、この分野に特有の問題意識の持ち方や手法を学べる本である。
本書の著者のティム・モードリンは、物理学の哲学の第一人者である。本書の他には、物理学をベースに伝統的な形而上学の問題にアプローチする論考を集めた論文集『物理学の中の形而上学』(Maudlin 2007)や、ベルの定理によって提起される非局所性の問題を論じる『量子の非局所性と相対論現代物理学が暗示する形而上学』(Maudlin 2011)などで知られている。モードリンは、語り口の明晰さもさることながら、分析の鋭さと視点のユニークさが際立つ哲学者である。本書でもこれらの特性は存分に発揮されており、特に双子のパラドックスの議論(第4 章)や、抽象的ブーストと物理的ブーストの議論(第5 章)は刮目に値する。本書は数式をなるべく使わず、物理と数学を明晰な言葉で概念的に説明しているが、議論のレベルの高さや話題の選び方において、巷の啓蒙書とは一線を画す本格的な入門書であると言える。また、入門書にありがちな「中立的」なスタンスを取らず、あえて著者自身の見解を前面に出した論争的なスタイルで書かれているのも、本書の特徴の一つである。その点でも、著者に同意するにせよしないにせよ、思考を触発する刺激的な本である。
物理学の哲学は日本ではまだなじみが薄く、物理学者からは誤解されることも少なくないが、本書の日本語訳の刊行によってこの状況が少しでも改善されるならば、訳者としては本望である。本訳書には、物理学者の立場から見た本書の議論の特徴や注目すべきポイントについて、谷村省吾さんに解説をいただいている。この解説は、科学哲学の本を読み慣れていない読者にとって有益な道案内になるのではないかと思う。お忙しい中、このような入念な解説を準備してくださった谷村さんには深く感謝したい。
本書の日本語訳を刊行することになった経緯について少し触れておきたい。もともとは、2022 年1 月に、私(ジミー・エイムズ)がTwitter(現X)上で、本書の日本語訳が望まれる旨の発言をし、それが植原亮さんの目にとまったのがきっかけである。植原さんは勁草書房に企画を持ち込んでくださり、翻訳プロジェクトが始まった。2022 年から2 年近くにわたって、訳者陣(植原さん、北島雄一郎さん、森田邦久さん、佐藤頼子さん、藤田翔さん、高橋和孝さん、そして私)でオンラインの翻訳検討会を定期的に実施し、訳文についてディスカッションを重ねてきた。そのため、本書は章ごとに分担者を決めて訳しているが、訳者全員で訳文をチェック・修正しており、どの章についても担当者以外の訳者も多大に貢献してくださっている。このような骨の折れる作業に長きにわたって付き合っていただき、訳者の皆さまには深く感謝申し上げる。
また、勁草書房の鈴木クニエさんは、私の個人的な事情により翻訳原稿の完成が当初の予定より大幅に遅れてしまったにもかかわらず、辛抱強く原稿を待ってくださった。さらに、それにとどまらず翻訳の細部にいたるまでさまざまな助言を下さり、本書を完成まで導いていただいた。訳者一同を代表して、心から感謝申し上げる。
2025年2月13日
ジミー・エイムズ
はじめに 本書の目的と構成
「物理学の哲学」は、物理的実在全体をなるべく一般的に考察する。たとえば、物理的世界は空間的、時間的な側面があるようにみえるので、空間と時間(もしくは時空)の存在と本性は中心的な話題となる。物質、つまり、テーブル、椅子や惑星を構成する種類についても、同様に中心的な話題となる。「なるべく一般的に」という表現で私は次のようなことを意図している。物質に関してわれわれが問うことができる最も一般的な問いは、それはどのような種類なのかということである。たとえば、物質が点のような粒子から構成されているとか、場から構成されているとか、1 次元の弦から構成されているとか、それらの組み合わせから構成されているとか、もしくはまったく違うものから構成されていると主張するかもしれない。このような一般的な説明の中の何か一つをもとに、より具体的な次のような問いが出てくる。何種類の場が存在するのか、粒子の質量はいくらなのか。ここでは、より具体的な問いではなく、最も一般的な問いに取り組む。
物理学の哲学は、学問分野として、物理学そのものと連続的である。ここで問いかける種類の問いは、物理学者が問いかける問いに含まれ、過去に物理理論が答えようとしてきた問いにも含まれる。しかし、物理学の驚くほど多くの部分は、こうした問いに答えることなく進むことができる。たとえば、熱力学という科学は、その名前が示しているように、当初は、熱がある物体の中をどのように伝わるのか、そして一方の物体からもう一方の物体へどのように伝わるのかについて、正確に数学的に説明することを目的としていた。しかし、熱の流れを決定するきわめて詳細な方程式を発見することができても、熱とは何かについての説明は得られない。(熱素説が主張するように)文字通り物体から別の物体へ流れるある種の流体なのだろうか、それとも(気体分子運動論が主張するように)ある物体から他の物体へ相互作用を通して伝えられるある種の運動なのだろうか。もし、華氏200 度〔摂氏約93 度〕、20 ポンド〔約9 kg〕の鉄の棒を、華氏50 度〔摂氏10 度〕の大きな水槽につけて華氏100 度〔摂氏約38 度〕まで冷やすのにどれくらい時間がかかるのかということだけを考えるのであれば、熱の流れの方程式によって答えることができる。しかし、答えを計算しても、熱の基本的な本性に関しては何も得ることはない。製鉄工は熱の本性を気にしないかもしれないし、物理学の哲学者も同じように、鉄が冷めるまでにかかる正確な時間をほとんど気にしないかもしれない。現場の物理学者は一般に両方とも関心があるが、時には一方に集中して取り組み、時には他方に集中して取り組む。現代の物理学教育における特徴は、熱の本性、時間と空間の本性、物質の本性にかかわるような「哲学的」な問いを議論するよりも、製鉄工のために方程式を解いて実用的な答えを得る方法を学ぶことにより時間を費やすことである。こうしたさらに基礎的な問いにひきつけられた物理学徒は、そのような問いに取り組まない物理学の授業に失望することがある。本書は物理的実在に興味を持つ哲学者のみならず、そのような物理学徒のためにも書かれている。
本書では、物理学の哲学は3 部に分けられ、2 巻にわたっている。それぞれの巻は互いに独立して読むことができる。しかし、いくつかのテーマ特に重要なのは、「測定」の手続きに関する完全に物理学的な説明の必要性については、両方の巻で扱っており、それゆえ本書を順番に読む手間をかける価値があるだろう。第1 巻は、時間と空間の本性を扱っている。古典物理学(ニュートン)から一般相対性理論までの時間と空間に関する議論の簡単な歴史を含んでいる。物理学では、時間と空間(後には時空)は、物理的宇宙の歴史が展開される舞台として機能する。しかし、時間と空間そのものは捉えどころのない存在である。物理的世界は、時間の中で共存もしくは相互に継起するような空間の中のものや事象の集まりとしてわれわれの前に現れる。しかし、時間と空間そのものはわれわれの感覚には現れない。色、風味、音、匂い、触ることのできる形を持たないのだ。時間と空間が持っていると思われるのは、幾何学的構造である。ここでは、構造とは正確には何か、何がそうした構造を持っているのかということについて、さまざまな理論を検討する。まず、相対性理論は時空の幾何学の理論として提示されている。特殊相対論については、相対論的世界における時計と剛体の振る舞いに関する具体的な問題を解ける程度に十分詳細に説明した。一般相対性理論については、そこまで厳密に提示していない。本書の目的は、物理学において座標を用いることがその背後にある幾何学的構造とどのように関係しているかについて特に注意を払いながら、こうした理論の概念的基礎を完全に明確にすることである。
第2 巻〔邦訳続刊予定〕では、物質の理論を取り上げる。この巻の前半では、物質の現代的な理論である量子論を提示する。相対論とは異なり、量子論をどのように理解するかについて物理学者の間で合意は得られていない。実際、「量子論」という言い回し自体が誤った呼び方であり、そのような理論は存在しない。むしろ、数学的形式と、その形式を使ってどのようにある種の予測をするかについての(きわめて有効な)経験則があるのだ。ここで、製鉄工と物理学の哲学者との違いがはっきりする。製鉄工(もしくは製鉄工モードの物理学者)は、物理的実在の本性に関して特に注意を払わない。さまざまな実験がどのようになるのかを計算するだけで十分である。物理学の哲学者は、その背後にある実在に関心を持ち、背後にある実在の説明が正しいことを支持するような証拠を提供しうる場合に限り予測に注意を払う。第2 巻では、物質の本性に関する競合するいくつかの説明を検討する。これらの理論において量子論の数学の大部分は共通しているが、それにもかかわらず何が存在するのかということの説明は根本的に異なる。
第1 巻で時空を扱い、第2 巻の前半で時空の中身である物質を扱うならば、これ以上議論することはないようにみえるかもしれない(訳註1)。これですべてなのだろうか。ある意味では、そうである。基礎的なレベルにおいて物理世界にあるものすべては、時空の理論と物質の理論で説明されているのだ。それにもかかわらず、時空論と量子論に特有な概念とは異なる概念を用いることによって、もっと明快に理解し説明できる物理現象がある。これに関して注目に値する例は、熱力学である。熱力学が扱う現象は基本的に時空における物質の運動にすぎないが、ある種の洞察、理解、もしくは説明には、統計力学の概念的道具を用いて分析する必要がある。同じこうした道具によって、物理学における確率の出現、振る舞いの統計的パターンによる説明、多くの現象における外見上の不可逆性や時間非対称性といった問題もより明確になる。熱力学、エントロピー、統計力学、不可逆性の関係を調べることによって、基礎的な存在論とその法則がすでに知られている場合でも、物理現象に対する新たな洞察がどのように見出されるかについての例を提供できる。
本書で提示するのは、あくまで私自身の視点からのまとめと整理である。こうしたトピックに関して提供されてきた物理理論や哲学的立場すべてを公平に扱うには、あまりに多くの資料があり紙数も限られているし、これを試みようというふりもしない。むしろ、明確であり、かつ有益であると私が考えた代替アプローチのみを検討する。最も有望でよく基礎づけられていると私が考えるアプローチを遠慮せずに提唱している。本書はこの分野の中立的な概観ではない。しかし、このように提示することによって、物理理論が明確で理解可能であるということがどういうことであるかを示せたと期待している。残念なことに、物理学では基礎的な問いに対して、明快さと正確性に関するきわめて低い基準が蔓延しており、物理学者は、ただ「黙って計算せよ」ということに慣れてしまって(さらには奨励されてさえ)いるので、理論の存在論的重要性を明確に理解しようとすることを意識的に控えている。こうした立場が長いこと支配的であったため、物理的実在に関する明快で正確な説明というのがどのようなものであるのかすら、ややもすれば見失いがちである。そのため、これから議論する(多くの物理学者は不快に思うであろう)物理理論に興味を持っても持たなくても、少なくともその理解可能性(intelligibility)を評価してもらいたい。これらの理論が正しくても正しくなくても、洞察に満ちていても、あるいは、誤った方向を向いていても、物理的世界に関してこうした理論が主張していることを知ることはできる。物理学者と哲学者は、われわれが住む宇宙をいつか理解しようとするならば、このような明快さを求めなければいけないのである。
(訳注は割愛しました)
解説 時空の哲学へのガイド
谷村省吾
1 本書の位置づけ
本書『物理学の哲学入門Ⅰ:空間と時間』は哲学者モードリンによる時空論あるいは相対性理論の解説である。アインシュタインの相対性理論は時間と空間のありようと、時空と物質のかかわり方に関する物理学理論だが、モードリンは本書において相対性理論以外の観点も含めて時間・空間の概念について深く掘り下げた論考を提示している。私は物理学者であり、ここでは本書の主たる読者として物理学を学ぶ大学生を思い浮かべて本書の概要を解説しよう。また、理系の人に向けた科学哲学についてのガイド的な話もしよう。
哲学にはさまざまな分野があり、科学哲学も哲学の分野の一つである。ただ、自然科学の各分野の境界は明瞭ではないように、どこからどこまでが科学哲学だという明確な境界線はない。おおよそ科学哲学は、自然科学の中に現れる諸概念・諸法則の意味を吟味したり、自然科学の方法論の正当性や限界を検討したりする学問分野だ、と言っておけばひどい間違いではないだろう。
自然科学の全体像を論じる「大きな科学哲学」もあるし、物理学・数学・生物学など個別分野を対象とする「個別科学の哲学」もある。さらには「自由意志の哲学」や「実在の哲学」のような「特定のテーマを掘り下げる哲学」もある。はじめて聞くと、自由意志は科学の対象ではないように思えるが、ニュートン力学を忠実に受け入れるなら、未来に起こること・未来にわれわれがすることはすべて力学の法則と宇宙の初期条件によって決まっており、われわれが自分の意志で何かを選んだり変更したりする余地はないように思える。そう考えると自由意志の存在は物理学と相容れないように思える。ここに自由意志と科学との接点・あつれきが生じるので、科学は自由意志の問題と無関係ではいられない。また、現代物理学の理論は電子や電磁場のように人間が直接感知できない概念を扱っているが、そのような概念物を実在と言ってよいかという問題は、科学と哲学が交差する問題になる。
哲学分野の分類という観点から言えば、本書が扱っているのは古典力学と相対性理論に焦点を絞った「個別科学分野の哲学」と言えるし、時空に関する「特定テーマの哲学」とも言える。さらに、本書を通して哲学的な疑問の持ち方や哲学的考察の進め方を知ることができるという意味で「哲学の入門書」にもなっている。
自然科学の研究では、疑問があれば、概念を数量・数式で表して計算・論証したり、命題の正否を実験で検証したりする。他方、科学哲学では、科学者が曖昧にしていた概念を論理的に分析・検討し、シャープな概念定式化や、もっともらしい解釈を試みる。したがって、科学哲学の研究は言葉による徹底的な分析と批判という形をとる。それゆえに通常の科学者には、科学哲学者たちは科学者がとっくになじんでいる概念を題材にしてまわりくどい議論をしているように見えることもあるし、科学者が深く考えることなく受け入れていた概念を見直す機会となり、結果的に深い洞察に導いてくれることもある。
このモードリンの本を読めば、相対性理論をはじめて学ぶ人でも相対性理論をかなり理解できるであろう。また、すでに相対論を学んだ学生や研究者でも、いままでに一度も考えたことがないような論点を本書に見出し新鮮な驚きを感じる可能性がある。そういう意味で本書は見どころが多く、エキサイティングな本である。
2 本書のあらまし
本書の内容を概観して私なりに検討を加える。第1 章「空間と時間の古典的説明」は、アインシュタインよりもはるか以前のアリストテレスやニュートンの時代に遡って空間と時間についての「そもそも論」を論じている。素朴な観察から言うと、時間はものごとの変化として顕在化し、とりわけ物体の運動は時間の経過に伴う物体の位置の変化として見えるため、時間と空間と運動はセットになって立ち現れる。
(以下、本文つづく)