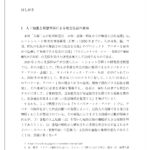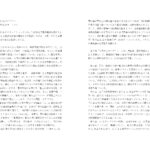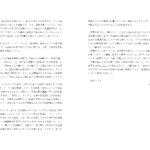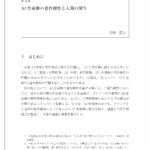あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
 斉藤邦史・橘雄介・鈴木康平 編著
斉藤邦史・橘雄介・鈴木康平 編著
『人間中心の知的財産法 身体・空間・時間からの解放と法的規律』
→〈「はしがき」「第3章」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「★」本文はサンプル画像の下に続いています。
はしがき
1 人工知能と仮想空間による社会生活の変容
本書『人間中心の知的財産法 身体・空間・時間からの解放と法的規律』は、ムーンショット型研究開発事業(目標1)「2050 年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」のプロジェクト「アバターを安全かつ信頼して利用できる社会の実現」(プロジェクトマネージャー:新保史生慶應義塾大学教授)の支援を受けた研究成果として公刊するものである。
2020 年2 月に文部科学省が公表したムーンショット目標1 の研究開発構想では、その内容として、「誰もが多様な社会活動に参画できるサイバネティック・アバター基盤」と、「サイバネティック・アバター生活」が挙げられている。2030 年の目標として、前者は「1 つのタスクに対して、1 人で10 体以上のアバターを、アバター1 体の場合と同等の速度、精度で操作できる技術を開発し、その運用等に必要な基盤を構築する」、後者は「望む人は誰でも特定のタスクに対して、身体的能力、認知能力及び知覚能力を拡張できる技術を開発し、社会通念を踏まえた新しい生活様式を提案する」を掲げている。
すなわち、ここで構想されている「サイバネティック・アバター」では、アバターの操作を介した社会活動への参画によって、自然人の発揮できる能力を増幅することが想定されている。その実現にはさまざまな技術の貢献が期待されるが、(1)各種の人工知能(AI)を用いた知的活動の増幅が大きな役割を担うであろうこと、(2)各種の制約から解放された多様な社会生活が営まれるサイバー・スペース(仮想空間)で産業的・文化的な価値の集積が進むであろうことは、想像に難くない。
2 知的財産の法的保護における「人間中心」の意義
もっとも、人間社会のあり方に変容をもたらす「破壊的イノベーション」は、法的・倫理的・社会的な課題(ELSI)を伴うことも確かであろう。今日ではさらに、経済や環境への影響をも視野に入れた、人類の文明における科学技術のガバナンスこそが、真の難問であるとの評価も成り立ち得るように思われる。
実際にも、いわゆる生成AI を用いたサービスの普及は、著作物を中心としたコンテンツに関する権利義務の帰属をめぐって、各国の世論を動揺させている。また、サイバー・スペースと現実空間との間におけるデザインの往還は、制定法の欠缺を浮き彫りにすることで、改正の議論を惹起している。これらの事象は、情報における価値の生産や流通に際して現行の法制度が明示または黙示の前提としてきた「事実上の障壁」が掘り崩されていないか、広い視野をもって展望する必要性を示唆している。
以上のような問題意識から、編著者らは、情報ネットワーク法学会のビジネス法務研究会において、2024 年9 月から2025 年2 月にかけて、「人間中心の知的財産法」と題する全5 回の連続公開セミナーを企画・開催した。本書は、その成果を学術的な論文の形式でまとめたものである。
周知のとおり、内閣府に設置された統合イノベーション戦略推進会議は、2019 年3 月に「人間中心のAI 社会原則」を決定した。そこでは、「AI の利用にあたっては、人が自らどのように利用するかの判断と決定を行うことが求められる」として、「AI の利用がもたらす結果については、問題の特性に応じて、AI の開発・提供・利用に関わった種々のステークホルダーが適切に分担して責任を負うべきである」との立場が表明されている。
AI の、インテリジェンス=知能という呼称は、その情報処理が自然人による知的活動の模倣に相当程度成功しているとの評価を示唆している。人間社会において正または負の価値が形成される過程にAI が介在することで、社会の構成員に対する責任の遡及(帰属)が妨げられるのではないか。「人間中心」というスローガンは、その円満な響きとは裏腹に、帰責を求めずにいられない人々の不安を逆照射している。
それでも、「身体、脳、空間、時間の制約」からの「解放」は、なお人間にとって福音であり得る。ただし、フィジカル(物理的)な「解放」による可能性の拡張を見定め、社会がその果実を享受するためには、その中心に存置される「人間」による「判断と決定」の本質とはなにか、あらためて確認されなければならない。
知的財産法は、「人間」による「判断と決定」を保護してきたとの見方も成り立ち得る。すなわち、いわゆる創作法の保護対象は、無数の可能性から価値のある選択肢を絞り込む情報処理としての「判断と決定」の成果として捉えることもできる。また、いわゆる標識法の保護対象は、市場における選択肢を絞り込む情報処理としての「判断と決定」を機能させるための条件と位置づけることもできる。さらに、いわゆる人格に関する保護の内容は、自律的な「判断と決定」の帰属主体を規範的に造形しているとも考えられる。
もっとも、「サイバー・スペース」とは、実は「空間」ではなく、むしろ空間からの「解放」を表象する概念である。そこにおける「人間」は、眼や耳による受信、そして指や舌による発信を通じて果てしない情報処理の奔流に接続された、中継装置に過ぎないようにすら感じられる。AI による情報処理がそこかしこに遍在するサイバー・スペースにおける情報の流通や、それに伴う「判断と決定」の探究は、価値形成の起点として仮定されてきた「人間」の概念を再検討する営みとならざるを得ない。
3 クリエイション/デザイン/オートノミー
本書は、広義の知的財産法を、「人間」による「判断と決定」の所在と価値をめぐる法制度として定位する観点から、以下の3 部による構成としている。各章の執筆は、それぞれの分野における気鋭の研究者に依頼し、当座の解釈論にとどまらない、中長期的な理論的課題をも見据えた問題設定に基づく論考を寄せていただいた。
第1 部 人間中心のクリエイション
第2 部 人間中心のデザイン
第3 部 人間中心のオートノミー
第1 部「人間中心のクリエイション」には、特許法及び著作権法を素材として、産業的または文化的な価値の創出とその保護における「人間」の存在意義を問い直す、4本の論文を収録している。
第1 章「発明における主体と客体──人工知能関連発明を素材として」(𠮷田悦子)は、特許法における「発明」の定義とその保護対象、さらにAI 関連発明における発明者の認定について検討している。本章では、AI 関連発明においても、人為的取り決め、人間の精神活動や数学的方法そのものを保護することがないように「技術的思想」を的確にとらえていく必要が指摘される。また、AI 関連発明については、人間の指示がどの程度具体的であれば発明者と認定するかなどの議論を提起する。
第2 章「発明の実施における分散と集中──複数主体による実施及び仮想空間における問題を中心に」(橘雄介)は、ネットワーク関連発明における複数主体による特許権侵害の問題を中心に、特許法上の実施行為の主体性や救済のあり方を検討する。特に、サービス提供者とユーザが分担して発明を実施する「一部実施」の場合に、近年は「適法用途の有無」や「差止判決の実効性」が実施主体性の判断の決め手となってきたことを析出する。また、仮想空間(メタバース)固有の問題として、発明の実施行為を担うアバターが複数主体により操作されている場合を想定し、これを「デスガン問題」と名づける。
第3 章「AI 生成物の著作物性と人間の関与」(髙野慧太)は、AI 生成物の著作権による保護の理論的基礎付けを論じる。従来の日本の議論では、創作性要件や思想感情要件の解釈を通じて、「著作物性が認められるためには人間の関与が必要である」とされてきた。これに対し、本章は、著作権法は創作インセンティブを与える制度で、行動変容が可能な人間に権利を付与することが前提となることを強調し、人間の関与を「著作物性」の条件ではなく、「著作権の発生の条件」として17 条1 項の問題として要求する解釈をも示唆する。
第4 章「著作権制限の正当化根拠としての受け手の利益」(平澤卓人)は、著作権が憲法上の財産権と位置づけられるとすれば、権利制限の創設を含む著作権の内容形成についてより重要な根拠・理由が求められることを指摘する。そして、従来の市場の失敗理論を踏まえつつ、著作権制限の正当化原理として、基本的情報への平等なアクセス及び情報の多様化という2 つの観点を提示する。さらに、著作者人格権の制限(公表権における公共利害関係の抗弁、20 条2 項4号)及び生成AI の機械学習(30 条の4)についても、これら2 つの観点からの解釈論の必要性を指摘する。
第2 部「人間中心のデザイン」には、意匠法、著作権法および不正競争防止法を素材として、機能的な価値と審美的な価値が交錯する領域における「人間」の居場所を探究する、3 本の論文を収録している。
第5 章「用途・機能から切り離された形態の利用と法的規制──建築デザインの場合」(末宗達行)は、建築デザインを素材として、現実空間と仮想空間を交錯した知的財産の利用の拡大に対して意匠法が対応すべきであるのか、あるいは著作権法をはじめとする他の法的手段で対応すべきであるのかを検討している。本章では、「人間中心デザイン(人間中心設計)」の考え方を参照しつつ、イギリス法との比較検討を踏まえ、建築デザインの著作権法による保護の利点を論じている。
第6 章「意匠の新規性判断におけるAI 生成デザインの引例適格性」(鈴木康平)は、AI により生成されたデザイン(AI 生成デザイン)が、意匠の新規性判断における引例適格性を有するのかを検討している。まず、意匠法上の「意匠」該当性の判断にあたっては、人間の創作的関与は不要であり、AI 生成デザインも意匠法上の「意匠」足り得ると論じている。また、従来は引例適格性を有さないとされていたコンテンツ画像についても、同じ美感を起こさせるデザインであれば、大量に生成される(物品等に化体しない)AI 生成デザインも引例適格性を有すると論じている。
第7 章「AI とデッドコピー規制」(山本真祐子)は、不正競争防止法2 条1項3 号のデッドコピー規制について、「他人の商品形態」と実質的同一の形態がAI 生成された場合、AI による学習データに含まれていなくても、利用者において他人の商品形態を念頭においてAI を利用した商品化をなしている場合には、依拠を認めるべきことを論証する。また、請求主体についても、少なくともデザインや形態への具現化の段階について商品化の決定権限があり、かつ最終的に販売を行う者については請求主体性が肯定されることになるとして、AI を用いたことがその結論に大きな影響を及ぼすことはないと論じている。
第3 部「人間中心のオートノミー」には、著作権法、民法および不正競争防止法を素材として、人格的な価値の所在と帰属に関する「人間」の自律を再検討する、3 本の論文を収録している。
第8 章「著作者人格権侵害要件の精緻化:序説──名誉権と同一性保持権との対話に向けて」(鈴木敬史)は、著作者人格権を「著作者の社会的評価」を保護する権利として再構成する立場から、名誉権において形成されてきた法理との対話を通じて、同一性保持権の侵害要件について精緻化を試みる。そこでは、名誉権との対応関係を援用することで、従来議論が不十分であった著作者人格権の論点について、過度に広範な規制を避ける解釈指針を提供できるとされる。
第9 章「パーソナルデータの収集・利用から生じる利益の帰属をめぐる問題」(橋本伸)は、データ主体が提供したデータの収集・利用から生じた利益の一部に対する権利を有するかという問いを、英米法圏の議論、特に原状回復法による保護論を参照して検討する。そこでは、従来の抑止論中心の利益吐き出し議論とは異なる、権利者の自律性という価値を実現する特定履行救済としての枠組みについて、日本における不法行為構成および不当利得構成との関係が考察される。
第10 章「パブリシティ権の正当化根拠とデジタル・レプリカの規制」(斉藤邦史)は、人工知能によるデジタル・レプリカの普及を背景に、パブリシティ権の正当化根拠をあらためて検討し、特に本人の死後における肖像等の利用規制について、米国の議論動向を参照しながら日本法への示唆を考察する。そこでは、パブリシティ権の正当化根拠を、人格の同一性に関する社会の公正感覚を反映した市場競争の秩序に求めるべきことが主張される。とりわけ、本人の死後における肖像等の保護については、創作に対するインセンティブの提供を根拠とすることはできないことが強調される。
本書の各章は、公開セミナーにおける討議を反映したものではあるが、なお各著者の研究に基づく学術的な主張を論旨とするものであり、実務および学説に対する問題提起としての色彩を有している。これらの多様な論考を、『人間中心の知的財産法』という表題のもとに公表する判断と決定に伴う責任は、もっぱら編著者らに帰属する。
本書の刊行にあたっては、勁草書房の鈴木クニエさんに原稿のとりまとめを、中東小百合さんに編集・校正をご担当いただいた。必ずしも出版の経験が豊富ではない編著者らに行き届いた助言をいただいたこと、記して感謝したい。
本書の出版および本書に収録した研究の遂行には、ムーンショット型研究開発事業JPMJMS2215 の支援を受けた。一部の章では、論述の便宜等のため他の資金等による研究の成果を部分的に併録しており、研究倫理の観点から必要に応じて各章に付記した。
2025 年7 月
編著者を代表して
斉藤 邦史
(注は割愛しました)
第3 章 AI 生成物の著作物性と人間の関与
髙野慧太
Ⅰ はじめに
生成AI 技術と著作権法に関する問題は、「AI と著作権に関する考え方」によれば、(1)開発・学習段階、(2)生成・利用段階、(3)生成物の著作物性の問題のおおよそ3 つに分けることができる。本章は、(3)にいう、AI 生成物の著作物性の問題を取り上げるものである。
わが国において、AI 生成物の著作物性を論ずる際には、①著作物性においては一定の人間の関与が必要であることを前提に、②いくつかの類型のAI 生成物の著作物性が論じられてきた。Ⅱでは、①著作物性において人間の関与が必要であることについて検討する。Ⅲでは、AI 生成物の中でも、プロンプトと選択の試行錯誤によって得られたAI 生成物に焦点を絞り、議論の当否と問題点を整理し、今後の議論の課題を提示する。
Ⅱ AI 生成物の著作物性において人間の関与が必要か
Ⅱにおいては、AI 生成物の著作物性において「人間の関与」という条件が必要であるかについて検討する。なお、結論を先取りすると、㋐「著作権の発生」の条件としては「人間の関与」は必要である、㋑「人間の関与」の条件は「著作物性」の条件として必要であるとは言えない、という結論を得る。
以下では、この点を論ずるために、まず、1 において従来の議論を整理し、2 において「著作者なき著作物」の可能性について概観する。そのうえで、3において日本法において「人間の関与」の条件がどのように位置付けられるか検討する。
1 従来の議論
まず、本項(Ⅱ 1)では、わが国におけるAI 生成物の著作物性に関する議論において、「著作物性が認められるためには人間の関与が必要である」ことが前提となっていることを析出する。
AI 生成物は、一般的には、AI 自律生成表現(AI-generated works)とAI 道具使用表現(AI-assisted works)に分けることができる。この表現は人間の関与が足りない場合には著作物性が否定されることを前提に、著作物性が否定されるべきAI 生成物を「AI 自律生成表現」、AI を介していても著作物性を肯定してよいAI 生成物を「AI 道具使用表現」と呼称しているものであり、「自律生成」であるかや「道具的に使用しているか」それ自体が著作物性の判断基準となるものではないと思われる。ただし、本項では便宜上、著作物性が否定されるAI 生成物を一般的に「AI 自律生成表現」と呼称することとする。
(以下、本文つづく。注は割愛しました)