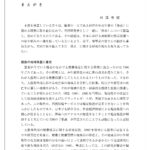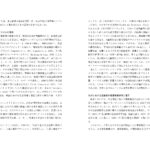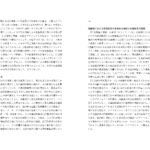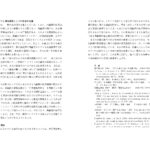あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
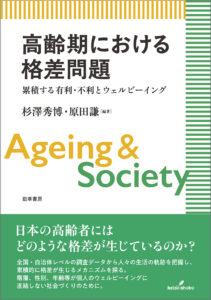 杉澤秀博・原田謙 編著
杉澤秀博・原田謙 編著
『高齢期における格差問題 累積する有利・不利とウェルビーイング』
→〈「まえがき」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「まえがき」本文はサンプル画像の下に続いています。
まえがき
杉澤秀博
本書を執筆している方々は、編者の一人である杉澤が中高年者の「格差」に関わる研究に取り組むなかで、共同研究者として一緒に「格差」について議論し、深めてきた人たちである。その経過は、日本における高齢期の格差問題への取り組みの一端を担っているといえよう。以下、執筆者の皆さんの紹介も兼ねながら、共同で取り組んできた「格差」に関する研究の流れを振り返ってみたい。
健康の地域格差に着目
筆者が今でいう格差のなかでも健康格差に関する研究に出会ったのは1980年ごろであった。その研究とは、中年期男性の死亡率の改善が遅れており、それが大都市における健康問題としてとらえられるというものであった。すなわち、大都市内部における死亡率の地域差を分析した結果、特に中年期男子の死亡率に著しい地域差があり、それが地域の社会・経済的な指標と密接に関連していることが明らかにされた(朝倉 1980)。1980 年当時は、健康格差の原因として社会経済階層を取り上げたブラックレポートが、英国で公表された時期であった。この報告は、国民保健サービスでは健康格差が是正できないことを明らかにしたものであり、日本でも紹介され、社会経済階層による健康格差への関心が高まるとともに、医療へのアクセスの格差をなくすことで健康格差が解消すると考えていた当時の「常識」が否定されたことでも話題になったと記憶している。
大都市内部の健康格差に関する研究以後、1980 年後半に大都市に居住する中年期男性を対象に、健康と健康習慣の地域差の存在と、その地域差が中年期男性の社会経済階層の分布の違いによって説明できるか否かという実証研究に取り組む機会を得た(杉澤ほか 1990)。筆者にとっては、この研究が健康や健康習慣の地域差を社会経済階層による健康格差との関連で解明した最初であり、大学院を修了した後、東京都老人総合研究所(現 東京都健康長寿医療センター研究所)に研究員として職を得たときの最初の仕事でもあった。
社会関係とエイジズムに着目
研究所では、高齢者の健康の維持・増進の要因を高齢者の社会・経済的要因に着目して解明することを目的に、米国のミシガン大学との共同研究が発足していた(以下、「日米共同プロジェクト」。1986 年に開始し、現在も継続中)。筆者は1990 年ごろからこのプロジェクトに加わり、健康格差を社会関係の面から追求する研究に着手した(Sugisawa et al. 1994;Sugisawa et al. 2002)。その理由は、米国で発表されたバークマンとサイム(Berkman & Syme 1979)による社会関係と健康に関する研究をはじめとして社会関係への関心が日本において高まっていたこと、そして、米国で明らかにされた「社会関係が死亡などの健康指標に与える影響」が、文化的・社会的に異なる日本においても同じように観察されるのか、その交差妥当性に関心があったからであった。このプロジェクトにかかわっていた日本の研究者は、筆者を含めて健康格差の要因としての社会経済階層に関心を持っていなかったものの、米国の研究者は社会経済階層に着目しており、このプロジェクトのデータを活用し、2000 年以降に高齢者の社会経済階層と健康に関する論文を公表している(Liang et al. 2002)。この日米のプロジェクトで用いられた調査項目の多くが、米国のAmerican Changing Lives(ACL)で用いられたものであり、ACL の中心メンバーであったHouse 博士は、米国における社会階層と健康に関する研究の第一人者であった。
「日米共同プロジェクト」については、杉澤が研究所から異動した後は、本書で社会経済階層による社会関係の格差に関する章を執筆している小林江里香が研究責任者となった。このプロジェクトは現在も継続しており、長期にわたる繰り返しの横断調査と縦断調査を組み合わせたデータベースを作成し、日本の高齢者の社会関係を時代効果、コーホート効果などを含めて多角的に解明してきている。
日米共同プロジェクトとは別に、1999 年に「中高年者の引退過程と健康プロジェクト」(以下、「引退と健康プロジェクト」)が発足した。「引退と健康プロジェクト」は、「日米共同プロジェクト」の研究の視点を拡大することを意図しており、そのモデルは米国のHealth and Retirement Study であった。視点の拡大とは、「日米共同プロジェクト」においては高齢者に着目していたが、より若い年齢における就労環境や就労の質が、高齢期の健康に少なからず影響するというライフコースの視点を加えた点である。高齢者の健康の維持・増進に資する対策は、高齢期以前の就労環境やライフスタイルを射程に収めて立案する必要があると考えたからである。そのため、「引退と健康プロジェクト」の調査対象は、平均的な引退年齢よりも前の55~64 歳とし、主な研究課題は、職業階層・産業による中高年者の健康格差、職業からの引退・失業の健康への影響の解明であった(杉澤・柴田編 2003)。第1 章で触れるように、現在においては、幼少期から高齢期までのライフコースを視野に収めて、高齢者の健康格差の原因と対策を考えることが一般的になっているが、このプロジェクトは、ライフコースの視点を意識して発足させたものであった。
加えて、このプロジェクトでは、中高年の就労にとって重要な課題であるエイジズムを位置づけ、若年者による中高年就労者に対するエイジズム、中高年就労者の職場におけるエイジズムの経験が仕事満足度や心身の健康に及ぼす影響、エイジズム経験に影響する社会・経済的要因の解明を研究課題として位置づけた。このエイジズムに関する研究を担ったのが編者である原田謙であり、それ以降、日本におけるエイジズム研究を牽引する役割を担っている。
日本における高齢者の健康格差研究に着手
欧米においては、社会関係に加えて健康格差の要因として社会経済階層に着目した研究が、特にブラックレポートが公表された1980 年代以降、数多く蓄積されるようになった。20 年くらい遅れて日本においても、中田知生(1999)が社会経済階層と健康に関する理論的な研究論文を発表し、その後、平岡公一ら(2001)が『高齢期の社会的不平等』、近藤克則ら(2007)が『検証「健康格差社会」』、川上憲人ら(2007)が『社会格差と健康』と題した本を出版している。
このように、日本における社会経済階層による健康格差への関心の高まりとともに、日本学術振興会の「新学術領域」の研究助成を受けて、「現代社会の階層化の機構理解と格差の制御─社会科学と健康科学の融合」と題したプロジェクト(通称:「社会階層と健康」。研究代表は東京大学の川上憲人氏)が発足し、活動を開始することになった(2009 年に開始、2013 年に終了)。「日米共同プロジェクト」の一環として行ってきた社会関係による健康格差に関する研究の蓄積が評価され、「社会階層と健康」の研究プロジェクトのなかで「社会連帯の形成・維持機構の解明」の研究プロジェクトが位置づけられ、そこに「日米共同プロジェクト」の研究メンバーのなかで社会関係と社会経済階層に関心のあるメンバーが参加することになった。「社会階層と健康」の研究プロジェクトにおける「社会連帯の形成・維持機構の解明」グループの研究課題は、社会関係を個人レベルと地域レベルで把握し、その健康影響を評価すること、社会関係の構成要素の違い(同じ特性をもった人や違う特性をもった人との関わり)による健康影響の違いを明らかにすること、社会経済階層による健康の影響を社会関係がどのように修飾する作用があるかを明らかにすること、住民の社会関係を豊富にするための方策を提示すること、などであった。
支援の格差に着目
以上の高齢者の社会関係に関する研究に加えて、東京都老人総合研究所に在職時、介護の社会化を理念とした介護保険制度の創設や、その財源となる消費税導入が世間をにぎわしていた。介護保険制度の評価を意図して、東京都下の市と共同して介護保険制度が導入された2000 年を挟んで、1996 年から数次にわたり、繰り返しの横断調査とパネル調査を実施した。その対象は介護サービスの利用者に限定されることなく、高齢者から要介護状態の人をスクリーニングするという代表性を確保した標本であった。この研究の主要な課題は介護保険制度導入に伴う支援の格差であり、経済的な基盤と家族構成による格差が、保険料負担、介護ニーズ、サービス利用の面で出現しているか否かを評価する機会を得た(杉澤・中谷・杉原編 2005)。この介護保険制度の評価研究の共同研究者が、本書の執筆者の一人である杉原陽子である。杉原は、この共同研究のデータに加え、制度発足以降になされた予防給付の創設、自己負担割合の引き上げなどの改定によって、その影響が高齢者のどのような層に集中的に表れているかという評価研究を独自に行い、支援の格差に関する研究蓄積を図っている。
高齢期における健康格差の多角的な検討と支援格差の展開
「社会階層と健康」の研究プロジェクトでは、高齢期になる前の人たちにおいて社会経済階層による健康格差が存在することを明らかにした。このような健康の階層間格差が高齢期にも存在するか否かを検討するために、「社会階層と健康」の研究プロジェクトが終了した後、同じ研究メンバーによって新たに「高齢者における社会的不利の重層化の機序とその制御要因の解明」プロジェクト(通称:「社会的不利研究グループ」)を、日本学術振興会の研究助成を受けて開始した(2014 年に開始、2017 年に終了)。研究課題は、社会経済階層による健康格差の大きさが若い人と高齢者で異なるのか、社会経済階層による健康格差が時代とともに拡大あるいは縮小しているのか、慢性疾患をもった人の間でも社会経済階層による健康格差は存在するのか、ライフコース上の経済的困窮が高齢期の健康格差に影響するのか、社会経済階層による健康格差のメカニズムは何かなどであった。このプロジェクト以降、筆者による高齢者の社会経済階層と健康に関する研究が、本格的に開始された。
「社会的不利研究グループ」の活動を継続・発展させるため、社会経済階層がなぜ高齢者の健康に影響を与えるのか、そのメカニズムの解明とそれを制御する方法を探るため、「高齢者における健康の社会階層による格差のメカニズムとその制御」プロジェクト(通称:「格差研究グループ」)という名称で、2018年度から日本学術振興会の研究助成を受けながら、継続的に研究に取り組んだ。
このプロジェクトの特徴は、高齢者の社会経済階層による健康格差のみに着目するのではなく、介護保険制度の評価研究の経験を活かし、経済的に困窮する高齢者の在宅ケアを支える役割を担うケアマネジャーを対象に、経済的困窮者に対する態度や、ケアマネジメントを行うことに伴う困難などを取りあげた。この支援格差の問題解明の中心を担ったのが、本書の執筆者である栁沢志津子である。経済的に困窮している要介護の高齢者へのケアマネジメントをどのような制約のもとで行わざるを得ないのか、さらにこのような制約があるなかで、どのように課題を克服しているのか、ケアマネジャーの視点から分析検討している。
格差問題の広がりと福祉国家としての日本の位置
以上の研究では、一般の高齢者を対象としていた。しかし、高齢期の問題は、すべての高齢者が同じように直面するとは限らない。高齢者の間でも、ある特性をもった人に不利益が集中している可能性がある。このような問題関心から、2023 年度以降においては、高齢の性的マイノリティ、経済的困窮者、女性を対象として、これらの特性に対する偏見・差別とエイジズムとの交差(intersectionality)という課題を取りあげることにした。加えて、高齢者に対する就労差別の一翼を担う企業経営者、要介護状態の高齢者をケアする介護従事者を対象に、高齢者に対する偏見・差別的な態度の存在と、その心理・社会的な要因・背景を解明する課題にも取り組んでいる。
以上のように、新しく取り組みはじめた研究課題のひとつが、日本における実証的な研究の蓄積が特に乏しい性的マイノリティの高齢化の課題である。それを担当しているのが、本書の執筆者の一人である北島洋美である。北島は、性的マイノリティという調査が難しい対象に対して質的調査を行い、性的マイノリティの高齢者の生活課題と不安に関する論文をまとめるとともに、要介護状態になった際の受け皿となる高齢者施設の職員の態度を取りあげ、分析を進めている。
本書の執筆者らが取り組んできた日本における高齢期の格差問題の現れ方や格差への対応には、伝統的な家族規範など「日本型福祉社会」を前提とした制度枠組みが影響している可能性がある。このような問題意識から、ミクロな視点で日本における個別の格差問題を解明するだけでは不十分であり、マクロな視点である文化的・社会的・制度的枠組みからも格差の問題をとらえる必要性を感じていた。そのため、「社会階層と健康」の研究プロジェクト発足以降、欧州、中でもフィンランドと日本の社会保障を比較文化的な視点で分析している新名正弥にメンバーとして加わってもらった。それにより、高齢期の格差をミクロの視点とともに、文化・社会・制度というマクロな視点からも克服する方法への示唆を得ることができるようになった。
本書を出版する理由
本書で明らかにされている格差の様々なさまざまについては、共同研究者とともに取り組み、シナジー効果として生み出されたものである。現時点で高齢期の格差に関する理論を提示し、筆者らが行ってきた日本における研究の到達点と課題を整理することは、日本における高齢者の格差研究の進展に少しは貢献するものと思われる。ただし、この成果はあくまでも現時点でのものであり、今後も高齢期の格差研究が継続され、蓄積されていくことが期待される。
本書の企画は編者である原田氏の提案によるものである。日ごろ私自身は、高齢期の健康格差に関する個別の研究課題を取り上げ、その解明のためにデータとの格闘に終始している。本書の執筆は、私個人にとっては私の定年というひとつの区切りとして自身の研究を俯瞰するよい機会となった。原田氏に感謝申し上げる。加えて、この企画に賛同し、格差に関する執筆を担っていただいた共同研究者の皆様に感謝申し上げる。
(文献は割愛しました)