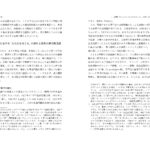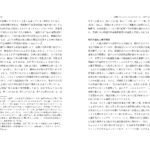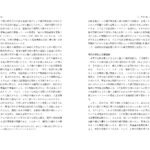あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
 新藤麻里 著
新藤麻里 著
『韓国の若者のライフコースと親子間支援 成人期移行における困難と家族主義の影響』
→〈「序章 問題の所在」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
*サンプル画像はクリックで拡大します。「序章」本文はサンプル画像の下に続いています。
序章 問題の所在
本書は,複雑に連関する一連の「大人になる」プロセスを連続的な事象と捉え,韓国社会を説明するうえで欠くことのできない家族という文脈から読み解こうとするものである.韓国社会では,青年失業,晩婚化など若者のライフコースをめぐる諸問題が近年深刻な社会問題となっている.こうした社会問題に対して,韓国や日本といった家族主義的な社会では,個人や家族の単位で問題を解決しようとする傾向が強い.特に家族の影響力が強いとされる韓国では,若者のスムーズな大人への移行,すなわち成人期移行が困難になり,親から子への支援期間が延長している.
このような若者の困難とライフコースの変容によって,家族による支援を受けられるか否かが若者の人生に影響を及ぼし得る状況にあるといえる.また,言説では出身家庭により選び取れる人生が異なるといったイメージが広がりをみせている.さらには,親からの支援が若者の生活を保障する機能の1 つに捉えられる一方で,親への依存が成人期移行の遅れを生じさせる要因となるとの見方もある.こうした背景から,本書は,韓国における親子間支援と若者のライフコースの関係を解明することを目的とするものである.
本書の問いは,若者の成人期移行が遅れているとされる現代韓国社会において,「大人になる過程で若者が親から受ける支援はどのような意味を持ち,彼らの成人期移行にどのような影響を与えるのか(与えないのか)」というものである.この問いに答えるために,現代韓国社会で若者は「どうやって大人になるのか」という成人期移行の実態,「支援はどのように行われているのか」という世代間支援の実態,「支援は移行に影響を与えるのか」という支援と移行の関係のそれぞれを明らかにしていく.これらの分析課題に対して,独自のウェブ調査データや大規模社会調査資料の分析を通じて,現代韓国社会で若者がいかにして大人になるのかという成人期移行の全体像を描写し,韓国社会における家族支援の意味と,親の支援が若者の人生に及ぼす影響を考察する.
成人期移行の不安定性の高まりは,ミクロでは若者の生きづらさの問題に繋がり,マクロでは標準移行を前提とした制度的枠組みの再考を要請する.本書は,現代韓国社会を対象に,学術的にも実践的にも重要なトピックである若者のライフコースと親子間支援の関係を実証的に分析し,成人期移行における困難と若者支援の在り方とその意味を問うものといえる.
1. 韓国社会における「大人になること」の遅れと家族の世代間支援
昨今,「大人になる」までの期間が延長,多様化していることが多くの社会で指摘されている.韓国でも既存の標準的な大人への道筋とされるものが確実に変化し,若者の社会的な自立が遅れている現状にある.特に韓国では,アジア通貨危機以降,労働市場参入の遅れや晩婚化をはじめとして成人期移行の時期が急速に後方移動している.韓国における移行の遅れは,先んじて若者の移行の遅れが問題化した欧米社会や,類似した若者問題を抱える日本などの他の社会と比べても類をみないほど急速に進展している.ここではまず,成人期移行の遅れの具体例として,韓国社会の就職の遅れと結婚の遅れに関する状況を確認してみたい.
初職移行と結婚移行の遅れ
第一に,初職移行の現状とその背景についてみていこう.韓国の青年失業率は,1990 年には5.5% であったが,1997 年のIMF 経済危機以降,1998 年には12.2% まで上昇し,1999 年にも依然として10% を超えている.2000 年代以降も長い間7% を下回ったことはなく,若者の失業問題が深刻な状況が続いてきた(統計庁各年度a).
また,韓国における若年層の雇用問題のもっとも深刻かつ特徴的な問題として大卒者の失業問題が挙げられる.大学進学率は,1990 年には33.2% であったのに対し,2000 年には68.0%,2008 年には83.8% まで上昇し,韓国では高等教育が急速かつきわめて広範囲まで拡大した(韓国教育開発院各年度).その結果,大量の大卒者が生まれ,大卒者の労働市場参入競争は激化した.また,企業規模により大きな賃金格差のある労働市場の二重構造により,韓国では大企業志向が強く,教育過剰による学歴ミスマッチと相まって,大卒者が希望の職に就くことはたやすくない状況が続いている.
もともと韓国では徴兵制を背景として,特に男性の学卒時期が遅く,就職年齢が高い傾向がある.近年では,熾烈な就職競争を背景として,より高い学歴効果を求めて大学院進学をする学生や,「スペック」と呼ばれる就職に有利な海外経験やボランティア経験,インターン経験,資格証取得のために,卒業を忌避するNG 族(No graduation 族),学卒後に就業準備に専念する就業準備生といった若者が増加している.その結果,失業率には表れない無就業の若者が増加し,経済活動人口を減少させている.たとえば,20 代男性の経済活動人口率は1990 年代初頭より15 ポイント近く急落している(統計庁各年度a).若者を取り巻く雇用環境の悪化は,韓国青少年政策研究院の報告書においても成人期移行の核心的な妨害要因とされている(イビョンヒほか2010).労働市場へのスムーズな移行と安定的な収入の確保は,一般的に若年層の雇用問題における重要な課題であり,一連の成人期移行の出発点ともされる.韓国以外の社会でも,たとえば,EU では雇用と教育訓練の間を行き来する若者の増加が,若者の低所得や社会保障給付率増加の要因といわれている.
第二に,結婚移行に関連する状況を確認しよう.結婚と出産が強く結びついている韓国では,晩婚化は少子化の主要な要因とされる(イサムシクほか2005).2000 年代に入ると若者の結婚時期は,急速に後方移動し,少子化が加速した.具体的には,韓国の平均初婚年齢は2000 年に男性29.3 歳,女性26.5歳,2010 年に男性31.8 歳,女性28.9 歳,2016 年には男女とも30 歳を超え,2023 年の平均初婚年齢は男性34.0 歳,女性31.5 歳と,結婚時期は年々遅くなっている(統計庁各年度b).それと同時に,韓国の合計特殊出生率は2018 年に初めて1 人を下回り,2023 年には0.72 人と過去最低を記録し,韓国社会に大きな衝撃を与えた.このような韓国の合計特殊出生率は世界的にみてももっとも低い水準であり,OECD 加盟国内で唯一の0 人台となり,現在では死亡者数が出生数を上回る人口の自然減少が初めて観察されるまでに至っている.平均出産年齢も初婚年齢と同様に後方移動しており,2020 年時点で33.1 歳(第1 子が32.3 歳,第2 子が33.9 歳,第3 子が35.4 歳,第4 子以降36.5 歳)と,10年で1.8 歳ほど(第1 子2.2 歳,第2 子1.9 歳,第3 子1.3 歳)遅くなっている(統計庁2021a).韓国は少子化だけでなく高齢化も深刻である.若者の未婚化,晩婚化,出産忌避といった若者の結婚・出産行動の遅れおよび選択性の高まりは,深刻な人口問題や社会保障制度の持続性の問題とも結合する.
移行の遅れと親子関係
こうした成人期移行の多様化および遅れは,韓国社会だけでなく既に多くの社会で観察されているが,韓国社会においてはその変化の急速さと問題の深刻度が際立っている.また,韓国社会における移行遅延の急速な進行と関連する深刻な社会問題は,様々な社会経済的要因が絡み合い起きているといえる.そこで,本書ではその複雑性を繙いて韓国的な特徴を理解するための視点として,韓国社会を説明するうえで欠くことのできない家族という文脈,より具体的には親子間支援という視点に着目して,成人期移行の遅れの問題を検討していく.
大人になる過程の時期は,日本では「ポスト青年期」とも呼ばれ,親への依存期間の延長という文脈からも捉えられる(宮本2004).日本と類似する社会背景を持つ韓国社会においても,成人移行期は親への依存期間の延長と捉えることが可能である.さらに,韓国社会では個人のライフコース選択における親の存在感が特に大きい.2010 年代後半には,生まれる家庭,親によって人生が左右されることを意味して,金のスプーンから土のスプーンまで出自を匙の素材に喩える「スプーン階級論」が広く知られた.日本でも「親ガチャ」という言葉があるが,韓国は親によって子どもの人生が決まるというイメージが他の社会に比べても強固であるようにみえる.
韓国は,もともと親子関係が密着的で親(特に母親)が教育熱心であることでも有名である.特に大学入学に向けた教育熱の高さで知られ,母豚が子豚を引き連れるようにほかの母親たちを連れ歩く経済力と情報力を持った教育系ボスママを意味するテジオンマ(豚のお母さん),子どもの上空を飛び回る過干渉な親を指すヘリコプターペアレントなど,韓国では時に過度に教育熱心で過干渉な親を批判する意味を含む新造語は枚挙に暇がない.また,カンガルーの赤ちゃんのように親の袋の中で同居し,生活諸条件を依存する韓国版パラサイト・シングルであるカンガルー族や,ストローで吸い上げるように親のすねを齧るストロー族といった親に依存する若者を指し示す語も多い.その多くは海外から輸入された言葉でもあるが,韓国社会の親子関係を表現するのにマッチするためか,新聞などのメディアで多数紹介されてきた.そして,このような韓国社会における強固な親子関係に関する自認は,メディアだけでなく政府報告書でも示され,青年失業の要因として親同居が「家族依存伝統」として取り上げられたこともある(労働部・韓国労働研究院2004).
一般的には,青年失業問題と親同居の問題は結びつきにくいだろう.韓国で所謂バックと呼ばれるコネで就職できるか否かといった話であれば別として,若者の就職と親から子への支援は直接的には関連しないようにみえる.しかし,親と同居していることと青年失業問題とが結びつけられるというのは,それだけ韓国社会で親の存在感が大きく,親による支援の重要性が社会的に認識されている証左ではないだろうか.このような社会的雰囲気を考慮すると,成人移行期という若者の人生を決定づける時期に親から支援を受けるか否かで,その後の人生に何らかの影響があるという関係が浮かび上がる.ともすれば,急速な移行遅延の背景に親から子への支援が影響しているかもしれない.
こうした若者に対する親からの支援が,若者の人生にどのような影響を与えるのかについては,言説のうえでは関連づけられながらも,これまで十分に検証されてこなかった.このような背景から,本書では,多くの役割移行を経験し,若者の人生を決定づける成人期移行期に,親から受けた支援が彼らのその後の人生に影響を与えるのかという問いを設定する.
2. 理論的背景と本書の位置づけ
ここまで,韓国の成人期移行の遅れに関する現状と,本書が成人期移行を理解するための着眼点として親子関係に関心を向ける理由を示してきた.つづいて,本書が親から子への世代間支援という視点から成人期移行を分析することで,一体どのようなことが明らかにできるのか,理論的背景から本書の位置づけを明示したい.
「大人になること」の複雑性
成人移行期(Transition to adulthood)は,ひと言でいえば,若者が大人へと移り変わる時期を指し,もともとは発達理論を背景とするライフコース上の概念である.このような大人でない存在が社会的存在として認識されるようになったのは,産業化社会の成立後のことである.産業化社会が成立し,子どもは大人とは異なる存在として社会に認識されるに至った.その後,産業化社会の本格化に伴い,今度は子どもと大人の間の中間的な時期として青年期という概念が登場し,子どもとも大人とも違う社会的存在として若者が捉えられるようになったといえる.さらに,ライフコースの多様化に伴って,若者が青年期から「大人」である成人期へと移り変わる固有かつ新たな時期として成人移行期と呼ばれる概念が提起された.
ライフコースの多様化が観察されるまで,人々は誰しもが同じように,大人になっていく道筋にパターンがあった.産業化社会では大人になる道筋は,おおよそ学卒→就職→結婚というパターンにより説明できる.日本では,「公的ライフコース」(嶋﨑2013)と定義づけられる男性稼ぎ手モデルを前提とした標準的(近代的)成人期移行のパターンが制度化された.このように人生を通じた道筋を意味するライフコースも以前は誰しもが同じような道筋を歩むパターンがあり,同じようなパターンが再生産される頻度が高かったため,ライフサイクル(生涯周期)と呼ばれていた(嶋﨑2008).つまり,昨今では成人期移行もライフコースも,多様性を含意する用語だとみることができる.それゆえ,何をもって成人期移行が完了したといえるのかは,そもそも流動的で多義的である.
本書で「大人になる」ことと,カギ括弧つきで示してきたのは,その多義的な性質を表すためである.「大人」は,時に年齢を,行動を,役割を指し示し,「大人になること」は,歴史的時間,社会,文化,あるいは,場面状況により可変的である.「大人になること」は,たとえば,学卒,就職,結婚,離家,経済的自立,親なり(親になること)といった成人期移行イベントによって説明されてきた.「大人になること」の条件を調査すると,そのほかには振る舞いや考えが大人の要件として人々に捉えられたりもする(石田編2017;アンソンヨンほか2011).また,「大人」の定義は社会の一員としての役割とも深い関連を持つ.先行研究では,成人期移行のゴールは,「結婚生活と職業生活」(クローセン2000=1986),「自立した大人としてシティズンシップの獲得」(ジョーンズ・ウォーレス2002=1992),「学校から就職への移行,出身家族からの移行,独立した世帯への移行」(Coles 1995)などと定義づけてきたが,近年では結婚が成人期移行の終了を意味しなくなるなどグレーゾーンが広がっているとされる(岩上編2010).ゴールだけでなく,成人期へ向かう道筋も同じく多様化した.成人期移行の多様化は,開始局面である初職移行の困難,終了局面である結婚における晩婚化・未婚化に特徴づけられ,移行期間の長期化は親への依存期間の長期化(宮本2004)として特徴づけられるだろう.また理論的側面からは,イベントの時期,順序,間隔の変化をその特徴として捉えることができ,そのほかには,結婚を条件としない移行,脱ジェンダー化と個人化が後期近代の成人期移行プロセスの特徴として挙げられる(岩上編2010).
複雑な成人期移行プロセスの全体像を理解するための視点と意味
このような成人期移行の多様化や遅れは,価値観や意識の次元では,成人期移行のプロセスがポスト近代的な様相へと多様化したことに起因しており,構造的側面では,移行期の若者の雇用不安定化によって起きている.要するに,成人期移行の多様化は,多様な道筋を自ら選択できるという価値観やライフスタイルの変化を意味するとともに,社会経済状況の変化を受けて,誰しもが同じ道筋を歩むことができなくなった社会の現状を映し出しているといえる.なぜ「大人になること」の多様化が検討すべき問題になるのかというと,こうした背景から,個人の次元でも社会の次元でも標準的な移行を前提とした既存の社会構造と実態との乖離が起きているためといえる.つまり,成人期移行の不安定性は,ミクロレベルでは若者個人の生きづらさの問題であり,マクロレベルでは制度的枠組みの再考を要請するものである.
成人期移行の遅れは,誰しもが就職し,家族を持ち,子どもを持ち,高齢になった親の面倒をみるといった標準的な成人期移行を前提とする教育制度,家族制度,社会保障制度や労働市場といった構造的枠組みの再考を促す.たとえば,非経済活動人口の増加は,若者が働き高齢者の生活を支えるといった社会保障制度の持続を困難にする.また,学卒から就職がスムーズに移行できないことは,若者のその後の結婚や親なりの経験にも影響を与え得る.これまでの社会では,皆が同じように大人になることが制度に組み込まれてきたとみることができる.しかし,現在の若者たちは社会的に期待される移行プロセスを歩むことが困難な状況にある.成人期移行が困難となった若者の生きづらさを理解し,社会全体で対策を検討するためには,個別的なイベントの移行についてだけでなく,移行プロセスの全体像を把握することが求められる.また,適切な若者支援を検討するには,個人の次元と社会構造の次元の双方への目配りが必要といえる.
ただし,複雑で多義的な成人期への移行というものと,それに関連する社会状況を理解するには,移行プロセス全体を見通す視点が必要となる.ライフコース研究の第一人者といえるクローセンは,ライフコースの全体を理解するためには1 つの理論では不十分であることを指摘している(クローセン2000=1986).若者のライフコースについて,先行研究では,ジョーンズとウォーレスは「シティズンシップ」(ジョーンズ・ウォーレス2002=1992),宮本は「親への依存」(宮本2004),岩上は「ハイモダニティ社会におけるリスクと若者の移行・自立」(岩上編2010),石田は「格差の連鎖と蓄積」(石田編2017)という観点を用いることで,成人期移行に説明を加えてきた.本書では,このような全体を見通す視点として,家族内の世代間支援(親子間支援)に注目する.
それでは,なぜ成人期移行の全体を見通す視点として親子間支援に注目するのかについて,社会的文脈に留意しながら整理してみたい.家族主義的な社会では,家族の責任が大きいとされる.福祉国家の類型化で知られるエスピン=アンデルセンは家族主義的な福祉レジームの特徴を「最大の福祉義務を家族に割り当てる体制」(エスピン= アンデルセン2000=1999: 78)としている.このような社会体制では,若者の困難により生じた福祉義務を家族(特に親)が担う構造的・文化的な背景があるといえる.
一定の年齢になると親から経済的にも住居的にも自立することが一般的であった英国などの欧米社会では,若者の雇用状況の悪化に起因する若者の自立の遅れに対する公的支援の不足を補うために親の支援が活用されるようになった(ジョーンズ・ウォーレス2002=1992).このような社会では,若者の雇用不安定化を原因とする成人期移行の遅れにより,それまで必要とされなかった親の支援が必要になった状況にあるといえる.この場合の親から子への世代間支援は公的な生活保障の代替となる意味合いを持つだろう.一方で,欧米社会の事例と対比的に捉えれば,住居的,経済的独立に対する年齢規範がそれほど強くない社会,つまり,韓国や日本では,親に依存する子どもとしての期間が延長したといえ,そもそもあった親の支援期間が長期化した状況にあるといえる.たとえば,親同居を例に取ると,日本や韓国では親同居は未婚者の一般的な居住形態であり,晩婚化や未婚化により,その期間が延びたり,社会全体としての同居者数が増えたりした.つまり,このような社会では既存の世代間支援の規模が大きくなったと捉えられる.この場合の親から子への支援は,人生初期の支援関係から基本的には途切れることなく続いているものといえるだろう.それゆえに,韓国や日本では,若者に対する支援が人々に支援として捉えられにくい状況にあり,若者に対する世代間支援が社会の問題として可視化されづらいといえる.たとえば,実際に日本や韓国で,未婚者の親同居を親から子への空間的支援と捉える見方は一般的な感覚ではないだろう.
要するに,これらの社会において若者に対する家族支援は,既存の家族扶養の延長線上にある世代間支援の問題である.したがって,親同居や親からの経済的支援といった親子間支援と成人期移行の関係は,支援メカニズム,支援のもたらす影響や支援の意味といった点で,欧米のそれとは異なる解釈が必要といえる.このような構造的コンテクストを活かし,それぞれの主題の抱える問題や背景を併せて検討する視点を持つことで,既存の分析枠組みからでは把握されなかった韓国社会における支援と移行のメカニズムの特徴を解明することができると期待される.そこで本書は韓国社会の固有性を反映し,なおかつ,韓国社会における成人期移行の遅れという現代的問題の特徴を理解する視点として,伝統的家族価値観に基づいた親子間支援に注目していく.
移行の遅れと支援関係
本書で分析対象とする若者と親との親子関係は,中期親子とも呼ばれる「親子が互いに自律可能と社会的に期待される時期」(保田2017)の親子関係であり,子が成人しており,親も介護などの必要性が高くない大人と大人の関係である.一生のファミリーステージを一本線で表すと,ちょうど中ごろに位置するような中間的な親子関係といえる.このような人生中期における親子の支援関係は,若者の成人期移行の遅れによって新たに注目される支援関係である.なぜならば,若者の成人期移行がスムーズに行われなくなったことで,本来であれば大人と大人の自律的な関係であった親子関係が変化したからである.家族内の世代間支援関係とは,人生初期では親から子どもに向けて支援が行われ,人生後期では子から親へ支援が行われるのが一般的である.したがって,家族成員のライフコースの変化に合わせて支援関係は移り変わっていくものとされる.
しかし,近年では,移行の遅れや多様化によって,成人になっても親から支援を受け続ける若者の存在が先進国をはじめとした多くの社会で確認されている.それに伴い,これまで世代間支援の提供者であった若者が,支援の受容者としても存在感を持ち始めた.この時期の親子間支援を決定づけるような明確な扶養義務規範はない.たとえば,幼い子の世話をする人生初期の親子関係や,高齢の親を介護する人生後期の親子関係に比べると,支援有無により生命を脅かすような事態は稀といえる.要するに,扶養義務規範を伴う支援関係と比べると,家族が支援を行うか否か,そして,若者が支援を受けるか否かを選択できる余地が相対的に大きい支援関係と位置づけられる.つまり,既存の世代間支援研究が主な対象としてきた初期や後期の親子の支援関係とは,異なる支援メカニズムを持つ新たな支援関係と捉えられる.
最後に,成人期移行と家族の世代間支援が韓国社会でどのように結びついてきたのか,先にも述べた韓国社会の移行の遅れと関連づけて仮説的ではあるが触れておきたい.まず,韓国社会において成人子と親の支援関係が可視化されたきっかけは,他の社会と同様に若者の雇用状況の悪化と経済状況の変化である.若者の雇用環境の悪化と就職困難が社会問題化する中で,若者と親の家族関係にも目が向けられたといえる.韓国においては,IMF 経済危機による経済的混乱の中で,1990 年代後半頃より親へ依存する若者を示すカンガルー族という言葉が言論に登場している.また,大卒者の労働市場参入の競争が激化した結果,就業準備生といった入職を遅らせる若者の存在が話題になった.奇しくも,そのような初職移行の変化と並行して,少子高齢化という人口学的変化が起き,家族の扶養機能の持続性に対する懸念が社会的に高まった.このような社会変化の中で,若者は社会の一員として大人の義務を果たさない存在としても捉えられ,親の支援は若者の成人期移行を阻害する家族依存としての意味合いを持つようになったのではないだろうか.このような仮説的解釈の是非を検討するために,本書では大人になる過程で若者が親から受ける支援が,個人にとって,社会にとって,どのような意味を持つのかについて考察する.
(脚注は割愛しました)