《要旨》
16世紀の中葉から17世紀の中葉にかけて、ヨーロッパ各地で宗教改革と反宗教改革の運動が政治・文化・社会に大きな影響を与えた。カトリック教会とそれを批判するプロテスタントの各派は、相互に批判しあうと同時に、それぞれの内部においても激しい論争と政争を展開させた。この宗教改革と密接に結びついて初期近代の国家や社会のモデルが形成されたと同時に、医療のさまざまな側面が大きく転換し発展した。
宗教改革と医学のかかわりがもっとも鮮明に現れるのが、パラケルスス主義と呼ばれた新しい医療の体系を提示した運動である。これは、ドイツを遍歴してほぼ無名の医師として没したパラケルスス(Paracelsus, 1493?-1541)の死後に現れた、彼の思想に即して当時の世界観と医学を根源から改革しようとした運動である。この運動は、パラケルススや同時代の思想家・医師が試みていた古代思想、宗教改革の基盤となったキリスト教思想、そして錬金術と化学的な実験を軸にして、新しい世界と人体の様子を示す思想を展開した。この新しい医学を提唱した運動は、既存のガレノス医学の体系を批判して、ヨーロッパ各地で大きな論争を引き起こした。このパラケルスス主義の展開は、宗教改革の激しい運動と結びついていたと同時に、この時期の医学と医療に起きていた近代化の動きとも結びついていた。
背景
1541年9月24日にドイツのザルツブルクで1人の医者が没した。その医者の名前は、テオフラストゥス・フィリップス・アウレオルス・ボンバストゥス・フォン・ホーエンハイム。晩年から死後はパラケルススと呼ばれた。妻と子供を持たなかったパラケルススの遺産は、数日前の遺言に基づいて、友人たちや彼の生地のスイスのアインジーデルンの司教などに分けられた。そのころ、アルプスを越えたパドヴァでは、若きヴェサリウスが解剖学の記念碑的な大著『人体構造論』を着々と準備していた。パラケルススの死の2年後の1543年に出版されたこの書物は、ヴェサリウスに輝かしい名誉と神聖ローマ帝国の宮廷医の地位をもたらしたことを思うと、ほぼ同時期のパラケルススの死は、歴史の中に埋もれて忘れられていく無数の医者の1人が静かに没したとしか見えなかった。
しかし、歴史は、死後のパラケルススに、まったく違う運命を準備していた。彼の思想を熱烈に奉ずる追随者が続々と現れ、主としてドイツ語で残された手稿から彼の著作が次々に刊行・翻訳され、「パラケルスス主義」と呼ばれる巨大な医学と思想の潮流が現れた。この潮流は、宗教と世界に関する新しい視点を提示して、鮮明に新しい医学のありかたを唱導するものであった。この潮流が敵視したのは、当時の医学の唯一の体系であったガレノス主義であった。中世キリスト教世界の大学がイスラム圏から導入し、ルネッサンス医学が批判的に復興したガレノス主義を、パラケルスス主義者たちが根本から否定した。それに応えて、ガレノス主義の医療を行っていたルネッサンスの医師たちは、パラケルスス主義者は無知ないかさま医師であるという悪罵を投げ返し、2つの陣営の激しい論争がヨーロッパ各国で起きた。1550年代から1650年代までの100年ほどの期間にわたって、ヨーロッパ全体を覆う広範で激烈な医学の論争がまきおこり、パラケルスス主義はその中心に位置していたのである。
この論争がこの時期に起きた理由を説明するのは、医学史における難問の1つである。確かに、パラケルススは、個人として非常に強い個性を持ち、鮮明に新奇な医学体系を提唱した医師であったし、パラケルスス主義は、医療に化学と実験を導入するという近代的な特徴を持っていた。化学の重視においてパラケルススは科学者であったとウォルター・パーゲルはまとめている。しかし、それらの特徴だけでは、この時期の医療がヨーロッパ各地で100年にわたって激烈な論争をしたことを説明できない。
パラケルスス主義がこの時期のヨーロッパ医学の論争の中心的な役割を占め続けた最大の理由が、その宗教性であったことは間違いない。トレヴァー・ローパーは、パラケルスス主義の重要な柱を3つ挙げて、「ネオプラトニズムの神学、終末論的な予言、そして化学的な医学――これら3つがパラケルススの哲学の主要な構成要素であった。そして、パラケルスス主義の運動の歴史は、かつては融合していたこの3つが次第に解体してゆき、断続的に再結合する歴史であった」と述べている。これは、16世紀から17世紀におけるパラケルスス主義の興隆と衰退に関する洞察として的確である。神学と予言という宗教的な2つの要素に、化学の導入が加わって、パラケルスス主義が作り出されるというモデルである。
同時代のヨーロッパでは宗教改革が進行していた。16世紀の初頭から、マルティン・ルター(1483-1546)、フルドリッヒ・ツヴィングリ(1484-1531)、ジャン・カルヴァン(1509-1564)らが新しい宗教意識と教会体制の形成を唱え、各地のカトリック教会がそれに反対したため、北方ヨーロッパ各地において、宗教戦争が頻発して和議が結ばれていた。1555年にはアウクスブルクの和議によって、ドイツと中欧の都市や領主にはルター派を選択する権利が認められた。16世紀に後半には、その傾向が各地に広まり、フランスの宗教戦争(1562-1598)、オランダ独立戦争(1568-1648)、三十年戦争(1618-1648)、イギリス革命(1642-1688)などにおいて、宗教上の対立が激化し、その問題を解決する原理が模索されていた。これらの宗教戦争の基本的な形は、カトリック教会側とプロテスタント諸宗派側の対立であったが、カトリック派とプロテスタント派の連合や、宗教改革派の内部での闘争などの形も生み出しつつ、各国で初期近代の国家と社会の到来を告げる重要なランドマークとなっていた。
パラケルスス主義と宗教改革は、その核心において類似した行為であった。前者は医学を根底から革新することを志向し、既存のガレノス主義を根本的に批判した。後者は真のキリスト教を志向して、カトリック教会や自分と意見を異にするキリスト教の集団を批判した。また、パラケルススらがガレノス主義を退ける批判の根底には、プロテスタント側のもっとも重要な主張であるのと同じ、聖書の重要性の強調があった。ガレノスの記述は聖書に記された世界と人間の創造に合わないというのが、ガレノス主義が拒まれた最大の理由であった。そのため、パラケルスス主義が宗教改革の諸派によって取り上げられ、ガレノス主義はカトリック側によって守られるという、宗教改革の図式と重なる革新と保守の構図が生まれた。このような、宗教改革とパラケルスス主義の重なりを説明することが、本章の1つの大きな目標となる。
その一方で、宗教改革と並行して当時のヨーロッパの思想と文化と医療で起きていた複数の現象も、パラケルススとパラケルスス主義者の活躍と深い関係があった。パラケルスス主義以外の脈絡においても、ヨーロッパ医学はガレノスの思想から徐々に離れはじめ、新しい形の医療が形成されていた。そもそも、16世紀から17世紀の医学が、全般として、ガレノス主義に盲従したと考えることは適切ではない。劇作家のモリエールは1670年代に『病は気から』などの傑作喜劇で、空文化したガレノスの言葉を唱えて得意になる医師たちを描いたが、これは、その時期の医学の状況の適切な姿ではない。前章で触れたルネサンスの解剖学の劇的な発展も、ガレノスのテキストと死体解剖の共存から生み出された。それと同じような意味で、ルネッサンス・宗教改革期の医師たちの観察や思考は、ガレノス主義と批判的な対決をするケースが多々あった。ガレノスが観察しなかった新しい疾病の解釈や、ガレノスが依拠したアリストテレス以外の思想家との出会いなどはその典型である。また、ヨーロッパにおける医療という営みが拡大して、多種多様な薬を用いるようになったこと、薬種商を中心とする多様な医療職が現れ始め、その薬を操作する新たな技法が拡散したことも重要である。
新しい疾病に関しては、アメリカ大陸から持ち込まれた可能性が高い梅毒が、ガレノスとは異なった形の疾病の発生の説明の1つのモデルとなった。ヴェローナの医師で人文主義者であったジロラモ・フラカストロ(Girolamo Fracastoro, 1478-1553)は、『伝染病の感染と治療について』(1546)において、ギリシアとローマの原子論者であったエピクロスやルクレティウスの思想を用いて疾病の種子という概念を作り上げ、ガレノスの四体液論とは異なった形で疾病の感染を説明した。フラカストロ自身はガレノス主義との差異を強調しなかったが、ここに存在したのは、ガレノスとは異なる疾病の理論を構築しようとする動きであった。ペストに関しても、ガレノス自身の流行病に対する考え方とは異なった概念が蓄積していた。ガレノスは、流行病は瘴気によるもので、その瘴気が温と湿の特徴を持つと考えたが、ペストの現実を目撃したマルシリオ・フィチーノ(Marcilio Ficino, 1433-1499)は、イスラム圏の医学を参照しながら、化学的な特徴を持つ瘴気として捉えていた。
アリストテレス以外の古代思想については、この時期に重要なテキストが発見され、ヨーロッパの思想に大きな影響を与えていた。とりわけ大きな重要性を持つのは、紀元3世紀から6世紀に至る期間に発展した新プラトニズムやヘルメス主義、それ以降のグノーシス主義やユダヤ教のカバラなどといった理論的な枠組みであった。先に触れたフィチーノは、ヘルメス文書をギリシア語で刊行してルネサンスの思想に大きな影響を与えた。医学の領域においては、これらの新思想は、アリストテレスとは異なる哲学体系で人体を説明する試みの起源となっていた。アリストテレス以外の古代思想の復活は、医療と占星術の組み合わせという運動をもたらす一方で、医学の根本原理に関して、ガレノス主義とは異なる発想をする動きを作り出していた。
医療という営みの拡大と分業の発展については、別章でより詳細に論じる主題であるが、ヨーロッパ各地において医療が拡大を始めたこと、その内部でさまざまな医療者たちの確執が顕著になったこと、それと並行して医療に付随するさまざまな組織と技術が発展したことを付言しておく。パラケルスス主義は、薬種商や外科医といった医師ではない医療者たちにも支持されていた。彼らがパラケルスス主義を標榜したのは、内科医たちが大学での教育を通じて独占していたガレノス主義への挑戦であるのと同時に、さまざまなタイプの医療者たちが力を発揮する社会への変化が始まっていたことのしるしである。薬の国内・国際的な流通は増加し、それを化学的に加工する実験の手法が拡散していた。薬物の数は増加し、ローマ時代のディオスコリデスの著作では850点、中世のイスラム教医学の時代には3,000点、そして17世紀の初頭のフランスでは6,000点の薬物が知られていた。これらの薬学は、講義と筆記を中心とする中世の大学とは異なる形で教えられ、教師と学生が大学・医学校の薬草園や大学周辺の野原や植物園などに出かける形をとるようになった。植物園で収集される薬物も、アメリカ大陸や、キリスト教と経済活動の拡大で発見された中国や東アジアから運び込まれた。前者としては、ペルーで発見された植物であるキナノキはマラリアの特効薬としてヨーロッパで多用され、後者では、中国地域で生産される大黄(ルバーブ)が、アラブの商人たちの媒介を経て16・17世紀にはヨーロッパ各地の商人が輸入を試みていた。これらの現象は、パラケルスス主義と宗教改革と並行して起きた初期近代社会への移行であると同時に、社会と文化と技術の新しい動向を作り出して同時期のパラケルスス主義の浸透と深く関連したものであった。
パラケルススの人生
パラケルススは、1493年頃にスイスの小都市のアインジーデルンに生まれた。医師であった父親から医学や自然哲学、植物学などを学び、同地の聖職者たちから、当時流行していたネオプラトニズム、オカルト哲学、神秘主義、魔術思想を学んだことは、後の医学への志向と知的な母胎を形作った。幼少期に父親とともに鉱山地であるフィラッハに移り住んだが、そこで鉱山技術に親しんだことは、後年の錬金術の重視と、金属・鉱物系の薬品の使用の淵源になっている。知的な背景に加えて、農民や鉱山技師たちの知恵と、僻地の民衆の素朴なキリスト教の敬虔さが、パラケルススの重要な要素となった。この教育は、当時の医学、ことに成立しつつあったルネッサンス医学が目指していた、都市のインテリ階層の人文主義者が理想とした、古典古代の書籍の優美な言葉遣いを重視したエレガントな教育とは対照的であった。
1513年から1516年までパラケルススは北イタリアのフェラーラ大学で医学を学び、そこで学位を取得したものと思われる。その後8年間にわたって、西はスペインから東はロシアにわたるヨーロッパ各地を遍歴して、医学の修行をしてすごす。この遍歴において、パラケルススは各地で魔術や錬金術なども吸収したが、学芸の華やかな中心地を次々と回っていったのではなく、むしろ、従軍医として戦場での傷の手当に携わったり、各地の農民と交わって病気の民間療法を吸収したり、自然を観察して過ごした。1524年にザルツブルクにとどまったころには、パラケルススはすでに自分の新しい医学の理論を構想していたと考えられている。
1527年に、パラケルススがバーゼル大学の医学教授になるという珍妙な事件が起きた。バーゼルの印刷業者を治療したのをきっかけに、バーゼル市の外科医に任命され、その流れで大学の教授に任命されるという経緯をたどった。同地でパラケルススはバーゼルの名士たちに紹介され、同地を訪れていた画家のハンス・ホルバイン(子)や人文主義者のエラスムスらと接触している。しかし、ヨーロッパの知的エリートのきらめくような世界は、パラケルススが安住する世界ではなかった。まず、教授職を始めるに先立って、医学の本質は称号や学位ではないと啖呵を切って、フェラーラの学位証明を提出することを拒むという形で問題を起こした。講義が実際に始まると、事態はさらに悪化した。パラケルススの講義は、医学の権威である古典医学のテキストを根底から批判し、それに従っている医師たちを無能呼ばわりするものであった。講義にドイツ語を用いたことも、医学の講義はラテン語で行われるのが当然だと思っていた大学と市の医者たちの反感を買った。1527年の6月に、当時の医学の権威を代表するイブン・シーナの『医学典範』を、公衆の面前で火にくべて焼き捨てたという行為は、たとえ伝説であったとしても、パラケルススの言動からして十分現実味を持っているものであった。バーゼルにきて数ヶ月で、すでに市の医者たちとの間に罵詈雑言の応酬を含む論争がはじまっていた。市の庇護者が没して後ろ盾を失ったパラケルススは、同地にとどまることは身の危険につながると判断し、1528年の2月にはバーゼルを去って知人を頼って小都市に身を寄せることとなった。
その後パラケルススは、ニュールンベルク、ザンクト=ガレン、アウグスブルクなどのドイツの諸都市を転々とした。それぞれの地で患者を治療し、富裕な名士の治療に呼ばれることもあったから、治療者としては少なくとも一定の名声を勝ち得ていたことがうかがえるが、他の医者と衝突することもたびたびであった。出版においては、梅毒の治療をめぐって、当時フッガー家が新世界から輸入して巨利を上げていた新薬であるグアヤクノキの効用を否定する論文を1529年と1530年に2点出版した。それ以外にも、医学書では外科学書を1536年に出版し、神学・自然哲学では彗星の解釈をめぐる小冊子を1531年には出版した。これ以外の著作は生前にはなかった。これは、印刷業者とのトラブルなどの理由もあったが、彼のライフスタイルが人文主義医学者のそれでなかったことが大きい。1541年にザルツブルクで没した時には、パラケルススがその後100年間以上にわたってヨーロッパ医学の焦点となる思想家にして医師になることを示唆するものは何もなかった。大学で学位を取得したかどうかさえ不確かで、刊行された著作は少なく、難病を治すと豪語するのに財産は少なかった。エキセントリックな性格で、喧嘩早くて敵が多く、一生独身で街から街へ不安定な人生を送り、自己流の医学を固く信じていた変わり者の医者であった。
パラケルスス主義の形成
パラケルススの死後20年ほどすると、状況の劇変がはじまった。パラケルススは、偉大な医学と思想の開拓者とみなされるようになったのである。パラケルススが存命中に描かれた肖像画と、死後に著名となってから復元された肖像画は、同一の人物を描いたと思えないような対照を示している(図1)(図2)。
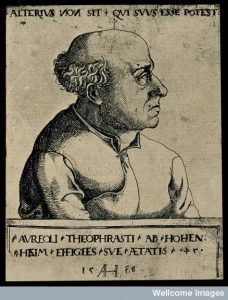
図1 1538年に刊行された版画の肖像画。画家であるアウグスティン・ヒルシュフォーゲル(Augustin Hirschvogel, 1503–1553)によるもの。ウェルカム図書館蔵。

図2 17世紀に作成された肖像画。パラケルススとほぼ同時代人である画家であるクエンティン・メトシス(Quentin Metsys, c.1465-1530)の肖像画の複写と考えられる。ルーブル美術館蔵。
1560年から1588年にかけて、彼が残した手稿が次々と刊行されはじめ、1589年にはドイツ語で10巻の全集が刊行され、17世紀初頭からこれらの著作がラテン語に訳された。世俗語であるドイツ語全集の出版がラテン語全集のそれに先行したことは、いかにもパラケルススらしい。これらの著作がパラケルスス自身の思想をどこまで忠実に反映しているかは議論の余地がある。そもそも、パラケルスス自身も首尾一貫した体系に仕上げる理論家ではなかった。それでも、この著作に書かれていることを唱え、それを発展させた者たちをパラケルスス主義者と呼ぶことが一般的である。
パラケルスス主義は、ガレノスの医学体系を「異教的」であるとして拒絶して、その対極として彼らが「キリスト教的」と考える体系を発展させた。当時の医師、医療者、そして患者たちの中には、キリスト教の原理と結びついた医療を高く評価する風潮が現れていた。たとえば、イングランドでもっとも初期にパラケルススの思想を紹介したプロテスタントの法律家で議会議員であったリチャード・ボストック(Richard Bostocke, d.1606)は、『古代の医学とその後の医学の相違について』(1585)という書物において、ガレノスの医学体系とパラケルススの医学体系を、異教的なものかキリスト教的なものかという二分法に重ねている。「ガレノスの医学は異教的であり、これは異教的なアリストテレスの哲学に基づいている。前者の医学は神の栄光を汚すものであり、後者の哲学もそれと同様である」とボストックはいう。ガレノス医学は、神が人間をいかに創造したかも知らず、宇宙と世界がどのように神にいよって作られたのかも知らない。そのため、人体と宇宙というミクロコスモスとマクロコスモスの2つの世界の対応の原理も理解していない。神がすべての種子を増やすことにしたことも知らぬので疾病の原因も理解しておらず、治療の原理も間違っている。それに対して、パラケルススは、ウィクリフ(John Wycliffe, c.1320s-1384)、ルター、ツヴィングリ、カルヴァンたちが真のキリスト教を探求したのと同様に、真にキリスト教的な医学を探求した医師であったと考察している。ここでパラケルススの医学が置かれている文脈は、宗教的な視点である。敬虔な宗教意識から見たときに、ガレノス医学がどのように見えるのか、そしてパラケルスス主義がどのように見えるのかという問題である。ガレノスはキリスト教の世界の根源的な原理を知らぬ医学であり、一方パラケルススは、カトリック教会の支配の原理に代えて根源的な宗教の改革が必要であると唱えた多くの宗教改革者と並んで、キリスト教の原理に基づいた医学を作り上げたとされた。
あるいは、フランスのパラケルスス主義者であるジョセフ・デュシェーヌ(Joseph Duchesne, c.1544-1609)は、聖書の世界の創造の記述に化学の問題を挟み込み、聖書こそが、世界のあり方、人間のあり方、そして化学的な実験の関係を語っていると説明した。デュシェーヌによれば、神が混沌(カオス)から世界を作り出し、宇宙と天体と地球上の事物と生物、そして最後には人間を作り上げたプロセスは、水銀、硫黄、塩というパラケスルスの三原質を用いて事物が形成されるものと同じである。人間の肉体・霊魂・精気は、それぞれ塩・硫黄・水銀と対応するものであり、この事態とパラレルなことを神は大宇宙(マクロコスモス)と小宇宙(ミクロコスモス)に対して行っている。そして、塩・硫黄・水銀は、化学的な実験操作の中で用いられる過程である。そのため、大宇宙と小宇宙の現実は、実験器具のフラスコの中などで実現される過程と重ねあわされる。大気において雨の原因となる蒸留や凝結は、人体におけるカタルの原因となるものと同じ現象であり、風やみぞれや雪の原因である水銀蒸気の凝結は、人体においては耳鳴りや卒中を起こすものである。このような議論は、聖書の記述を根底において、大宇宙(天上界と月下界)―小宇宙(人体)―化学的な実験の三者を密接に結びつける視点を与えるものであり、多くのパラケルスス主義者たちが好んだものであった(図3)。

図3 イギリスのパラケルスス主義者、ロバート・フラッド(Robert Fludd, 1574-1637)の著作『大世界と小世界の2つの世界における形而上学、自然学、技術的な記述』(1617-1621)の挿絵。ウェルカム図書館蔵。
塩、硫黄、水銀というパラケルスス主義の三原質は、ガレノス主義の四元素・四体液のような状態を記述する概念でなく、よりアクティヴに何かを生成し、現象を変化させる原理を記述したものであると考えられていた。塩は固体化の、硫黄は燃焼の、水銀は流体化・揮発化の原理であった。パラケルスス自身の言葉を借りれば、これらは男性的な概念であり、ガレノス主義の受動的で女性的な概念よりも上位にあるものであった。この概念装置を通じて理解されるパラケルススの世界は、活動する原理を内に持つ、ダイナミックな世界であった。それと同様に、人間の体も、活動する原理を中心にすえた概念で理解されていた。人体の各部分には、それぞれの機能を能動的につかさどる「アルケウス」と呼ばれる原理が宿っていた。また、神からやってくる「セミナ」(種子)と呼ばれる実体も人体の中の変化に関与していた。人体におきる病気も、同じようなダイナミズムを持っていた。外界から侵入する何かが、アルケウスの働きを損なうと、病気がもたらされた。そして、何が侵入するかに応じて生じる病気も定まっていた。この疾病概念は、それぞれの病気が特定の外的原因に基因する病気観であるという意味で現代的に見えるが、そこには現代の生物学的医学にはない、能動的で目的論的な原理を根底に据えた聖書と宗教の発想があるのは明らかだろう。
このような化学的な実験の原理に基づいて考案されたパラケルススの治療法は、パラケルスス主義が拡大した大きな原因であった。この療法について、讃美者と批判者が全く異なった態度を示しているのは当然である。パラケルスス主義を批判する者たちは、彼らの装置は大がかりだが結局は顧客を騙す錬金術であると批判していた(図4)。

図4 ピーテル・ブリューゲル(Pieter Bruegel, c,1525-1569)の版画『錬金術師』(c.1558)。化学的な装置を持つ錬金術師が、顧客や自らの家族を破滅させるような道筋が描かれている。
それに対して、パラケルススとパラケルスス主義者たちは、自らの治療が優れている理由は、それが化学と実験の操作に基づいているからだと考えていた。パラケルスス主義を宗教改革の精神性と結びつけて理解することは正しいと同時に、それと並行して、パラケルスス主義は、医学の中に化学的な実験という新しい技術的な操作を導入したことも強調されねばならない。ガレノス主義が植物を中心とした薬物の処理に優れていたのに対し、パラケルスス主義者たちは、水銀、アンチンモン、砒素といった重金属の化合物を処理して治療に有効な成分を取り出す技術にかけて優れた技量を持っていた。そのような化学的な薬の調合は、中世の医師や錬金術師たちによってはぐくまれ、パラケルスス自身も、ライモンドゥス・ルルス(Raimundus Lullus, c.1235-1315)、ビラノバのアーノルド(Arnaldus de Villa Nova, 1240?-1311)などの中世の錬金術師たちの著作から学んでいた。また、16世紀の初頭に現れた外科医で軍医であったと考えられるヒエロニムス・ブルンシュヴィヒ(Hieronymus Brunschwig or Hieronymus Brunschwygk c.1450–c.1512)が刊行した蒸留の技術を紹介した著作は各国で再刊・翻訳されていた。パラケルスス主義は、このような錬金術と化学の伝統にも位置づけることができる(図5)。

図5 オズヴァルド・クロール(Oswald Croll, c.1563-1609)の『王の化学』(Basilica Chymica, 1608)の表紙。左上から、ヘルメス・トリスメギストゥス、アラビアのゲベル、ロジャー・ベイコン、パラケルスス、ライムンドゥス・ルルス、ローマのモリエヌスなどの化学者たちが描かれている。ウェルカム図書館蔵。
パラケルスス主義の医学は化学的な実験を伴うものであった。それまで薬を作るのは薬剤師であり、それも植物を煮出すとか砕くとかいった比較的単純な操作にとどまっていたのに対し、パラケルスス主義の医師たちにとって、炉、フラスコ、ランビキといった大規模な設備がある実験室で、金属を化合させて蒸留して薬を精製することが重要な仕事になる。これは、患者を診て、処方を薬剤師に渡すという普通の医者の行いとははっきりと異なった次元を持っている。診断と処方が対人的で社交的でさえあるビジネスであるとすれば、実験室で薬品を化学的に精製することは、炉の熱にあてられながら薬剤の本質を取り出す緊張を維持する重労働であるだけでなく、きわめて孤独な営みであった。さらに、パラケルススが言うように、薬を見つけることが、神が世界に記した署名を発見することであるとしたら、実験室での営みは、神のメッセージと一対一で向き合うことになる。そうだとすれば、パラケルスス派の医者の実験室は、彼岸の世界のエッセンスがフラスコやランビキで立ち現れるのを孤独な観察者として目撃する、高度に宗教的で個人的な空間となる。パラケルスス主義が、当時の医師たちに新しい次元を与えただけでなく、ゲーテの『ファウスト』(1803, 1833)からマルグリット・ユルスナール『黒の過程』(1968)まで、思索的で孤高の個人を描く仕掛けになっていることも頷ける。
ドイツのパラケルスス主義――宗教改革による伸展
宗教改革が下からの改革と上からの改革の2つの特徴を持っていたように、パラケルスス主義も2つの側面を持っていた。一方で、大学でガレノス主義の医学を学んだ医師のエリートへの攻撃であり、軍医・外科医や薬種商に支持される新しい医学であったと同時に、君主や領主に庇護されることが重要であった。ルターその人の宗教改革がザクセン公フリードリッヒの庇護のもとで可能になったように、「医学のルター」と呼ばれたパラケルスス主義にとっても君主の庇護は成功の鍵を握っていた。
パラケルススの主要な活動はドイツ語圏であり、パラケルスス主義の拠点はまずドイツの諸侯の宮廷で築かれた。最初にパラケルスス主義を庇護したのは、ノイブルク選帝侯のオットー・ハインリヒ(1502-1559)であった。オットー・ハインリヒは、ルター派でパラケルスス主義に転向したアダム・フォン・ボーデンシュタイン(Adam von Bodenstein, 1528-1577)を宮廷医に任命した。彼らは、人文主義者の君主の例にもれずパラケルススの手稿を収集して図書館にパラケルススのコレクションを作り、40点もの著作を出版した。この著作の刊行が、後のヨーロッパ地域へのパラケルスス主義の基盤を築いた。ヘッセのモーリッツ伯(Moritz of Hesse, 1572-1632)も、自分自身化学実験に手を染め、侍医のヨハネス・ハルトマン(Johannes Hartman, 1568-1631)を教授にして、マールブルクに化学協会を設立させた。
ドイツの周辺地域にも、パラケルスス主義は拡散していた。神聖ローマ皇帝のルドルフ2世(Emperor Rudulf II, 1576-1612)は、中部ヨーロッパ最大の芸術と科学の庇護者であり、プラハを短期間ながらヨーロッパの文化の中心地に仕立てた。彼の宮廷は人文主義者、マニエリスムの画家、天文学者のディコ・ブラーエやケプラーを抱え、芸術作品と自然誌の一大コレクションが作り上げられた。ルドルフは特に魔術・錬金術の庇護に熱心で、パラケルスス主義者のマルティン・ルーランド父(Martin Ruland, 1532-1602)と子(1569-1611)を庇護した。ルドルフのプラハの宮廷に出入りしていたオスヴァルト・クロール(Oswald Croll, 1560-1609)は、化学が医学に不可欠であるというパラケルスス派の主張を展開した書物をラテン語で出版した。この書物は、パラケルスス主義がドイツ語圏を越えて広がるのに大きな貢献をしたが、そのタイトルが『王の化学』(Basilica Chimica)であるのは、君主によるパラケルスス主義の保護を象徴している。ルドルフの宮廷には、ハインリッヒ・コルネリウス・アグリッパ(Heinrich Cornelius Agrippa, 1486-1535)、カルダーノ(Gerolamo Cardano, 1501-1576)、J.B. デッラ・ポルタ(Giambattista della Porta, 1535-1615)などの、医学を含めて多様な学問に通じた博学者やその弟子たちが招かれて、多彩な学問の中でパラケルスス主義が発展していた。
デンマークにおいては、デンマーク王の侍医となり、強力なパラケルスス主義者となったペトルス・セヴェリヌス(Petrus Severinus, 1542-1602)が、1570年に『哲学的医学の理念』(Idea Medicinae Philosophicae)と題された書物を出版して、パラケルスス医学の哲学的な体系を紹介した。また、デンマークにおいては、ルター派とパラケルスス主義が結びついた状態から、宗教を離脱して科学的になった医学が現れた状態を、16世紀末から17世紀中葉にかけての「聖なる鉱泉」に関してたどることができる興味深い事例が報告されている。これは、もともと神の行為と考えられていた聖なる鉱泉が、自然の中に存在する薬効がある事物へと性格を変えていくプロセスであり、パラケルスス主義と近代科学をつなぐ1つの道筋であると考えられている。
フランスのパラケルスス主義――ガレノス主義との共存
小さな領邦国家に分かれたドイツとは対照的に、大きな国土に1つの主権を打ち立てる動きが顕著であったフランスにおいては、宗教改革もパラケルスス主義も似たような形をとった。フランスの宗教においては、カトリックとプロテスタント諸派が激しい敵意をはらみながら併存したように、フランスのパラケルスス主義も、ガレノス主義と対立しながら共存していた。それとともに、当時の医学教育と医療の構造の変容による新たな空間の誕生に沿ってパラケルスス主義が広まるという興味深い特徴も示している。
フランスにおいても、パラケルスス主義と宗教改革のプロテスタント側の宗派の結びつきを示す事例は数多い。フランスで最初にパラケルスス主義の実践が導入されたのは、1560年代に、モンペリエ医科大学の出身で、当時ラ・ロシェルに在った医師が、化学的に調合されたアンチモン化合物を吐剤として用いることを提唱した例である(図6)。
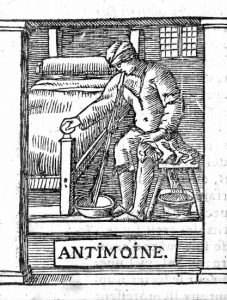
図6 アニバル・バルレ(Annibal Barlet)『一般に化学的と呼ばれる分析的治療法の真の方法的な手段』(1657)より、アンチモニーの図版。強力な吐しゃ剤としての様子が生き生きと描かれている。ウェルカム図書館蔵。
これに対し、パリ大学の医学部は高等法院に働きかけて、1566年にその使用を禁じさせ、パラケルスス派とガレノス派の対決が始まった。このようなパラケルスス主義とガレノス主義の対立が、プロテスタンティズムと親近性を持つモンペリエ医科大学と、カトリックと結びついたパリ大学という2つの大学の対立と重なって現れた。また、ドイツと同様に、プロテスタントの王侯貴族たちも、自らの周辺にパラケルスス主義者を引き付けていた。フランスにおいてもっとも重要だったのは、ナヴァル国出身で後にブルボン朝の初代国王となったアンリ4世(1553-1610)が、ナヴァル王時代にはプロテスタントの王としてパラケルスス主義者たちを厚遇して宮廷に呼び寄せたことである。アンリ4世は政治的な安定のためにカトリックに改宗するが、その後もパラケルスス主義者たちの厚遇を続け、パラケルスス主義者たちがパリの宮廷と貴族たちを治療するきっかけが作り出される。17世紀には枢機卿となったリシュリュー(1585-1642)がパラケルスス主義者の厚遇を続けた。これらの権力者の庇護に基づいて、モンペリエやバーゼル大学で学んだジョセフ・デュシェーヌ、モンペリエで学んだテオフラスト・ルノード(Theophraste Renaudot, 1586-1653)、王立植物園を設立したギ・ド・ラ・ブロス(Guy de La Brosse, 1586-1641)などが、この時期のフランスでパラケルスス主義者として活躍した。
フランスではカトリック教会とガレノス主義が優位を保ちつつ、パラケルスス主義者の活躍も観られた大きな理由は、フランスのガレノス主義が可塑的なものであったことである。もともと、パラケルスス主義と既存のガレノス主義の橋渡しを試みる医師たちも多く、ドイツのヨハン・ヴィンター(Johann Winter von Andernach,1505-1574)は、パラケルススの三原質はアリストテレスの四元素のことであり、ミクロコスモスとマクロコスモスは対応するとアリストテレスが述べていると主張した。フランスのガレノス主義の可塑性を象徴するのが、パリ大学の教授であったジャン・フェルネル(Jean Fernel, 1497-1558)であり、彼が試みたガレノス自身の著作を改善しながら医学を発展させようとする動きである。フェルネルの思想はガレノス主義であると同時に、ガレノスの原型とは大きく異なったものになっていた。ガレノスの思想においては薄弱であったキリスト教の神・創造者がもつオカルトな力を強調する考え方が、後期中世のオッカムのウィリアム(William of Occam, c.1285-1349)や、ネオプラトニズムの思想を組み込んで作り上げられていた。しかも、ペストと梅毒というガレノス自身が観察しなかった2つの重要な疾病に関して、神が仕掛けたオカルトな原因が語られていた。そのため、フェルネルを尊敬する人々は、しばしばパラケルスス主義者でもあった。また、フェルネル主義者たちが推薦した鉱泉については、ルイ13世、その王妃、そして宰相のリシュリューたちが熱心な利用者であった。
ルノードのキャリアは、パラケルスス主義者の近代性を証する1つの証拠として興味深い。ルノードは生地のルーダンで医療を開業しており、そこでリシュリューに出会って、貧困者にどのように医療や生計の具を提供するかを論じた。このアイデアをパリの貧困者に対して実現するために、ルノードは王の侍医の1人として任命され、パリで医療を行う権限を得るためにカトリックに改宗した。この体制のもと、パリで貧困者を無料で診断し他の医師が治療できるシステムを1630年代には作り上げると同時に、学者や医師たちが情報を交換できる新聞を刊行するなどの新規性を見せていた。ルノードのキャリアは、いったん妨害されるが、その後、妨害は薄弱になっていった。1658年には、ルイ13世その人が、長く悩んでいた疾病をアンチモン化合物の服用により治療され、その後、パリの高等法院はほぼ100年前に出したアンチモン化合物の禁令を撤回する方向に進むことになった。
イングランドのパラケルスス主義――革命を通じた発展
16世紀から17世紀にわたって、イングランドにもパラケルスス主義が浸透した。この時期には、イギリス国教会というプロテスタントの国家におけるパラケルスス主義者の活躍と、その宗派による統治が崩壊して共和政に移行し、多様なプロテスタントの宗派が活躍した時期におけるパラケルスス主義者の活躍という2つの様相を見ることができる。前者においては、フランスにおけるユグノーのパラケルスス主義の活躍と深い関係を持つ医師であるセオドル・ド・マイヤーン(Theodore Turquet de Mayerne, 1573-1654)が、イングランドの国王、その家族、有力な貴族や聖職者などの医師として活躍するのと並行して、パラケルスス主義の影響を受けた一連の改革を「上から」行った部分を見ることができる。一方、後者においては、ニコラス・カルペパー(Nicholas Culpeper, 1616-1654)のような正規の医学的な訓練を受けていない医療者が、「下から」新しい治療文化を作り上げたありさまを検討することができる。
マイヤーンの父はリヨンで活躍していたユグノー(フランスのカルヴィン主義者)の人文主義者であり、聖バルテルミーの大虐殺を逃れてスイスのジュネーヴに移住した。マイヤーンはハイデルベルクとモンペリエの医学校で医学を学び、後者ではデュシェーヌに指導されて化学的な治療の優越を説くパラケルスス主義の博士論文を書き上げた。その後も、フランスでユグノーの貴族や国王のアンリ4世の侍医となった。パリでは、ユグノーのパラケルスス主義者、新プラトニズムやヘルメス主義にも共感を示す知識人たちの中で有力な地位を占めていた。しかし、1610年にアンリ4世がカトリック教徒により暗殺されると、フランスのユグノーの勢力は衰退に向き始めた。マイヤーン自身は、カルヴィニズムの教義を過度に真摯に信じていたわけではなく、カトリックの王や貴族を診療することをしていたが、一方で、カルヴィニズムの知的で国際的な運動には深くかかわっていた。そのため、ジェームズ王がスコットランド王であった時期にはユグノー貴族に同伴してエディンバラで何度か拝謁したことがあり、当時はイングランドの国王も兼ねてロンドンにいたジェームズ1世の宮廷に侍医として招聘された。ジェームズ1世はスコットランド王の時期からプロテスタントの宗派に属し、イギリス国教会は、フランスのユグノーはもちろん、デンマークやオランダといったプロテスタント国家と結びついていた。マイヤーンは、数多くのイギリス宮廷の王侯貴族の侍医として活躍すると同時に、ジェームズに命じられて外国で外交の任務を行った。彼がロンドンに持っていた屋敷は、フランスのユグノーたちを中心とする国際派のプロテスタントの1つの拠点となっていた。
マイヤーンの権力がもっとも発揮されたのは、イギリスの薬種商の独立である。薬種商と外科医は、広い意味での医療という行為の内部にある重要な分業のシステムであった。大学で医学を学んだ医師によれば、薬種商と外科医は訓練の度合いが低い職業であり、前者は八百屋と後者は理髪師と合併したギルドを持っていた。しかし、16世紀に登場したパラケルスス主義は、各地で薬種商と外科医にサポートされ、イングランドやロンドンにおいても、同じような傾向を持っていた。ことに、ロンドンの薬種商の改革は16世紀の末に伸展し、トマス・マフェット(Thomas Muffet, 1553-1604)という薬種商にして王立医師協会の会員となった人物が活躍して八百屋と離別した独立のギルドを作ろうとした。この運動を引きついだのがマイヤーンであった。マイヤーンは、王立医師協会の会長となってロンドンの薬種商を独立した組織にすると同時に、1618年には数多くの化学的な治療法の記述を含む『ロンドン薬局方』を刊行した(図7)。
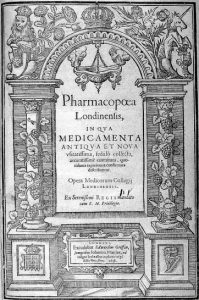
図7 『ロンドン薬局方』(1617))の表紙。王立医師協会の優美なデザインを伴うラテン語版である。ウェルカム図書館蔵。
薬種商の権限を高め、パラケルスス主義の治療法を新たに入れる動きであった。
この『ロンドン薬局方』が、カルペパーのもと、別の方向への発展をするのが興味深い。カルペパーはイギリスの薬種商であり、イングランドの共和政期に非常に活発に医学書を刊行した人物である。カルペパー自身は、当初はケンブリッジ大学で学んだ後、ロンドンで薬種商の修行をし、国王と議会派の軍事的な対立に際しては議会軍の一員となって著名な占星術の学徒であるウィリアム・リリーの影響を受けた。カルペパーは、化学的な薬学と占星術に基づいた医療として自らの医療を宣伝していた。当時のイングランドで刊行された医学書の様子を見ると、それがどの言語を用いているか、何を主題としているかという様相は、イングランドの宗教体制と深く関連している。この時期のイングランドで刊行された医学書は、清教徒革命と深く関連し、ラテン語という学術語ではなくて英語という一般語で人々に語り掛けていた。
この流れに沿って、カルペパー自身も、医学書の英訳をはじめ、医学を民衆に開かれたものにする作業をしていた。その中で興味深いのは、1649年に刊行された『薬の一覧』(Physical Directory)であった。この著作は1618年の『ロンドン薬局方』を、王立医師協会の許可なく英語に訳したものであった。その翌年の1650年には、カルペパー自身の意見も書き込まれた第2版が刊行される。カルペパーによれば、ラテン語という学者階層の言語で書かれた書物は「教皇派的 」であり、イングランド人の言語である英語によって同じ内容の書物が書かれなければならない。ラテン語で医薬の情報を刊行することは、イギリス人の自由を抑制する鎖「ノルマンのくびき」であり、英語の書物は「国民の自由」に貢献するものである。イングランドは人々が生活する空間や庭園に貴重な薬剤がある世界であり、そのような薬剤を教えてくれる素材が占星術によって開かれるときには、英語の医薬書が刊行されなければならない。このような書物が刊行されると、議会派によって称賛されると同時に、王党派によって攻撃された。1652年には、さらに配列方法を変えて、薬剤のアルファベット順に並びなおされたのち、それぞれにカルペパーが書き下ろしたさまざまな付録を加えたものが、『イギリスの医者』(English Physician)として刊行された。この著作はイギリスとアメリカの民間医療の古典的な著作となり、20世紀まで刊行され続けた。
イングランドのパラケルスス主義をめぐる連続と断裂は、マイヤーンの力で1618年に刊行されたラテン語の『ロンドン薬局方』と、カルペパーが英訳して1650年近辺に刊行した『薬の一覧』『イギリスの医者』などの著作が明らかにしている。まずは、パラケルスス主義と宗教改革が結びつくありかたが非常に多様なものであること、そして場合によっては対立するものでもあったことが明らかになる。マイヤーンは決して教皇派の徒ではなくユグノーであり、プロテスタントの国王の侍医であると同時に有力な医学組織の会長を務め、知的・社会的エリートのパラケルスス主義者であり、その地位を利用して医療の改革を進展させた人物であった。一方でカルペパーは、そのような権威とは無縁の世界に生きており、ラテン語の薬局方を敵視し、それを英訳することを通じて、イギリス国民の自由と薬へのアクセスを確保しようとした。彼自身は早世したが、彼の著作はイギリス国民にとって古典的な著作となるという形で医療と社会に刻み込まれることとなった。いずれのパラケルスス主義者も、異なった経路を通る異なった形で、その思想を歴史に刻み込んでいるのである。
おわりに
本章は、パラケルスス個人の人生とパラケルスス主義の概要を紹介したのち、ドイツとその周辺の地帯、フランス、イングランドにおけるパラケルスス主義を概観した。パラケルスス個人とパラケルスス主義において、宗教改革が非常に重要であったことと、その時期に並行して起きた他の現象も深くかかわっていたことの2点を明らかにした。いずれの地域においても、プロテスタント諸派が積極的にパラケルスス主義を主張して、ガレノス主義とは根本的に異なる医学の体系を主張した。このような、新しい医学の体系が待ち望まれた最大の理由は、宗教改革を根源的な駆動力とする、宗教改革が待ち望んでいた真のキリスト教世界にふさわしいキリスト教の世界と人間の創造と病の形成を含みこんだ医学が現れることを人々が期待していたからである。
その一方で、各地域におけるパラケルスス主義の現れ方は、地域ごとに比較する場合でも、同一の地域における時間的な差を通じて検討しても、大きな変異があった。プロテスタントの領主が発展させたドイツ、カトリック教会とプロテスタントが併存したフランス、そして、パラケルスス主義の流れから生まれた基本的には同じ2つの薬局方が対立する状況が作られたイングランド。これらの地域差と時系列による変異は、宗教改革だけではなく、それにともなって起きていたヨーロッパの医学の世界の変化が、パラケルスス主義の拡散に貢献したからであると考えられる。あるいは、ドイツの小さな領邦におけるパラケルスス主義者と、デンマーク、フランス、イングランドにおけるパラケルスス主義者たちを較べると、前者は純粋にパラケルスス自身の思想に従う傾向が強く、後者はパラケルススに従いつつも国際的な運動性とヨーロッパに広がる価値観を持つことが多かった。パラケルスス主義は、宗教改革だけでなく、国ごとの特徴、ヨーロッパの融合性、そしてヨーロッパの外の世界との関係の中で起きた大きな事件であった。
参考文献
Brockliss, L. W. B., and Colin Jones. The Medical World of Early Modern France. Oxford: Clarendon Press, 1997.
Debus, Allen G. The Chemical Philosophy : Paracelsian Science and Medicine in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. 2 vols. Mineola, N.Y.: Dover Publications, 2002.
Evans, Robert John Weston, and中野春夫. 魔術の帝国 : ルドルフ二世とその世界. ちくま学芸文庫. 筑摩書房, 2006.
French, R. K., and A. Wear. The Medical Revolution of the Seventeenth Century. Cambridge University Press, 1989.
Hirai, Hiro. “Bodies and Their Internal Powers.” In A Companion to Sixteenth-Century Philosophy, edited by Henrik Lagerlund, 394-410. London: Routledge, 2017.
Johansen, Jens Chr V., “Holy Springs and Protestantism in Early Modern Denmark: a Medical Rationale for a Religious Practice”, Medical History, 41(1997), 59-69.
Moran, Bruce Thomas. Distilling Knowledge : Alchemy, Chemistry, and the Scientific Revolution. New Histories of Science, Technology, and Medicine. Harvard University Press, 2006.
Pagel, Walter. Paracelsus: An Introduction to Philosophical Medicine in the Era of the Renaissance. 2nd, rev. ed. ed. Basel ; London: Karger, 1982.
Paracelsus, Jolande Székács Jacobi, and 博司 大橋. 自然の光. 人文書院, 1984.
Paracelsus, C. Lilian Temkin, and Henry Ernest Sigerist. Four Treatises of Theophrastus Von Hohenheim, Called Paracelsus. Johns Hopkins University Press, 1996.
Trevor-Roper, Hugh, “The Paracelsian Movement”, in Renaissance Essays (London: Secker & Warburg,1985), 149-199.
Trevor-Roper, H. R. Europe’s Physician : The Various Life of Sir Theodore De Mayerne. New Haven, Conn. ; London: Yale University Press, 2006.
Wallis, Patrick, “Exotic Drugs and English Medicine: England’s Drug Trade, c.1550-c.1800”, Social History of Medicine, vol.25, no.1, 2012: 20-46.
Wear, A., R. K. French, and I. M. Lonie. The Medical Renaissance of the Sixteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
Wear, A. Knowledge and Practice in English Medicine, 1550-1680. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Webster, Charles. The Great Instauration : Science, Medicine and Reform, 1626-1660. Duckworth, 1975.
これまでの連載一覧はこちら 》》》


