めいのサイェは、毎日のように、学校の帰り、わたしのところに寄って、母親が迎えにくるまで、過ごしてゆく。
わたしがしごとをしているとなりの部屋で、ソファに腰かけたり、腹ばいになったりしながら、宿題をしたり、本を読んだり、ぼんやりしたりする。
ある日、『セロひきのゴーシュ』って知ってる?ときいてきた。
うん。もちろん。
はじめて宮澤賢治を読んだのは『ゴーシュ』、だったよ。
サイェとおなじ年頃だったんじゃないかな。
だまってサイェは、うん、とうなずく。
そのあとで、あのね、と、つづける。
ちょっとひっかかる、ひっかかることがあるの。
――ゴーシュで?
――うん。
金星音楽団の楽長が、「演奏まであと十日」という。
その日の夜から、ゴーシュの家、
「町はずれの川ばたにあるこわれた水車小屋」に、動物たちが訪れる。
「ごうごうごう」
と、
セロをひいていると、だれか、うしろの扉を
「とんとん」
と、たたく音がする。
――うん、それが「大きな三毛猫」。
「トロメライ」を頼まれたけど、ゴーシュははげしい「インドのとらがり」を「あらしのようないきおい」でひく。
三毛猫は目が「ぱちぱち」しちゃって、ゴーシュのまわり、「ぐるぐるぐるぐる」まわってしまう。
――二晩目、「ぐんぐん」セロをひいていると、「カッコウ」、だったかな。
――「屋根裏をコツコツ叩く」の。
ガラスに何度もぶつかって、しまいには「どこまでもどこまでもまっすぐに飛んで」いく。
――三晩目は狸の子だけど、ここからゴーシュは動物にあまり反感や敵意を持たなくなってくるんだよ。
――そして野ねずみの親子がやってくる。
ゴーシュは「あああ。ねずみと話すのもなかなかつかれるぞ」と言って、眠りこんじゃう。
そうすると、ね、いきなり、ほんとにいきなり、「それから六日目の晩でした」なの。で、金星音楽団の本番……。
――そっか。一晩、二晩、三晩、四晩と動物が訪れてくる。つづいて、五、六、七、八、九ときて、十で六日目。あいだに五日、なにもいわれてない日がある。それがひっかかる?
きっと、ただ、なにも来なかっただけじゃないかな。
ゴーシュはひたすら、熱心に、「ゴオゴオゴオゴオ」ってセロを練習してたんだろうけど。
サイェはとくにちがうという表情もせず、しばらく黙っている。
なにか、言いたい、言いたいけどなかなかいい言いかたがみつからない。
てさぐりで、ゆっくり、と、あたまのなかにちらばっていることばを、ひろいあつめている――みたいだ。
わたしは待っている。
――おじさん、いま、きいていた? ううん、きこえてた?
サイェは、ふと、問いかけてくる。
え? なに?
なにを?
サイェのいってたこと、ゴーシュの空白の五日間、だよね?
――ええとね、おじさん、わたし、だまってたでしょ、いま、いまさっき。
だまってるあいだ、なに、きいてたか、って。
あいかわらず、わたしはとまどったままだ。
――きいてた、って……なにもきいてないよ……
サイェがなにかいうのを待ってただけだもの。
サイェはゆっくりとまぶたをとじて、ひらく。
この子のくせみたいなものだ。
いや、くせ、というより、儀式みたいなもの、か。
――ゴーシュ、はね、いまのおじさんみたいなかんじだったんじゃないか、って。
三毛猫さんがきて、カッコウさんがきて、狸の子、野ねずみ親子。
そうしたら、また次の日、きっと――っておもうんじゃないかな。
きっと誰かが、って。
「扉をこつこつ」って。
それに、いろいろな動物たちが、自分のひいてるセロに耳をかたむけるのを、もう、ゴーシュはしってる、でしょう?
――そうだね。
ゴーシュは、姿はあらわさないけど、
「きいている」動物たちがいて、
「きいている」耳があることを、知ってる。
そして、動物たちがきいているものを、ゴーシュも「きいている」。
きこえないかもしれないけど、
そこにいる動物たちのこと、動物たちがそこに生きていることを「きいて」いる。
ゴーシュは耳をすます。
きっと、いろいろな音が、無数の音がしたのだろうとおもう。
虫の、水の、風の。
もしかすると、天空の星のまたたきや、遠くをはしってゆく鉄道の音も。
動物たちが耳にしているさまざまな音や、通りを歩くひとの声、あしおと、冷蔵庫のモーター、自分やサイェの息づかい、などなど、などなど、届いているはずだった――。
「表情というものがまるで、できてない」と、金星音楽団の楽長にいわれてしまうゴーシュ。
水車小屋で動物たちとやりとりしながら、
おこったり、いらだったり、あわれんだり、やさしいきもちになったりして、
きっと自分の「表情」を、自分のからだだけじゃなく、
セロからもだすことができるようになった、かな。
カッコウにドレミファを、狸の子にリズムを、そして三毛猫と野ねずみ親子に表情を教わって。
ゴーシュは、楽器の音そのものをたのしむのも、
音楽を奏でるのも、
もちろんあるけど、
なにか、もっと、べつのなにかを、
伝えたり、
べつのものをきいたりできるようになったんだ、きっと。
何日かして、サイェはソファのうえから、ぽつりというのだった――
いつか、楽器、やってみたいな。
[編集部より]
東日本大震災をきっかけに編まれた詩と短編のアンソロジー『ろうそくの炎がささやく言葉』。言葉はそれ自体としては無力ですが、慰めにも、勇気の根源にもなります。物語と詩は、その意味で人間が生きることにとって、もっとも実用的なものだと思います。不安な夜に小さな炎をかこみ、互いに身を寄せあって声低く語られる物語に心をゆだねるとき、やがて必ずやってくるはずの朝への新たな頼と希望もすでに始まっているはず、こうした想いに共感した作家、詩人、翻訳者の方々が短編を寄せてくださいました。その一人である小沼純一さんが書いてくださったのが、「めいのレッスン」です。サイェちゃんの豊かな音の世界を感じられる小さなお話、本の刊行を記念した朗読会に小沼さんが参加されるたびに続編が生まれていきました。ここではその続編にくわえ、書き下ろしもご紹介していきます。今回からしばらく金曜日に週1回の更新予定です。
【バックナンバー】
〉めいのレッスン ~クリスマス・ツリー
〉めいのレッスン ~秋の庭
〉めいのレッスン ~手紙
〉めいのレッスン ~かぜひいて
〉めいのレッスン ~クローゼットの隅から
これまでの連載一覧はこちら 》》》
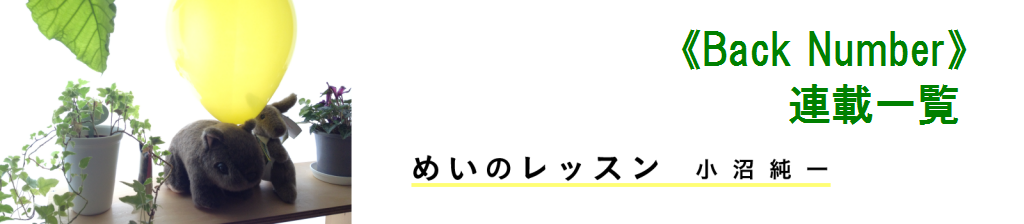
 管啓次郎、野崎歓編『ろうそくの炎がささやく言葉』
管啓次郎、野崎歓編『ろうそくの炎がささやく言葉』「東日本大震災」復興支援チャリティ書籍。ろうそくの炎で朗読して楽しめる詩と短編のアンソロジー。東北にささげる言葉の花束。
[執筆者]谷川俊太郎、堀江敏幸、古川日出男、明川哲也、柴田元幸、山崎佳代子、林巧、文月悠光、関口涼子、旦敬介、エイミー・ベンダー、J-P.トゥーサンほか全31名
書誌情報 → http://www.keisoshobo.co.jp/book/b92615.html


