融けたロウが揺れている。
春、まだ肌寒さののこるころ、サイェはわたしの父の、つまりはサイェの祖父の命日にお寺に行って、何回忌かの法要に参加した。寺の庭には父がおくった河津桜が、枝にまだすこし残っていた。
はじめてではないはずだったが、もっとずっと小さかったサイェにこうした儀式の記憶はなかった。そのぶん、おとなしくしていたし、いつもながらにほとんど口はきかず、そのかわりまわりのものや出来事に、とても惹かれているようだった。
ともすれば居眠りしてしまいそうな、意味のわからないお経のうねりや、あいだにはいってくる、やわらかくバウンドする木魚の音、ながくのびてゆく鉦、と、もちろんまわりに配されているきらびやかな仏具、花や香のにおいすべてを、サイェは全身で感じているのだった。
みんなで蕎麦を食べ、じゃあ、そろそろ、とひきあげるとき、母は、孫に何本かの和ろうそくを、ティッシュペーパーに包んで、さしだした。下から上にむかって、すこし開いていくようなかたちをしたもの。何色かで花が描かれているもの。ちょっと黄ばんでいるもの、白いもの。円錐台を積み重ねていったようなもの。どれも、ロウからでている芯がふとく、かたまったようになっている。
――きれいでしょう? 火なんかつけなくて、つかわずに、持っておいたら。鼻をよせると、ほんのすこし、においがあったりもして、ね。
サイェは学校の帰り、両親のいないうちにまっすぐ帰らずに、わたしのところに寄ってゆく。幼稚園から小学校にはいったころから、もう何年か経っているのに、ほとんど習慣として。
法要からしばらく経って、サイェは、あるとき、ろうそくを持ってきた。
何の模様もなく、かたちも平凡なもの。
これを灯して、とサイェは言うのだった。
どこに置いたらいいのかわからずに、使っていない灰皿を洗面所から持ってきて、用意する。古びた喫茶店のマッチがかろうじてみつかったから、火はそれで。
夕方になっていたものの、日がのびていたから、外はまだあかるい。とはいえ、部屋は夜のほうへ、すこし、ほんのすこし、むかいはじめていた。春にはね、畳の目ひとつ分、一日、一日、陽がのびていくんだよ、と母が言っていたのは、この季節だったろうか。
まだちょっと早いかも、と、せめて暗くなるまで、と、お茶など飲みながらときをやりすごし、ちょっとだけ我慢してもらってから、火をつける。
――「世界」が生まれてくるのが、ここに、あるみたい。
聞き間違いかと、おもわず、え?と、サイェの顔をのぞきこんでしまう。小学生がこんなことを言う、だろうか。
世界のはじまり、をね、
いくつも教わったの。
先生が、いろんな国や宗教のはなしをしてくれた。
いくつかは、
はじめ、世のなかはふるふるしてた、って、
ブリンやゼリーみたいに、ちょっと揺らすと、ふるふる、って。
ここに、みんな、あるんだ、って。
そうだね。
地面があって、水があって、火があり風がある。
大昔、この世のものはつきつめていけば、どんなものでも、四つのものからできている、って考える人がいた。
エンペドクレス、とか、アリストテレス、とか、ね。
サイェは、こんな名にとくに興味は示さない。
かみさま、は、こんなふうにみてたのかな、
わたしたち、みたいに、世界、があるのを、さ。
ふるふるしてるロウが、海みたいにまわりをかこんでる。
炎の熱で風がおこって、空気がまわる。
ロウも炎もゆれるけど、
やわらかいけどかたまっている地面がちゃんと支えて……
とても静か。
こんなふうに静かに、世界をみていたのかな、かみさま。
どんなかみさまを想像してる、サイェ?
鉾の先から雫をたらして、ぽとり、ぽとり、と、ひとつ、ふたつ、島が、島々ができてきて?
氷と炎だけだったのが、淵がひらいて、小さな炎が火の粉となって氷にぶつかって?
すべてがまじりあっているところから、天と地が分かれて?
かたまっているロウがあって、融けているロウがふるふるしてる。
空気が揺れると、炎が、あわせて、ゆれる。
かみさまからすると、世界はこれくらい小さくて。
夜にやってくる闇。まわりも、自分の手先も、すぐそばにいる人の顔もわからない。色もわからない。そんな暗さはどれくらいつづいたのだったろう。一晩なら半日。でも、その半日が、何万年、何億年も。
たまたま手にいれられても、火はなつかない。
なつくまで、なだめたりすかしたり、これもまた長いことかかって。
松やにの残った枯れ木や、油にひたした綿糸がつかって、
やっとそばにいてもらえるようになった小さな火。
ときに飼いならされずにあたりをのみこんでしまうこともあったけれど。
――手もとの字はみえる? ちょっとはなすと、字だっていうのはわかるけど、読めるわけじゃないね。こんなあかりで、字を読んだり書いたりしていたんだ、昔は。書いたり読んだりしないで、考えるほうが長かったのかな。
こういうの、和ろうそく、っていうんだけど、サイェ、ミツバチの巣からとったロウでできてるわけじゃないんだ。
うるし、や、はぜ、って木の実から。
だから、けもののかんじがなくて、どこか、静かに感じられ。
誰かが、あるとき、火を灯して、いつか消えてしまうのって、わたし、わたしたちと変わらないかもしれない、ね。
世界、みたいに、わたし、これ、みてる。
ろうそくの火をみてる。
それでいて、わたし、でもあるんだね、これ。
わたしのなかに、ろうそく、がある、って。
わたしのなか、ろうそくが、ゆらゆら、ふるふる、してる。
夜を明るくする、なんて、ほんとはできないでしょう。
たいまつからろうそくへ、ろうそくから電灯へ、ってあかりが変わる。
ひとの身のたけにあっているあかり、って、
いま、いる、いま、生きてる、のを、いつか、いなくなっちゃう、のを
忘れないで、って、ろうそく、なのかも、しれないね。
東でも、西でも、
お寺にろうそくがいまだって欠かせないのは、そのせい、だったりして。
サイェ、こんどは、
いくつもいくつも、たくさん、ろうそくが灯っているのをみにいこう。
ひとつが消えても、ほかのたくさんが灯っていて、
空気のぐあいでおなじように揺れたりはするけど、
ろうそくのかたちや色が、それぞれにちがう。
とけたロウがながれて、どこかの山のようだったり、ちょっと鼻につくにおいだったり、さわると柔らかさが違っていたり、を――。
[編集部より]
東日本大震災をきっかけに編まれた詩と短編のアンソロジー『ろうそくの炎がささやく言葉』。言葉はそれ自体としては無力ですが、慰めにも、勇気の根源にもなります。物語と詩は、その意味で人間が生きることにとって、もっとも実用的なものだと思います。不安な夜に小さな炎をかこみ、互いに身を寄せあって声低く語られる物語に心をゆだねるとき、やがて必ずやってくるはずの朝への新たな頼と希望もすでに始まっているはず、こうした想いに共感した作家、詩人、翻訳者の方々が短編を寄せてくださいました。その一人である小沼純一さんが書いてくださったのが、「めいのレッスン」です。サイェちゃんの豊かな音の世界を感じられる小さなお話、本の刊行を記念した朗読会に小沼さんが参加されるたびに続編が生まれていきました。ここではその続編にくわえ、書き下ろしもご紹介しています。
【バックナンバー】
〉めいのレッスン ~気にかかるゴーシュ
〉めいのレッスン ~クリスマス・ツリー
〉めいのレッスン ~秋の庭
〉めいのレッスン ~手紙
〉めいのレッスン ~かぜひいて
これまでの連載一覧はこちら 》》》
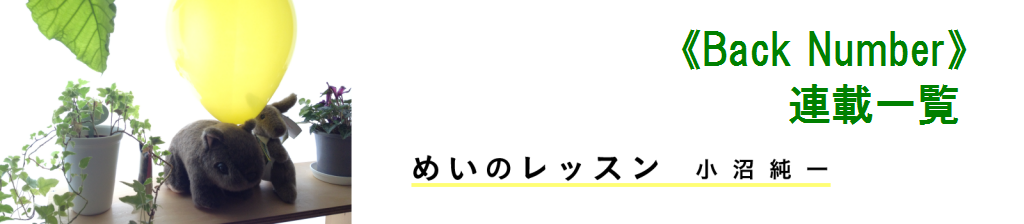
 管啓次郎、野崎歓編『ろうそくの炎がささやく言葉』
管啓次郎、野崎歓編『ろうそくの炎がささやく言葉』「東日本大震災」復興支援チャリティ書籍。ろうそくの炎で朗読して楽しめる詩と短編のアンソロジー。東北にささげる言葉の花束。
[執筆者]谷川俊太郎、堀江敏幸、古川日出男、明川哲也、柴田元幸、山崎佳代子、林巧、文月悠光、関口涼子、旦敬介、エイミー・ベンダー、J-P.トゥーサンほか全31名
書誌情報 → http://www.keisoshobo.co.jp/book/b92615.html


