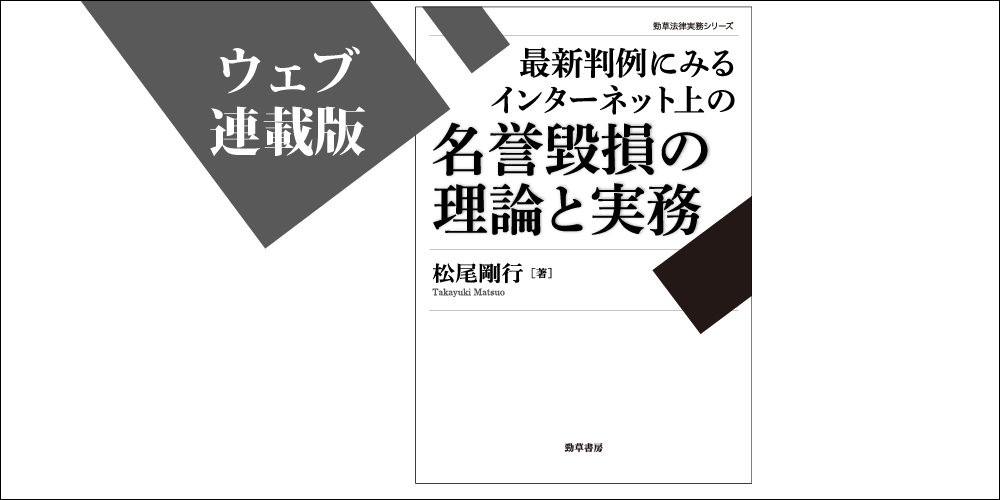事実関係が不明な段階で公表しないといけない場合には、それなりのやり方があるのですね。[編集部]
取引先に解任を通知したメールが不正確な内容だった事案から、真実性・相当性以外の正当化法理について探る
たとえ名誉を毀損する表現であっても免責される場合があるということは、これまでの連載でも重ねて解説をしてきました。今回は、そのうち、正確性がやや欠けている内容の表現の免責ないし正当化について検討します。
会社では、役職員の解雇・解職等について口頭で社員等に通知するほか、イントラネット(企業内ネットワーク)で回覧したり、取引先には書面やメール等で知らせたり、場合によっては記者会見やインターネット上で公表することがあります(注1)。
この内容によっては、当該役職員の名誉を毀損する可能性があります。たとえば、「当社社員の●●が当社の財産を横領したので懲戒免職としました。」といった内容を多くの関係者にメールすれば、当該社員の社会的評価を低下させるでしょう。この点は、連載第8回、第9回、第12回、第13回で解説してきたように、真実性・相当性の法理による免責の可能性について検討することになります。
とはいえ、真実性・相当性の法理による免責の余地は比較的狭いものです。事実誤認があり、それについて相当な理由がなければ、真実性・相当性の法理では免責されません。
もっとも、実際には、初期段階で何かしらを連絡・公表すべきで、しかし、その段階では事実関係に関する十分な調査ができていなかったというケースもありうると思われます。そのような場合でも、結果的に事実誤認があるとされると、公表はまったく正当とされないのでしょうか。
このような問題は、名誉毀損的表現の正当化の問題として捉えることができます。真実性・相当性の法理以外でも、正当な労働組合の活動であるとか、正当防衛であるとか、一定の場合には、名誉毀損が正当化されることがあるのです。
では、上記のような解雇等の公表・連絡はどうでしょうか。解任通知による名誉毀損が正当化されるかが問題となった事案(注2)について、東京地方裁判所の判決を題材に検討してみたいと思います。
*以下の「相談事例」は、本判決の内容をわかりやすく説明するために、本判決を参考に筆者が創作したものであり、省略等、実際の事案とは異なる部分があります。本判決の事案の詳細は、判決文をご参照ください。
相談事例:不正確な内容の解任通知の正当化が問題となった事案
A社の元共同代表取締役Bが、他の共同代表取締役や経理部門にも知らせず、こっそりとA名義の口座を開設して、通帳等を自分個人で管理した上で、取引先に対し当該口座に代金等を振り込むように指示することで、本来Aが受け取るべき代金を私物化していたことが発覚した。
AはBに対して通帳や印鑑を返還するよう求めたが、Bはこれを拒絶した。
平成X年3月3日、AはBを臨時取締役会で代表取締役の地位から解職し、「弊社代表取締役Bは平成X年3月3日開催の臨時取締役会において解任致し弊社とは今後一切の関係がなくなりましたのでこの段ご通知申し上げます何卒ご了承ください。」という通知を多数の取引先にメールで送付した(注3)。もっとも、実際は3月3日にBを「代表」取締役から解職したものの、Bはその後も平取締役として残っており、その後一切の関係がなくなったわけではない。
BはAのこのようなメールに激怒し、Aを訴えると言っている。
M弁護士はAにどのようなアドバイスをすべきであろうか。
1.法律上の問題点
まず、この程度の通知が本当にBの社会的評価を毀損するものかは重要な問題となります。本判決も、この程度の具体的な解任原因を述べていない通知はBの社会的な評価を低下させたとはいえず、名誉を毀損しないとしています(注4)。
もっとも、解任・解雇等に関する説明文が社会的評価を低下させるかという判断には微妙な問題があり、これまでも肯定例と否定例があることは、『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』でご説明したとおりです(注5)。
そうすると、裁判所は結果的に今回の通知が社会的評価を低下させないと判断してはいるものの、これだけに依拠するのは不安定です。たとえば、上記の通知に「今後BからA名義の●●銀行の口座へ振込先を変更するよう依頼があっても、これはBが個人的に管理している口座ですので、そのような依頼に応じないでください。」と書いた場合でも同様に社会的評価の低下が否定されるかは微妙なところでしょう(注6)。
実際、裁判所は社会的評価を低下させないことだけを理由に直裁にBの請求を棄却することもできましたが、同時に免責事由をも検討しています。
ここで重要なのは、本件のAの通知には不正確な点があったことです。Aが取引先にBと取引をしてほしくないという気持ちから「一切の関係がな」いと述べたというのは心情的には理解可能ですが、BはAの平取締役として残っていたのであって、表現が不正確です。そこで、真実性の法理や相当性の法理が使えない可能性がありました(注7)。
真実性の法理や相当性の法理が使えなければ、問題となるのは真実性の法理や相当性の法理以外の事由で正当化されないかという点です。
【次ページ】不正確な場合は?