あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
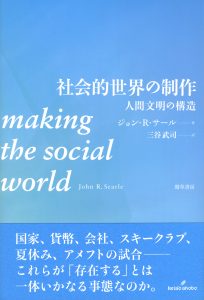 ジョン・R・サール 著
ジョン・R・サール 著
三谷武司 訳
『社会的世界の制作 人間文明の構造』
→〈「訳者解説」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報はこちら〉
訳者解説
三谷武司
1 はじめに
本書は、John R. Searle, Making the Social World: The Structure of Human Civilization, Oxford University Press, 2010 の全訳である。本文にも言及のある通り、本書はJohn R. Searle, The Construction of Social Reality, The Free Press, 1995(『社会的現実の構築』、未邦訳)の続編であり、同書から引き継がれた研究テーマを著者は「社会的存在論(social ontology)」と呼んでいる。前著刊行後、サールの立論をめぐって多くの議論が生じたが、その詳細については本書「謝辞」に詳しいのでそちらを参照のこと。
社会的存在論が扱うのは、「〇〇は大統領である」のような、自然科学の範疇には明らかに含まれないが、かといって個々人の主観的な思い込みに還元されるわけでもないような客観的事実としての制度的事実である。この種の事実が有する特殊な性質を剔出し、その創出・維持のしくみを解明すること、それが社会的存在論の課題とされる。現時点におけるその理論の全体構想(後述)と、一九三二年生まれの著者の年齢(原書刊行時点で七十八歳、本訳書刊行時点で八十六歳)に鑑みて、本書の主題であるこの社会的存在論を、サール哲学の集大成ないし終着点と見るのは決して無理な態度ではあるまい。実際、言語哲学や心の哲学に関するサールの議論に親しんできた読者は、その先に「社会の哲学」が展開される様を目にして一定の感慨を抱くであろうし、本書からサール哲学に入門しようという読者は、社会的存在論において不可欠の成分としての位置づけを与えられている発話行為論や志向性論の詳細を求めて、著者の既刊書をひもとくことができる。
ところで本来訳者の仕事というのは良質な訳文を提供することにあり、責任上一応その課題は果たしえたと言わざるをえない現時点にあっては、訳者としては自分の訳文を通じて読者が原著者の議論を理解し、社会的存在論をめぐる哲学的・理論的問題に関して示唆を得、あるいは直観と論理の両面から本書を批判的検討の素材とし、ひいては直接間接の経路を通じてこの研究分野の発展に少しでも貢献できることを望むばかりであるから、ここに改めて本書全体の要約じみた解説を書こうという気にはなかなかならないし、原著者の人脈や既刊著作等と本書の関係についても「謝辞」や本文に散りばめられた文献参照・原注を見ていただくので十分かと思う。
しかしせっかく解説の紙幅を与えられたのであるから、読者の便に資するため、(1)本書に関連する既存の紹介・解説類に比して留意すべき点、(2)本書の議論の根幹に関わる不備であると、したがって有意義な批判的検討の出発点たりうると訳者が考える点、(3)明らかに不備だが議論の根幹に関わらないので指摘される機会が少ないだろうし指摘されたところでそこから有意義な発展も見込めないのでここで潰しておきたい点を、それぞれ簡単に述べておくことにする。
2 「基礎的要件」について
サールの社会的存在論を(あるいはその言語哲学を、心の哲学を)理解し、また支持あるいは批判の対象とするにあたり絶対に踏まえておくべき根本前提は、それが徹底した自然主義の立場を堅持していることである。本書ではこの立場は「序文」で示唆され、第1章第1節で「基礎的要件」として定式化され、その後に続く各章でも、そのつど提出される理論のチェックのために繰り返し登場している。内容はごく単純で、要するに心(志向性)であれ言語であれ社会的・制度的事実であれ、すべては自然科学の知見と矛盾することなく記述され、またその延長上に、それを基礎として説明されなければならないということである。具体的に言うと、サールの理論は脳→心→言語→社会の順に、基礎から発展へのきれいな単線的構成をもっている。社会的存在論はこの全体構想の最後に位置するものであるから、その当否を最終的に判断するためには、その前に志向性論と言語論の当否をこの要件に照らして検討する必要がある。本書の第2章・第3章で心の哲学(志向性論)に、第4章で言語哲学(発話行為論)に、かなりまとまった説明が与えられている所以である。いずれにせよ、社会的存在論に関し、この「基礎的要件」の制約下でどこまで豊かな理論が構築できているかが本書の読み所であり、さしあたり批判的検討の足場となるべき問題設定であることは論を俟たない。
本書冒頭の数ページを読めば書いてあることをわざわざこの限られた紙幅の中で改めて強調したのは、本書の議論を紹介・検討した邦語文献(中山 2011: Ch. 3; 倉田 2017; 大河原2017)がいずれもこの自然主義ないし「基礎的要件」への言及を欠いているためである。その結果、例えば会社=法人を「個人のそれには還元できない固有の義務論的力の担い手」として扱い、それをもって「サール的な枠組みを維持したうえで」の社会的存在論の「拡張」と称する議論(倉田 2017: 100-104)が出てきてしまう。しかし「サール的な枠組み」において、自然科学的な存在根拠をもたない――端的に言えば脳を有する生物個体でない――会社=法人が、それ以上還元不可能な義務論的権力の担い手となりうる余地は一切ないのである。仮に議論の基礎にこの種の「集団的行為者」を置き、そこに「表象(信念)や動機(欲求や目標)といった心的状態(志向的状態)を帰属」(倉田 2017: 103)させてもよいのであれば、集合的行為に必要とされる集合的意図を、意図を含め志向性は個人の脳内にしか存在しえないとの要件と齟齬をきたさないように定式化するための本書第3章の議論は無用の長物以外のなにものでもなくなってしまう。いずれにせよ「基礎的要件」に違反する任意の議論は、サール社会的存在論の――拡張ではなく――端的な拒絶と言わなければならない。
3 「地位機能宣言」について
訳者の考えでは、サール社会的存在論の根幹は、「○○は大統領である」といった社会的事実の存在様態を、この種の事実についての我々の直観的知識もしくは常識に基づき、また前述の「基礎的要件」の制約を受けつつ記述・分析していく部分と、そうやって明らかにされた存在様態を有する社会的事実がいかにして成立するかを、やはり「基礎的要件」の制約のもとで――具体的には志向性論と発話行為論によって――説明していく部分の二つに分けることができる。もちろんこの二つの課題は合わせて一つの社会的存在論を成すべきものであるから、互いに他に対する制約ともなっている。
まず、「○○は大統領である」を典型例とするこの種の事実が一定の制度の存在を前提とし、その内部でのみ成立する制度的事実であること、制度的事実を可能ならしめるこの制度が構成的規則の体系であること、構成的規則が「XはCにおいてYとみなされる」の形式をとること、このY項(例えば「大統領」)がX項に一定の機能を付与する地位であること、この地位機能の内実は義務論的権力に見出されること、義務論的権力は人に願望独立的な行為理由を与えるものであること、地位機能の作用には集合的承認が必要であること、地位機能の成立には必ずしも構成的規則を(したがって制度の存在を)要しない場合もあること、最も一般的には地位機能は地位機能宣言によって創出されること、地位機能宣言には地位機能付与の対象となるべき物理的実体としてのX項を要しない場合(会社設立等)もあること、等々――これらはいずれも、社会的事実の存在様態に関する我々の直観・常識を、「基礎的要件」への違反を周到に回避しながらサール独特の用語に落とし込んだ命題群にほかならない。
実際これら命題に関する本書の議論は、読者に対し既知の事柄についての想起を促すような書き方になっている。したがって読者は批判的検討に際し、サールによる用語定義を厳密に把握し内的な論理構造を確認したうえで、社会的世界についての自分の直観や常識を振り返り、これら命題群が十分網羅的であるかどうか、あるいは直観や常識に反する部分がないかどうかをチェックすることを求められる。第1章補論には『社会的現実の構築』の議論に対して提起され、本書執筆のきっかけを与えたとされる三つの論点が示されているが、それらはいずれも、いま述べたような種類の批判的検討から出てきたものである。
そのようにして体系的に整理された制度的事実の存在様態に対し、その生成メカニズムを志向性論および発話行為論の自然な延長として説明するのが、サール社会的存在論のもう一つの側面である。そして訳者の考えでは、この側面において本書の議論は重大な不備を抱えている。
サール曰く、地位機能は――したがって制度的事実は――地位機能宣言によって創出される。任意の制度は構成的規則の体系であるが、構成的規則は地位機能宣言の一特殊事例(「定立的」な地位機能宣言)にすぎず、したがって一般に地位機能宣言は制度の存在を必要としない。にもかかわらず地位機能宣言が地位機能を――制度的事実を――創出する力をもつのはなぜか。本書の説明上の課題はこの点に集約され、その解決のために志向性論と発話行為論が動員される。サールが与えた答えは、地位機能宣言が地位機能を創出しうるのは、それが宣言だからだ、というものである。宣言という発話行為類型は、それが本来的に――言語的に――有する性質のゆえに、制度に依存することなく世界内に、その命題内容が表象する事態を創出する能力をもつというのである。「我々は意味論の力を用いて意味論を超える力を創出している」(本書179頁)とはこの謂いである。
そこで鍵となるのが「適合方向」である。この概念は心(志向性)と言語(発話行為)の双方に適用され、志向的状態としての信念は〈心から世界へ〉、発話行為としての陳述は〈言語から世界へ〉の下向きの適合方向→を有し、志向的状態としての願望は〈世界から心へ〉、発話行為としての約束は〈世界から言語へ〉の上向きの適合方向←を有する、等とされる。志向的状態も発話行為も一定の世界状態の「表象」を含むが、この表象が現実の世界状態と合致するときに当該の志向的状態ないし発話行為は「充足」を得る。当該の志向的状態ないし発話行為において、この充足を獲得する「責任」が、その志向的状態ないし発話行為と世界のいずれにあるかを示したのが適合方向である。信念や陳述は充足を得るにあたりその表象内容を所与の世界状態と合致させるべきことを含意するがゆえに下向きの適合方向を、願望や約束は充足を得るにあたりその表象内容を所与として世界状態の方がそれと合致するよう必要なら変化すべきことを含意するがゆえに上向きの適合方向を有するという。
そのうえでサールは、発話内行為の一類型としての「宣言」は、例えば終戦宣言が戦争の終結を宣言することによって実際に戦争を終結させるように、ある世界状態を表象することでその世界状態を実現するのであり、宣言一般のもつこの性質のゆえに地位機能宣言は地位機能を創出することができ、またしたがって宣言は〈言語から世界へ〉と〈世界から言語へ〉を併せた二重の適合方向↔を伴うとする。この議論はさらに、二重の適合方向をもった類型は心=志向的状態には見られず、言語(発話行為)に特有のものであるから、人間が制度的事実を創出するにあたっては言語が不可欠の役割を担うとの主張へと繋がる。
しかしここで注意が必要である。サールは確かに前段落の通りのことを述べているのだが、なぜ宣言が宣言であることそれ自体によって一定の世界状態を創出する能力をもつのかについては、依然何一つ説明されていないからである。実は以前の論考では、宣言のもつこの力の源泉についてきわめて明示的な記述があった。すなわち「発話内行為の分類」(Searle 1975: 359)でも、『志向性』(Searle 1983:171-72)でも、『心・言語・社会』(Searle 1998: 150)でも、宣言による世界状態の創出は「言語外的な制度(extra-linguistic institution)」の存在を前提とし、その内部でのみ可能であることが明言されている。もちろん『社会的現実の構築』(Searle 1995)がこの線に沿って書かれた作品であることは本書32頁で明記されている通りである。
ところが本書ではとりわけ「アドホックな事例」への対応のために、制度外での地位機能創出に説明を与えることが必要になった。一方、宣言による地位機能創出という立場は堅持され、その結果、制度と宣言の間で説明/被説明の関係が入れ替わることとなった。しかしサールは宣言型発話行為に関しては以前の所説を繰り返すばかりで、本書で新たに生じた課題にとって有効な性質が宣言に帰属されることはなく、結局、宣言を特徴づける性質としては「二重の適合方向」だけが残ることとなったのである。
しかし前述の通り「適合方向」というのは充足の責任の所在を示す概念にすぎず、適合方向が二重であることをもって宣言に地位機能創出の能力を認める議論は成り立たない。仮に適合方向概念がその種の説明力を有するのであれば、信念や陳述はその適合方向のゆえに自動的に真となり、願望や約束はその適合方向のゆえに自動的に実現するのでなければおかしい。しかしもちろんそんなわけはないのだから、適合方向概念によって地位機能宣言の有効性を基礎づけることは不可能である。二重の適合方向は、地位機能宣言が地位機能を創出しうることを前提に見出される性質であって逆ではないのである。
さて、サール自身この不備にどこかで気づいているのか、この点を補うべき重要な役割を、「集合的承認」の概念に与えている。本書では一応、地位機能の創出は地位機能宣言が担い、地位機能の作用または維持の保障を集合的承認が担うという役割分担がなされているように見える。しかし随所で、あたかも集合的承認こそが地位機能の創出を可能にしているかのような記述も見られる(例えば本書147頁以下)。この混在状況により、本書の議論は全体として大きな曖昧さを抱えることとなる。訳者が考える整合的解釈の一つの可能性は、宣言(厳密には宣言と同じ論理形式を有する表象)は集合的承認の対象として含まれているのであり、それゆえ、一見集合的承認だけで地位機能の創出が得られているかのように読める箇所でも、実際には宣言による創出という論理が貫かれている、とするものである。
しかし仮にこの解釈が一定の妥当性をもつとした場合、表面上の曖昧さを我慢すれば理論それ自体は無傷で救出できるのかというと、事はそう単純ではない。というのもサールの言う集合的承認は、「各人の個人的承認の集合に相互的信念を加えたもの」(本書88頁)へと還元可能とされているからである。これは要するに、集合的承認とは世界と他人に関する個人の主観的態度の集合にほかならないということである。地位機能の、したがって制度的事実の存在が、こうした主観的承認に支えられているとした場合、はたして制度的事実は一般に客観的事実であるという前提が維持できるのかどうか、はなはだ心許ないと言わざるをえない。制度的事実の客観性はあくまでも宣言のもつ創出能力によって担保されていたからである。
以上、ごく簡単にではあるが、社会的存在論における説明部分の根幹をなす地位機能宣言の概念にまつわる不備、議論の揺れ、曖昧さ、整合的解釈の可能性とその問題的帰結を指摘してきた(1)のは、訳者として、ここから社会的存在論の本格的な検討が始まってほしいと考えているからである。実際訳者自身、この解説を書く過程で、すでに何度も通読している本書を、例えば原著者の先行文献との対比において、あるいは訳者の本来の専門分野であるニクラス・ルーマンの社会的システム理論との対比において改めて読み直す必要を痛感するに至った。望むらくは読者各位においても、それぞれの仕方で本書がさらなる思考の契機となってくれればと思う次第である(2)。
この関連で、本書の一般理論に対し特殊理論の位置づけを与えられた前著『社会的現実の構築』について一言付しておく。もし本書の議論が大成功を収めていたならば、少なくとも社会的存在論の一般理論の水準では、本書刊行により依拠すべき文献が更新されたと言われてしかるべきであった。しかし前段までの訳者の指摘が一定の説得力をもつと言えるのであれば、宣言の理論的地位を制度の内部に保留していた『構築』の理論に再度立ち戻っての検討が必要となるはずである。それ以外にも『構築』には読者の直観に訴える制度的事実の事例呈示が本書よりも多く丁寧に掲載されていること、また最後の三章で展開される実在論をめぐる議論は本書が欠く要素であると同時に、本書の理論を再考する際の足掛かりを含むものであることを考えると、『構築』は依然一読の価値を失っていないと言うべきである。
4 「積極的人権」について
他方、社会的存在論の根幹には関わらないところで著者が非常に強い主張をしていて、しかも訳者の考えではそれが明らかに間違っている箇所というのもある。「積極的人権」の観念に対する批判(本書289頁以下)である。
サール曰く、「消極的人権」がすべての人に対して不干渉の義務を課すのと同様に「積極的人権」はすべての人に対して支援の義務を課すものであるが、常識的に考えてそんな義務が存在するわけはなく、それゆえ巷間「積極的人権」とされているもの(「誰もが十分な生活水準を得る権利」等)のほとんどは実際には人権ではない。だから、さもそれが人権であるかのように述べる世界人権宣言は「普遍的権利と普遍的義務の間に論理的な含意関係の存在することまで頭が回ら」ない人が書いた「きわめて無責任な文書」である(本書289頁)。
だがここで用いられている「普遍的権利は普遍的義務を論理的に含意する」という前提は、訳者の考えでは、権利や義務の概念それ自体から導かれるものではなく、消極的権利の場合にのみ成り立つ命題にすぎない。消極的権利の例として「殺されない権利」を考えると、ある人が「殺されない」という事態は、「殺す」人が一人でもいたら実現されないのであり、だからこそすべての人に対して「殺さない」義務を課すのである。論理的な含意関係は、権利の消極性と義務の普遍性の間に見出されるのであって、権利の権利性が義務の普遍性を導くのではない。また権利の普遍性が義務の普遍性を導くのでもない。仮にこの権利をもつ人が世界に一人しかいなくても、その人の「殺されない権利」はすべての人に「殺さない義務」を課すのである。
一方、積極的権利として「十分な生活水準を得る権利」を考えると、ある人が「十分な生活水準を得る」という事態が実現しないのは、その人に「十分な生活水準を与える」人が一人もいない場合である。したがってこの権利が求めるのは、その人に「十分な生活水準を与える義務」をもつ人が(少なくとも一人)存在することである。論理的な含意関係は、権利の積極性と義務の存在の間に見出される。この権利を普遍的権利として定めたところで、論理的含意は「誰にでも自分に対して十分な生活水準を与える義務をもつ人が存在する」ことにすぎず、「すべての人が他のすべての人に対して十分な生活水準を与える」普遍的義務は導かれないのである。
要するに、サールは本来権利の消極性に由来するにすぎない義務の普遍性を、権利の権利性それ自体に由来するものと誤認し、そこから普遍的な積極的権利は普遍的義務を含意するがゆえに(多くの場合)積極的権利は普遍的人権ではないと結論づけてしまったのである。しかし以上示した通り、普遍的な積極的権利が含意するのはあくまでも義務の存在にすぎない。
このようにサールの「積極的人権」批判は端的に誤りだというのが訳者の読みなのだが、訳者が何か大事な要素を捉え損なっている可能性もないわけではないので、その当否はぜひ読者各位の目で直接ご確認いただきたい。特に人権を扱った第8章は応用的な性格の強い章で、ここだけを読んでも比較的理解に支障がないと思われる。
5 翻訳について
翻訳は正確さと明確さ、そして読みやすさを旨とし、そのためには時に原書の構成に対して批判的な立場をとることも厭わなかった。特に原書の段落構成はお世辞にも読みやすいものではなく、箇所によっては適切に考えられたものとも思われなかったため、訳者が適当と判断したところに改段落を入れてある。また原書脚注の多くは文献挙示の目的にしか用いられていないうえ原書巻末には文献一覧がなく、これは非常に不便であるから、原書脚注の文献情報を巻末にまとめ、文献参照のみの原注は本文に埋め込んだ。(以上、凡例を参照のこと。)
訳語は既訳を参照のうえ、訳者が最適と考えるものを採用した。deontic power を「義務論的権力」と訳すのだけは最後まで迷ったが、(「義務論的パワー」は言うまでもなく)「義務論的力」の術語としての据わりの悪さと、特に第7章の章題(および同章に登場する無数のpower)は議論の内容からして「権力」と訳すほかないという事情から、やはり「義務論的権力」が最適と判断した。これはフーコーなりルークスなりの既存の権力論でも発生していた問題で、結局は「権力」を全部「力」にしてしまうか、日本語の「権力」の意味内容を、違和感を伴いつつ拡張してやるかのいずれかしか手がないのであって、従来の議論が採ってきた後者の方途を本訳書でも採用したものである。
本訳書の企画は、勁草書房編集部の渡邊光さんから紹介いただいたものである。ここまで結構批判的なことを書き連ねてきたので最後に急いで付け加えておくが、社会を脳と心と言語とともに単一の世界の中に描き切ろうというサールの社会的存在論は、実に壮大でとんでもないプロジェクトなのである。本書は社会科学の基礎に関心をもつ人なら誰もが真剣に批判的に読む価値のある一書であり、今回その翻訳を担当できたことは望外の幸せであった。作業開始から現在までこちらの多忙やらあちらの都合やらで結構な時間がかかってしまったが、なんとか刊行にこぎつけることができてほっとしている。脱稿してからなかなか初校が出てこなくてやきもきした一方、こちらもぎりぎりまで初校・再校・三校と大量の修正を入れさせてもらったのでお互い様かなと思いつつ、渡邊さんには諸々感謝申し上げる。
1 Tsohatzidis(2010)も地位機能宣言の問題性に着目し、本書の議論全体に対して本節の指摘とも関連する三点の批判を寄せている。
2 大河原(2017)は、原書刊行後に寄せられた批判的反応を多く紹介しているほか、本書の議論をかなり詳細に検討していて実に有用である。
文献
倉田剛、二〇一七、「社会存在論 ―― 分析哲学における新たな社会理論」、『現代思想 一二月臨時増刊号(総特集:分析哲学)』四五巻二一号、八九-一〇七頁
中山康雄、二〇一一、『規範とゲーム ―― 社会の哲学入門』、勁草書房
大河原伸夫、二〇一七、「サールの社会的存在論における「宣言」及び「認知」・「受容」について」、『法政研究』八四巻二号、三九九-四五三頁https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1854775/p161.pdf
Searle, John R., 1975, “A Taxonomy of Illocutionary Acts,” in: Keith Gunderson (ed.), Language, Mind and Knowledge, Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol. VII, Minneapolis: University of Minnesota Press, 344-69.
Searle, John R., 1983, Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind, Cambridge: Cambridge University Press.
Searle, John R., 1995, The Construction of Social Reality, New York: Free Press.
Searle, John R., 1998, Mind, Language, and Society: Philosophy in the Real World, Basic Books, 1998.
Tsohatzidis, Savas L., 2010, “Review of John R. Searle, Making the Social World: The Structure of Human Civilization,” Notre Dame Philosophical Reviews (2010.9.19)https://ndpr.nd.edu/news/making-the-social-world-the-structure-of-human-civilization/

