あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
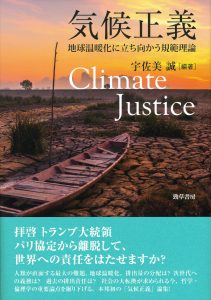 宇佐美 誠 編著
宇佐美 誠 編著
『気候正義 地球温暖化に立ち向かう規範理論』
→〈「はしがき」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報はこちら〉
はしがき
2018年は気象災害の年だった。平成30年7月豪雨では、総雨量が四国地方で1800ミリに達し、224名の人命が奪われ、全壊は約7700戸、床上浸水は約8600戸に上った。それに続く猛暑では、気温が埼玉県で全国歴代第1位の41.1℃を記録し、熱中症の死者は133名、緊急搬送された人は約5万4200名に達した。さらに、台風21 号が日本を襲い、最大瞬間風速が全国の観測点927か所中100か所で史上最大となり、高潮は第二室戸台風(1961年)での記録を上回った。
このような一連の気象災害を目の当たりにすると、多くの人は、ある疑念を払いのけるのがますます難しくなるだろう。地球温暖化はすでに起こっているのではないか。無論、気象はさまざまな要因が組み合わさる複雑な現象だから、地球の平均気温の上昇という平均的変化のみによって、ある国で特定の年に起こった個々の事象を説明することはできない。だが、夏季の猛暑の昂進は、誰もがただちに思いつく温暖化の影響の一つである。また、温暖化によって南洋の海水温が上昇すれば、より多量の海水が蒸発して、低気圧が生じやすくなり、台風が大型化しやすいだろうということも、たやすく理解できる。
実際、地球温暖化をふくむ気候変動は、いずれは生じるかもしれない変化ではないばかりか、やがて訪れるだろう変化でさえない。それは、すでに起こり始めた変化である。全米科学振興会は、ウェブサイト「私たちが知っていること」(whatweknow.aaas.org)のなかで述べている。十分に確立された証拠にもとづいて、約97%の気候科学者は、人間が原因の気候変動が起こっていると結論づけてきた。……地球の平均気温は、過去100年間に約1.4℉〔約0.8℃〕上がった。海面は上昇しており、熱波や大雨のようないくつかのタイプの極端な現象はよりひんぱんに起こっている。
しかも、すでに表れている気候変動の悪影響は、これから何十年、何世紀にもわたって深刻化し続けるだろうと予想されている。何よりもまず、二酸化炭素(CO2)、メタンなどの温室効果ガス(GHG)の地球全体での排出は年々増加しており、その増加率は上昇している。たしかに、国連気候変動枠組条約(1992年)の下、京都議定書(1997年)やその後続であるパリ協定(2015年)に代表されるとおり、国際社会でさまざまな枠組みが構築され、実施されてきた。しかしながら、石炭・石油の産出国が化石燃料に巨額の補助金を与えるなど、気候変動への取り組みに逆行する政策は多くの国で現に維持されている。そして、大気中のCO2 濃度は空前の高水準に達している。1850年時点では280ppm だったところ、2018年には月平均で410ppmを超えたが、これは過去80 万年で最高の数値である。人間の排出するCO2が増加の一途をたどってきたことを踏まえて、現在の歴史的な高濃度は今後いっそう顕著になるだろうと、多くの研究者は予測している。
だが、CO2などのGHGの大幅な排出削減が近い将来に実現されるといったん仮定してみよう。その場合、私たちは早晩のうちに気候変動の悪影響から逃れられるか。残念ながら、答えはノーである。まず、CO2の特徴の一つは長期残留性にある。大気中のCO2の一部は数年以内に植物や海水などに吸収されるが、しかし別の部分は数十年間、数百年間も滞留し、さらに別の部分は1000年以上も残存する。私たちがたとえ排出をやめたとしても、大気中にすでにあるCO2は、今後の何世紀にもわたって人類に悪影響を与え続けるだろう。
それに加えて、さまざまなフィードバックが生じる。たとえば、現在までのGHG 排出によって気温が高くなると、海水温も上がるから、水蒸気が増える。水蒸気は、総体としては温室効果が最も大きいGHGだから、地球をいっそう温める。また、GHG排出による気温上昇の結果、グリーンランド・南極の氷床や山地の氷河が融解すると、露出した土壌からメタンが発生する。しかも、土は氷と比べて、太陽光線を反射せずむしろ吸収するから、温暖化がいっそう進行する。他には、CO2濃度の上昇により、植物が光合成を活発化させ、いったんはより多くのCO2を吸収するようになる。しかし、気温が上昇しつづけると、植物は生育環境に適応できず、光合成を減退させるので、CO2の吸収量はむしろ減少する。CO2の長期的残留の下でフィードバックが螺施的に進行すると、人類は、何十年、何世紀にもわたって加速度的に深刻化する気候変動の悪影響にさらされるだろう。
気候変動、とくに地球温暖化は、今後どこまで進行するか。最も知られているのは、米国科学アカデミーのチャーニー報告書(1979年)から、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第五次評価報告書(2007年)にいたるまで示されてきた、産業革命前と比べて1.5°~4.5℃上昇という気候感度だろう。気候感度とは、CO2濃度が倍増した場合に地球の平均気温が平衡状態にいたったときの上昇分である。だが、事態はより急速に悪化している。IPCCは2018年、現在の排出ペースでは、早ければ2030年にも1.5℃上昇に達するだろうと予測している。2100年あるいはそれ以後での6℃上昇の可能性を指摘する欧米の研究者も少なくない。6℃は起こりにくいとされるものの、気候変動は顕著に不確実だから、生起の可能性を否定することはできない。しかも、不確実性は、特定の時点での上昇幅だけでなく上昇法についても言える。多くの研究では緩やかな気温変化が想定されているが、過去数十万年について明らかとなっている気温変化の軌跡から、急激な変化の可能性を否定できないという指摘もある。
たとえば4.5℃上昇が起こるならば、私たちはどのような影響を受けるか。この問いについて考えるため、遠い過去の状況を振り返ってみよう。いまから約2万1000年前の最終氷期最盛期には、地球の平均気温は現在よりも4°~5℃低かったという。これにすぐ続く時代に、地球はどのようだったか。海面は現在よりもはるかに低かったため、シベリアから北海道まで、北海道から九州まではすべて地続きで、瀬戸内海も陸地だった。シベリアとアラスカも地続きだったため、人類の一部はユーラシア大陸からアメリカ大陸へと移動できた。平均気温が現在よりも数度低かった時代の状況を参照すると、いまよりも数度高くなった場合に、いかに大規模な変化が生じるかを推測できる。とくにわが国では、国土の7 割が山地・丘陵地であるため、臨海の平野部に人口の大半が居住し、産業が集積している。海面上昇は将来の日本居住者に、大規模な集団移住や事業所施設の移転・廃棄を強い、莫大な金額の経済的損失をおよぼすと考えられる。
気候変動の悪影響は海面上昇にとどまらない。台風・サイクロン・ハリケーンの大型化や頻発、暑熱の昂進や熱波、乾燥化・砂漠化、マラリア・デング熱等の熱帯性伝染病の拡大、膨大な数の生物種の絶滅など、枚挙にいとまがない。そして、これらの一例と考えられる現象は、すでに世界各地で発生しており、近い将来にはいっそう激化するだろうと言われる。ヨーロッパで気候変動による悪夢として記憶されている2003 年の熱波では、死者数はフランスだけで1万5000人、ヨーロッパ全体では少なくとも3 万人に上った。2008年のサイクロン・ナルギスでは、ミャンマーを中心に14 万人以上が命を奪われた。2011 年の東アフリカ大旱魃では、ソマリアなどで1200万人が生存をおびやかされた。さらに、世界保健機関(WHO)によれば、2030年から2050年の間に、毎年約25万人が栄養失調・マラリア・熱中症などにより死亡するだろう。気候変動は、海面上昇の他にも種々の悪影響をすでに引き起こしており、その悪影響は徐々に深刻化しつつあり、そして先進国以上に途上国でいっそう甚大な被害を生むのである。
* * *
気候変動がもたらしつつある深刻な事態を前にして、1990年代初頭から、気候変動や気候変動政策をめぐる哲学的・倫理学的な諸論点に取り組む新たな研究領域が形成され発展してきた。これは今日では、気候正義(climate justice)と呼ばれる。気候正義の一つの主要論点は、気候変動を遅らせ緩やかにするための緩和策にともなう負担をいかに分配するかである。とりわけ、GHG排出権をどのように分配するかが論じられてきた。IPCCの評価報告書に集約された世界中の気候科学者の研究成果が示すように、現下の気候変動の原因がGHG排出にあるならば、気候変動への緩和策として地球全体での排出削減が必須であることになる。排出してもよい総量の上限がどこかに定まるならば、次にその総量を世界中の国々または人々の間でどのように分配するかを決めなくてはならない。あるものを分配するときには、どのような分配が正しいか、つまり分配的正義の問いを避けられない。そして、この主題に取り組む際、多くの論者は二重の南北格差に注目してきた。先進国の一人当たり排出量は、途上国のそれを大きく上回る一方で、途上国は先進国と比べて、気候変動の影響に対してはるかに脆弱である。こうした二重の格差を是正することを多くの論者がめざしてきた点に、GHG排出権の分配的正義論の大きな特徴がある。
他方、気候変動の悪影響を小さくしようとする適応策についても、費用分配が問われる。前述のように、先進国がおもに気候変動を引き起こす一方で、その被害は途上国でいっそう大きいならば、各途上国での適応策の費用を先進諸国が部分的に負担することは、理にかなうように思われる。そこで、先進諸国は各途上国の適応策の費用を負担するべきかが問われる。また、負担するべきだとすれば、どこまでか。そして、費用負担を先進国間でどのように分担するかも問われる。さらに、緩和策であれ適応策であれ、負担を怠る国が現れた場合に、他国はその負担を代わりにはたすべきかという問いも生じる。これらもまた、気候正義上の論点となる。
CO2の長期残留性やフィードバックの螺施的進行という特徴は、気候正義にとって二つの重要な規範的含意をもつ。第一は、現在世代と将来世代の規範的関係である。現在の先進国市民や新興国の中産階級は、化石燃料に依存した大量生産・大量消費の経済システムを通じて、快適で便利な生活を享受している。他方、現在の経済システムの下で排出される膨大なGHG排出によって、将来世代は、多数の死者をふくむ甚大な損失をこうむるだろう。このような関係において、現在世代は将来世代の利益を配慮する義務を負うか。負うならば、その根拠は何か。どれほど遠い将来世代までを配慮するべきか。配慮義務は具体的にいかなる政策・行動を求めるか。将来世代への配慮が現在世代内部での配慮と衝突するならば、優先順位はどのようになるか。これらの問いは、1970 年前後に興隆し、今日では世代間正義(intergenerational justice)と呼ばれる領域で考察されてきたが、気候変動をめぐってとりわけ先鋭化する。
第二の含意は、過去の排出に対する現在世代の歴史的責任である。先進国に住む私たちは、過去の産業化のおかげで富裕・快適な生活を営んでいる。他方、1850年以降に大気中のCO2濃度が上昇してきたという事実が示すように、産業化はGHG排出量の増大をもたらし、それが招く気候変動は途上国の人々やその子孫に対して重大な悪影響を与える。そのため、先進国市民は、過去の排出にもとづく特別な責任を負うかが問われる。具体的には、上記のGHG排出権の分配において、過去の排出を理由として排出権の縮小を求められる排出債務や、途上国での適応策の費用を一部負担する適応債務を負うかが論じられている。
気候変動からの悪影響にさらされているのは、人間だけではない。他の多くの動植物が、個体数の減少、生存環境の悪化、さらには種の絶滅の危機にさらされる。そこで、人間は、他の生物種の個体・種や生態系についていかなる義務を負うか、その根拠は何であるか、どの範囲の生物種が配慮されるべきかなどが問われうる。これらの問いへの答えは、環境倫理学でかつてさかんに対比された人間中心主義と生態系中心主義のいずれに立つかによって異なる。ただ、ローカルな環境破壊と異なって、グローバルな気候変動の場合には、はるかに広範囲にわたる含意をもつ。ここにも、従来からの論点が、気候変動をめぐって先鋭化された形で現れている。
これまでに概観してきた諸論点をめぐって、この四半世紀間に膨大な研究がおもに英語圏で蓄積されてきた。とくに近年には、学術論文は言うにおよばず、単行本や論文集も毎年のように公刊されている。他方、わが国に目を移すと、気候正義はいまなおほぼ未開拓のままである。こうした大きな間隙を多少とも埋めるために、気候正義やそれに密接に関連する諸論点について多角的検討を行ったのが、本書である。執筆者の専門は法哲学・政治哲学・経済哲学にわたり、相互に関連しつつも多様な観点から考察を行っている。
* * *
各章を概観しよう。第Ⅰ部は、グローバルな射程をもった諸論点をあつかう。第1章(ヘンリー・シュー)には、気候正義の学説史における記念碑的論文である“Subsistence Emissions and Luxury Emissions,” Law and Policy 15(1), 1993, pp. 39─60 の全訳が収録されている。ただし、節番号などには、本書の形式的統一性の観点から最小限の変更を加えた。人権論や拷問・戦争の分析でも著名なシューは、本章において、緩和策費用の分配、適応策費用の分配、これらをめぐる国際交渉を公正なプロセスとする富の背景的分配、排出権の分配および移行という四つの論点を区別した上で、論点間の関連にも留意しつつ順に考察している。排出権の分配に関しては、途上国の人々が生計のために行う排出と、先進国の私たちが奢侈的に行う排出という重要な区別を提示する。そして、これらの区別を活用しつつ、すべての種類のGHGを包括的にあつかう条約か、CO2 などの特定の種類に焦点をしぼった条約かという実践的論点について、前者よりも後者が望ましいと結論づける。
第2章(宇佐美誠)は、GHG排出権の分配を主題とする。この論点をめぐって、過去準拠説は、過去の特定時点での排出量の分布を基準とし、平等排出説は、国を問わない平等な一人当たり排出量を唱え、基底的ニーズ説は、人間の基底的ニーズの充足に必要な排出量を認める。加えて、途上国の発展の権利に訴えかける発展権説も構成できる。他方、従来の分配的正義論では、格差が小さいほど望ましいという平等主義、より不利な個人への裨益ほど重視する優先主義、万人に閾値までを保障する十分主義が、三つ巴の論争を繰り広げてきた。宇佐美は、平等排出説─平等主義、発展権説─優先主義、基底的ニーズ説─十分主義という対応関係に着目する。過去準拠説を退けた後、分配的正義論での知見を活用しつつ、平等排出説・発展権説を批判的に検討した上で、基底的ニーズ説の一形態を擁護している。
第3章(佐野亘)は、一部の行為主体が正義のルールを遵守しない場合に、他の行為主体はいかなる義務を負うかを考察する。アメリカのトランプ政権における気候変動政策の大幅な後退を見るだけでも、この理論的論点が気候変動政策についていかに重要な実践的含意をもつかが分かるだろう。佐野は、非遵守者の肩代わりをする義務の有無に焦点をあて、否定説、肯定説、肯定説への批判を順に紹介し検討してゆく。続いて、義務の遂行能力への着目、責任概念の見直し、連帯責任への訴えかけが、俎上に載せられる。最後に、現在世代の将来世代に対する義務は、特殊な関係にもとづく連帯責任として捉えられ、その観点から肩代わりの義務を正当化できると論じられる。本章は、気候正義のグローバルな次元を主題としつつ、世代間の次元への橋渡しともなっている。
第Ⅱ部は、世代間関係をめぐる二つの論点に目を向ける。第4章(森村進)は、遠い未来世代に配慮する理由について、著者の従前の主張に加えて新たな議論を提示している。旧稿では、未来世代の不幸への人道主義的配慮を最善の理由とし、そこから十分説的義務が導かれると論じたが、現在では正義も理由として認めており、未来世代の福利については客観的リスト説をとるという。まず、気候変動が現に生じており、その主因はGHG の大量排出にあるといったん想定した上で、社会的割引率をゼロとする自説を改めて擁護する。次に、私たちは自分の死後にも人類が存続することに大きな関心・利益をもつというサミュエル・シェフラーの議論と、他の論者たちによるコメントとが、詳細に紹介され検討される。そして、シェフラーの議論から、人類全体の文化の存続が未来世代への配慮の一理由を与え、また緩和策よりも適応策の方が重要になるという含意を導いている。
第5章(井上彰)は、左派リバタリアニズムと運の平等論の世代間正義理論を批判的に精査する。はじめに、GHG 排出の分配的正義について、共時的問題と通時的問題を区別し、後者の重要性が指摘される。通時的問題では、将来世代は現在世代に裨益も加害もなしえないという非互恵性問題に対して、ジョン・ロールズ流の契約論は満足のゆく応答をなしえない。また、非互恵性問題に応えうる合理的契約論は、定常状態の想定という限界をもつ。自己所有権論を維持しつつ、その射程から自然資源を除く左派リバタリアニズムは、定常状態を想定しないという利点をもつ半面、将来世代の人数が現在世代のそれと異なるケースでは、理にかなった原理を導けない。他方、自発的選択による不平等を個人の責任に帰し、選択によらない不平等を不正とみなす運の平等論も、定常状態を想定しないが、将来の福利水準が世代を追うごとに向上するケースでは、直観に反する帰結をもたらす。
第6章(宇佐美・阿部久恵)は、過去の排出への歴史的責任ないし気候債務に焦点をあわせる。先進国市民は、過去のGHG 排出を理由として、排出債務または適応債務を負うか。この設問に肯定的解答を与える超世代的集合責任論は、過去世代が自らの排出行為の帰結を知りえなかったという無知性の議論によって掘り崩される。また、ある事象の後に受胎が起こり誕生した個人は、当該事象が仮になければ誕生しなかっただろうという非同一性問題にさらされる。世代間責任継承論もこれらの問題を避けられない。他方、受益者負担論は無知性の議論をまぬがれているものの、この論拠による適応債務の主張は非同一性問題におびやかされ、その結果を避けようとする最近の学説は失敗に終わる。それに対して、受益者負担論による排出債務の主張は非同一性問題から救出されうる。
第Ⅲ部は、気候変動が従来の学問分野に対してもつ含意を考える。第7章(後藤玲子)は、気候変動問題への経済的アプローチがもつ限界を浮き彫りにする。このアプローチは、共通に便益を受ける社会内4 の構成員間での負担分配を定式化できるが、私たちが存在のあり方を左右できる社会外の主体に対する負担の先送りをあつかえない。だが、そもそも外を外としていかに認識しうるか。新古典派経済学における外部性の内部化は、CO2排出規制の費用と便益を社会内の主体の効用関数に組み込むのに対して、エコロジー経済学は、社会外の環境への非対称的責任を問う。ここで問われる境遇の隔絶と行為による到達を考察するため、後藤は、アキレスと亀のパラドックスを考察する。また、マーサ・ヌスバウムに見られる、新古典派経済学と親和的な連続性の想定を批判的に検討する。結論として、経済学における連続性の想定は、内/外の境界への無感応性をもたらすと指摘している。
第8章(瀧川裕英)は思想史に沈潜し、イマヌエル・カントにそくして、気候変動の悪影響にさらされる動物の道徳的地位を分析する。カントは、動物に対する義務を否定するが、動物に関する義務を肯定し、暴力的・残虐な扱いを禁止する。その背後には、人間─動物間の行為の類似性、動物の扱いと人間性への義務、自己に対する義務としての人間性への義務、人間相互の義務、徳の完全義務という5点がある。続いて、現代のカント主義者であるロールズ、トマス・スキャンロン、クリスティン・コースガードの見解が、丁寧に紹介されてゆく。カントは、理性のある人間のみが道徳的地位をもつと考えたのに対して、現代のカント主義者たちは、動物をそれ自体として考慮に入れ、動物の扱いを正当化することを求める。こうした正当化の要請は、カントが述べていた類似性にもとづく我汝契約によって根拠づけられる。
* * *
本書は、科学研究費・基盤研究(B)「地球温暖化問題の正義論─グローバルな正義原理とその法制度化」(課題番号26285002、2014年度~2016年度)の最終成果物である。研究期間の最終年度に研究協力者として参画してくださった鬼頭秀一氏(東京大学名誉教授、星槎大学副学長・教授)に、厚くお礼を申し上げたい。また、シュー氏のご厚情にも感謝している。同氏の論文の翻訳については、ジョン・ワイリー・アンド・サンズ社より許諾を得た。研究分担者の各氏には、早々に論文原稿を提出されたにもかかわらず、公刊が予定よりも大きく遅れたことについて、お詫びを申さねばならない。今回の出版でも、企画から仕上げにいたるまで、勁草書房の鈴木クニエ氏に一方ならぬお世話になった。
2018年11月
宇佐美誠

