10月刊行の『問答の言語哲学』について、著者入江幸男先生のブログ「哲学の森」では本書の各章の解説、追加説明を連載されています。読者の方々へのガイドとして、弊社サイトにも記事転載させていただくことになりました。全6回シリーズでお届けいたします。読む前に、読んだ後に、ぜひお楽しみください。[編集部]
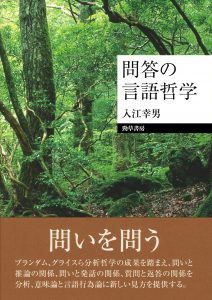
拙著『問答の言語哲学』(勁草書房、2020)について、解説したり、追加説明したり、ご批判やご質問に答えたりしたいとおもいます。素朴な疑問、忌憚のないご意見、励ましの声、なども歓迎いたします。→【哲学の森|入江幸男のブログ】
第2章「問答関係と発話の意味――問答推論的語用論へ向けて(1)」は、文の意味ではなく、ある文脈において現実に行われる発話がもつ意味について、問答の観点から説明します。
第2章の2.1「文と命題内容と発話の違い」は3つに分かれています。
まず2.1.1で、第1章では触れなかった、文の意味、命題内容、発話の意味などの区別について説明します。 文は、文脈を入力として、それに応じて異なる意味を出力する関数だと見なすことができます。そこで厳密には「文の意味」とはこの「関数」のことであり、文脈に応じて出力される意味を「命題」ないし「命題内容」と呼ぶことにします(この命題内容には2.2で扱う「焦点」は考慮されていません。その点で「命題内容」は「発話の意味」とは区別されます。これについては次回説明します)。
次に2.1.2で、関数についての考察を挿入しました。関数は推論規則であり、それゆえに問答と関係しています。そこで、関数について「機械的に使用すること」と「選択して使用すること」に区別し、それに応じて推論も二種類に区別しました。ところで、言語表現を使用するとは、その表現が持つ複数の関数から一つを選択することであり、一つの関数にコミットすることです。ここに言語表現の理解とコミットメントの区別が生じます。
2.1.3では、(第1章では、発話がコミットしている意味(命題内容)を、問答推論関係として説明しましたが)、命題内容にコミットするとはどういうことかを説明しました。
命題「これはべジマイトである」を理解することと、この命題にコミットすること(この例では命題の真理性を主張すること)は、別のことです。つまり、命題を理解することと命題にコミットすることは別のことです。では、命題にコミットするとはどういうことでしょうか。これに答えるために、まず、語句の意味と指示対象の区別、および意味の理解と指示へのコミットメントの区別は、すでに問いにおいて暗黙的に行われており、問答関係において明示化されるということを示しました。次に、語の意味から文の意味がどのように合成されるのか、といういわゆる「合成の問題」(デイヴィドソンのいう「述定の問題」)を「語の使用におけるコミットメントを結合することによって、どのようにして文の発話によるコミットメントが成立するのか」という問いとして捉えて、次の答えを提案しました。
<文未満表現の使用におけるコミットメントの結合は、問いへのコミットメントと答えへのコミットメントの結合となるときに、命題内容へのコミットメントとなる。>
この提案は、<命題は潜在的には問答によって構成されている>という提案になります。例えば、
「次のアメリカ大統領はバイデンになると思います」
という命題へのコミットメントは、
「次のアメリカ大統領は誰になると思いますか?」
「バイデンになると思います」
という暗黙的な問答によって成立するということです。
第2章の「2.2 発話が焦点を持つとはどういうことか」では、この問いに答えました。
発話が焦点をもつとは、発話の中のある部分に注目しているということです。同じ文の発話でも異なる部分に注目している発話は、異なる焦点を持つことになります。例えば
「バイデンは、ペンシルベニア州で勝つだろう」
という文の発話は、次の三か所に焦点を持つことができるでしょう。
「[バイデン]F が、ペンシルベニア州で、勝つだろう」
「バイデンは、[ペンシルベニア州]F で、勝つだろう」
「バイデンは、ペンシルベニア州で、[勝つ]F だろう」
(ここで 「[バイデン]F が」の場合、「は」を「が」に変えた方が自然な日本語になると思います。それは、日本語の「は」と「が」の違いが、焦点位置を示しているためです。これについては、脚注で説明し、関連する拙論を示しました。)
次のように「(他でもなく)」を付け加えると、ニュアンスの違いが明確になると思います。ただしそれをそれぞれの焦点の前につけると、別の文になってしまうので、説明のための便宜上のこととになります。
「(他でもなく)[バイデン]F が、ペンシルベニア州で、勝つだろう」
「バイデンは、(他でもなく)[ペンシルベニア州]F で、勝つだろう」
「バイデンは、ペンシルベニア州で、(他でもなく)[勝つ]F だろう」
ところで、発話の焦点位置は、その発話を答えとする補足疑問の相関質問によって、明示できることが知られています。たとえば、次のように対応します。
「誰が、ペンシルベニア州で勝ちますか?」
「[バイデン]F が、ペンシルベニア州で、勝つだろう」
「バイデンは、どこで勝ちますか?」
「バイデンは、[ペンシルベニア州]F で、勝つだろう」
「バイデンは、ペンシルベニア州で、どうなりますか?」
「バイデンは、ペンシルベニア州で、[勝つ]F だろう」
つまり、発話の焦点位置は、発話の現実の上流問答推論(相関質問と上流推論)を示しています。
ところで、このように焦点位置の異なっていても、同一の命題内容の発話であるならば、その真理条件は変わりません。それでは、焦点位置の違いは、意味の違いではないのでしょうか。たしかに問答推論関係で明示化される命題内容は同一です。しかし、現実的な問答推論は、焦点が異なれば、異なっています。そこで、同一の命題内容の焦点位置の違いは、命題内容の与えられ方の違いであると考えることを提案しました。
発話の焦点位置の違いは、このように問答上流推論の違いを示すだけでなく、問答下流推論の違いも示していることも示しました。私たちが、問いを立てるのは、より上位の目的のためです。その目的は、より上位の問い(理論的問いや実践的問い)に答えることとして理解できます。ここでの二つの問いの関係を「二重問答関係」と名付け、それを次のように表現しました。
「Q2→Q1→A1→A2」
これは、問いQ2の答えを得るために、Q1 を立て、Q1 の答えA1 を得て、A1 を前提にQ2 の答えA2 を得る、という二つの問答関係の入れ子型の関係「二重問答関係」を表現しているものとします。
ここで発話A1の焦点位置は、相関質問Q1によって決まります。Q1を前提とする上流問答推論によってA1がえられます。ところでのこのQ1を問うたのは、Q2の答えを求めるためでした。したがって、Q2とA1(と必要ならば他の平叙文)を前提とする問答推論によってA2を得ることになります。この推論は、A1の下流問答推論になっています。
A1の焦点位置は、相関質問Q1によるものでしたが、Q1を設定するのは、Q2に答えるためでした。したがって、Q2は、A1の焦点位置を間接的に規定しています。つまり、A1の焦点位置は、A1の問答下流推論とも密接な関係にあります。
なお、この2.2では、補足疑問(wh疑問)と決定疑問(yes/no疑問)の返答文の関係についても、詳細に分析しましたが、ここでは説明を省略します。
第2章の「2.3 会話の含み」を紹介します。
例えば、夏の暑い日に教師が教室に入ってきて「今日は暑いね」と言ったとき、それは「窓を開けましょう」とか、「暑いけれど頑張って勉強しましょう」とか、「教室にクーラーが欲しいね」とかの言外の意味を持つでしょう。このような言外の意味は「会話の含み」(グライス)と呼ばれている。会話の含みやそれと類似のものを含めて、次のように整理されています。
①論理的含意 「pかつq」→「p」
②意味論的含意 「これはリンゴだ」→「これは果物だ」
③一般的な会話の含み 「女性がやって来た」→「母親以外の女性がやって来た」
④特殊的な会話の含み 「今日は暑いね」→「窓を開けましょう」
グライスが「会話の含み」と呼んでいるのは、③と④で、③は発話の特定の文脈に依存せず、一般的に成り立つ含みであり、③は特定の文脈で成り立つ会話の含みです。①と②と、③と④の違いは、後者の含みは、その後の発話によって否定されることもありうるということです。例えば「今日は暑いね」に続いて、「しかし夏休みまで後一週間ですね」と言えば、会話の含みは「窓を開けましょう」から「暑いけれど頑張って勉強しましょう」に修正することになります。
さて、聞き手が会話の含みを理解するメカニズムについて、グライスは通常の会話では「協調の原則」と「会話の格率」に私たちが従っていることを指摘し、それが破られているときには、聞き手は、その理由を考え、それがある「含み」を伝えるためなのだと理解する、と説明します。
これに対して、スペルベルとウィルソンの「関連性理論」は、通常の発話の意味(「表意」)と会話の含意(「推意」)の関係を連続的なものと考えます。どちらも「関連性の原則」(「すべての意図明示的伝達行為は、その行為自体の最適な関連性の見込みを伝達する」)に基づいて、推論されることになります。
これらに対して、私は、二重問答関係によって「会話の含み」を説明することを提案しました。
店長X と店員Y の次の会話があったとしよう。
X「そろそろ閉店の準備をした方がいいだろうか?」
Y「もうすぐ5 時です」
〔そろそろ閉店の準備をした方がよいでしょう〕(会話の含み)
この場合、Y の返答の含みは、次のような二重問答関係で説明できるでしょう。(「」は実際に行われた発話であり、〔〕は暗黙的な思考や会話の含みを示す)。
Q2「そろそろ閉店の準備をした方がいいだろうか?」
Q1〔今何時だろうか?〕
A1「もうすぐ5 時です」
A2〔そろそろ閉店の準備をした方がよいでしょう〕
発話A1は、相手の質問Q2に答えるために立てた問いQ1の答えであり、この答えA1を前提にして、Q2の答えA2を推論できる。
一般に、発話は、その相関質問のより上位の問いの答えを「会話の含み」とする。発話がどのような「含み」を持つかは、このような二重問答関係のなかで説明できるでしょう。
最後に、このアプローチの、グライスの説明と「関連性理論」に対する長所を整理しました。
次回は、第3章の見取り図を紹介します。[編集部]
入江幸男(いりえ・ゆきお) 1953年生香川県出身。1983年大阪大学大学院文学研究科博士課程単位修得退学。現在大阪大学文学研究科名誉教授、文学博士。著書に『ドイツ観念論の実践哲学研究』(弘文堂、2001年)、『ボランティア学を学ぶ人のために』(入江・内海・水野編、世界思想社、1999年)、『コミュニケーション理論の射程』(入江・霜田編、ナカニシヤ出版、2000年)、『フィヒテ知識学の全容』(入江・長沢編、晃洋書房、2014年)。訳書に『真理』(P. ホーリッジ/入江幸男・原田淳平訳、勁草書房、2016年)。
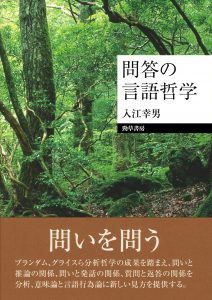 分析哲学の成果を踏まえ言語行為について問いと推論の関係、問いと発話との関係を分析、意味論と言語行為論に新しい見方を提供する。
分析哲学の成果を踏まえ言語行為について問いと推論の関係、問いと発話との関係を分析、意味論と言語行為論に新しい見方を提供する。
入江幸男 著
『問答の言語哲学』
https://www.keisoshobo.co.jp/book/b535722.html
ISBN:978-4-326-10287-7
A5判・272ページ・本体4,300円+税
本書のたちよみはこちら→【あとがきたちよみ『問答の言語哲学』】
