あとがき、はしがき、はじめに、おわりに、解説などのページをご紹介します。気軽にページをめくる感覚で、ぜひ本の雰囲気を感じてください。目次などの概要は「書誌情報」からもご覧いただけます。
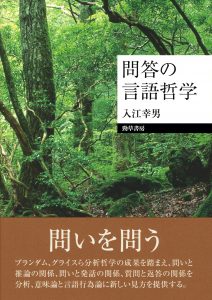 入江幸男 著
入江幸男 著
『問答の言語哲学』
→〈「序文 問いの重要性に向けて」(pdfファイルへのリンク)〉
→〈目次・書誌情報・オンライン書店へのリンクはこちら〉
序文 問いの重要性に向けて
「心が思考しているときの姿というものは、こうしたものだと僕には見えるのだ。その場合に心のしていることは、自分が自分に問いかけたり、答えたり、そしてそれを肯定したり、否定したりする問答(すなわち言論の語り分け)にほかならないと見えるのだ。」(プラトン『テアイテトス』田中美知太郎訳189e-190a)
「問いに対して明確な解答を得るために哲学を学ぶのではない。なぜなら、明確な解答は概して、それが正しいということを知りえないようなものだからである。むしろ問いそのものを目的として哲学を学ぶのである。なぜなら、それらの問いは、「何がありうるか」に関する考えをおしひろげ、知的想像力を豊かにし、多面的な考察から心を閉ざしてしまう独断的な確信を減らすからだ。そして何より、哲学が観想する宇宙の偉大さを通じて、心もまた偉大になり、心にとって最も良いものである宇宙と一つになれるからである。」(ラッセル『哲学入門』高村夏輝訳第15 章)
朝起きたとき、今日は何をする予定だろう、とか、何をしなければならないのだろう、と問うことによって、私たちは一日を始めるだろう。朝に限らず、ひとは常に多くの問いを立てる。「彼女は何をしているだろう」「あの仕事はいつまでにしないといけないのか」「あのニュースはどうなっただろう」など、そのすべてに答えるわけではないが、そのいくつかに答えることで生活している。すべてに答えるわけではないのに、常に多くの問いを立てるのは、問いに答えることによってではなくて、むしろ問いを立てることによって、家族や仕事や社会への向き合い方や課題を確認したり、世界に対する態度や生きる姿勢を絶えず調整したり確認したりしているからではないだろうか。
動物も探索行動をする場合があるが、人間の場合には、何かを探求することは、問うことから始まる。ただし、私たちは、問うことよりも答えることを重要視しがちである。なぜなら、探求において私たちが求めているのは答えであって、問いではないからである。問いは答えを求めており、答えは問いの目的であり成果である。その意味で、問いは手段であり、答えは問いよりも重要である。しかし、主張は、問いへの答えとして成立し、問いを前提とする。主張の半分はすでに問いによって与えられており、問いは主張の半製品である。答えは、問いを補完して完成品にするものである。答えとなる主張の基礎部分は、問いにおいてすでに与えられているので、間違った問題設定からは正しい答えは得られないし、(N.ベルナップ(Nuel Belnap)によると古代インドの偉いお坊さんによれば)愚かな問題設定からは愚かな答えしか得られない。従って、問いに正しく答えること以上に、どのように問いを立てるかが重要である。問いは様々な前提を持つが、その問いの前提は答えに継承され答えの前提となる。この意味で、問いは答えよりも重要である。
このように問いは重要なはずだが、哲学はこれまで答えにばかり注目して、問いそのものに注目してこなかったのではないだろうか。認識論は、「何を知りうるか」を問うてきたが、「何を問いうるか」がより重要なのではないか。存在論は、「何が存在するか」とか「存在するとはどういうことか」を問うてきたが、「存在について問うことはどういうことか」を問うことがより重要なのではないか。価値論は、「価値とは何か」を問うてきたが、この問いの価値を問うことがより重要なのではないか。自由論は、「意志が自由であるかどうか」とか「意志が自由であるとはどういうことか」を問うてきたが、これらを問うことと自由の関係を問うことがより重要なのではないだろうか。社会には問題があふれており、社会制度は社会問題への答えとして構築され、正当化されているのではないか。(橋本努氏が言うように)ある人がどのような人物であるかは、その人がどのような問いを抱えているかによって規定されているのではないか(橋本努1999)。集団はそれが抱える問題によって構成され維持されているのではないか。哲学はこれまで答えにばかり注目してきたが、現実を構成しているこのような問いおよび問答関係に注目することがより重要なのではないだろうか。
このことは本書の主題である言語の研究についても言えるだろう。J. L.オースティン(John Langshaw Austin)は、これまでの哲学が、おもに真理値を持つ言明を考察して、真理値を持たない言明を軽視してきたことを「記述主義的誤」と呼んで批判した(Austin 1962 : 3, 訳7)。約束や命名などの真理値を持たない発話が、私たちの言語使用において重要な役割を果たしていることを指摘した。この指摘に加えて、私たちは従来の言語哲学研究において問いや質問の研究があまりなされていなかったことを指摘できるだろう。私たちは、これを「平叙文中心主義の誤」と呼べるだろう。この背景には、疑問文は平叙文を変形することによって得られた文型であるという一般的な理解があるのかもしれない。しかしこれは間違いである。確かに私たちは平叙文を変形することによって疑問文を作ることができるが、しかし疑問文を作る学習の段階では、平叙文を変形することによって疑問文を作ることを学習するのではなくて、平叙文の構文を学習する前に、あるいはそれと並行して、疑問構文を独自の構文として学習する、ということが指摘されているからである。それゆえ、私たちが使用する文形を、平叙文を中心に理解することはできない。
幼児は変形規則を用いて疑問文をつくっているのだというものではなくて、子供は他の構文と同じように疑問文をある特徴的な機能を持つ言語ゲシュタルトとして学習し、それは項目依拠的なものから徐々により抽象的なものへと変わっていくのである(Tomasello 2003 : 訳175)
世界が言語でできており、私たちの言語活動において問答関係が重要であるとすれば、世界は問答でできていると言えるだろう。マルクスは、哲学は世界を解釈するのではなく変革しなければならないと述べたが、現代では世界もその理解も一層複雑で曖昧なものになっており、変革の前に「世界がどうなっているのか」を理解することがどうしても必要だと考える。「世界はどうなっているのか」という問いに対する私の答えは、「世界は問答でできている」である。これを具体的に説明するには、たくさんの仕事が必要になるが、少しずつ進めていくしかない。本書は、その仕事の始まりに過ぎない。
本書の目的は、問答関係から認識や行為や社会を考察するに先立って、その準備として問いと言語の関係を明らかにすることである。問うことは、言語によって可能になる。動物も言語と呼べるものを持つのだが、しかし、動物の言語には、問うという機能はない。何かを問い、それに答えるということが人間の言語に特有のことであり、これによってヒトは人間になったと言えるかもしれない。問うことは、人間の言語にとって、そしておそらくは未来のAI の言語にとっても(もしそれが人間と似た仕方で思考するものならば)、基本的な機能になるだろう。なぜなら、本書で説明するように、考えたり会話したりすることにとって問うことは不可欠だからである。
問いは、答えの半製品である。本書で詳しく述べるが、疑問文の中に、答えの文の内容の半分以上はすでに与えられている。「問いは答えの半製品である」という見方は、答えが得られたならば問いは解消し、答えだけが残る、という見方への批判でもある。確かに、答えは、汎用性を持ち、他の問いへの答えともなりうる。その意味では、答えが得られたら、それが作られるプロセスを無視して結果だけを利用できるように見える。しかしその場合には、答えは元の問いの答えとしてでなく、別の問いの答えとして理解され使用されている。つまり、何らかの問いが答えの基礎部分として答えを構成していることには変わりない。
これもまた本書で詳しく語ることだが、文の発話は焦点を持つが、答えの発話の焦点位置は、すでに問いにおいて指示されている。また、返答の発語内行為は、すでに質問の中で指定されている。その意味で、答えによる世界へのコミットは、問いにおいてすでに始まっている。私たちが世界に対してどういう態度をとるかは、私たちが立てる問いにおいてすでに決定している。
以下本書の概要を説明しよう。
第1 章「問答関係と命題の意味―問答推論的意味論へ向けて―」では、命題の意味を問答推論関係から説明する。従来の真理条件意味論や主張可能性意味論は真理値を持つ命題の意味を説明し、真理値を持たない命題(命令や約束や問い)の意味は、真理値を持つ命題の意味に基づいて二次的に説明することしかできなかった。それに対して、R.ブランダム(Robert Brandom)の推論的意味論は、真理値を持たない命題(命令や約束)であっても、それらが推論関係を持つ限りで、意味を説明できるので、真理値を持つ命題と持たない命題の意味を同様の仕方で説明できるというメリットを持っていた。ただし疑問文は通常の推論関係の中に含まれないので、推論的意味論では疑問文の意味を説明できないという限界があった。もし問いを推論の前提や結論として含むような推論体系を考えることができれば、その問答推論における役割によって、疑問文の意味を説明できるだろう。私たちは「それは何か?」「それはどうなっているのか?」などの問いを立てることによって、事実を明らかにしようとするが、それが可能なのは、そうした問答が対象を変化させないだけでなく言葉の意味が変化させないからである。もし問答によって言葉の意味が変化すれば、探求は不可能になる。逆に言うと、問答によって言葉の意味を明示化することが可能になるので、言葉の意味を問答推論関係によって理解できるのである。これが問答推論的意味論の基本的なアイデアである。
第2 章「問答関係と発話の意味―問答推論的語用論へ向けて(1)―」では、2. 1で、文と命題と発話の違いを検討し、文を関数とし、文脈を入力として、出力されるものを命題(命題内容)とし、この命題にコミットすることを発話の意味とみなすことを説明する。また語句の意味の理解と指示対象へのコミットメントの区別が、問答によって学習され成立することを示し、これらの語句へのコミットメントの合成として命題内容とそれへのコミットメントが成立することを説明する。このコミットメントの合成は、典型的には、主語による指示へのコミットメントと述語による述定へのコミットメントが問答において結合することによって成立することを提案する。2.2 では、焦点を論じる。文や命題そのものは焦点を持たないが、発話は常に焦点を持つ。この焦点位置は、相関質問に応じて変化し、他方で、焦点位置の異なる発話は異なる上流推論を持つことを明らかにする。相関質問の異なる発話、つまり焦点の異なる発話は、同じ命題であっても語句へのコミットメントの合成の仕方において異なっており、その合成の仕方の違いを示している。この合成の仕方の違いは、命題内容の与えられ方の違いである。それゆえに、焦点位置は、命題の与えられ方を示している。他方で、焦点位置は二重問答関係において説明できることを示す。最後に2. 3 で、発話の持つもう一つの特徴である「会話の含み」を紹介し、会話の含みを二重問答関係から割り出すアプローチを説明する。
第3 章「問答関係と言語行為―問答推論的語用論へ向けて(2)―」では、3. 1で、オースティンとJ. サール(John Searle)の言語行為論を紹介し、サールの言語行為論における質問発話の位置づけを批判し、質問発話の特殊性を明らかにするとともに、すべての発話が暗黙的に質問の意味を持っていることを示す。3. 2 では、従来の言語行為論ではヘイトスピーチをうまく説明できないことを手がかりにして、言語行為の新しい分類を提案する。3. 3 では、指示を含めた伝達がある種の不可避性によって可能になることを示す。その不可避性は、究極的には、問われたら答えざるをえないという問答の不可避性に基づくことを論じる。
第4 章「問答論的超越論的論証」では、4. 1で、構文論的矛盾、意味論的矛盾、語用論的矛盾という従来の三種類の矛盾とは異なる「問答論的矛盾」について説明し、これの分析と分類を試みる。4. 2では、問答論的矛盾をさらに分析するために、問答関係一般の必要条件である「照応」関係と問いの前提について考察する。4. 3 では、問答論的矛盾を避けなければならないという必然性から、問答が成立するための不可避な超越論的条件があることを示す。これは新しいタイプの超越論的論証の提案である。この論証によって、問答における照応の不可避性、規則遵守問題、論理法則(同一律と矛盾律)、規範(根拠を持ってすべきこと、噓をつくことの禁止、相互承認)などについての新しいアプローチを示す。4. 4 では、最後にこの超越論的論証が究極的な基礎づけを与えるものではないことを説明する。

